Gサイエンス学術会議2023

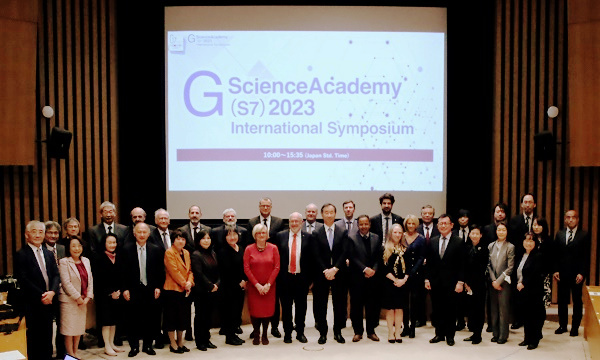

令和5年3月7日、日本学術会議が主催して、Gサイエンス学術会議2023が日本学術会議講堂及びオンラインで以下のとおり開催されました。G7ナショナルアカデミーの代表者等が地球規模の重要課題について議論するとともに、共同声明が取りまとめられ、公表されました。
また、同日、G 7ナショナルアカデミーの代表者が岸田文雄内閣総理大臣を表敬し、後藤茂之内閣府特命担当大臣(経済財政政策)の立ち合いのもと、Gサイエンス学術会議2023共同声明を梶田隆章日本学術会議会長より岸田総理に手交しました。
さらに、翌8日には、G7ナショナルアカデミー代表者と招請者による共同記者会見を行いました。
共同声明、Gサイエンス学術会議2023の概要は以下のとおりです。
1. Gサイエンス学術会議2023共同声明(2023年3月7日公開)
| Addressing systemic risks in a changing climate | |
| 気候変化に伴うシステミックリスクに対応する分野横断的意思決定を支える科学技術 | |
| Delivering better health and well-being of older people through wisdom sharing and innovation | |
| 知見の共有とイノベーションによる高齢者の健康増進とより良いウェルビーイングの実現 | |
| Restoration and recovery of the ocean and its biodiversity | |
| 海洋と生物多様性の再生・回復 |
2. Gサイエンス学術会議2023 登壇者
- (1)G7ナショナルアカデミー代表者
- 梶田隆章 日本学術会議会長
- 高村ゆかり 日本学術会議副会長
- ミシェル・トランブレ カナダ王立協会科学アカデミー会長
- アラン・フィッシャー フランス科学アカデミー会長
- ジェラルド・ハウグ ドイツ科学アカデミー・レオポルディーナ会長
- マリア・クリスティーナ・マルクッツォ イタリア・リンチェイ国立科学アカデミー国際担当役員
- イアン・ウィギンス 英国王立協会国際部長
- マルシア・マクナット 全米科学アカデミー会長
- (2)招請者
- ナリンダー・クマール・メヘラ インド科学アカデミー副会長
- ピーター・グルックマン 国際学術会議会長
- フィリッポ・ロッシ グローバルヤングアカデミー理事
- (3)日本学術会議会員等
- 三村信男 茨城大学地球・地域環境共創機構特命教授
- 日本学術会議Gサイエンス学術会議2023「Gサイエンス学術会議2023『気候変動』執筆対応小分科会」委員
(小池俊雄第三部会員、三枝信子第三部会員、森章連携会員、高橋潔連携会員(特任)) - 同「Gサイエンス学術会議2023『ヘルス』執筆対応小分科会」委員
(荒井秀典第二部会員、郡山千早連携会員、和氣純子第一部会員、飯島勝矢連携会員、山田あすか連携会員) - 同「Gサイエンス学術会議2023『海洋』執筆対応小分科会」委員
(原田尚美連携会員、大越和加第二部会員、安田仁奈連携会員、西本健太郎連携会員(特任))
3. Gサイエンス学術会議2023 プログラム
日時:3月7日(火)10:00~15:35
会場:日本学術会議及びオンライン(YouTube)
YouTubeアーカイブ配信は こちら 【英語版】 【日本語同時通訳版】
| 3月7日 | ||
| 時間 | 内容 | 登壇者 |
| 10:00-10:30 | 開会挨拶 |
|
| 10:30-11:30 | 基調講演・ディスカッション Session 1: 気候変動 |
|
| 11:30-12:30 | 基調講演・ディスカッション Session 2: ヘルス |
|
| 13:30-14:30 | 基調講演・ディスカッション Session 3: 海洋 |
|
| 14:45-15:30 | ディスカッション Session 4: 社会と科学 |
|
| 15:30-15:35 | 閉会挨拶 |
|
| 3月8日 | ||
| 12:10-12:45 | 共同記者会見 | YouTubeアーカイブ配信は こちら |
4. 各セッション概要
(1)基調講演・パネルディスカッション - Session 1: 気候変動
冒頭、小池俊雄Gサイエンス学術会議2023「気候変動」執筆対応小分科会委員長より、共同声明を説明した後、森章委員の進行で、ミシェル・トランブレカナダ王立協会科学アカデミー会長、三村信男茨城大学特命教授、イアン・ウィギンズ英国王立協会国際部長が基調講演を行いました。
続いて、小池委員長、トランブレ会長、三村教授、ウィギンズ部長をパネリスト、高橋潔委員をモデレーターとしてパネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションでは、①具体的にどのような研究協力を進めていくべきか、②科学者は社会とのコミュニケーションをどのように進めていくべきかについて議論されました。①については、衛星などを活用した観測などICTの活用・統合、データの国際的な標準化、気候の影響評価の精緻化、データが不足するグローバルサウスの開発、共同研究の動機付けなどについて発言がありました。②については、原住民などローカルレベルのソリューションの統合、政策立案者と科学者が共同して進めるプログラムの開発、ファシリテーターの制度化、メディアの活用などについて発言がありました。
(2)基調講演・パネルディスカッション - Session 2: ヘルス
冒頭、郡山千早Gサイエンス学術会議2023「ヘルス」執筆対応小分科会副委員長より、共同声明を説明した後、アラン・フィッシャーフランス科学アカデミー会長、マリア・クリスティーナ・マルクッツォイタリア・リンチェイ国立アカデミー国際担当役員による基調講演が行われました。
続いて、フィッシャー会長、マルクッツォ役員、飯島勝矢委員、和氣純子委員をパネリスト、郡山副委員長をモデレーターとしてパネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションでは、ケアサービスの提供に係るインセンティブ、高齢者の尊重と社会的に平等なケア負担、柔軟・持続可能な会保障制度の構築、若年層の活躍の場の確保などについて発言がありました。
(3)基調講演・パネルディスカッション - Session 3: 海洋
冒頭、原田尚美Gサイエンス学術会議2023「海洋」執筆対応小分科会委員長より、共同声明を説明した後、ジェラルド・ハウグドイツ科学アカデミー・レオポルディーナ会長、マルシア・マクナット全米科学アカデミー会長による基調講演が行われました。
続いて、原田委員長、ハウグ会長、マクナット会長、大越和加委員、安田仁奈委員をパネリスト、西本健太郎委員をモデレーターとしてパネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションでは、海洋における基礎研究の重要性、海洋の危機的状況や脱炭素化がほとんど進んでいない等の研究成果の普及・啓発、観測システムを活用した責任主体の明確化等について発言がありました。
(4)ディスカッション - Session 4: 社会と科学
梶田隆章日本学術会議会長、ナリンダー・クマール・メヘラインド国立科学アカデミー副会長、ピーター・グラックマン国際学術会議会長、フィリッポ・ロッシグローバルヤングアカデミー理事、マルクッツォ役員をパネリスト、高村ゆかり副会長をモデレーターとして、パネルディスカッションが行われました。パネルディスカッションでは、研究がどのように社会に役に立つのかという意識の重要性、共同声明で特に強調すべき点、Gサイエンス学術会議2024やサイエンス20との連携などについて発言がありました。
過去の共同声明
※PDFファイルを表示させるには、Adobe Reader が必要です。お持ちでない方はこちらから無償でダウンロードできます。







