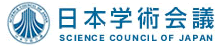代表派遣会議出席報告
会議概要
- 名 称
(和文) 国際宗教学宗教史学会 理事会
(英文) International Association for the History of Religions (IAHR), Executive Committee Meeting - 会 期
令和元年9月13日~17日(5日間)
- 会議出席者名
藤原聖子
- 会議開催地
ギリシャ・デルフォイ
- 参加状況
参加国名 : デンマーク、スイス、ドイツ、フィンランド、スウェーデン、リトアニア、ギリシャ、インド、ニュージーランド、メキシコ、カナダ、米国、日本 (米国からの1名はカメルーン出身のアフリカ宗教学会会長)参加国数 : 13か国参加者数 : 20名(うち日本人 : 2名)
- 会議内容
国際宗教学宗教史学会 拡大理事会
議題 「本学会の目的の再定義と将来構想」
本学会の理事会は毎年開催されるが、今回は1950年に設立された本学会の歴史に残る特別な会合となった。本学会の目的を再検討し今後の方針を議論するために、歴代の会長、事務局長、世界大会開催者代表、学会誌編集委員長、主要地域学会の会長を招いて拡大理事会として開催されたためである。議論の結論もまさに本学会のターニングポイントとなるものになった。
そのことを象徴的に示すのが学会の名称変更である。本学会の英文名称はInternational Association for the History of Religionsだが、これをInternational Association for the Study of Religionsに変更することを、来年の世界大会時に開催される総会に提案することが決議された。この決議がどのような意味を持つのかを以下に少し詳しく記したい。世界の学術の中で宗教学が今どのような状況にあるのかを示す格好の事例と考えられるためである。
これまで名称がHistory of Religionsだったのは、宗教学の成り立ちに深く関係している。宗教学は近代以前から存在するキリスト教神学とは異なり、宗教を経験科学的に研究する近代的学問分野の一つである。それはまず19世紀後半ヨーロッパにおいて、古代オリエント・アジアの聖典や神話の比較文献学的研究として始まった。このためにヨーロッパの宗教学者は、自らをhistorian of religionsとみなすようになり、そのような研究者たちが本学会を立ち上げたために、その自己規定が国際宗教学会の名称にも反映されたのである。この場合のhistoryとは、単に過去の宗教を研究対象として選んだことを意味するだけでなく、思弁的神学に対して実証性を重んじる経験科学としての人文学であることを示唆していた。
しかしこの名称は、本学会が20世紀後半に拡張するにつれ、本学会の会員の研究範囲に合わないものになっていった。本学会の拡張は、宗教学の研究分野としての広がりと加盟学会の地理的拡大の双方において起こった。一方では、宗教学は、文献学・歴史学だけでなく、社会学・心理学・人類学等の社会科学的方法をも包み込んでいった。それに従い、本学会の会員の研究方法も領域も多様化した。他方では、本学会の加盟学会はヨーロッパの外にも徐々に広がり、各国学会の他、1992年には地域学会としてアフリカ宗教学会が、2005年には南・東南アジア宗教学会が設立された。
1点目の拡張、宗教学の研究の多様化を受けて、本学会の名称としてhistoryよりも包摂的な呼称、たとえばStudy of Religionが良いのではないかという意見が事あるごとに出るようになった。変わったのは方法論だけではない。1990年代後半から、ヨーロッパの宗教学は、古代オリエントやアジアといった過去の「他者」の宗教のテキスト研究から、現代ヨーロッパの宗教の実態の研究へと、研究対象の面でもシフトし始めた。つまり、古代インドの神話の研究よりも、現代のグローバル化の中でヨーロッパに流入する移民との宗教的共存といったアクチュアルなテーマを扱う研究が増え始めたのである。少なくとも学会の内部では伝統的な研究の意義も認められ続けたが、History of Religionsという呼称はあまりに狭いと思われるようになったのである。(なお、本学会の日本語訳を「国際宗教学宗教史学会」としてきたのは、まさにこの問題に対処するためであった。「宗教史学会」では歴史学会の一分野のように見えてしまうため、宗教研究の幅広さを表す「宗教学」と併記するという表記法を1950年代から続けているのである。)
しかし、Study of Religionへの変更を良しとしない会員も一定数存在してきた。そのような会員にも二種類ある。一方で旧来の呼称に何らかの理由で思い入れがあるため、名称変更に反対する者もいれば、他方でStudy of Religion(文字通りには「宗教の研究」)では神学をも包摂し、経験科学としての宗教学のアイデンティティを保てないという理由で、Science of ReligionまたはHistorical and Scientific Studies of Religionという名称を代替案として提案する者も現れた。
この議論には2点目の拡張、すなわち本学会の加盟学会の地理的拡張も絡み、問題を複雑化してきた。アジア・アフリカの開発途上地域の宗教学は、実用的な社会的要請の高いテーマを研究する傾向がある。たとえば、諸宗教を研究する目的は、宗教の相互理解を促進し、諸宗教の共存を実現することであるといった考え方や、HIV感染予防に宗教はどう寄与できるかといった社会課題解決型の研究である。制度的基盤が十分ではない中で、人文社会科学が成立するには、社会的ニーズに応える研究が必要であるという事情は十分に理解できるものである。しかしそのような“science for society”型の研究は、純粋科学としての宗教学の存立基盤を危うくするものであるという考えが、前述の科学派の会員の一部には非常に強い。そのような会員は、「社会に役立つ宗教学」は、しばしば「社会に役立つ宗教の推進」を伴い、したがって、宗教学者が宗教を広める宗教家になってしまうと警戒してきた。つまり、そうなっては宗教学が神学に回帰してしまうと言うのである。よって、前述のScience of ReligionやHistorical and Scientific Studies of Religionという名称を推す会員は、“science for society”型の研究者を、本学会の会員として認めるべきではないと主張してきた。しかしそのような方針をとるならば、本学会の会員や役員の構成において地域バランスをとることが極めて難しくなる。また、“science for society”型の研究者は開発途上国だけでなく、研究とアクティヴィズムがしばしば融合するアメリカ合衆国にも多い。よって、“science for society”を排除するならば、本学会の加盟学会の範囲は限りなくヨーロッパ宗教学会に同一化していくのである。ヨーロッパではキリスト教神学が大学での一大権威であり、それに対抗して、新たな宗教研究の場を切り開いてきたヨーロッパの宗教学者たちが、純粋科学としての宗教学のアイデンティティを守ろうとするのも、理解できなくはない。だが、それに同調しては、本学会は収縮し、世界規模の「国際学会」とは言えなくなってしまうだろう。
(なお、以上は複雑な状況をわかりやすく説明するために「ヨーロッパ」「アメリカ」「開発途上国」をそれぞれ一般化しているが、実際には、同じヨーロッパでも、純粋科学派は北欧に多く、それに比すと英独には包摂派が多い。また、アメリカ・カナダの一部には強硬な純粋科学派が存在する。さらに、アフリカ・アジアでも国によって、信仰や政治上の理由から宗教を研究するよりも、遺跡・文化財研究として宗教を研究する方が自由に取りくめる場合があり、そのような研究はヨーロッパの経験科学的なhistory of religionsに近いというケースもある。)
このような対立状況の中で、日本の役員の役目は、その間に立ち、インクルージョンとダイバーシティを旗印に、本学会の分裂を防ぐこと、そして最大のイベントである5年に1度の世界大会をscience for science派もscience for society派もともに満足させるような、両派それぞれの最高の研究成果を競えるような場にすることであった。すなわち、純粋科学派の意見にも理解を示し(それは基礎研究の基盤が脅かされる昨今の[一部を除く]世界的な状況に照らしても必要である)、かといって神学寄りの研究者、アクティヴィストの研究者を本学会から排除するのではなく、むしろ包摂することで、宗教と宗教研究の世界的な状況についてより深い認識に達することが本学会の目ざすべきところではないかと提言することであった。
その提言を作成する段階で参考にしたのは、この会議の準備期間と同時期に議論が進行した、学術会議の『日本の展望2020(仮)』である。20XX年の未来図を示し、そこに到るためのシナリオを作成するというバックキャスティング方式は、本学会程度の規模で、5年ごとに期が変わるという国際組織の行動計画を立てる上では、非常に有効であるということに気づいた。そこで “IAHR Scenarios: 2020 and Beyond”という、論点整理のための文書を作ることを日本の役員から会長に申し入れ、2名の欧米の役員の協力を得て作成、理事会当日にプレゼンを行った。結果的には、1名のもっとも強硬な科学派の賛同を得ることまではできなかったが、この文書により、純粋科学派のシナリオと包摂派のシナリオの両方の利点と欠点について、全員で議論を尽くすことが可能になり、最終的には、両方を統合したシナリオが採用され、本学会の目ざすところを更新することができた。本学会の名称も、Science of ReligionよりもインクルーシヴなStudy ofに、しかもreligionを複数形にすることにより、さらにダイバーシティを可視化するStudy of Religionsにすることに決まった(正式な変更は、来年の総会時に行われる予定)。
「無宗教」な人が多いと言われる日本だが、宗教学の蓄積はあり(大学での宗教学講座設置の早さは欧米の大学に引けを取らない)、日本の宗教学者と本学会との関わりも長く大きい。1950年代から現在まで継続して役員を送り込み、1958年には初の非西洋圏での世界大会を東京・京都で開催、2005年には学会史上最大規模の世界大会を東京で開催してきた。この度の歴史的なターニングポイントとなった理事会でも、日本からの2名(事務局長を代行する報告者と、2005年大会の主催者の代表として招聘された委員)はしかるべき役割を果たすことができたと考えられる。
会場並びに宿泊所となったEuropean Cultural Centre of Delphiは、1977年に欧州評議会の後援のもと、デルフォイをヨーロッパの文化的中心地にするためにギリシャ文化省が設立した施設である。古代ギリシャの世界観において、デルフォイは世界の中心(臍)であった。国際学会の来し方と行く末を考え、民主的に議論し、再生を図るにはまたとないロケーションと施設であった。
次回開催予定 : 令和 2年 8月末