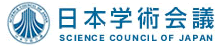代表派遣会議出席報告
第23回世界哲学会議とFISPの運営委員会の報告
世界哲学会議(World Congress of Philosophy =WCP)は5年に1度、世界中の哲学者たちを集めて開催される。その運営母体がFISP(Federation Internationale des Societes de Philosophie国際哲学会連合)で、開催地はFISPの総会で決定され、現地の組織委員会とのあいだで「契約」が締結され、それに基づいて立案され、運営される。立案を担当する「プログラム委員会」は双方から選ばれた委員によって構成され、全体会議、シンポジウムのテーマを選び、招待講演者を決定するだけでなく、分科会のテーマの設定、そのそれぞれの責任者の選定を行う。会議の基本的な事柄(全体テーマ、日程、会場、ロゴのデザインなど)については、FISPの運営委員会も決定に参与する。このように、この会議はFISPと地元の運営委員会との密接な協力関係によって、企画運営されている。
今回は Philosophy as Inquiry and Way of Life (探究と生き方としての哲学) を全体の統一テーマとして、8月4日~10日の1週間、ギリシアのアテネ大学において開催された。西洋哲学の源流の地であるギリシアでの会議として、その全体テーマの設定にも、古代ギリシアの哲学の基調が反映されている。それは歴史的な意味だけではなく、現代社会の投げかける問題に対する哲学の取り組みを照射するという意味をも含んでいる。準備期間の5年の間に、ギリシアの経済危機という予期しなかった深刻な状況を経験した。運営委員会のなかにも危惧の念が生じたが、客観的な状況判断に立つマックブライド会長(William McBride 米国)の強い意思のもと、最終的な決断によってギリシア開催が敢行され、大きな成功を収めた。8月上旬のアテネは高温が懸念されるが、地元のひとも今年は例年になくマイルドと言う気候で、日中の日差しは肌を刺すように暑いが、朝夕は涼しく感じられるほどだった。会場は、市の中心にあるキャンパスではなく、哲学部が入っている東側丘陵の斜面を占めるゾグラフォス(Zografos)のキャンパスだった。ここは入口から会場の建物まで、上り坂を歩けば小一時間かかるほど広大なエリアである。毎日、相当頻繁に、麓の地下鉄の駅から会場まで、シャトルバスが運行された。
初日の夕刻には、オープニング・セレモニーがヘロデス・アッティコスで開かれた。ここは紀元2世紀にアクロポリス南の斜面につくられた音楽堂もしくは公会堂で、今も夏の野外劇の上演に使われている。セレモニーとしては、FISP会長、ギリシアの組織委員長ブドーリス教授、ギリシアの首相の挨拶、アテネ交響楽団のコンサートがあった(首相の挨拶に対してはブーイングと少数派の拍手が起こった)。この他、特別セッションが、プラトンのアカデメイア、アリストテレスのリュケイオン、古代に民会の会場だったプニュックスの丘、『パイドロス』の対話の展開されたと考えられている場所の4か所で、夕刻に持たれた。これらは、全体のテーマ設定とともに、アテネでのWCPの開催を印象深いものにするイヴェントと言える。
参加者は、登録者ベースで3114名に及んだ。これは空前の成功と言えるのではないかと思われる。もっとも多かったのは、当然、ギリシアで、678人が参加した。以下多い国を挙げると、ロシア384、米国224、中国185、インド144、ドイツ104、日本とメキシコがそれぞれ101と続く。印象的なのはヨーロッパからの参加者が比較的少ないことで、ドイツを除くと100人以上が参加した国はなく、スペイン78、イタリア77、トルコ59が多く、現代哲学で存在感を見せるフランスは42名、イギリスは13名に過ぎない。このことは、現代の哲学地図について、またこの会議の性格について、何かを物語っているように思われる。
参加者の数は、使用言語の問題と密接に連関している。FISPの公用語は英語とフランス語だが、WCPではこのほかにドイツ語、ロシア語、スペイン語、中国語が公用語として認められており、さらに開催地の言語がこれに加わるので、ギリシア語を加えた8か国語が今回の公用語であった。公用語とは、その言語での研究発表ができる、というだけではない。全体会議(plenary sessions)、「シンポジウム」、FISPの総会では、これらの言語相互の間の同時通訳のサービスがある。わたしなどは、公用語を増やすことは(中国語は今回からそこに加わった)、研究発表会をバベルの塔にする、という危惧を覚えるし、運営上も、同時通訳のための出費が多額に上るので、これを問題視する意見もある。しかし他面において、公用語が設定されているために、上記の多くの参加者があった、という面も否定できない。
研究発表の数についてのデータは、得られていない。目算で2000を超えるのではなかろうか。その内容を総括することは、おそらく不可能であり、少なくともわたしにはできない。研究発表の形態にはいくつもの種別がある。最も一般的なのは分科会で、75のテーマが設定されている。多くは前回のものが踏襲されているが、プログラム委員会は前回の登録者の数を見て、入れ替えを行っている。次にオーガナイザーの構想とイニシアティブによって構成されるセッションが二種類ある。ひとつは invited sessions と呼ばれているもので、FISPの運営委員が中心となって構成される。もうひとつは「ラウンドテーブル」で、公募される。この2つの間に実質的な違いはない。更に、FISPに加入している国際学会によるセッション、ポスターセッションもある。日本哲学会は、前回のソウル大会のときから、中国、韓国の哲学会と共同のセッションを試みており、今回は納富信留氏(慶應義塾大学)がオーガナイザーとなって「哲学とアジア的価値」のラウンドテーブルが持たれた(日本からは、日本哲学会会長の飯田隆日本大学教授が参加した)。
招待講演には3つのカテゴリーがある。全体会議(plenary session)、シンポジウム、寄付講座による講演(endowed lecture)である。この最初の2つは、ことばのうえでは(つまり理念的には)相当に異なるが、実際の運営のうえでは大きな違いは見られない。全体会議は朝一番に行われ、当然、その時間帯にほかのセッションはない。シンポジウムは(上記の特別セッションは別として)同じ時間帯かその次の時間帯に置かれる(同時に他のセッションが置かれることもある)。全体会議は4つ、シンポジウムは7つ設定され、スピーカーは地域的なバランスを考えて選ばれている。それは単に機会の平等ということではなく、文化的背景の違いが異なる哲学思想をはぐくむ、という考え方によるものと思われる。今回は、日本から4名の招待講演者が選ばれた。かつてないことなので、この方々の報告を主に紹介したいと思う。そこに全体の基調を読み取ることができると思う。一般の投稿論文の場合、会議の全体テーマとの関連は問われないが、全体会議やシンポジウムは、それぞれのテーマを設定する際にすでに、全体テーマに即して考えられ、スピーカーもそれを意識しているからである。
まず野家啓一氏(東北大学)は「哲学と科学」の全体会議(5日)において、「東日本大震災後の哲学と科学」について講演した。その概要は次の通りである。"Science" は単数名詞(uncountable)の「学問」の意味の用法と、複数の「科学」のそれがある。歴史的には前者から後者へと展開してきたが、両者は共存している。19世紀後半に西洋からこれを学んだ日本は、当時の潮流に従い、また、日本の置かれていた状況の力にもよることだが、もっぱら「科学」としてこれを捉え、実利的な効果と結び付けてきた(福沢の「実学」)。東日本大震災は、このような科学的文明に関する批判的議論を巻き起こした(寺田寅彦の予言的洞察、梅原猛の発言)。この災害が明らかにしたことの核心は、科学が "trans-science" (Alwin Weinberg) の段階に入っているということである。"trans-science" の特徴は、科学の問題でありながら、科学によっては答えられないものをはらんでいることにある。その典型としての環境汚染や核のゴミの問題に見られるように、それは世代間の倫理の問題を惹起する。われわれの生きている「リスク社会」(U. Beck)は組織的無責任なシステムの性格をもつ。そこで、"trans-science"の哲学、科学者の倫理が問題となる。キー概念の頭文字を組み合わせた R. Merton のCUDOS、市場の論理に巻き込まれた科学者に対する揶揄としての J. Ziman のPLACEに対して、野家氏はRISKを提唱する。Regulatory deliberation (自己規制的な熟慮)、intergenerational ethics (世代間倫理)、social accountability (社会的説明責任)、knowledge-product liability (知の所産に関する責任)である。
このセッションは、司会者(M. C. Galavotti氏)の導入も平明、S. Haack 氏の科学哲学そのものを反省する原理的講演も刺激的で、全体として、わたしのような門外漢にとって非常に興味深いものであった。野家氏の講演も感銘をあたえ、終了後も人々に囲まれた。
その翌日(6日)の早朝には、「テクノロジーと環境」のシンポジウムがあり、村田純一氏(立正大学)が「FUKUSHIMAから何を学ぶか。テクノロジーの多次元性」と題して講演を行った。表題がすでに示すように、村田氏の問題意識は、野家氏のそれと重なるところが多い。はしなくも、科学と、テクノロジー、環境の問題が深くつながっていることを印象付けることとなった。村田氏の論旨の概要は次のごとくである。FUKUSHIMAの災害の要求しているのはテクノロジーの新しい哲学である。何故なら、その事故はテクノロジーが閉じたシステムではなく、社会的、文化的、自然的な環境と結ばれ、それらによって構成されている多次元的な在り様のものであることを示しており、この多次元性への視点の欠如が事故の重要な原因と考えられるからである。かつてテクノロジーは独立した機械のように表象され、環境を決定する要因と見なされていた。ベイコンの技術観を典型とするこの見方は長く続いたが、1970年ころから、社会構成主義的なアプローチが擡頭し、テクノロジーの内側に切り込むようになってきた。そこで暴き出されてきたのは、テクノロジーが技術的要因だけでなく、経済、政治、文化、価値などの社会的要因によっても構成されていることで、テクノロジーと社会は相互に規定しあう関係のものである。この見方を拡張して考えるならば、真剣な translation の仕事なしに、或るテクノロジーをその元の環境から別の環境に移植することはうまくいかないことは明らかである。実際、アメリカ・GEで作られた基本設計をそのままにして、福島に原子力発電所を建設すること自体に問題があった。さらに根本的には、事故が必ず予期せざる仕方で起こる、ということがある(Tennerの言葉として、"technology bites back")。予期せざる、不可避的な、理解不能の仕方で起こるのが「正常な事故 normal accidents」(Perrow)であり、このことは現代の「リスク社会」(ベック)の状況そのものである。テクノロジーの哲学は、理解できないものを理解するというパラドックスの性格を帯びる。根本的に重要なのは態度の変更であり、「失敗への健全なおそれ」を持つことである。日本では原子力政策をはじめとして、「安全」を「安心」という心理的効果の問題にすり替えてきたこと、それが事故後もなお続いていることに、村田氏は警鐘を鳴らす。
村田氏の報告も野家氏のものと同様、そのアクチュアルな問題意識によって、多くの聴衆を引き付けた。両氏の報告が科学、技術、環境という現代特有の問題を多く含む主題に関わるものであるのに対して、関根、納富両氏の主題は、「よりよく生きるための哲学」という全体テーマに、言い換えれば古典的な哲学の基調とのつながりがより濃厚である。「哲学と宗教」というシンポジウム(5日)の主題は、旧約学者で倫理学の教授という関根清三氏(東京大学)にとって恰好のものと言える。残念なのは、体調を崩された氏がアテネに来られなかったことだが、氏は朗読付きのパワーポイントのプレゼンテーションで責を果たした。その概要を次に記す。まずは宗教の側から哲学の必要性が語られる。すなわち、経典を読むうえで、それを聖典として絶対視しようとする信仰の立場からのアプローチと、それをテクストとして批判的に検討する学問的アプローチがあるが、いずれにも限界がみとめられる。前者は党派的一面的なものであり、後者は価値の観点を欠いている。ただ哲学的な解釈だけが、十全な理解を与えてくれる。その例として関根氏は旧約聖書の2か所、すなわち「伝道の書」の「一切は無」という言葉と、「第二イザヤ書」に見られる「身代わりの贖罪」という思想を挙げる。前者については、ニーチェ(『力への意志』)を参照することによって、著者コヘーレスが真の意味においてニヒリストであったことが分かるし、後者についてはM・ウェーバー(『古代ユダヤ教』)に照らして、第二イザヤの思想を明晰に理解することができる、とする。次に、いわば逆の面から、哲学が個々の宗教の違いを超える共通項を捉えうるということを語るために、西田の神論(「場所的論理と宗教的世界観」)を取り上げる。西田はまず、人格神の概念を相対的絶対という矛盾を犯すものとして批判する。しかし、他のものとの関係を欠けば、神は無力である。そこで神の人間との関係は、外なる相対者との関係ではなく、内なるもろもろの相対者との関係でなければならない。すなわち神は絶対的矛盾の自己同一であり、人間を含む万象は神の中にあり、一切のものは神の自己否定によって存在を得ている。この万有内在神論(panentheism)にはヘーゲルの影響が見られるものの、すべての宗教経験に共通の基盤を与える思想である。そのことを示すために、関根氏は、創造神話、父による子の殺害、悪人の救済(親鸞)というドグマをこの思想によって説明してみせる。更に、西田の思想の展開ともみられる八木誠一の非実体的な愛の磁場としての神という概念に言及している。このように、それぞれの側からの考察を重ねたうえで、宗教と哲学=倫理学の関係を次のように総括する。宗教は主客を超える真の神に関わる実践であり、倫理学は秩序に基づく共存の道の探究である。両者はともに働いて、人間存在を全体化し、形成する。
以上三氏の研究報告を通覧して、どなたも、それぞれのセッションの主題について論ずるだけでなく、会議全体のテーマに応えるとともに、日本の哲学的伝統や文化状況への言及、あるいはむしろそのような文化的背景から立論されていることが分かる。最後に紹介する納富氏の報告は、上記の特別セッションのひとつで、「今日における古代ギリシア哲学の有効性(relevance)」を主題とするシンポジウムにおいてなされたが、これはプラトンのアカデメイアの遺跡でおいて行われた(6日)。特別セッションに参加するには予約が必要ということを知らなかったために、わたしはこれを聴くことができなかった。そこで、原稿によって論旨を紹介するが、それは、古代ギリシア哲学(プラトン)-「探究と生き方としての哲学」-日本の哲学的伝統-アカデメイアの精神の4つの観点もしくはモチーフが、緊密に織りなされたものになっている。
納富氏は、その「"ideal" のプラトン的観念とその東アジアにおける受用」という報告を、アカデメイアにおけるプラトンの教育が、受講者の能動的な参与を慫慂し、自説への批判を積極的に認めていた、という事実から説き起こす。そこで、プラトンの学説のなかでも特に批判の多かったイデア(もしくは形相)(Form)説に焦点を絞り、最も有力な3つの批判を取り上げて、このプラトン的精神において反駁するのが氏の構想であり、この駁論において、西周が idea の訳語として工夫し、東アジアにおいて共有されるようになった「理想」の概念が参照されている。有力な批判の3つとは、アリストテレス、ニーチェ、ポパーによるものである。アリストテレスはイデアを永遠の感覚的事物と見なし、無用であるだけでなく、間違った考えである、と批判する(『形而上学』第2巻)。ニーチェは、キリスト教とともに観念論的形而上学が「背後世界」を想定することによって、生命に敵対するデカダンスを生んできたと非難する(『この人を見よ』のなかの「人間的…」の節)。ポパーは、プラトンにおけるイデア説に3つの機能を認める。基本は歴史が一般的に堕落への傾向をもつことに対する対抗的な意思であり、不変のイデアを考えることで、純粋に学問的な知が、また変化を理論的に説明することも可能になる。更には社会の変化を圧しとどめる社会工学に道を拓く。この第3の可能性を専制と全体主義につながるものとして、(自らの苦難の経験に照らして)ポパーは烈しく攻撃した(『開いた社会とその敵』)。
ここで納富氏は、西周の「理想」が、イデアの意味から離れて日常語化したことを捉え、「理想」がプラトン的イデアといかなる関係があるのか、という問いを立て、それに則して、以上の3つの批判にこたえようとする。まず、アリストテレスについて言えば、プラトン哲学のなかで、かれが殆ど言及していないのはエロス説である。ところが、それこそがプラトンの思想のなかで影響力の強かったものであり、イデアはエロスを惹起し、われわれの超越を促すという意味をもっている。アリストテレスのイデア批判はこの面を無視している。次にポパーだが、かれが理想国家を考えることが全面的にイデア説に依存していると考えたのは、イデアと理想を同一視したからである。しかし、理想はわれわれが心中に思い描き、言葉で表現するものという点で、現実とつながっており、理想の追求が理性的議論を生む。事実、理想国家の議論は歴史を通して連綿と続けられてきた。今日においてイデア説に対するもっとも強力な反論は、ニーチェのものである。超越的イデアなしに理想があり得ない、と考える点でプラトンと同じ考え方をしながら、理想が無用であると考える点で、かれはプラトンと根本的と対立する。このように3者に対して反論を試みたうえで、日本における「理想」に論及し、戦時下に国粋主義者がプラトンを援用した事実を指摘しつつ、それを超える思想として、現実を見るには絶対的真理を求めることが必要とした田中美知太郎(『ロゴスとイデア』)を挙げている。
以上4本の招待講演の紹介は、このWCP全体の性格を映し出すものと思うが、これを補う情報として、9月17日の朝日新聞夕刊に島薗進会員の寄稿した「EUと福島 問われる倫理」というリポートを挙げておく。島薗氏は2つのセッションを紹介している。ひとつはハバーマスの講演、もうひとつは山脇直司氏(星槎大学)の企画によるラウンドテーブル「福島後の哲学と倫理」である。前者はEUの視点に立ちつつ、グローバル経済の富裕者支配のもとでの倫理的連帯性の困難な状況を論じ、後者は科学と倫理の関係を照射する、という趣旨である。このラウンドテーブルの時間帯は、上記した村田純一氏のシンポジウムと同じで、さらに河野哲也氏(立教大学)の企画した「場所の現象学と環境倫理学」とも重なる、という盛況であった。伊藤邦武氏(京都大学)や末木文美士氏(国際日本研究センター)は分科会の責任者を務められたし、ラウンドテーブルを企画した日本の哲学者も多かった(ひとつだけ、これも納富氏の企画になるものだが、日本哲学会の協賛による「日本における哲学」を挙げておこう。スペイン、香港、および日本の哲学者が参加し、活発な討論が行われた)。
また、仄聞するところによれば、河野氏の周辺では、WCPを日本で開催したいという機運が高まっている。困難ではあるが、頼もしい動向と思う。それは日本の多くの哲学者がWCPに参加し、その経験のなかから盛り上がってきた意思である。その人びとが、自らの経験を多くの、特に若い世代の同僚たちに共有してほしいと考えたうえでの強い願望である。その経験とはなにか。自らの仕事に対する自負、発信の意志のあることは間違いない。しかし同時に、世界のなかでの自らの位置を知り、日本の哲学と文化をいわば相対化する、という発見を伴う経験でもあり、更に異文化の同僚たちとの絆の形成でもあるだろう。しかし、それは、経験してみなければ、実はわからない。だからこそ、日本で開催したい、という願望なのである。WCPよりはずっと小さいが、わたし自身、2001年に国際美学会議が幕張で開催された際に、その責任を担った経験がある。その経験は、その後のわたしの学問に決定的な影響を残している。WCPの日本開催の機運がさらに高まるなら、微力ながらサポートしたいと思っている。ただそのためにも重要なことは、WCPに参加するだけでなく、世界哲学の日や、哲学オリンピアードなど、FISPのさまざまな活動に積極的にかかわることではないかと思う。
最後に委員会と総会について報告しておこう。FISPの委員会はWCPから次のWCPまでが任期である。旧委員会は会議の始まる前日(8月4日)に、新委員会は最終日(10日)の午前に開かれた。旧委員会は、もはや重要案件はなく、新委員会はまだない、という状況なので、報告すべきことは少ない。旧委員会では、毎年繰り返される報告だが、ユネスコとの関係の現状が、会長と事務局長から詳しく説明された。米国の国連関係諸機関への拠出金の停止によって、ユネスコは予算の25%を削減せざるを得なくなったことが根底にあり、特に人文系に対する締め付けがきつい(現事務局長の考え方によるところも大きい)。この間、ユネスコは本部建物に入居している関連NPOから家賃を徴収することを決議した。そのひとつがCIPSH(the International Council for Philosophy and the Human Sciences)で、FISPはそれに加盟しているだけでなく、FISP本部の住所はこのCIPSHの部屋を間借りするかたちになっている。予想される家賃は負担可能な額を超えるもので、CIPSHはユネスコ以外からの寄付金を集める方策などと考えているが、楽観をゆるさない。問題は、全体的な文化状況のなかで、哲学や人文学の意義をどのように見るか、ということにかかっている。
総会は9日に開催された。プログラムの上では、早朝から夕刻までとなっていたが、幸いなことに昼過ぎには終わった。その重要議題は、次期会長、運営委員の選出、次回のWCPの開催地の決定である。日本は投票権を2票もっており、日本学術会議哲学委員会の野家啓一委員長と、日本哲学会会長の飯田隆氏が出席して投票権を行使した。会長選には、Dermot Moran 氏(アイルランド)とBhuvan Chandel氏(インド)が立候補していたが、投票の結果、モラン氏が次の5年間の重責をになうことになった。2018年のWCPについては、北京とリオ・デ・ジャネイロが立候補したが、投票によって北京開催が決定した。FISP運営委員で、数年前ハーヴァード大学から北京大学に移籍したTu Weiming (杜維明) 教授の存在感と説得力あるスピーチが、大きな要因と思われた。リオについては、2023年の開催権を認めてはどうか、という意見も出されたことを付言しておく。運営委員の選挙の結果、わたしも次期を続投することになった。更に新委員会(10日)において、事務局長に Luca Scarantino教授の続投が圧倒的支持で承認されたほか、Tanella Boni教授(コートジボワール)、Lourdes Velazquez教授(メキシコ)とともにわたしは副会長に指名された。また、財務担当者としては、Guido Kung教授(スイス)の続投が承認された。また、次回の委員会は、来春、北京で開かれることになった。
付記 この報告には3枚の写真を添付してある。1枚はアカデメイアにおける納富氏の、もう1枚は大講堂における野家氏の発表風景である。この大講堂は、特別セッションを除くすべての全体会議、シンポジウムの会場であった。そして3枚目は、WCPを記念して発行された切手と封筒のセットである。プラトンの像とイオニア式の柱頭(おそらくエレクテイオンのもの)がデザインされている。
 |
 |
 |
アカデメイア遺跡における納富信留氏の講演 | 大講堂での野家啓一氏の講演 | WCP記念切手と封筒 |