| |
|
 |
1 会議概要
1)名 称 (和文) 第33回万国地質学会議
(英文) The 33rd International Geological Congress
2)会 期 平成20年8月6日?14日(9日間)
3)会議出席者名 松本 良(東京大学)、北里 洋(JAMSTEC)、斉藤靖二(生命の星・地球博物館)、小川勇二郎(筑波大学)、奥村 晃史(広島大学)、佃 栄吉(産総研)、加藤碵一(産総研)、西脇二一(奈良大学)ほか
4)会議開催地 オスロ近郊のリルストローム(ノルウェー)
5)参加状況(参加国数、参加者数、日本人参加者) 113カ国 参加者6260人 日本人は150人程度
主な参加国:ノルウェー(960人)、ロシア(505人)、アメリカ(394人)、中国(376人)、イタリア(267人)、ドイツ(261人)
6)会議内容
万国地質学会議 (IGC)は、国際地質科学連合(IUGS)が4年毎に開く学術大会である。IGCの開催期間中には、IUGSの執行委員会や評議会などの事務会議も開かれ次回の開催地や執行委員の改選が行なわれる。
学術大会(IGC)は毎日特定のテーマを決められ、そのテーマに関連するセッションが配置されていた。
・日程及び会議の主な議題
8月5日 執行委員会
IUGSとIGCの組織的統合のため定款と附則を改訂する件につき議論。評議会への提案を審議。
8月6日 開会式(ハロルド国王臨席)
IUGS-IGC統合評議会:IUGSに加盟する国際学術団体の活動報告とIUGSの役員の改選があった。議長(President)の選挙は先送りされた。
IGCテーマ1:OneGeology
各国の地質調査所などが連携し、世界の地質図を同じ基準とスケールで統合編集しようというプロジェクトに関連して地球の進化や地質図成立の歴史などが議論された。
8月7日 IGCテーマ2:生物と進化
生命の起源、大量絶滅などについて多くの発表があった。
8月8日 IGCテーマ3:古気候と人類の進化
時間スケールを第四紀に絞り、環境-気候―人類進化など今日的課題についての発表と討論。
8月9日 IGCテーマ4:地質災害
スマトラ地震―インド洋津波以降、地質災害に如何に寄与するかは地質科学の主要な責務との認識が高まっている。日本からの発表が注目を集めていた。
8月10日 科学セッションな休みでワークショップや地質見学会が行なわれた。 IUGS-IGC統合評議会 6日の評議会の続き。次期のUGS会長にアルゼンチンのAlberto Riccardiが選ばれ、8年後のIGCの開催地は南アフリカのケープタウンと決まった。定款の改訂は承認されなかったが、前回フィレンツェでIGC-IUGSの統合と必要な定款の改訂は出来ているので、今回の提案が承認されなかったことは組織運営上、大きな問題にはならない。
8月11日 IGCテーマ5:水とエコシステム
今日、水資源は国際的に大きな問題に成って来た。とくに低開発国での水資源解決は焦眉の課題である。
8月12日 IGCテーマ6:資源
石油価格の高騰で象徴的に示される資源の枯渇と偏在の問題について、最新のデータが提示され議論された。
8月13日 IGCテーマ7:将来のエネルギー
テーマ6に続いて人類の持続的発展のためのエネルギー確保の問題が多面的に議論された。
8月14日 IGCテーマ8:惑星科学
宇宙科学の発展により惑星の情報が大量に取得できるようになり、地質科学は惑星をも研究対象とするようになった。生命の起源、地球の起源と進化の理解が飛躍的に進むものと期待される。
閉会式
ボランティアや優秀は発表の表彰、次回開催のオーストラリアからのメッセージなどあり、和やかに閉会した。
・会議における審議内容・成果
(添付資料1:評議会報告を参照されたい)
・会議において日本が果たした役割
(添付資料1、添付資料2を参照されたい)
・その他特筆すべき事項(共同声明や新聞等で報道されたもの等)
(添付資料2を参照されたい)
2.会議の模様
添付資料2を参照されたい。
次回開催予定 2012年8月 ブリスベーン(オーストラリア)
|
|
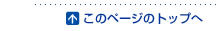
|
|
|