代表派遣会議出席報告
会議概要
- 名 称
(和文)国際土壌科学連合(IUSS)中間会議
(英文)International Union of Soil Sciences(IUSS)Inter-Congress Meeting - 会 期
2024年10月21日から2024年10月24日まで(4日間) - 会議概要
- 会議の形式:対面、オンライン、運営委員会、シンポジウム、現地検討会
- 会議の開催周期:定期(4年に1回)
- 会議開催地、会議場:中華人民共和国南京市、南京国際会議場
- 会議開催母体機関:国際土壌科学連合(International Union of Soil Sciences:IUSS)
- 会議開催主催機関及びその性格:
国際土壌科学連合(International Union of Soil Sciences:IUSS)、国際学術会議(ISC)加入国際学術団体
- 参加状況:
参加国・数:日本、中国、韓国、台湾、米国、メキシコ、カナダ、ポーランド、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、ノルウェー、
ハンガリー、ナイジェリア、南アフリカ、計15か国1地域。参加者数:38名
日本人参加者:
犬伏和之・東京農業大学教授(IUSS Honorary member)・日本学術会議
信濃卓郎・北海道大学教授(IUSS Commission 4.2 Chair)・北海道大学
前田守弘・岡山大学教授(IUSS Commission 3.2 vice-Chair)・日本土壌肥料学会
早川智恵・宇都宮大学助教・宇都宮大学 - 次回会議予定(会期、開催地、主なテーマ):
会期:2026年6月7日~12日
開催地:南京国際展示場
準備組織:IUSS及び中国土壌学会
テーマ:人類が共有すべき未来の土壌
- 会議の学術的内容
- 日程と主な議題:
10月21日:開会式(IUSS会長挨拶、中国土壌学会長挨拶、中国科学普及研究所長挨拶、基調講演4題)、国際フォーラム(IUSS Division 1~4および水田土壌ワーキンググループ国際シンポジウム)
10月22日:大気CO2増加加温試験水田および中国科学院土壌研究所視察
10月23日:IUSS理事会及び次回会議会場視察
10月24日:IUSS理事会 - 提出論文:
・水田大豆連作土壌肥沃度の変遷(西田瑞彦・東北大学教授・IUSS水田土壌ワーキンググループChair、オンライン)
・水田における生分解性プラスチックの温室効果ガスと作物生育への影響(筆者)
・火山灰水田からのメタン放出に及ぼす施肥の影響(早川)
・中国水田における施肥窒素の適正化(Xu Zhan・中国科学院土壌研教授)
・水田土壌のリン酸供給に及ぼす水管理の影響(Luisella Celi・イタリアチューリン大学教授)
・水田へのセレニウム施用と水稲生育収量への影響(Benito Purwanto・インドネシアガジャマダ大学教授・IUSS水田土壌ワーキンググループvice-Chair、オンライン)
・水田における有機物管理のジレンマ(Pil Joo Kim・韓国慶尚大学教授)
以上は水田土壌ワーキンググループのシンポジウム
・水田における重金属汚染と鉄の生物地球科学からのイノベーション(Fangbai Li・中国広東省農業科学院博士)
・植物コンケン由来物質による消火脱窒の制御(Weiming Shi・中国科学院土壌研究所教授)ほか。
以上が基調講演
- 学術的内容に関する事項:
創立100周年を迎えたIUSSが取り組む食料生産基盤である土壌機能の維持強化と砂漠化や温暖化など地域・地球環境の変動に対応し資源保全を両立させるため、最新の技術や関連分野との連携を進めている。土壌の健全性Soil Healthの機構解明と社会的認知を強化する取組が、欧米各国などで進んでいる。世界各地で特徴的な土壌をIUSSが毎年選定する取組が始まり、今年は戦禍にさらされているウクライナのチェルノーゼムが選定された。FAO(国際連合食糧農業機関)やUNESCO(国際連合教育科学文化機関)と連携し土壌教育の強化の取組も進展している。
- その他の特記事項:
① IUSS名誉会員として8名が選出され、元会長の小崎隆氏(現日本学術会議連携会員・本分科会委員)が7人目の日本人として加わった。
② 次期会長の選挙が行われ3名の候補者から前英国土壌学会長のBruce Lascelles氏が選出された。
③ 次期役員選挙のための選挙管理委員会が本年末までにDivisionごとに設置される予定である。
④ Division 1では本年6月に北海道で開催された土壌分類に関する国際会議SCC2024について、また、Division 2では、本年10月に筑波で開催された土壌有機無機相互作用に関する国際会議ISMOM2024について開催状況などが報告された。Division 3では、水田土壌ワーキンググループが中国土壌学会と日本土壌肥料学会と共催で本会議初日に開催された上記シンポジウムが開催されたことなどが報告された。Division 4では、信濃卓郎氏がDivision Chairに代わってIUSS100周年記念大会のシンポジウムや世界土壌デーに連携して12月に日本などで開催予定のシンポジウム予定などを報告した。
⑤ 基調講演の1つで紹介された「重金属汚染土壌の修復技術」や現地視察した「大気CO2増加加温試験水田」の計測技術は日本側との共同研究成果が反映されており、今後さらなる展開が期待される。
⑥ 土壌教育や土壌保全に向けた情報発信がIUSS会長、前会長を中心に世界各地で精力的に進められていることが報告された。
⑦ 次回会議は2026年6月7~12日に中国・南京で開催される予定で、開催予定会場を視察し大小の会議場やポスター会場などを視察した。シンポジウム課題がDivisionごとに中国側Vice-Chairと連携して、また現地巡検が中国国内の土壌や農業形態ごとに複数コースの準備が進められていることが報告された。その次の会議は2030年7月14~19日にカナダ・トロントで開催予定であり、その準備状況が報告された。さらに、その次の2034年に開催予定の会議候補地として、ドイツ、ポーランド、チェコがドイツ・ライプツィヒでの開催を提案した。
- 日程と主な議題:
所見
今回のIUSS中間会議への中国側の準備・対応は概ね期待通りであった。またIUSS会長、前会長の活動、特にIUSS100周年記念大会を中心に進められた記念誌の刊行やFAOやUNESCO、ISCとの連携も進展しており、食糧安全保障や土壌教育の強化など重要課題への土壌科学の貢献が更に重視されると期待される。
名誉会員としてIUSS元会長の小崎隆氏が7人目の日本人として加わり、現在6名に上るIUSS役員を選出している日本側の一層の貢献も期待されている。一方、ワーキンググループの改廃が議論されており、30年以上の活動を続けている水田土壌ワーキンググループ(Chair西田氏)のシンポジウムが今回、中国土壌学会との共催で実現したが、今後さらなる活動強化が必要である。
 |
||
| 水田土壌ワーキンググループの国際ワークショップ | ||
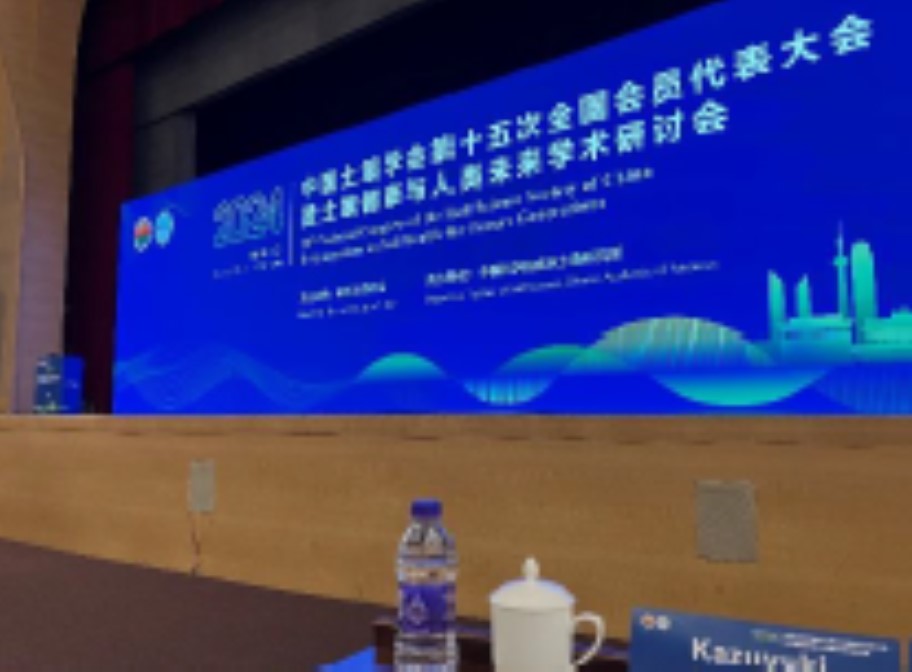 |
 |
 |
| 南京国際会議と試験水田視察 | ||



