1 開催概要
(1)会 議 名 :(和文) 第16回コンピュータ医用画像処理ならびにコンピュータ支援治療に関する国際会議
(英文) 16th International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention (MICCAI 2013)
(2)報 告 者 : 第16回コンピュータ医用画像処理ならびにコンピュータ支援治療に関する国際会議組織委員会共同委員長 森 健策、 佐久間 一郎
(3)主 催 : 第16回コンピュータ医用画像処理ならびにコンピュータ支援治療に関する国際会議組織委員会、日本コンピュータ外科学会(共同主催)、日本学術会議(共同主催)
(4)開催期間 : 2013年9月22日(日)~ 9月26日(木)
(5)開催場所 : 名古屋大学豊田講堂・野依学術交流館・IB電子情報館(愛知県名古屋市)
(6)参加状況 : 39ヵ国/地域・933人(国外791人、国内142人)
2 会議結果概要
(1) 会議の背景(歴史)、日本開催の経緯:
第16回コンピュータ医用画像処理ならびにコンピュータ支援治療に関する国際会議は、コンピュータ医用画像処理ならびにコンピュータ支援治療学会 (The Society of Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention; MICCAI Society)が毎年開催する会議である。1998年にアメリカ合衆国ボストンで第1回目の会議が開催されて以来、名古屋大学での開催で16回目を数え、コンピュータ医用画像処理ならびにコンピュータ支援治療分野で最も権威のある国際会議である。日本での開催は2010年9月19日に第13回会議の直前に開催された理事会において、正式に第16回コンピュータ医用画像処理ならびにコンピュータ支援治療に関する国際会議を日本で開催することが決定された。準備段階から、日本コンピュータ外科学会は当該会議の日本開催の誘致活動を進めてきており、開催の正式決定を受け、2010年10月27日に開催された日本コンピュータ外科学会理事会にて、当該国際会議の運営に協力することを正式決定し、国内組織委員会を組織し、その委員会が開催の任にあたることになった。
(2) 会議開催の意義・成果:
日本での開催は2002年に東京大学にて開催して以来11年ぶりである。当該分野におけるエース級の研究者が一堂に日本で会し、コンピュータを利用した医用画像処理技術ならびに治療支援技術に関しての最先端の議論が展開されることになった。これらを通じ、当該分野の発展が期待される。
この会議を日本で開催することは、我が国で活発に行われている医工連携研究プロジェクトの成果を全世界の研究者に大きくアピールすることにもつながったと考える。多くの研究者の医工連携研究への参画を促すとともに、本分野における我が国の研究者、とりわけ博士課程学生を含む若い研究者が、最新の研究を行っている世界中の研究者と直に交流できるまたとない機会を提供することにつながったと考える。本会議の参加者は海外からの参加者が8割であり、日本からの参加者には大きな刺激になったと考える。将来的には、我が国におけるコンピュータ医用画像処理ならびにコンピュータ支援治療分野の発展へとつながると強く考える。
(3) 当会議における主な議題(テーマ):
医用画像認識理解とコンピュータ支援治療の高度な融合に関する研究が数多く行われた。主な議題としては、生理学的モデリング、コンピュータ支援治療、脳イメージング、画像位置合わせ、画像アトラス、画像再構成、臓器動きモデリング、機械学習などがある。
(4) 次回会議への動き:
新しい医用画像処理手法に関する研究とそれを利用した新たな治療方法の開発は、本会議が目的としている普遍的なテーマであり、来年度以降も本会議が目指そうとした研究に関する情報交換を目的とした会議が開かれる予定である。2014年以降の開催地を以下に示す。
- 2014年 アメリカ・ボストン
- 2015年 ドイツ・ミュンヘン
- 2016年 トルコ・イスタンブール
- 2017年 カナダ・ケベック
(5) 当会議開催中の模様:
本国際会議は、以下のような日程で実施された。
- 9月22日(日)
- 午前 ワークショップ・チュートリアル・チャレンジ
- 午後 ワークショップ・チュートリアル・チャレンジ
- 夜 レセプション
- 9月23日(月)
- 午前 開会式、本会議(口頭発表、招待講演)
- 午後 本会議(口頭発表、ポスターセッション)
- 9月24日(火)
- 午前 開会式、本会議(口頭発表、招待講演)
- 午後 本会議(口頭発表、ポスターセッション)
- 夜 バンケット
- 9月25日(水)
- 午前 本会議(口頭発表)
- 午後 本会議(ポスターセッション、特別セッション、アワード贈呈式閉会式)
- 9月26日(木)
- 午前 ワークショップ・チュートリアル
- 午後 ワークショップ・チュートリアル
- 夜 謝恩会
また、これらの日程における詳細は以下のようになる。
- (a) 開会式
会期2日目(本会議1日目)に開催された開会式では、共同主催団体である日本学術会議副会長春日文子先生、日本コンピュータ外科学会副理事長佐久間一郎(第16回国際コンピュータ医用画像処理ならびにコンピュータ支援治療に関する国際会議組織委員会共同委員長)に開会に当たり挨拶をいただいた。また、安倍晋三内閣総理大臣、大村秀章愛知県知事、河村たかし名古屋市長からの祝辞を披露させていただき、参加者の大多数を占める海外からの参加者へのWelcomeメッセージを紹介した。
- (b) 本会議口頭発表
本会議の口頭発表セッションは、
- Oral Session 1 Physiological modeling and computer assisted intervention
- Oral Session 2 Brain imaging
- Oral Session 3 Registration and atlas construction
- Oral Session 4 Microscopy, histology, and computer aided diagnosis
- Oral Session 5 Image reconstruction and motion modeling
- Oral Session 6 Machine learning in medical image computing
の6つのセッションからなり、合計37本の論文に対して活発な議論が行われた。口頭発表では、特に 最先端の診断治療工学の中でも核となる画像処理手法について活発に議論が行われた。各発表ともに12分の持ち時間であるが、質疑応答が活発に行われたことは特筆に値すると言えよう。
- (c)ポスター発表
ポスター発表はMICCAIにおける重要な発表形態の一つであり、口頭発表と同じように重要視される。各ポスター発表ともに2時間30分の時間を確保し、十分な量のコーヒーなどをサーブすることで、活発な議論が行われるよう工夫した。ポスター発表の際には、大きな液晶モニタの前で、発表者が30秒ほどのその概要を発表し、その後各ポスターブースに移動する形態をとった。これにより、数多くあるポスター発表全体の概要を把握しながら、各ポスターで詳細を確認できるようにした。ポスター発表は、以下のカテゴリで行われており、非常に活発な議論が行われた。MICCAIではこれまで、CT/MRIの画像処理が主であったが、今回のMICCAIでは病理顕微鏡画像処理に関する論文が増加していることは特筆に値する。
- Poster Session 1 (本会議第1日目)
- Imaging, reconstruction, and enhancement I
- Registration I
- Machine learning, statistical modeling, and atlases I
- Computer aided diagnosis and imaging biomarkers I
- Intraoperative guidance and robotics I
- Microscope, optical imaging, and histology I
- Cardiology I
- Vasculatures and tubular structures I
- Brain imaging and basic techniques
- Diffusion MRI I
- Brain segmentation and atlases I
- Poster Session 2 (本会議第2日目)
- Motion modeling and compensation
- Segmentation I
- Machine learning, statistical modeling, and atlases II
- Computer aided diagnosis and imaging biomarkers II
- Physiological modeling, simulation, and planning I
- Microscope, optical imaging, and histology II
- Cardiology II
- Brain segmentation and atlases II
- Functional MRI and neuroscience applications I
- Poster Session 3 (本会議第3日目)
- Imaging, reconstruction, and enhancement II
- Registration II
- Segmentation II
- Physiological modeling, simulation, and planning II
- Intraoperative guidance and robotics II
- Microscope, optical imaging, and histology III
- Diffusion MRI II
- Brain segmentation and atlases III
- Functional MRI and neuroscience applications II
- (d)招待講演
本会議一日目には、名城大学の福田敏男先生から、医療分野におけるシミュレーション技術についての紹介があった。本会議二日目には、理化学研究所の宮脇敦先生から、細胞レベルの新しいイメージングに関する講演があった。
- (e)スペシャルセッション
MICCAI分野における今後の研究について、これまでにMICCAIのGeneral Chairをとつめた著名な研究者による分析などが行われた。特にマルチスケール技術については、各人の共通する認識であった。日本人もこのスペシャルセッションで発表し、将来における本分野の形づくりに貢献したといえる。
- (f) ワークショップ・チャレンジ・チュートリアル
本会議前後各一日で、併設ワークショップ、チュートリアル、画像処理アルゴリズムを競うチャレンジが開催された。2日間で合計31のワークショップ・チャレンジ・チュートリアルが開催された。これらは、公募によって得られた開催プロポーザルを、MICCAI 2013 Workshop Chairsによって審議し、どのワークショップ、チャレンジ、チュートリアルを開催するかを決定した。これらのワークショップでは、本会議におけるテーマとするにはまだ少し早い段階の研究が数多く発表されており、将来的にMICCAI本会議の柱となるような研究討論の場になると思われた。
- 9月22日
- 4th International Workshop on Machine Learning in Medical Imaging
- MICCAI Workshop on Computational Biomechanics for Medicine VIII
- Mathematical Foundations of Computational Anatomy
- 2nd MICCAI Workshop on CLinical Image-based Procedures (CLIP 2013): Translational Research in Medical Imaging
- Computational Diffusion MRI (CDMRI'13): a MICCAI Workshop
- The 2nd MICCAI-Workshop on Computer Assisted Stenting (MICCAI-STENT)
- Mathematical Methods for Brain Connectivity
- Modeling and Monitoring of Computer Assisted Interventions (M2CAI)
- 5th International Workshop on Abdominal Imaging: Computational and Clinical Applications
- 3rd International Workshop on Multimodal Brain Image Analysis (MBIA 2013)
- The 6th International Workshop on Medical Imaging and Augmented Reality (MIAR 2013)
- Stochastic Modeling for Medical Image Analysis
- Introduction to Analysis and Applications of Molecular Imaging
- Visual tracking and 3D reconstruction for computer assisted interventions: state-of-the-art and challenges
- MICCAI DTI Tractography Challenge on Peritumoral White Matter Anatomy for Neurosurgical Decision-Making
- NCI-MICCAI 2013 Challenges: Automated Segmentation of Prostate Structures (ASPS) and Multiparametric Brain Tumor Segmentation (BRATS)
- MICCAI Grand Challenge: Assessment of Mitosis Detection Algorithms 2013
- 9月26日
- Computational Methods and Clinical Applications for Spine Imaging
- MICCAI Workshop on Mesh Processing in Medical Image Analysis
- The Sixth International Workshop on Systems and Architectures for Computer Assisted Interventions (SACAI)
- Workshop on Medical Computer Vision: Large Data in Medical Imaging
- MICCAI workshop on Bio- Imaging and Visualization for Patient-Customized Simulations
- Statistical Atlases and Computational Models of the Heart (STACOM’13)
- Workshop on High Performance Computing: HPC-MICCAI
- MICCAI workshop on Medical Content-Based Retrieval for Clinical Decision Support
- The Fifth International Workshop on Pulmonary Image Analysis
- MICCAI 2013 workshop on Breast Image Analysis
- The R programming language: a statistical foundation for reproducible studies in medical image analysis
- Intelligent imaging: Linking MR acquisition and processing
- Common architecture for algorithm development and deployment
- MICCAI Challenge Workshop on Segmentation: Algorithms, Theory and Applications
- MICCAI Grand Challenge on MR Brain Image Segmentation (MRBrainS13)
(6) その他特筆すべき事項:
本会議の誘致にあたっては、2009年から2年間、日本開催を表明した2008年から数えると3年間にわたる招致活動を実施した。日本開催の意義、名古屋開催の意義、また、国際会議場ではなく名古屋大学の豊田講堂で開催する意義を注意深く説明することで日本誘致に成功したと考える。また、為替相場の変動等、アジアで開催することによる参加者数の減少(実際には杞憂であったが)を考慮し、様々なシミュレーションを実施したことがMICCAI理事会での開催に関する信任にいたったものと考える。
3 市民公開講座結果概要
(1)開催日時:2013年9月22日(日)
(2)開催場所:名古屋大学豊田講堂
(3)メインテーマ:「医用画像認識理解とロボット外科の高度な融合」
サブテーマ:「マイクロマシンは未来医療を拓けるか」「外科医の新しい目と脳と手を創る」「計算解剖学とその診断・治療への応用」
(4)参加者数、参加者の構成:65名 (出席者名簿しかないため構成は不明)
(5)開催の意義:我々国民の「健康」への関心は年々高まっている。一方、近年の計算機を利用した診断支援・治療支援に関する研究の進歩は著しい。これまでには無かった新しい取り組みや診断法、治療法が開発されている。このようなコンピュータを利用した医療支援の現在と未来の医療について、市民に分かりやすく伝える場を提供することが本市民講座の意義であると考える。
(6)社会に対する還元効果とその成果:コンピュータを利用した医療支援の研究において、大きく3つの視点から国内の著名な研究者3名に講演をお願いした。
1つ目は、ロボットによる手術支援に関する話題である。内視鏡手術のロボット手術は保険が適用されるようになり、新しい治療法の一つとして関心を集めている。さらなる未来の注目は、マイクロマシン(極小のロボット)の活用である。マイクロマシンは我が国の得意分野の一つであり、細胞レベルのミクロの世界の治療を可能にする未来の技術である。世界的先駆者である東京大学の生田幸士先生からご講演を頂き、実際のビデオを駆使して小学生にも十分理解できる内容となっていた。
2つ目は、外科治療の最新技術についてである。脳外科手術の第一人者である東京女子医科大学の村垣善浩先生をお招きし、MRI下での脳手術や覚醒下脳手術について、その利点と治療効果を分かりやすく解説頂いた。
3つ目は、コンピュータによる診断・治療支援の新しいパラダイムである「計算解剖学」について、国立高等専門学校機構理事長の小畑秀文先生にご講演頂いた。計算解剖学は、CTやMRIといった医用画像からあらゆる人体解剖を自動的に認識し、実際に切り開いて解剖したのとほぼ等価な情報を抽出する新しい基盤技術である。これを用いて、誤診や異常部位の見落としを防ぐ診断支援システムや手術支援を行うシステムを開発している。これらの現状と未来展開について分かりやすくご紹介頂いた。
(7)その他:本市民講座開催に当たっては、新聞広告などを通じた宣伝等を行った。
4 日本学術会議との共同主催の意義・成果
日本学術会議との共同主催による意義・成果であるが、予算的な問題の解決もさることながら、我が国が本分野の研究において力を入れていることを諸外国にアピールできたのではないかと考える。本会議が対象とする内容は、平成25年6月7日閣議決定の「科学技術イノベーション総合戦略」に合致するものである。ここでは、重点的な取組として、(2-1)がんの革新的予防・診断・治療法の開発と、(4)医薬品、医療機器分野の産業競争力強化(最先端の技術の実用化研究の推進を含む)が記載されている。この内容としては「非侵襲・低侵襲の検査・早期診断技術、放射線治療技術、ナノバイオデバイス、手術支援ロボット、診断支援等に用いる医療用ソフトウエア等、医療機器の開発を進めるとともに、バイオ医薬品等の革新的医薬品の創出に向けた研究開発や支援体制の構築を進める。」とある。日本学術会議がMICCAI 2014の共同主催となることで、我が国の本分野のおける研究開発の取り組みを重視していることを十二分にアピールできたのではないかと考える。
 |
 |
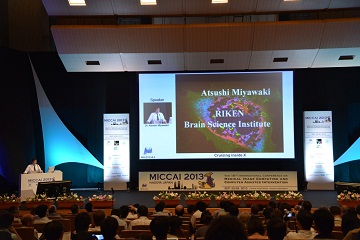 |
| (開催の挨拶を述べるMICCAI Society President Alison Noble教授) |
(主催者挨拶を行う春日文子副会長) |
(宮脇先生による特別講演) |
 |
 |
 |
| (福田教授による特別講演) |
(口頭発表の様子) |
(ポスター発表) |
 |
 |
 |
| (Award Ceremonyの様子) |
(Welcome Reception) |
(バンケットの様子) |
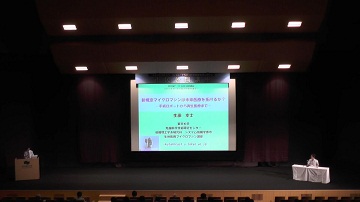 |
|
|
| (市民公開講座生田先生による講演) |
|
|
|