| |
|
 |
1 名 称 2011年太平洋学術評議会および第22回太平洋学術会議
(2011 PSA Council and Executive Board Meeting and 22nd Pacific Science Congress)
2 会 期 2011年6月13日~17日( 5日間)
3 会議出席者名 山内 晧平(第二部会員、PSA分科会委員長)
谷口 旭(PSA分科会委員)
4 会議開催地 マレーシア国クアラルンプール市
5 参加状況(参加国数、参加者数、日本人参加者)
太平洋学術評議会:14ヶ国・地域から24名、うち日本から6名
第22回太平洋学術会議:44ヶ国・地域から800名、うち日本から16名
6 会議概要
日程及び会議の主な議題
・6月13日 参加登録、評議会諸資料および学術会議要旨集当配布
・6月14日 開会式典、基調講演第一および第二、11分科のシンポジウム、並行して太平洋学術評議会(主な議題:前回評議会以降の活動・財務等の報告と承認、第11回中間会議報告、第12回中間会議開催要項の提案と承認、第23回会議開催地に関する討議)
・6月15日 基調講演第三および第四、14分科のシンポジウム、懇親会
・6月16日 基調講演第五および第六、15分科のシンポジウム、並行して太平洋学術評議会(主な議題:2011-2013期執行理事等の選出、科学作業委員会活動報告と承認、今後の科学活動のあり方に関する討議、財務強化に関する討議)
・6月17日 基調講演第六および第七、2分科のシンポジウム、8領域の一般研究発表会、並行して太平洋学術評議会(主な議題:決議案文の作成と確定)、閉会式
会議における審議内容・成果
太平洋学術評議会:審議事項は上記「日程及び会議の主な議題」に掲げた通りで、主な審議内容は次の通り。
・PSA新役員(平成23年6月18日から2年間):会長 Nancy LEWIS(米)、副会長 Chang-Hung CHOU (台湾)、財務担当監事 土屋 誠(沖縄地区)、事務局長(タイ国から指名される予定)
・加盟分担金の変更:加盟国分担金を増額して財務強化を図ることに関して討議し、平成25年7月11-15日に行われる次回の太平洋学術評議会で賛否の採決をすることとした。したがって、日本もそれまでに諾否を決定しなければならない。
因みに過去10年間据え置かれてきている現行の日本の単位額はUS$10,000.-で、これをUS$11,250.-へ引き上げることの諾否が問われる。
会議において日本が果たした役割
・前PSA会長である黒川 清(元日本学術会議会長、現PSA分科会委員)が“Age of Uncertainty: Have We Become Wiser?”の基調講演をした。
・日本学術会議の農学委員会PSA分科会および食料科学委員会水産学分科会が中心となり“SUSTAINABLE FISHERIES MANAGEMENT UNDER THE WARMING CLIMATE REGIME” のシンポジウムをコンビーンし、日本から3件の講演を招請した。
・植松光夫東京大学教授が、IGBPの中核プロジェクトであるSOLASの日本研究班 JAPAN SOLASを代表して“COASTAL ZONE MANAGEMENT UNDER RAPID URBANIZATION”のシンポジウムのコンビーナのひとりとして貢献し、自らも講演した。
・大城 肇琉球大学副学長が中心となり“POLICIES AND ECONOMICAL ISSUES ON E-LEARNING AND E-HEALTH IN PACIFIC”のシンポジウムをコンビーンし、日本から5件の講演を招請した(プログラムによる)。
・PSA分科会委員長山内晧平会員が塚本勝巳東大教授に太平洋学術会議畑井新喜司メダル(Shinkishi Hatai Medal)を授与した。
その他特筆すべき事項(共同声明や新聞等で報道されたもの等)
太平洋学術協会は、人文社会科学から自然科学、医科学等の全領域をカバーし、加盟国も小さな島嶼国から巨大な国まで、科学技術が発展の途上にある国から高度な科学技術先進国まであるという、極めて多様性が高い学術協会である。
その協会が主催する太平洋学術会議もまた、多数の分科会シンポジウムが並行して開催される多様な研究集会である。したがって、隔年交互に開催される太平洋学術会議と太平洋学術中間会議のたびに幅の広い共通テーマを一つ掲げて統一性を表徴させている。
今回は“Meeting the Challenges of Global Changes”であり、次回は“Human Security of the Pacific”とすることになった。ただし、これらのテーマは緩やかな標語であり、シンポジウムやワークショップの内容を拘束するものではなく、コンビーナやスピーカはそれぞれ
の分野に固有の課題を掲げ、多様な国から多様な科学者が参集できるように工夫している。
7 会議の模様
・上記のような多様性に鑑みて、日本から選出する評議員(3名)に人文系の人を加えるべきである。
・本会議はマレーシアの科学アカデミーが主催したものであるが、背景にはマレーシア連邦政府の強い支援があった。開会式では科学技術及刷新省大臣が歓迎の挨拶をし、懇親会では首相のメッセージが紹介された。会場のKuala Lumpur Convention Center (KLCC)は、
国威をかけて設置し運営している壮大な施設であり、大きなボールルームのほかに10以上のシンポジウム等を同時並行して開催することができるフロアーが2層、個別の会合や展示等を行う大会場や小会議室などが「無数」にあった。今回の会議の全プログラムが1フロア
ーで進行し、昼食や茶菓も同一フロアーで摂ることができたので、800名を越える参加者は常に接触することができ、Communication を最重要視するPSAの会議の実を高めることができた。因みにKLCCは、連邦政府が建造し、国営企業であるペトロナスが指定管理者になっ
て運営しているとのことであった。
・次回開催予定:平成25年 6月11-15日、フィジー国スバ市の南太平洋大学で開催することが決定した。会議場は、日本のODA援助で同大学に設置されたPacific ICT Center の予定。
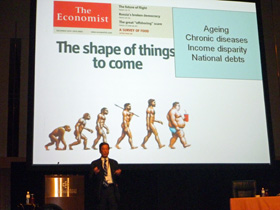
基調講演(Age of Uncertainty: Have We Become Wiser?) 黒川清PSA分科会委員(前PSA会長、元日本学術会議会長)

畑井メダルの授与式(左:Congbin Fu PSA会長 中央:畑井メダル受賞者:塚本勝巳東京大学大気海洋研究所教授 右:山内晧平日本学術会議PSA分科会委員長)
|
|
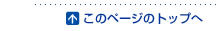
|
|
|