| |
|
 |
1 会議概要
1)名 称 (和文)国際北極科学委員会(IASC評議会およびIASC関連会議)
(英文)International Arctic Science Committee (Council Meeting and it’related meetings)
2)2008年3月26日?4月2日(8日間)
3)会議出席者名 神田啓史
4)会議開催地 ロシア、コミ共和国 シクティフカル共和国
5)参加状況(参加国数、参加者数、日本人参加者):18か国 各国代表1名で18名、オブザーバを含めて35名 日本人1名
6)会議内容
北極科学委員会評議会 (IASC Council )は3月28日に開催された。
現在の加盟国は18か国であるが、来年度参加予定のスペインが手続き中である。評議会の主な議題は新しいIASCの組織改革と戦略(IASC structure and strategy to support science development)であった。
・日程及び会議の主な議題
3月26日 太平洋北極グループ(PAG: Pacific Arctic Group) 会議
3月27日 サイエンス・デイ
北極科学サミット週間と第4回北方社会及び環境に関する会議とのジョイントシンポジウムとして開催、300人ほどの参加があった。
3月28日 国際北極科学委員会オープンセッション及び評議会
オープンセッションでは主として新しいIASCの組織改革について説明、評議会では、戦略グループ会議を挟んで議論があった。最終的にいくつかの修正を加え、IASCの新しい組織改革の採択に入った。
3月29日 プロジェクト・デイ
議題はIPY後の科学的協力、インフラストラクチャー、評価に関する取り組み(Post-IPY)について講演と質疑応答
3月30日 午前 北極海洋科学会議(AOSB)
IASCの新しい組織改革の中でのAOSB管理、戦略計画、予算、AOSBの将来
3月30日 午後 北極観測管理者フォーラム(FARO)
ロシアの新原子力砕氷船、韓国の砕氷船,”ARAON” の建造、ドイツの砕氷船, ”Aurora Borealis”のシップタイム、新しい航空機“POLAR
5”の運航計画
3月31日 コモン・デイ
ASSW参加者の共通理解
4月1日 分科会
スバールバル諸島における韓国との共同観測の可能性についての意見交換
4月2日 分科会
カナダ、エルズミア島におけるサポート体制、新基地構想に関する意見交換
・会議における審議内容・成果
新しい国際北極科学委員会の組織改革が本年度の主な議題であった。この改革の動きは2006年から始まった。すなわちIASCの1996-2005年の10年間の活動に対するレビューと将来にわたっての戦略の評価を得るために、
「レビューと戦略の国際専門委員会」を設けて準備してきた。この専門委員会による勧告は、今日の極地科学が十分に反映された新しい構造改革、新しい技術、データマネージメント、教育、パブリックアウトリーチ、
北極評議会、とくに社会科学との連携、ASSWの活性化等に関することであった。これらの勧告に従い、今回の会合はIASC運営委員会(Executive
Committee)が(A)評議会、運営委員会、事務局、(B) 科学常置委員会、 (C) 活動グループを柱とした構造改革を提案した。
これらの新しい組織に対して、各国に関係する最も重要なことはこれまでよりも多くの代表を委員として参加する必要があるということである。すなわち、新しい評議会は正・副の代表で2名づつ、科学常置委員会は現在、
5つの分科会を考えているが、それぞれについて、各国より2名づつの代表を送ることが提案された。これによって常置委員会だけでも10名の代表を送ることになる。結果的には、長い議論の末、科学常置委員会は
(1)海洋システム、(2)陸上システム、(3)雪氷圏システム、(4)大気システム、(5)社会システムの5分科会が決定した。これらの5つの分科会の議長は各国のIASC代表によって推薦を受けることになった。
・会議において日本が果たした役割
IASC Councilにおいては議題の最も重要な案件が新しいIASCの組織改革であった。日本の立場として、IASCは現在の方向を反映した組織改編と、ASSWの実質的な役割、機能を発揮できる体制が必要である案に賛成した。
また、IASCは単に自然科学ではなく、社会科学の主導的役割をすることを重要と受け止め、IASCが国際北極社会科学連合(IASSA)と提携することに賛同した。
・その他特筆すべき事項(共同声明や新聞等で報道されたもの等)
最近の地球規模の気候温暖化によって地球規模の海水準を調整する上での氷床の重要性と氷床のモデルが一致しない等に関して、IASCはSCAR、WCRP-CliCと連携し、
来るセント・ピータースバーグでワークショップを開催することが決まった。そこで、IASC評議会はCliCを支援するためにWCRP-IASC-SCAR MoUを取り交わした。
さらに、IASCの運営委員会は上記の評価・戦略委員の勧告を受けて、IASC と国際北極社会科学連合(IASSA)との間で協力を重要と受け止め、LoA (Letter of Agreement)を交わした。
IASCの組織として科学常置委員会が置かれることになったが、海洋システム分科会と北極海洋科学会議(AOSB)との関連について議論された。
AOSB代表のヘラルド ロエングによってIASCの新しい組織に対するAOSBの見解について示された。これまでに米国のNSFによってAOSBの事務局が支えられてきた資金は、
今後、途絶えることになり、これまでの存続は難しい状況である。メンバーシップ、期間、経費については早急に検討が必要であり、18か月後にIASC組織がスタートする前にメンバ?シップが示されるであろう。
また、AOSB代表は結本委員会においてはAOSBという委員会名を残して、科学常置委員会の海洋システムの中に組み込む形で活動することを希望し、検討の結果、
科学常置委員会の海洋システムの議長はこれまでのAOSBの議長が務めることに決定した。
2.会議の模様
今回提案されたIASCの新しい組織改革は各国において、大きな議論を巻き起こした。2年ほど前から、改革の必要性が叫ばれていたが、原案が形になって現れたのは数カ月前ほどである。
まだまだ、議論の余地は必要であると感じたが、南極のSCARとの歩調合わせもあり、7月のSCAR/IASCオープンコンファレンスを前にして、IASCとしては、今回の評議会で決定に踏み切った。
このことにより、日本からはIASC2名、科学常置委員会10名、合計12名の代表を送るという事態になった。日本として北極を本格的に考える時期に来ていることを痛感し、
国内の北極観測体制、対応をどのようかじ取りしていくかが今後の我々に課された問題であろう。
本年度の会合は、シクティフカルという北部シベリア地域が会場になっていたこともあり、ASSWへの参加はそれほど多くはなかった。とくにこれまでのサイエンス・デイはASSWの主要な科学的成果を発表する場という位置づけであったが、
今回はロシアの北方社会及び環境に関する会議と合同でシンポジウムが企画されたため、ほとんどはロシア人によるロシア語による発表であった。北極全体というよりはやや、地域的な活動や環境保護の内容が多かった。
しかし、温暖化を代表とする北極の問題はシベリア等の地域での諸問題がクローズアップされていることは大いに意義のあることである。
昨年も感じたことであるが、韓国、中国は国策として北極観測を進めていることが強く印象に残った。それぞれ、5名ずつの参加者があり積極的に外交を行っていた。
とくに両国は砕氷船を北極に展開するという共通点があり、諸外国はそのシップタイム、共同観測に期待している。 残念ながら日本は北極域に船を持っていく計画はJAMSTECの
「みらい」がIPYの機会に調査することだけが決まっているが、韓国、中国のような国策として、極点に近いところまで調査対象にしている計画はない。
次回開催予定 2009年3月23日?28日、ノルウェー ベルゲン市 |
|
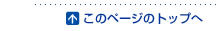
|
|
|