| 委員会名 | 荒廃した生活環境の先端技術による回復研究連絡委員会 |
| 報告年月日 | 平成15年5月20日 |
| 議決された会議 | 第991回運営審議会 |
| 整理番号 | 18期−36 |
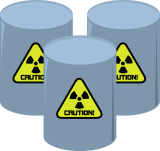
| 放射性物質による環境汚染の予防と環境の回復 |
|||||||||
|
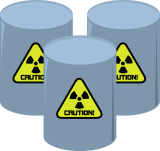 |
||||||||
![]()
| 20世紀の科学における大きな発見の一つとして、放射線と原子力(核分裂)エネルギーがあり、その利用は産業の発展と人間生活の向上に大きく寄与したが、一方では核兵器が開発されそれがわが国に投下されて惨禍を招き、またその開発の場および原子力発電所の事故によって環境が放射性物質で汚染し、従事者と一般公衆が放射線被曝した。幸いこれまでわが国では放射性物質による重大な環境の汚染の例はないが、幅広く放射線と原子力エネルギーが利用されるなかで、まずはその予防を第一にし、しかし万一それが発生した場合の対策について汚染の回復まで含めて考えておく必要がある。 |
![]()
| 核兵器の開発の場や原子力発電所の事故による大きなものから、放射性同位元素利用上の事故など小規模のものまでいろいろな形で放射性物質による環境の汚染例があるが、それらを総合的に調査し、学術的視点で深く分析し、さらに環境回復の方法まで追求することはほとんどなかった。また、海外での環境回復に対するわが国からの積極的協力も少なかった。 わが国では、(株)JCOの臨界事故により、原子力防災の法規、体制、設備などは充実し、大がかりな訓練も行われているが、それに関連する研究は少ない。また、放射線と原子力エネルギーの利用を通じ、放射性物質による環境の汚染防止と回復に関する研究開発もまだまだ不十分である。有害化学物質など非放射性物質による環境汚染は現実に多発し、その修復も行われているが、放射性物質による環境汚染の防止と回復の研究開発との交流はきわめて少なかった。 |
![]()
| これまでに世界とわが国で発生した放射性物質による環境汚染事故の中で重要なものについて詳細に調査し、分析を加えた。また、海外で試みられてきた環境汚染回復技術の例も調査した。さらに非放射性物質による環境汚染の修復についても調査し、放射性物質による汚染の回復への適用性を検討した。これらの調査と分析をとおして、以下のような点で改善が必要であり、ここに提言することとした。 | |
| 1) | 核エネルギーと放射線の利用に伴って発生してきた放射性物質による環境の汚染の事例のデータベースは、貴重な人類の知的財産として分析整理して、再発を防ぐよう積極的に役立てるべきである。 |
| 2) | 放射性物質と非放射性物質による環境汚染を統一的に評価し、管理する体系を構築する必要がある。 |
| 3) | 大学、研究機関においては、革新的な除染方法、新しい核種分離・核変換の方法とシステムの探求およびその基盤となるデータベースの整備を進めるべきである。 |
| 4) | 放射性物質の環境への漏洩ないしはその徴候を早期に検出するための先端的計測技術の研究開発が必要である。 |
| 5) | 放射性物質による環境汚染の回復技術についてわが国でも取り組み、有効性を学術的に評価することが望ましい。 |
| 1.チェルノブイリ事故の環境復旧努力,
2.英国ウインズケールでの軍事用原子炉の事故と取られた対策,
3.スリーマイル島原子力発電所の事故と対策,4.ハンフォードのプルトニウム生産施設における廃棄物処理, 5.ハンフォードの環境修復,6.旧ソ連の核兵器開発による高度環境汚染, 7.旧ソ連およびロシアによる放射性廃棄物の海洋投棄,8.人工放射能による地球規模の汚染 関連学協会 原子力安全システム研究所、国立環境研究所、(財)原子力安全研究協会、核燃料サイクル開発機構、 京都大学原子炉実験所、東京大学原子力研究総合センター、 自然計測応用研究センター低レベル放射能実験施設、日本原子力研究所 |
Copyright 2010 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN