| 委員会名 | 社会・産業・エネルギー研究連絡委員会 |
| 報告年月日 | 平成11年2月22日 |
| 議決された会議 | 第915回運営審議会 |
| 整理番号 | 17期−5 |
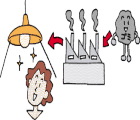
| 21世紀を展望したエネルギーに係る研究開発・教育について | |||||||||
|
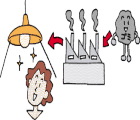 |
||||||||
![]()
![]()
| エネルギーの需給は、世界人口の推移やエネルギー消費構造に強く影響される。発展途上国における急速な人口増加や、エネルギー消費の動向を考えるとき、100年を超える超長期にわたる国際的エネルギー需給の展望なしには、我が国のエネルギーの将来を考えることは出来ない。 加えて、エネルギー資源の枯渇、エネルギー消費に伴う地球環境問題など、国際的なエネルギー情勢は、長期的に、より抜本的かつ総合的な究明をしていく必要性があることが明らかである。 |
![]()
| 1. | 「エネルギー研究開発総合戦略」の確立 国においては、今後、進めるべきエネルギー研究開発について、多面的な調査研究、評価を行い、各省庁協議の上「エネルギー研究開発の総合戦略」を審議、立案、決定する。総合戦略審議にあたっては、複数の選択肢を勘案し、情勢変化に応じて見直しを行うなど多様性、柔軟性を持つものとする。 |
| 2. | 民間における「総合戦略」研究機能の強化 民間においては、国の総合戦略確立に呼応し、既存エネルギー研究機関を「総合戦略」の研究に重点を置くよう機能強化する。 |
| 3. | エネルギー研究の国際的拠点形成 国は、国立研究機関の独立行政法人化に際して、各研究機関が分散して実施しているエネルギー研究機能を、相互に補完出来るよう整理統合して、新しいエネルギー研究組織を形成し、国際的研究拠点とする。同時に大学におけるエネルギーの学術的基礎研究については、総合戦略でその位置付けを明確にし、研究設備を拡充して、その機能を強化する。産業界は上記研究組織、大学などと連携し、必要な支援を得て、エネルギー技術実用化のための研究開発を進める。これらの研究開発にはアジア諸国をはじめとする海外からの参加を求め、国内外のエネルギー技術に携わる研究者、教育者、産業技術者の人材を育成する。 |
| 4. | 「エネルギー学」の創出、進展 現状のエネルギー産業技術の維持、発展と、21世紀の新しいエネルギー技術の確立には、産業現場における不断の研鑚とともに、自然科学、人文科学、社会科学を、それぞれの観点からの研究開発を進め、これらを俯瞰する新しい学術−「エネルギー学」を創出し進展をはかる必要がある。 日本学術会議においては、関連の学協会、各研究機関と協力し「エネルギー学」の概念形成、方法論等を研究し、当該分野を支える基盤の育成に努めるとともに、実効性を高めるため、必要に応じ勧告、提言を行う。日本学術会議内に、このための体制を整備する。 |
![]() 目次を見る 全文HTML(44k)
目次を見る 全文HTML(44k) 全文PDFファイル
![]() 青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
|
エネルギー需給動向、
エネルギー、
エネルギー消費構造、
研究開発、
再生エネルギー、 エネルギー研究開発総合戦略、 エネルギー学、 国際的拠点、 地球温暖化、 エネルギー資源の枯渇,21世紀、 バイオマスエネルギー、 化石燃料、 再生エネルギー、 省エネルギー、 産・官・学連携、エネルギー教育 関連研究機関・団体・学協会 財団法人エネルギー総合工学研究所、アジア環境技術推進機構、財団法人日本エネルギー経済研究所、 科学技術庁科学技術政策研究所、国立環境研究所 |
Copyright 2001 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN