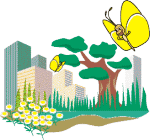
| 委員会名 | 地理学研究連絡委員会 |
| 報告年月日 | 平成12年3月27日 |
| 議決された会議 | 第933回運営審議会 |
| 整理番号 | 17期-39 |
| 環境問題についての地理学からの提言 | 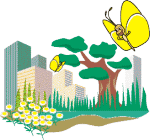 |
|||||||
|
![]()
環境問題には、
| ① | エネルギー・水・物質の循環にかかわる科学的問題、 |
| ② | ゼロエミッション・リサイクル・住民運動など環境の保全や改善にかかわる技術的・政策的・市民的問題のほかに、 |
| ①と②の問題の根底を貫いている、 | |
| ③ | 自然と人間との関係性にかかわる哲学的・倫理的問題がある。 |
| 本報告では③について「風土の倫理」の立場から提言を行う。 | |
![]()
| 人間存在の根源は自然にある。東洋の伝統はそれを物心(心身)一如と表した。自然と人間は切り離すことのできない存在であるとの認識から、風土の概念が、日本で生まれた。 人間(文化)と自然(環境)とが一体となって風土のおもむきが生まれる。風土とは、限定的には、国家体系をもつ地域についての人間のありかたを意味する。しかし風土の概念の重要性の主張は、自然主義的な人間的母型への回帰を意味してはいない。 逆に、近代科学に欠如していた自然と人間との関係性の問題を再浮上させて、「風土の倫理」の重要性を提言することにある。 |
![]()
| 人間の居住空間が全地球表面にまで拡大した現在、私たちには「風土の倫理」を発展させて、地球を生きるに値する場所であるように再創造する義務がある。倫理は「心」にかかわる問題である。「心」は脳と環境との身体を介した相互作用で個別につくられるが、人間存在は個別的であると同時に社会的である。 心的なものと身体的なもの、身体的なものと社会的なものとはゆるやかに連続している。人をとりまく環境には自然的環境と社会的環境がある。これらの環境と人間が一体となって風土のおもむきが生まれる。感受性・倫理観・社会性などは、人が十代まで育った歴史性と地域性をもつ風土の中で培われる。おもむきをもつ風土の中で培われた感受性が、美や秩序や伝統に価値を見いだす「心」のもとになる。 「風土の倫理」は人間存在と地球との関係のあり方にかかわる倫理である。「風土の倫理」が環境破壊を心の痛みとして感受させる。風土の表象である風景や景観には、その場所に住む人々の「心」が投影されている。望ましい風土への志向が、都市計画や国土計画、さらには地球計画の基本になければならない。 |
![]() 目次を見る 全文HTML(27k)
目次を見る 全文HTML(27k) ![]() 全文PDFファイル(52k)
全文PDFファイル(52k)
| 環境問題,地理学,ゼロエミッション,風土の倫理,環境倫理,環境保護運動(エコロジー), 和辻哲郎,オギュスタン・ベルク,生態学的な全体論(ホーリズム) 関連研究機関・団体・学協会 環境社会学会、財団法人日本地図センター、農林水産省農業環境技術研究所 |