| 委員会名 | 第4部附置分子レベルの構造生物学振興・推進小委員会) |
| 報告年月日 | 平成12年6月26日 |
| 議決された会議 | 第936回運営審議会 |
| 整理番号 | 17期−71 |
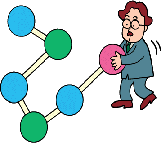
| 分子レベルの構造生物学の推進に向けて | |||||||||
|
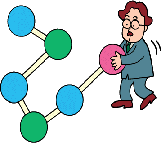 |
||||||||
![]()
| すでに第16期にて報告されたが,この研究分野は,激しい研究環境・状況にいるため,第17期においても前期の活動を引き継ぎ,現時点での振興・推進策を検討した。 |
![]()
| 構造生物学は生体高分子およびそれの作る細胞内複合体の立体構造を原子レベルの解像能で明らかにし,それに基づいて生命現象の諸相を明らかにしようとする研究分野である。この分野は,立体構造の実験的解明がいろいろいな技術的展開の結果著しく加速されてきたこと,および密接な関係にあるゲノム科学の爆発的展開の結果,現在大きな展開の時期を迎えている。この時点で我が国における構造生物学研究を如何に推進していくべきか,当該分野研究者の深い洞察にもとづく判断が必要とされている。小委員会では,この問題を「構造生物学とはなにか」の原点に立ち戻り,議論を重ねて提言を纏めた。 |
![]()
| 提言ではこの分野の現状における研究を次の三本柱にまとめ,いずれをも深く推進する必要があるとしている。(1)重要な生物学上の問題を構造に基づいて解明する研究。(2)特定の集団のタンパク質の構造を網羅的に調べ上げる研究。(3)最先端の技術・方法を構築する研究。 | ||
| 構造生物学は放射光などの大型設備を用いることを除けば,本質的にはスモールサイエンスであり,さらに,対象・方法の多様性にその特徴がある。この特徴の認識に立脚し,各研究者のキャリアパスを考慮に入れ,国内の構造生物学研究全体の活性を高く保つための多様なサイズ・性格の研究室の全国的配置を骨子とする全国的研究体制を提言している。 構造生物学は,多様な方向に展開しつつ,あらたな生命科学の中核を形成しつつある。用いられる方法も多様で,しかも激しく発展しつつある。展開しつつあるいずれの方向においても,純粋な基礎と応用との距離が短い。この短さゆえ,国際的な知的財産権をめぐる競争に立ち向かわざるを得ない。この状況の中で,研究のための財政的・物的資源を適切に配分し,人的資源を急速に育成しつつ適切に配分しなければならない。この複雑な問題に研究者社会は叡智をもって立ち向かわなければならない。 |
||
![]() 目次を見る 全文HTML(131k)
目次を見る 全文HTML(131k) ![]() 全文PDFファイル(206k)
全文PDFファイル(206k)
| 1.構造生物学,
2.X線結晶構造解析,
3.NMR,
4.中性子散乱・回折の特徴,
5.構造生物学の主要な課題 関連研究機関・学協会 理化学研究所,高輝度光科学研究センター(JASRI),筑波大学粒子線医学研究センター,ゲノム科学総合研究センター |
Copyright 2001 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN