| 委員会名 | 第7部 |
| 報告年月日 | 平成13年3月26日 |
| 議決された会議 | 第956回運営審議会 |
| 整理番号 | 18期−65 |
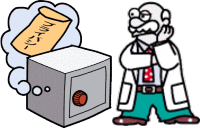
| 医学研究からみた個人情報の保護に関する法制の在り方について | |||||||||
|
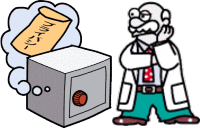 |
||||||||
![]()
| 医学研究を含めた学術活動が個人情報保護基本法の制定により円滑に進まなくなることの問題は大きい。 |
![]()
| 医師等の医療関係者については、資格法等に罰則付きの守秘義務規定が定められ、厳格な個人情報保護措置がとられている。診療報酬の請求、要介護認定におけるかかりつけ医の意見書、感染症発生時の行政機関への報告、児童虐待発見時の通告等については、法律に定められたルールが存在する。また疫学研究等について、個人情報の取扱のルールがガイドラインとして検討されている。その他、遺伝子解析による疾病対策・創薬等に関する研究班、疫学研究におけるインフォームド・コンセントに関する研究班、個人情報保護と疾病登録に関する研究班、診療情報保護のあり方に関する研究班、診療報酬明細書の取扱者の情報保護措置に関する研究班等、厚生科学研究補助金による研究班において検討されている。 |
![]()
| 医学研究を進めるためには、個人情報を含む健康関連情報を適切に収集、蓄積、データベース化し、有効に活用することが不可欠で、こうした情報を解析検討することによって、はじめて客観的で科学的な根拠に基づいた疾病の診断や治療方法の確立、予防対策の推進が期待される。医学研究を推進する機関、団体、個人が「個人情報取扱事業者」に認定され、その義務等を負わされる場合には、ヒトを対象とする医学研究の発展に重大な影響を及ぼす可能性がある。よって医学研究について例外的な取扱いが必要であり、「基本原則」及び「個人情報取扱事業者の義務等」の諸規定について適切な適用の除外を行うことが必要である。 |
| 1.外科領域と個人情報保護と事故予防の関係,
2.個人情報を蓄積、結合して実施する必要のある医学研究の例, 3.全数調査が必要な医学研究の例,4.個人情報保護と倫理的原則に関する倫理綱領の作成 関連学協会 日本医師会、医学系関連学協会 |
Copyright 2010 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN