| 委員会名 | 核科学総合研究連絡委員会核融合専門委員会 |
| 報告年月日 | 平成14年11月26日 |
| 議決された会議 | 第985回運営審議会 |
| 整理番号 | 18期−49 |
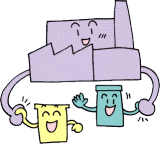
| 核融合研究の新しいあり方について | |||||||||
|
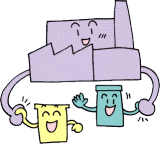 |
||||||||
![]()
| (イ) | 現在、国際熱核融合実験炉(ITER)の建設を目指してサイト国や誘致条件などに関して関係国間で公式協議が続けられている。このような状況下にあって、本年5月31日にITERの日本誘致に向けた措置が閣議了解された。 |
| (ロ) | 核融合開発のこのような展開に対して、ITER計画の成功と核融合実用化の早期達成に向けた開発計画を具体化する必要がある。そこで第18期日本学術会議核科学総合研究連絡委員会核融合専門委員会では小委員会を設置して、新しい状況に相応しい核融合研究の新しいあり方について検討してきた。 |
![]()
| (イ) | 研究初期の段階で色々な概念開拓が核融合界に閉じて並行、競争的に進められたことは、より良い方式の追求、効率の観点から仕方がない。この状態は約30年間継続した。しかしながら、ITERの建設が現実のものとなろうとしているとき、研究課題と全日本的な開発体制に関して従来の枠組みのままで良いのかどうか検討の必要性がある。 |
| (ロ) | これまでの核融合研究は要素技術的であったが、ITER建設を目前に控えて、システム工学的研究の側面が重要となるが、現在十分な研究環境にあるとは思えない。 |
| (ハ) | また、実用化を目指した開発を加速する必要があるが、そのためには、核融合炉の実用化に必要な技術開発を促進することが不可欠である。その重要性は従来から認識されていたが、研究は期待通りに進捗していない。 |
![]()
| (イ) | 核融合実用化に責任を有する方式としてトカマク型を確定する。慣性核融合については最近の成果を反映して研究の更なる進展に努力を傾注する。他の方式については学術研究として位置づけ、適宜に成果を評価し研究の進め方を検討する。 |
| (ロ) | 核融合炉の実用化に欠かせない材料、ブランケット及び炉心プラズマに関する技術を開発するため、「強力中性子源を活用した材料開発」、「ブランケット総合工学の構築」及び「高ベータ定常化高性能炉心プラズマの開発」を重点的に取り上げ、強力に推進すべきである。さらに、要素技術の結合である核融合システムの構築のため、「システム統合化技術の開発」も進めるべきである。 |
| (ハ) | ITER計画の成功と早期実用化に向けた革新的技術開発に資するため、大学研究者の自己組織化と日本原子力研究所・大学間の今まで以上の密接な連携が望まれる。また、核融合研究開発の進展を推進機関から独立して評価する民間の評価機関が自律的に形成されることが望まれる。 |
| 1.巨大プロジェクトと人類の夢−核融合−,
2.最終段階での技術的困難−核融合−,
3.核融合炉の特徴, 関連学協会 核融合科学研究所、日本原子力研究所、電力中央研究所 |
Copyright 2010 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN