−次世代を担う人材育成に向けて−
| 委員会名 | 社会環境工学研究連絡委員会地盤環境工学専門委員会報告 |
| 報告年月日 | 平成15年4月22日 |
| 議決された会議 | 第990回運営審議会 |
| 整理番号 | 18期−38 |
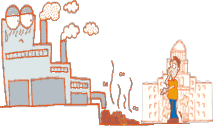
| 地盤環境工学の新たな展開 −次世代を担う人材育成に向けて− |
|||||||||
|
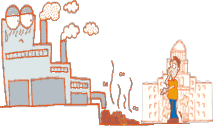 |
||||||||
![]()
| 17期地盤環境工学専門委員会は、新たな工学領域として“地盤環境工学”の創設を提言した。従来の力学を基盤とした地盤工学に、土壌科学、微生物学、化学、化学工学、生態環境工学、毒物学、等を援用統合すると共に、社会科学、人文科学とも広く連携するものである。新しい工学領域が体系化され社会に貢献するものとなるためには、研究、教育、実務の各側面に優れた人的資源の充足が重要であり、必要とされる人材を育成する必要がある。 |
![]()
| 地盤環境工学が先取的に取り組むべき課題として、汚染地盤、廃棄物・核廃棄物の貯蔵ならびに処分、酸性雨・酸性土壌、砂漠化、海面上昇、環境影響物質、生物・生態系、等を例示して、これら問題にビジネスとして取り組んでいる企業、高等教育機関、国立研究機関、等に協力を願ってアンケート調査を行った。 地盤環境工学に関するわが国の教育、研究、社会的認知は、いずれも欧米に比べて遅れていると意識されていることが明らかとなった。にも拘わらず、大学において海外研究機関との交流は進んでいない。また、国内における学外との交流も多くないことが明らかとなった。また、地盤の環境問題の実務に取り組む多くの企業で、これに関わる技術者は土木工学系が主体で、農業土木系や環境工学系(衛生工学等)がこれに次いでいる。しかし、極めて学際的な地盤環境の問題に取り組むために企業が求める人材と、既存の体系で育成されてきた人材にはミスマッチがある。産・官・学の共同の下、人材育成のシステムを構築することは急務である。 |
![]()
| 新規卒業生の採用と社内教育と言う伝統的な人材育成方法にのみ頼ることを、現在の社会・経済環境は許す余裕がない。高等教育機関における新人教育に加えて、継続教育(社会人教育)による人材の再教育、あるいは人材の流動化が求められている。 高等教育機関は、学部、大学院博士課程前期、同後期の教育システムを再検討し、多様な人材育成のシステムを準備し提供することが望まれる。また、人材の円滑な流動化を図るためには、行政レベル、会社間、業界枠を越えて、各界が歩調をあわせての連携協調が欠かせない。 本提言では、ゼネラリスト育成のための学部教育のあり方、高度専門職業人教育に特化する大学院と従来型の研究者養成を主体とする大学院教育の複線化、また、そのためのカリキュラムを例示した。 さらに、効果的な産・官・学連携のためには、関連学協会の主体的な取組が重要であることを提言した。 |
| 1.地球環境と地盤の関わり,
2.地盤の役割−浄化機能、貯蔵機能−,
3.地盤環境工学の課題群, 4.国際的環境技術分野で必要な人材,5.地球環境工学の科目例 関連学協会 日本土木学会、農業土木学会 |
Copyright 2010 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN