| 委員会名 | 牛海綿状脳症(BSE)と食品の安全特別委員会 |
| 報告年月日 | 平成15年6月24日 |
| 議決された会議 | 第995回運営審議会 |
| 整理番号 | 18期-33 |
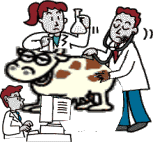
| 食品の「安全」のための科学と「安心」のための対話の推進を |
|||||||||
|
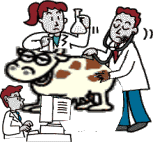 |
||||||||
![]()
| 2001年9月に発生したわが国初の牛海綿状脳症(bovine spongiform encephalopathy:BSE)は、多くの国民に食品に対する不安を与えた。BSEはこれまでに世界23ケ国で発見され、1986年以来、英国だけでも18万5千頭余りの牛が発病し、約600万頭が処分された。 |
![]()
| 1996年には、BSEが人に感染して変異型クロイツフェルト・ヤコブ病を引き起こす可能性が高いことが指摘された。BSEの病原体は感染した牛の脳、脊髄などに蓄積するので、これらの組織やその汚染物を含む飼料や食品を摂取しない限り、牛から牛へも、牛から人へも感染を起さない。対策が効を奏して、現在は世界的にBSEの発生は減少している。各国政府はBSEの教訓に学んで新しい食品安全のシステムを構築し、実施した。そしてBSE対策もこのような新たなシステムに組み込まれている。その基本は生産者保護から消費者保護への食品関連政策の転換であり、その手法として取り入れられたのがリスク分析である。わが国もこのような考え方を取り入れて、食品安全基本法が制定され、食品安全委員会が設置されようとしている。 食品の安全確保にリスク分析の概念が国際的に取り入れられたのは1990年代であり、その作業はリスク評価、リスク管理、リスク・コミュニケーションから成り立つ。わが国においても食品添加物や農薬等の化学物質についてはすでにリスク評価とリスク管理が行われ、その安全性は確保されている。しかし、消費者に対する調査では、食品に関する不安の要因として、これらの化学物質が常に上位に挙げられている。「安全は科学により確保されるが、安心は対話がなければ生まれない」といわれるとおり、このような「安全」と「安心」のギャップは、リスク・コミュニケーションの不足によるところが大きい。 |
![]()
| 有効なリスク分析を実現するためには、リスク評価を行う食品安全委員会と、リスク管理を担当する厚生労働省及び農林水産省など国の関係機関において、それぞれの機能を強化し緊密な連携体制を確立することが求められる。また、リスク分析に関する研究の活性化と専門家の養成や、国民がリスク・コミュニケーションを通じてこの問題に対する関心を高めることも重要である。国の諸機関と関係国民そして科学者のそれぞれの役割の発揮を期待して、本特別委員会は以下の提言を行う。 | ||
| 1) | 食品の「安全」を確保するための科学と技術の推進 | |
| ① | 研究体制の強化 | |
| ② | 専門家の養成 | |
| ③ | 実務担当者の知識・技術の向上 | |
| 2) | 「安心」を確保するための対話の推進 | |
| ① | 対話のための組織の支援 | |
| ② | リスク分析システムに対する外部検証機能の強化 | |
| 3) | 国際協力体制の構築と緊急事態への対応 | |
| 1.BSEと対策,
2.食の安全を脅かす要因,
3.Codex委員会(FAO/WHO合同規格食料委員会) 4.リスク・コミュニケーション,5.食品の安全性と国際協力体制の構築, 関連学協会 独立行政法人国立健康・栄養研究所、国際獣疫事務局、独立行政法人農業技術研究機構動 物衛生研究所プリオン病研究センター、厚生労働省東京検疫所 |
Copyright 2010 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN