| 委員会名 | 学術と社会常置委員会 |
| 報告年月日 | 平成15年6月24日 |
| 議決された会議 | 第995回運営審議会 |
| 整理番号 | 18期−23 |
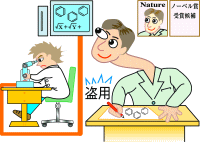
| 科学における不正行為とその防止について |
|||||||||
|
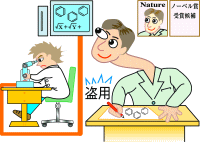 |
||||||||
![]()
| 科学(技術を含む)が社会に果たす役割が増大し変化するにともない、科学者(技術者を含む)の倫理、規範が、科学にとって、また、社会にとって看過できない大きな問題となりつつある。本報告は、科学者倫理につき、科学者の研究遂行、成果発表における「不正行為」(scientific misconduct)―捏造、改ざん、盗用など―に関わる問題を中心に、その組織的背景について論じたのち、その実態、特徴、誘因と対応策を検討し、科学者コミュニティが果たすべき課題につき問題提起を行うものである。 |
![]()
| 科学における「不正行為」は、科学と社会の関係が緊密になり科学の社会的役割が大きくなった現在、人々の生存、生活、福祉に重大な影響を与え、基本的人権や人間の尊厳を傷つける結果にもなりかねない。そのことはまた、ひるがえって、科学に対する社会的評価を損ない、科学と科学者に人々が託した夢と信頼を裏切る行為であることを意味している。「不正行為」の防止は、したがって、科学者コミュニティが社会に対する説明責任を果たし、「科学者が広く国民から評価され、尊敬される社会」(『科学技術白書』)を築くためには不可欠な実践的課題であり、「負託自治」の倫理の核心をなす責務なのである。 |
![]()
| 日本学術会議が「科学者の代表」として、本報告の問題提起をひとつの契機とし、今後さらに公開シンポジウムや公聴会を開き学協会との懇談を開催するなど、社会との対話と科学者コミュニティにおける議論を深め、研究行動規範(ガイドライン)の作成、公正な審理機関の設立など、不正行為の抑止と研究上の「誠実」(integrity)の確保に関する具体案の策定に向け、鋭意、審議をすすめることを提言する。 |
| 1.急増するデータ捏造事件,
2.最近の有名なデータ捏造事件, 3.なぜ、科学における不正行為(ミスコンダクト)が問題か?, 4.科学における不正行為−FFP, 5.科学における新たなる倫理問題, 6.海外の動向と日本 関連学協会 全学協会、全研究者に対して |
Copyright 2010 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN