| 委員会名 | 国際協力常置委員会 |
| 報告年月日 | 平成15年7月15日 |
| 議決された会議 | 第996回運営審議会 |
| 整理番号 | 18期−13 |
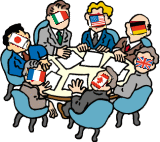
| 各国アカデミー等調査報告書 |
|||||||||
|
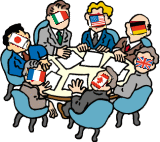 |
||||||||
![]()
| 21世紀、政治・経済・産業等のグローバリゼイションが進行する。学術も、その趨勢のなかにある。そして、科学技術・科学技術政策・公共社会と市民生活に対する学術の役割と責務は拡大する一方、さらには、増強されていかねばならない。学術の状況を世界的に俯瞰しようとするとき、科学者コミュニティを代表する各国アカデミーの歴史、伝統、現体制と活動状況を把握することは重要である。 日本学術会議第18期の国際協力常置委員会では、国際基本問題ワーキンググループ(座長:岸輝雄(第5部))において各国科学アカデミーの組織体制、付与機能および活動等の実情を把握することとし、二国間学術交流派遣事業を活用しつつ、平成12年度以降3か年にわたり、訪問及び文書による調査を実施した。 |
![]()
| 国際協力常置委員会は、3か年にわたる各国アカデミー調査結果を総括するとともに、得られた事実関係を分析し、考察した結果をとりまとめた。本報告書は、世界のアカデミーの組織・付与機能・活動等を知る上での客観的資料として、日本学術会議の内外で、学術の在り方と21世紀社会における学術体制および国際協力の枠組みを構築するための広範な議論に資することを念頭に編纂されている。 設置形態については、おおむね欧米では非営利団体・法人等の非政府組織、アジアでは政府組織である。会員については、任期は、終身制のものが多く、任期制や定年制のものも若干ある。また、その会員の選出方法は、ほとんどのアカデミーでco-optationを採用している。栄誉機関としての顕彰機能や助成金制度を有するアカデミーが多い。 ほぼすべてのアカデミーが、政府、議会に対して中立的な立場で助言を行っており、また国際学術団体や他国のアカデミーとの連携を行っている。また、政府からの財政支援のほかに、政府や民間からのコントラクトなどにより収入を得ていることが判明した。 |
![]()
| 各国アカデミーは、一流の科学者で構成され、その国における学術界の頂上に位置付けられている。すべてのアカデミーは、科学を通して実質的に社会に寄与・貢献する学術の最高機関として社会の中に定着し、国民に認知されている。 このためには、社会におけるアカデミーの機能と位置付けの改善、会員の質の向上、アカデミー活動の活性化、審議における迅速性の確保などに留意した諸方策につき議論することが必要である。 |
| 1.各国のアカデミー,
2.アカデミーの設置形態−欧米とアジアの差,
3.アカデミーの任期−終身制と任期制の問題点, 4.会員の選出方法−推薦, 5.アカデミーの規模−対科学者比では日本は最低, 6.栄誉・顕彰機能, 7.助成機能, 8.助言機能 関連学協会 日本学術会議 |
Copyright 2010 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN