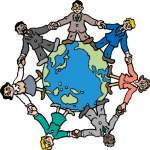
| 委員会名 | 比較法学研究連絡委員会 |
| 報告年月日 | 平成12年4月24日 |
| 議決された会議 | 第934回運営審議会 |
| 整理番号 | 17期−47 |
| 諸外国における法学研究者養成制度 | 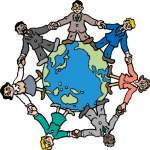 |
|||||||
|
![]()
| 1. | わが国において法学研究者の後継者養成のあり方が問われている |
| 2. | 諸外国の状況を検討することにより有益な示唆を得ることが可能である |
![]()
| わが国では各大学により極めて多様であり、共通する特徴が据え難く、あるべき養成制度も指摘することができない状況にある |
![]()
| 1. | 諸外国においては、画一性が制度上もしくは実質的に確保されている |
| 2. | わが国においても教員資格の客観化、公募制の実施による競争原理の導入などにより、透明性を高める必要がある |
| 3. | その前提として、大学法学教育そのものについても質の充実と統一を図る必要がある |
![]() 目次を見る 全文HTML(32k)
目次を見る 全文HTML(32k) ![]() 全文PDFファイル(43k)
全文PDFファイル(43k)
![]() 青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
| 法学研究者養成,画一性,教員資格,公募制,第二次国家試験,教授資格試験(アグレガシォン), ロースクール,アメリカ法律家協会,わが国の法学教育,法曹養成,法学教員養成制度,大学制度 |
Copyright 2001 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN