研究開発のあり方
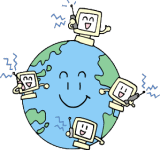
| 委員会名 | 基盤情報通信研究連絡委員会 モバイル・グローバル通信専門委員会 |
| 報告年月日 | 平成12年6月26日 |
| 議決された会議 | 第936回運営審議会 |
| 整理番号 | 17期−64 |
| 移動通信の国際化に向けた 研究開発のあり方 |
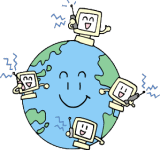 |
|||||||
|
![]()
| 次世代の移動通信技術の技術開発と標準化について熾烈な主導権争いが世界的規模で展開されている。 一方、従来の国内通信、国際通信という事業区分は消滅して、両通信技術の統合的適用によるグローバルネットワークが今後の通信業者の主要ターゲットとなっている。 わが国としてこれら通信技術の新動向に的確に対処するため、本専門委員会において、研究開発の在り方の検討を行ってきた。 |
![]()
| わが国の移動通信のサービスおよび市場規模は現在では世界のトップレベルであり、研究開発の過程では、優れた技術開発も行われ、サービスも飛躍的に進展して来たが、日本システムそのものを世界に普及させるまでには至っていない。一方、欧州や米国主導のシステムが世界市場を席巻しつつある。 2001年にわが国で導入が予定されている第三世代の移動通信では、このような反省から世界との共通性を重視して研究開発が進められつつある。しかし、長期的な観点からのコンセプトの提言、コアシステム技術の先導性など世界レベルの研究開発推進では、なお一層の課題を有している。 世界と協調しかつ競争する枠組みの中で、研究開発を推進させることが重要である。このような認識の上にたち具体的な課題抽出を行うとともに課題と取り組みに対するコンセンサス形成が必要である。 |
![]()
| 1. | グローバル化を前提とした移動通信では、世界とのパートナシップを形成しつつ研究開発の競争を行うことが必要で、そのために長期的視野に立ったシステムコンセプト提言を醸成する環境作りが必要である。 |
| 2. | 研究開発と標準化は車の両輪であり、世界における標準化は主要ベンダーが研究開発をベースに強力に進めている。わが国においてはベンダーの活動や役割が必ずしも充分でなく、今後一層取り組みを強化する必要がある。 |
| 3. | 移動通信の研究を加速し、かつグローバル化に対応できる人材の育成を行うため、大学における移動通信の教育と研究の一層の充実が必要である。特に、大学院における研究開発の体制や人材が不十分で、そのため種々の施策が必要である。 |
| 4. | 移動通信の研究開発拠点として、横須賀リサーチパークは第三世代移動通信の研究開発に大きく寄与したが、今後、さらに研究開発のシナジー効果を生み出すことが望まれ、大学との連携や人材の流動性およびベンチャーの育成等の施策が必要である。 |
| 今後の具体的な検討事項 今後、課題の絞り込みを行い具体的な提言に向けた検討を進めることが必要であり、そのための検討課題案を以下に示す。
|
![]() 目次を見る 全文HTML(27k)
目次を見る 全文HTML(27k) ![]() 全文PDFファイル(33k)
全文PDFファイル(33k)
| 移動通信,移動通信の国際化,GSM,CDMA,IMT-2000,Bluetooth,HDML
関連研究機関・団体・学協会 国際電気通信連盟(ITU)、3GPP、WAP、CDG、横須賀リサーチパーク |