| 科学技術の発展と新たな平和問題 |
| 委員会名 |
科学技術の発展と新たな平和問題特別委員会 |
| 報告年月日 |
平成11年9月20日 |
| 議決された会議 |
第924回運営審議会 |
| 整理番号 |
17期−17 |
|
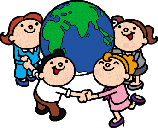 |
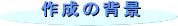
| 20世紀は,第一次,第二次世界大戦の象徴されるように,まさに「戦争の世紀」であった。直接暴力による伝統的な平和問題が重要であることを認識しながらも,そのような「戦争」という形をとらない新たな平和問題が一段と重要になりつつあるという認識に立っている。本報告では,主として科学技術の発展との関連において新たなる平和問題を検討する。 |
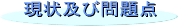
| 飢餓・貧困,社会的差別,非衛生・健康破壊,地球環境破壊,人間破壊などのように,直接的暴力(戦争)以外の諸力によって引き起こされる新たな平和問題がグローバルな課題になりつつある。このような新たな平和問題の多くは,科学技術の発展と無関係ではない。もとより,新たな平和問題はひとり科学技術からもたらされるものではないが,科学技術が独走した結果として,科学技術が残した負の遺産の影響は大きい。 |
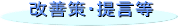
| 1. |
進んで,科学技術の発展それ自体が平和問題の解決に積極的に貢献するものになるようにしなければならない。 |
| 2. |
自然科学と人文・社会科学との協同による研究が行われなければならない。たとえば,食糧問題については,食糧問題が世界戦略の手段となることを抑制することが大切である。同時に,砂漠化など耕地の荒廃,環境汚染をもたらさない,新たな農業技術の開発のための努力をしなければならない。 |
| 3. |
「物質文明」依存よりも,よい意味で「精神文明」を重視するという人々の意識改革を行うことも人文・社会科学の課題である。 |
| 4. |
人々による平和運動の意義は大きい。この種の運動の意義,新たなる平和問題に関する科学情報を社会に伝えるジャーナリズムの使命の重要性も指摘されなければならない。 |
| 5. |
自然科学の専攻者自身が,同時に人間や社会についてあたたかい理解と配慮を持つことが大切である。その意味で教育のあり方が重要である。 |
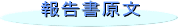 目次を見る 全文HTML(99k)
目次を見る 全文HTML(99k)
 全文PDFファイル(1)(1,173k) 全文PDFファイル(2)(1,026k)
全文PDFファイル(1)(1,173k) 全文PDFファイル(2)(1,026k)
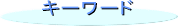 青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
Copyright 2001 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN
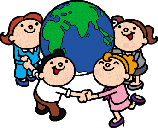
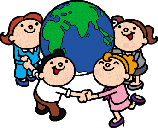
![]()
![]()
![]()
![]() 目次を見る 全文HTML(99k)
目次を見る 全文HTML(99k) ![]() 全文PDFファイル(1)(1,173k) 全文PDFファイル(2)(1,026k)
全文PDFファイル(1)(1,173k) 全文PDFファイル(2)(1,026k)