附属文書(個別報告資料)目次
○テクノロジカル・イメージと変質する日常-美学的な観点から-(淺沼委員)
○環境と感性-景観の問題を中心に-(淺沼委員)
○学問の理論性と社会性(渡邊幹事)
○文科系の純粋基礎研究の重要性(渡邊幹事)
○現代における哲学の社会的役割(渡邊幹事)
○経済学における実証理論と規範理論(大山委員)
○学術と社会-経済学の視点-(大山委員)
○地震予知と火山噴火予知・・・・・理学と工学のはざま(荒牧委員)
○「科学者の社会的責任」をめぐって(長岡委員)
○学術の社会的役割と教育(長岡委員)
○学術の社会的役割-物理学の場合(長岡委員)
○社会における科学・技術の共有-地球・資源・エネルギーの工学の立場から-(小島委員)
○第5部研究連絡委員会の改編について(三井委員)
○工学の社会的役割について(三井委員)
○食料・エネルギー・環境(高倉委員)
○農学分野における社会的許容性の事例(武田委員)
○公衆衛生学の社会的役割をめぐって(角田委員)
○生命倫理について(栁澤幹事)
○日本学術会議の社会的役割-『日本学術会議50年史』を手掛かりに-
(加藤幸三郎 日本学術会議50年史編集室長、第3部会員)
○新しい科学論の挑戦-学術の社会的役割との関係で-
(竹内啓20世紀の学術と新しい科学の形態・方法特別委員会委員長、第3部会員)
○政策過程研究の課題と方法--学術の社会的役割との関連で--(武藤博己 法政大学教授)
テクノロジカル・イメージと変質する日常
--美学的な観点から--
淺沼圭司
1 問題の所在
へーゲルのように美学を芸術の哲学に限定することが、やや極端に偏した考えだとしても、美学が芸術の根源的思索としての側面をもつことを否定するひとはいないだろう。そして芸術は、すくなくともある観点からみれば、美的価値をもったイメージの制作であり、あるいは制作された美的イメージの総体にほかならないといえるのだから、美学はまたイメージの哲学、あるいは制作の哲学という一面をもつことになる。ここで重要なのは、イメージの制作があくまでも自律的な、制作そのものを目的としたいとなみとみなされてきたことなのだが、産業革命を経過した社会において、まず効用的な制作過程にたいして機械の導入がくわだてられ、さらに19世紀にはいると、イメージの制作過程にすら機械が介入しはじめる--いうまでもなく写真や映画の成立である。このことはイメージの性質に根本的な変化をもたらしただけではなく、認識全体の構造をもおおきくゆるがしたと考えられる。イメージの変質は、やがて芸術という特定の領域をこえて、多様な領域にその影響をひろげていった。というよりは、現在の世界が直面するおおくの問題は、このイメージの変質に端を発しているとさえみなされるのだが、このことについての検討は、これまでかならずしも十分にはなされてこなかった。そして、その理由のひとつとして、研究領域の自律性に固執する近代的な学術の在り方をあげることも、けっして不可能ではない。ここでは、このような反省にもとづいて、問題のある側面をとりあげ、イメージの哲学としての美学の観点から、ごく概略的な検討をこころみてみたい。
2 テクノロジカル・イメージ
「テクノロジカル・イメージ」は、学術的に十分に定着した用語ではないが、ここでは、写真や映画などのような、近代のテクノロジーが作り出した機械的手段によって形成され、あるいは伝播されるイメージの総体を意味するものとして用いられている。まず映画のイメージ(映像)を例に、その形成過程をとおして特質をあきらかにしてみよう。映像形成の過程は、(1)カメラの前の対象(被写体)が、レンズの作用によって--物理的(光学的)に--視覚的性質(光学像)に還元され、 (2)この性質が、フィルムの感光物質の変化によって--化学的に--記録され、 (3)記録された性質が、映写機のレンズの作用によって--物理的(光学的)に--スクリーン上に再生される、そう図式化してとらえることができる。映像は、視覚的な平面像である点で絵画のイメージに共通するが、絵画の場合、イメージ(視覚的性質)は、特定の物質的存在--キャンパスに塗られた一定の色彩と形状をもった絵具--によって直接支えられているが、映画においては、視覚的性質はなんらかの物質的な存在によって支えられているのではない。なるほどフィルムやスクリーンは映画に特有の物質的存在ではあるが、映画に特有の視覚的性質を直接支えているのではない。このことは、映写の過程から取り出された、そのものとしてのフィルムやスクリーンが、特定の映像とまったく関わりないという事実からも理解されるだろう。観客は、したがって、なんらかの物質的存在に媒介されることなしにスクリーンのうえの視覚的な性質に出会うのだが、この視覚的性質は、基本的には、撮影時カメラの前に存在していた具体的対象のそれにほかならない。このことからいえば、映像は具体的な対象の視覚的性質への還元の結果であり、あるいはむしろ視覚的性質に還元された対象そのものにほかならない(1)。存在の仕方からみれば、具体的対象と映像のあいだには、あきらかにある差異が--実在と非実在という差異が--成立するが、意識との関係を中心にみるならば、二者の差異はむしろ解消する傾向にある。観客は映写のあいだ、ある対象の(機械的に還元され、記録され、再生された)視覚的性質を意識にとらえている、いいかえるなら、不在の対象をほぼ現前のものとしてみていることになるだろう。
スクリーン上の映像は、それを超えた他のなにものか--実物ないし原像--に観客の意識を送りとどけはしない--観客の意識はスクリーン上の映像に留まりつづけるしかない--のだから、映像は、通念に反して、他のなにものかに類似したイメージなのではなく、イメージそのもの、視覚的(感性的)性質そのものというべきことになるだろう。プラトン的な文脈にうつしていうなら、映像は「エイコン」ではなく「パンタスマ」というべきことになる(2)。
映像は、感性的な性質に還元された現実的な世界、いいかえれば世界の表面の恣意的な切りとりの結果であり、一本の映画は、そのような映像の恣意的な配列によって構成される。そして、現在、世界内のあらゆる存在ないし現象が、ロラン・バルトのいう「普遍的な記号化」の詰果として(3)、記号に化しているとすれば、世界の表面はこれら記号の戯れによって織りなされたもの、つまり「テクスト」によって覆われていると考えるべきだろう。世界の表面の切りとりである映像は、そのものがテクストにほかならず、そのような映像の恣意的な配列である映画そのものもまたテクストであるというべきだろ。
映像の形成過程は、基本的には機械的(自然科学的)過程である。そして機械は、正確な反復性を、すくなくともひとつの特性としてもつだろう。陰画(ネガ)を陽画(ポジ)に転換する過程も、それが機械的過程であるかぎり、当然反復可能である。このことは、いうまでもなく、同一のイメージが大量に存在しうることを意味する。もちろん制作の機械的過程を人間化(個性化)しようとするこころみもなされた。というより、写真や映画の主要な展開は、このようなこころみ--芸術化のこころみ--によってもたらされたといえる(4)。にもかかわらず、映像制作過程が、その基本的レヴエルにおいて、機械的であることは否定しえない。近代的な芸術観の枠内で主張された作品の唯一性は、だからここでその意味を失うことになる。
結論的にいうなら、実物とイメージとの、あるいは不在と現前との差異の曖昧化、イメージの複数(大量)性、そしてテクスト性、これらがテクノロジカル・イメージの、さしあたってとらえたれた特質である。
3 マス・イメージ
近代のテクノロジーは、模造と伝播のためのさまざまな手段(媒体)を作り出してきた。唯一性を不可欠の条件としていた既存の美的(芸術的)イメージでさえも、これらの手段(媒体)によって、大量に模造され、しかも広大な範囲に伝播してゆくだろう。ところで、イメージそのものの性質という点では、映画とテレヴィジョンのあいだに決定的な差異は成立しない。二者の差異は、基本的には、映画のイメージが観客の意識にたいしてほぼ直接的にあたえられるのにたいして、テレヴィジョンのイメージは、電波の媒介によってのみ意識に与えられるという点にある。換言すれば、対象のイメージヘの変換過程は、この二者においてほぼ同一なのだが(5)、テレヴィジョンは伝播の過程をもそのなかに含んでいる。したがってテレヴィジョンの特有性を規定するのは、伝播媒体としての電波の特性にほかならない--伝播の広域性、同時(即時)性そして多(無)方向性、いいかえるなら、空間的、時間的そして個体的な差異(距離)の解消--。電波は、こうして、不特定多数のひとびとに、たえまなくイメージを送りつづけているのだが、しかしその媒介的な役割が受容者に意識されることはほとんどない--意識にたいする透明--。テレヴィジョンのイメージは、こうして映画のイメージに匹敵する現前性をたもちながらも、映画のイメージがもちえない、ほぼ絶対的ともいうべき遍在性を獲得する。映画のイメージとの出会いが、美術館やコンサート・ホールとはことなるにしろ、なお一種の聖域である映画館においておこなわれる--その意味では映画体験は非日常的である--のにたいして、テレヴィジョンは、その遍在性のゆえに特定の聖域をもたず、そのイメージは、いつでも、どこでも、そしてだれによっても、受容可能である。
すでに写真や映画という機械的な手段の出現によって、イメージの大量生産ははじまっていたのだが、電波媒体はさらにイメージの大量伝播--むしろ拡散--をもたらしたというべきだろう。かつてイメージは、芸術という聖域に閉じこめられ、自足していたのだったが、電波媒体の出現によって聖域はその意味を失い、イメージは日常世界にあふれて行った。かつて印刷が一部特権者による文字の独占体制を崩壊させたように、電波はイメージを囲いこんでいた枠組の解消に大きく寄与したといえるだろう。現在、大衆(the
masses)--個別的な規定性(差異)を解消されたひとびとの集合--は、さまざまな手段(媒体)によって生産され、あるいは伝播される無数の、しかも規定性を欠いたイメージを共有していると考えられる。これらのイメージは、変動しつづける媒体の錯綜した網目(ネットワーク)をとおして、大量に、かつ反復的に伝播されるために、ひとはその起源にまでさかのぼることができず、したがってその作者を明確に同定することは不可能である(6)。今日の世界において、ひとびとは、このような起源(作者)から切りはなされて浮遊する、大量のイメージ--「マス・イメージ」--にとりかこまれて生きざるをえない。
たとえばアンディ・ウォーホルの『マリリン・モンロー』(7)は、実在の、人格的存在としてのマリリン・モンローの再現(表現)なのではなく、「マリリン・モンロー」と呼びならされたマス・イメージの引用--切りとりと配列と呈示--にほかならない。映画や他の媒体によって大量に伝播された「マリリン」のイメージは、けっして実在のノーマ・ジーン・ベーカー(8)にひとびとの意識を送り届けはしないだろう。ひとびとの意識が出会うのは、ノーマ・ジーン・ベーカーのイメージではなく、おそらくはマリリン・モンローのイメージでさえなく、ただ単に「マリリン」と名づけられたマス・イメージであり、それ以上のものでもそれ以下のものでもない。にもかかわらず、おおくのひとは、マス・イメージをイメージそのものとしてではなく、なにものかのイメージとしてとらえようとする。ひとびとは、だからイメージを離れて、その起源(実物)と出会うことを求めるのだが、それはどこにも存在しない。スターとの直接的、具体的なふれあいを期待して舞台に殺到し、あるいは楽屋の出口に群がるひとびとが出会うのは、イメージの起源としての存在(実物)ではなく、慣習的に「スター」と名づけれているもうひとつのマス・イメージにすぎない。出会いの場が、スクリーンであれ、舞台であれ、あるいは楽屋の出口であれ、ひとびとが出会うのはつねに「スター」というマス・イメージなのである。こうして、起源を求めてイメージを離れようとしても、出会うのはべつの、もうひとつのイメージにすぎず、しかもこのイメージの連鎖は、ほぼ無限に反復されるだろう。思いきって一般化していえば、現在の世界は、このような連鎖の戯れの織りなすもの(テクスト)によって覆われているのかもしれない。あるいは、このようなイメージの戯れに組みこまれることによって、すべての存在と現象もまたイメージに転化するのかもしれない。媒体の網目に覆われた世界で生きるしかないひとびとのまなざしは、あのミダス王の手にすこしばかり似ているといえるかもしれない。なぜなら、ひとびとがまなざしをむけたるやいなや、すべてのものはイメージになってしまうのだから。問題なのは、ひとびとがこのことをほとんど意識していないことだ。プラトンが洞窟に閉じこめたひとびとのように、いまのひとびとは、イメージそのものの世界にありながら、なお実在(真実)の世界に生きていると信じているのではないだろうか。しかしこの世界のそとには、もはやなにものもない--もちろんイデア的な存在も。
よくいわれるように、ひとびとがイメージを現実ととりちがえているのではなく、またただ単にイメージと現実の差異が曖昧になっているのでもなく、むしろイメージが現実になり、現実がイメージになっている--イメージと現実が簡単にいれかわる--のではないだろうか。しかもこのことは、たとえば「ヴァーチュアル・リアリティ」の技術の展開によって突然生じたものではなく、マス・イメージの成立と氾濫にこそ、その本来の原因をもつのだろう。さきに電波媒体の特性のひとつとして、個体的な差異の解消をあげた。テレヴィジョンの番組は、その基本的な受容者である大衆が容易に受けいれられるものでなければならない。それぞれの番組もまた、そのあいだに、極端な差異があってはならない。テレヴィジョンには、この意味で、たとえば近代芸術におけるような、明確なジャンル差は成立しない--たとえば演出者と出演者(演技者)の介在によって、「ニュース」と「ショウ」の差異すらも解消する(ニュース・ショウ)--。そして価値の序列も、厳密なものとしては、おそらくありえない。
4 イメージと無意識
さきにこの世界のすべての存在や現象は記号と化していると述べた。実用的な目的で生産されたものでさえ、意味機能を帯びて記号となるだろう--バルトのいう「機能=記号」である(9)。たとえば道具そのものは、人間が恣意的に作り出したものだが、その記号的(意味的)な性質は、同一の形態をもった道具が、おおくのひとによって、同一の目的実現のために、反復的に使用される結果生じると考えられる--道具の形態(意味するもの)と使用目的(意味されるもの)のあいだに成立する慣習的な関係(コード)--。そして道具は、とくに日常的なものの場合、ほぼ無意識的に使用されるだろう。「みぶり」や「しぐさ」もまた、おおくのひとによる反復の結果記号となるのだが、そのような身体的動作のおおくは、なかば無意識的におこなわれるだろう。いまは結論だけいうしかないのだが、これらのものの意味は、そしてこれらの記号によって織りなされ、世界の表面を覆いつくしているテクストの意味は、無意識的ないとなみの反復の結果生じたものにほかならず、この点を強調すれば、意識の光のさすことのない、その意味で暗黒の無意識界こそ、これらの意味が生成する場にほかならない。
映画は、世界の表面の切りとりであり、配列であり、呈示であり、したがってそれ自身が表面にすぎないものだった。一般的にいえば、表面とはつねになにものかの表面にほかならず、その背後にはかならずある実体的なものの存在が想定される。しかし映画の場合、表面(視覚的性質)の背後には、なにものも存在しないのだった。ところでこの表面は、世界を覆いつくしているテクストを切りとり、配列し、呈示したものでもあった。そして世界を覆うテクストの意味は、暗黒の無意識界において生成するものと考えられた。映画のイメージは、その点からすれば、暗黒の無意識界において生成した意味が意識にあらわれたものといえるのだが、しかしひとがスクリーン上に輝く映像と出会うやいなや、映像はその背後を完全に失い、純粋な表面ないしテクストとして成立する。輝きと暗黒は、意識と無意識は、ここでどのような関係にあるのだろうか。
鏡にみいるひとは、自分と周囲の反映像しかみないだろう。このひとにとって、鏡の固くなめらかな表面の背後には、なにものも存在しない。ところがコクトーのオルフェ(10)にとっては、鏡はべつの世界に通じる入口にほかならない--オルフェは鏡を通りぬけ、べつの世界にはいってゆく。だが、べつの世界とはいったいなんなのだろう。ギリシャ神話によれば、それはエウリュディケーを求めて降りていった冥界(死の世界)なのだが、あるいは意識の死としての無意識界なのだろうか。オルフェは、この世界ではたしかに意識的に生きているのだから、べつの世界にはいってゆくのは、べつのオルフェ、その無意識なのだろうか。神話的なオルフェはすぐれた詩人であり音楽家なのだが、ここでのべつのオルフェとは、感性(想像力)そのものに還元された存在であり、べつの世界とは「想像界」にほかならないのだろうか。ふたつの世界は、あらゆる点においてことなっているにもかかわらず、そのあいだには、鏡の実体のない表面しかないのだから、ふたつの世界はほぼ直接的に接しているというべきだろう。意識にとって、映画やテレヴィジョンのイメージは、自足する視覚的性質にほかならないのだが、無意識にたいしてはべつの世界にみちびくものとして、つまり「意味するもの」として成立するのではないだろうか。といってそれは通念的な「意味するもの」のように、なんらかの実在的ないし観念的なものにつながるのではなく、ラカン的な意味での「想像界」(「l'imaginaire)に(11)、あるいは意味生成の場としての無意識の暗黒界に通じるのではないだろうか。これらのイメージは、想像界にたいする「意味するもの」であるという意味で、まさしく「シニフィアン・イマジネール」(le
signifiant imaginaire)というべきかもしれない(12)。もちろんこの暗黒界は、あの純粋な表面によって覆われているのだから、それをそのものとして意識することはありえないだろう。しかし観客の無意識は、オルフェのように、この表面を通りぬけて、自由に暗黒界と往還しているのではないだろうか。映画を、テレヴィジョンをみることは、イメージそのものを意識することであり、あるいは世界の表面から切りとられたテクストを読むことにほかならないのだが、それと同時に、あの暗黒界と無意識的に交流することでもあるのだろう。それ以外のものとの、とくに理念的なものとの関係をまったく欠いた感覚的性質は、プロティノス的な脈絡においては、完全な「闇」といわれる(13)。スクリーンの上で、そしてモニターの上で輝くイメージは、同時に完璧な闇でもある。
このようなイメージが、いま日常のなかにあふれている。ひとびとは、おそらく、意識的に(選択的に)これらのイメージと接しているというだろう。しかし、テレヴィジョンの視聴がしめすように、これらのイメージの受容はほぼ慣習的に反復されているのだが、このことは受容がなかば無意識的におこなわれていることを物語るだろう。そしてこれらのイメージは、あの暗黒の世界とほぼ直接的に隣りあっているのである。あるいは、ひとびとは、それと意識することなく、日常の世界とあの暗黒の世界を自由に往来しているのかもしれない。あるいは、無意識の暗黒は、イメージの表面をすり抜けて、日常の世界にはいりこんでいるのだろうか。とすれば意識の在り方も、行動の形態も、おおきくかわらざるをえないはずだが、ことがらの在り方からいって、このことが意識されることはおそらくない。かつてサルトルは、意識がみずからを想像的なものとして構成するためには、「根源的な回心」(la
conversion radicale)が必要だと述べていたが(14)、ここでは意識は--いかなる回心もはたすことなく--日常的、現実的であるがままに想像的に、あるいは想像的であるがままに日常的、現実的になっているのだろうか。
5 自閉する過程
テクノロジカル・イメージにはいかなる聖域もないのだから、たとえばテレヴィジョンは、本性上、万人にむかってひらかれており、その意味で「公的」(public)な性質をもつ。それにたいして、いわゆるホーム・ヴィデオの場合には、撮影(入力)もプレイ・バック(出力)もすべて個人的(私的)におこなわれるのだから、この過程は閉鎖的であり、私的である--ヴィデオによる放送の録画は、ひらかれた過程の遮断であり、公的なものの私有化にほかならない--。カメラ、デッキ、テープなど、ヴィデオ過程を構成する要素はすべて私的に所有され、しかも過程そのものが自閉的なのだから、ヴィデオの受容空間は、二重の意味で閉鎖的というべきだろう。この自閉的な空間のなかで、意識はすでにいくぶんか「魅せられて(魔法をかけられて)いる」(etre
enchantee)のだろうが、その意識が直面しているのは、基本的にはテレヴィジョンのそれと同質のヴィデオ・イメージである。おそらくそこでは、意識はきわめて容易にあの暗黒界にはいりこみ、無意識界の暗黒はやすやすと表面を通りぬけるだろう。この自閉的な空間は、ある意味で薄明の世界であり、あらゆる差異はそこで解消する傾向にあるのだろう。それはテクノロジーというきわめてロゴス的なものの支配する世界のただなかに、しかもテクノロジーそのものが作りだした、暗く混沌とした「呪術的な」--合理と非合理、能動と受動、現前と不在、原像と模像など、すべての差異が解消する--世界にほかならないかもしれない。
コンピュータ・イメージについても、同様のことがいえるのではないだろうか。なるほどコンピュータは、ネットワークに組みこまれて外部空間に連続するだろう。しかしネットワークが、たとえばインターネットが示すように、あまりにも錯綜した、実態のとらえがたいものであること、コンピュータ過程が、大多数のひとびとにとっては、ほぼ完全なブラックボックスであることなどによって、モニター上のイメージは、発信源から切りとられ、そのものとして自足し、「私」にたいしている。にもかかわらずこのイメージは、「私」の恣意的なキーボード操作に瞬間的に反応し、「私」のために出現し、「私」によって所有されるものでもある。私性と他者性の差異は、ここで完全に曖昧化する。ネットワークをとおして形成されるコンピュータ空間は、いかなる定点ももたない、カオス的としかいいようのない空間である。しかもこの空間内を、無数の、起源不明のイメージが、猛烈なスピードで飛びかい、衝突し、分裂しあっている。広漠としたコンピュータ空間はまた、このような自己増殖を反復するイメージによって暗く満たされた、自閉する空間でもある。
6 問題の展望
世界のなかにテクノロジカル・イメージが形成する特殊な領域があるのではなく、テクノロジカル・イメージの形成する空間こそがいま大多数のひとびとがそのなかで生きている世界なのかもしれない。ひとは、もはや「世界内存在」ではなく、「イメージ的世界内存在」(l'etre
dans le monde imaginaire)としてとらえられるべきかもしれない。もちろん簡単に断定することは避けなければならない。しかしながら、いまおぼろげにそのすがたをあらわしつつあるこの問題が、発想の根本的な転換を要請していることは否めないのではないだろうか。
イメージの哲学としての美学は、テクノロジカル・イメージの問題にたいして、たしかにある有効性をもつだろうし、ある視点にたつ美学のまなざしにたいして、テクノロジカル・イメージがここで略述したようなものとしてあらわれることもあきらかである。しかしテクノロジカル・イメージの形成が自然科学的過程をとおしておこなわれる以上、この問題は自然科学的検討にも付されなければならないだろう。その在り方からみて、この問題はまた認識論、社会学、社会心理学、文化人類学、情報論、記号論など多様な観点からの検討を要請するだろう。この問題を全体的に把握するためには、あきらかに個別的な学問領域を超える必要があるし、おそらくはこれまでの学際的研究の枠組をすら超えた、あたらしい視点をとることが要請されると思われるが、そのことの論議は、もはやここだけの問題ではない。
註
(1) cf. ASANUMA Keiji: Structure de l'image
cinematographique et du plan comme unite,
in Cacinema, No.3, Editions Albatros, Paris.
pp.38-47
(2) cf. Platon: Le Sophiste 236a-c, texte
etabli et traduit par Auguste Dies, Oeuvres
Completes Ⅷ, 3e partie, Societe d'Editions
Les Belles Lettres, Paris, 1969. p.334.
(3) cf. Roland Barthes: Elements de semiologie,
1965, repris dans l'Oeuvres Completes Tome
Ⅱ,Editions du Seuil, Paris. pp.1465-1526.
(4) いわゆる「オリジナル・プリント」を重視する傾向は、このことと関連するだろう。しかしそれは、ある意味では、近代的な芸術観の枠内での、作家性ないし作品性の主張にほかならないと考えられ、写真というテクノロジカル・イメージの特性をかえって覆い隠すものというべきかもしれない。
(5) もっとも、映画の変換過程が、基本的には光学的-化学的であるのにたいして、テレヴィジョンのそれは、光学的-電子工学的であり、そのことが形成されたイメージの電波による伝播を可能にしたというべきだろう。
(6) もちろん作者の名前を知ることは可能である。しかしその名によって指示される存在と出会うこと--名と存在の同一性を確認すること--は、いま不可能にちかい。
(7) Andy Warhol: Marilyn Monroe, 1962, 1967
et alt..
(8) Norma Jean Baker--マリリン・モンローの実名。
(9) cf. R.Barthes: op. cit.
(10) cf. Jean Cocteau: Orphee, 1950.
(11) cf. Jacques Lacan: Ecrits, Editions
du Seuil, Paris, 1966. p.349sqq.
(12) この用語は、クリスチアン・メッツからの借用であるが、その意味はこのテクストの文脈に
あわせて変えてある。cf. Christian Metz: Le
signifiant imaginaire, psychanalyse et cinema,
Unions Generales
d'Editions, Paris, 1977.
(13) cf. Plotionos: Enneades Ⅱ, Texte etabli
et traduit par Emile Brehier, Societe d'Editions
Bells
Lettres, Paris, 1964.Ⅱ,4,5. p.59 et alt..
(14) Jean-Paul Sartre: L'imaginaire, Psychologie
phenomenologique de l'imagination, Librairie
Gallimard, Paris, 1940. p.230.
参考文献
淺沼圭司:『映画のために Ⅰ、Ⅱ』、1986、1990。
同 :『読書について』、1997。
Asanuma, Keiji: Litterature et imprimerie-Essai
sur l'institution litteraire, in Aesthetics
No.3, 1988.
Asanuma, Keiji: Technologie moderne et diffusion
de l'art, Essai de la critique de l'image
mecanique, 1991.
Asanuma, Keiji: Imitation, representation
et citation, in Journal of Faculty of Letters,
the University of Tokyo, 1992.
Barthes, Roland: Rhetorique de l'image, in
Communication No.4, 1964.
Barthes, Roland: Le plaisir du texte, 1973.
Benjamin, Walter: Das Kunstwerk in seiner
technischen Reproduzierbarkeit, 1937.
Kristeva, Julia: Semeiotike, Recherches pour
une semanalyse, 1969.
Lacan, Jacques: Ecrits, 1966.
Metz, Christian: Le signifiant imaginaire,
psychanalyse et cinema, 1977.
環境と感性
--景観の問題を中心に--
淺沼圭司
1 問題の所在
「美学」という学を一義的に規定することはほぼ不可能にちかいが、すくなくともそれが美という価値領域、感性という認識領域、そして芸術という文化領域に関する根源的な思索(哲学)であることは否定しえないだろう。そして美、感性、芸術のそれぞれが、なんらかのかたちで現実からの離脱を基本的な傾向としてもつこともたしかなのだから、このことからだけでも、美学と社会の関係を「肯定的(積極的)」なものとしてとらえることは、きわめてむずかしいといわざるをえないだろう。しかしこのことは、美学が社会になんらの寄与もなしえないことを、かならずしも意味しない。たとえば「環境」の問題を美学的な観点からみることは可能であり、それによって、自然科学的ないし社会科学的な観点からとらえれるものとはべつのすがたがあらわれることもありうるだろう。このことが問題の解決に直接結びつくかどうか、知らない。しかしすくなくとも問題の多面的な把握になんらかの寄与をなしうることはたしかである。以下は、美学的にとらえられた環境としての「景観」についての、ごく概略的な考察である。
2 風景
「風景は、美学的にいうなら、ただみるひとにたいしてだけ、とくに特定の態度でみるひとにたいしてだけ、それとしてあらわれる」(1)。ニコライ・ハルトマンのことばなのだが、ここでいう「特定の態度」が「美的態度」を意味することはいうまでもない。かれはまたつぎのようにもいう、「ふたりのひとが、早春の野原をあるいている。ひとりは、周囲をみまわし、作物の生育状況や立ち木の値段などを判断しようとする。べつのひとのこころは、あわい緑の色、大地のかおり、そして遠山の青みなどで満たされている。感覚的な印象とそれを喚起した事物はおなじなのだが、それらが媒介する対象は、まったくことなっている。」 この野原の地質に関心をもち、露出した地層を探しあるくもうひとりのひとを、べつに想定してみてもいい。経済的なものに関心をもつひと、科学的なものに関心をもつひとは、いずれもそれぞれが関心とするもの(対象)に注意を奪われているために、この野原そのものの色、かおり、形態などの感覚的性質が、全体としてその意識にあらわれることはおそらくないだろう。この野原の全体的なかたちを、その色やかおりや形態などの特徴を、それとして意識し、たのしむのは、経済的関心にも、科学的関心にもとらえられていない、第三のひとだけではないだろうか。風景とは、この第三のひとの意識にあらわれた、自然環境の全体的な「すがた・かたち」にほかならない。あるいは、風景は、さきに述べたような経済的(実際的)、学問的などの関心からはなれた意識--カントのいう「関心からの自由」(die
Interesselosigkeit)をはたした意識--にたいしてだけあらわれる、そうもいえるのだろう。
風景はそれとしてあるのではなく、周囲の自然を特定の態度で、「美的」な態度でとらえる意識にたいして、その都度あらわれる(erscheinen)ものだろう。経済的な価値を判断するために、あるいは科学的法則を発見するために、見、聞き、嗅ぐのではなく、ひたすらに見、聞き、嗅ぐこと、そういってもいいだろう。風景とは、こうして、いかなる目的にもしたがうことのない、それとして純粋化した感覚、つまり感性の対象であり、あるいは感性的(aesthetic)な性質に還元された自然環境にほかならない。ひとは、風景をながめるとき、ある満足(こころよさ)をおぼえることがあるだろう。この満足(こころよさ)は、そのものに還元された感性的な性質と、そのものが目的となった純粋な感覚との照応にのみその根拠をもち、具体的な世界とは直接の関係をもたない。そしてこのような満足こそが「美」にほかならないと考えられるのだから、風景体験は「美的(aesthetic)体験としてとらえられるべきことになる。風景は、その本性上、「美的」性質をもつというべきだろう。
3 タウンスケープとシティスケープ
ときに家屋や橋などの人工物を構成要素として含むことはあるが、風景は、基本的には、自然に属している。かつて人間は自然のただなかで暮らしており、だから人間はほぼ直接的に自然に接していたと考えられる。しかし、技術の展開にともなって、人間の生活領域は自然領域にまで拡大しはじめ、とくに機械技術の成立以降拡大はその加速度を増し、その結果、人間はいまその周囲に自然ではなく、人間化された自然--もはや自然ではなく、しかしいまだ完全に人間的ではない領域--、ないしは人工物によってかたちづくられた周囲世界しか見いだすことができない。そしてこのような現象には、「都市」の出現と展開が密接に関連している。
ところで、都市は特定の地域への人口の集中がもたらしたものと考えられるが、その集中の理由ないし原理にしたがって、多様な種類と規模の都市が生まれた(2)。集中の進展とともに、都市の規摸は次第に拡大するが、やがて到来した過剰な集中は、かえって人口の拡散をもたらし、その結果都市の規模はさらに拡大することになった。この集中=拡散の際限のない循環ないし戯れは、農村的な共同体(村)と都市の差異(境界)を曖昧にしただけではなく、やがて「メガロポリス」という、まったくあたらしい形態の都市を生み出してさえゆく。
都市化--メガロポリス化--とは、ときにそう考えられるように、特定地域への人工の集中を意味するのではなく、むしろ集中の結果としての、大量人口の不特定地域への拡散を意味するのではないだろうか。そしてこの拡散は、当然の結果として、生活のあらゆる領域における画一化をもたらす。拡散と画一化、それがメガロポリスの特質である。
いま論議されるべきは、もはや村と都市(town)の対比ではなく、都市とメガロポリスの対比ではないだろうか。といっても、このふたつのものの境界は明確でない--むしろ境界の曖昧化こそメガロポリスの特徴である--。にもかかわらず、ふたつのあいだになんらかの差異が存在することもまたたしかなのだから、問題の把握のためには、なんらかの基準によってこの差異を明確にする必要があるだろう。ここでは「ふさわしい大きさ(規模)」という基準をこころみに採択してみよう。この基準によってあきらかになるのは、いうまでもなく「ふさわしい大きさをもつ」都市と、「ふさわしい大きさ」の規模を超えてしまった都市の対比である(3)。いま、便宜のため、前者を「都市」、後者を「メガロポリス」と呼んでおく。
さきに人口の集中にはなんらかの原因(原理)があると考えたが、ほかならぬこの集中原因(集中原理)が、集中の、そしてさらには拡散の度合をも規定すると考えられる。そしてこの原因ないし原理が、ある都市の全体的な景観をとおして、直観的に把握されうるかどうかを判断することは、おそらく可能だろう。いいかえるなら、ある都市が、一定の原理によって支配された統一的な景観をもつかどうか、あるいは、ある都市の「大きさ(規模)」が、その全体を直観的に把握するにふさわしいものかどうかの判断である。たとえば鳥瞰的な視点からとらえたある中世的な「都市」の全体的景観を、一枚のタブローに描き出すこと--景観の表象を再提示する(表現する)こと--は、おそらく可能だろうが、19世紀のパリについては、それはもはや不可能にちがいない。たしかに、たとえば「凱旋門」の屋上から見たとしても、パリの景観全体を一挙にとらえることはできない。しかしながら、「エトワル広場」から放射状にはしる道路をとおして、19世紀パリ(4)の視覚的な構築原理を直観的に把握することは可能だろうし、そのことによってこの都市の全体的景観を想像的に把握すること--その統一的表象を形成すること--も、十分に可能だろう。19世紀的なパリは、もはや典型的な「都市」ではないにしても、いまだメガロポリスには達していない。一般化していえば、「都市」は、中世都市のような、その景観全体を実際にとらえることができるものと、19世紀的なパリのように、その構築原理を直観的に把握する--全体的景観を想像的に把握する--ことができるものという、ふたつに区分して考えることができるのではないか。そしてこれらみられ(知覚され)、あるいは想像される全体的景観を「タウンスケープ」(townscape)と仮称しておこう。「タウンスケープ」は、さきに述べた風景から類推していえば、純粋に感性的な性質に還元された全体的な都市環境にほかならない。
拡散と画一化から生じたメガロポリスは、あきらかに「ふさわしい大きさ」を超過しているのだが、この拡散と画一化は、基本的には個人的な欲求の集積によって生じるために、集中化にみられるような明確な原理をもってはいない。このことは、たとえば「都市」の広場から放射状にはしる道路と高速自動車道路網の比較によってあきらかになるのだが、その検討はここでは断念せざるをえない。ただつぎのことは指摘しておくべきだろう。道路そのものは、すべての個人によって共有される、その意味で公的(public)な性質をもつはずだが、基本的には私的(private)な性質をもつ交通媒体である「自動車」のためにのみ作られ、しかも歩行者すべてをそこから排除するとき、道路は私的なものに変質する--すくなくとも「公的」性質を減じる--。高速自動車道路は、結局は自動車の利用者の欲求を満たすために建設されるのだから、その意味では私的な欲求の「大量集積」にその起源をもつというべきであり、その公的な性格は、その結果として生じる疑似的なものにすぎない。広場から放射状にはしる道路が、あきらかにひとつの原理にもとづいて建設され、またそのことを明確に--直感的に--示しているのにたいして、高速自動車道路網は、先述のように一定の原理なしに建設されるために、「都市」の空間の秩序をゆるがし、その統一的な景観を解体してしまうのではないだろうか。
循環する集中と拡散がメガロポリスの境界を不分明なものにし、しかもそこには明確な構築原理もないのだから、メガロポリスの全体的、統一的な景観をとらえることは不可能というしかない。すくなくとも「タウンスケープ」を見るのとおなじ仕方でメガロポリスをながめようとするかぎり、その全体的、統一的な景観があらわれでることはないだろう。メガロポリスは、この意味で、「表現」--統一的な表象像の再提示--にはふさわしくない。あたらしい環境はそれにふさわしい「見方」を要請する。メガロポリス的空間とそれに適応するあたらしい「見方」が出会うとき、まったくあたらしい景観が出現するにちがいない。さしあたってそれを「シティスケープ」(cityscape)と呼んでおこう。
4 感覚の複合--景観体験の特質
近代の美学においては、個々の芸術ジャンルは、おおむねただひとつの感覚領域に対応するとされており、感覚領域の曖昧な混淆は、ジャンルの頽廃をもたらすと考えられていた。いまこのことについて詳述することはできないが、芸術がただひとつの感覚領域に限定されることによって--その意味で、諸感覚領域の複合体である現実的世界から切りはなされることによって--、対応する感覚領域に関しては、日常の世界では認知できないような、微妙でニュアンスに富んだ性質が識別可能になると考えられていた--ときに「美的明瞭性」(aesthetic
precision)とよばれる現象である。それとともに、この「美的明瞭性」を保持するために、芸術はそれにのみ捧げられた場所(聖域)に囲いこまれ、現実世界から切り離されることが必要だと考えられていた--近代における美術館、コンサート・ホールは、このような聖域の具体化であると考えることもできるだろう--。
日常の世界(生活世界)においては、あらゆる感覚が相互に、かつ密接に関連しあっているため、感覚領域の厳密な区分とそれにもとづく「美的明瞭性」は、むしろ否定的な結果をもたらしかねない。言語記号の有効性は、その「意味するもの」(le
signifiant)--聴覚的性質(ことば)や視覚的性質(文字)--にたいする寛容(無頓着)におおく負っているとさえいえる--たとえば「訛」の存在--。ひとが語音や字形の差異にあまりにも厳密であるならば、それは「記号」としての機能をほぼ喪失するにちがいない。
景観体験は、それに特有の聖域においてではなく、現実世界のただなかでおこなわれる。そして、たとえばひとが春の野をながめやるとき、鳥の歌声や花々のかおりも同時に意識されはしないだろうか。視覚的体験と、それと同時におこなわれる--かならずしも明確に意識されることのない--多様な感覚的体験、これらすべての感覚的体験の照応ないしひびきあいこそが、景観体験の充実相をかたちづくっていると考えられる。とすれば、鳥の声も虫の音も消えはてた「沈黙の春」の野で、十全の景観体験をおこなうことは不可能というべきだろう。景観体験の特質は、このような感覚領域の複合にあると考えられ、その意味でそれは日常的体験に近づく。一方、わたくしどもの生活世界(現実世界)は、もろもろの感覚的性質だけではなく、それ以外のきわめて多様な性質から構成される、複合体としてとらえられるのだから、景観はまた、そのような複合性を特質とする現実的な環境の、感性的性質への還元にほかならない。景観体験においては、だから感性的以外の性質は否定され、その点では芸術体験にちかづく。こうして景観体験は、日常的体験と芸術体験の中間にその位置をもつということができるだろう。
5 芸術の自律と環境の汚染
景観とは、「感性的」な性質に還元された環境(周囲世界)であり、このことからそれを「感性的環境」とよぶことも可能だろう。しかしいま問われているは、このような感性的に還元された環境ではなく、その具体的なあり方における環境にほかならない。このような問題状況のなかで、「感性的(美的)環境」を問うことに、はたしてなにほどの意義があるのだろうか。
自然環境の汚染ないし破壊には、すくなくともふたつの基本的な原因が考えられる。ひとつは、自然科学--理性的ないとなみによる自然の法則的な所有--に基礎をおいた、近代テクノロジーによる自然の人間化--実践的ないとなみによる自然の実際的な所有--であり、他のひとつは、個人的な欲求と世俗的な利益の肯定に根拠をもつ、資本主義経済システムである(5)。環境汚染は、だから、いくぶん極端化していえば理性中心主義(logo-centrism)と功利主義(utilitarianism)(6)を原理とする、近代的な社会に特有のものと考えられる。
このような世界においては、感性はつねに理性に従属させられているのだが、にもかかわらず感性に自由と本来のゆたかさをとり戻そうとするなら、可能な唯一の方策は、感性を現実の世界から切り離された自足的な領域に閉じこめ、そのうえで自律的に展開させることだろう。技術は、機械的過程をそのなかに導入することによって、制作過程そのもののもたらすよろこびを目的とする技術、つまりアリストテレス的な「模倣技術」をその領域外に追いやったのだったが、その結果技術の領域は、ふたつの対立する領域に、実際的な目的のために大量かつ均質の製品を生産する機械的・効用的な技術と、美的(感性的)価値とのみかかわる模倣的(表現的)・非効用的な技術に分割されることになった。この後者の領域こそが、感性の特権的な場としての芸術にほかならない。
しかしながら、感性を現実世界から取りだし、芸術の自律的で自足的な領域に隔離することは、現実世界からの感性の「疎外」にほかならず、きわめてアイロニカルなことに、日常の世界における感性の、想像力の衰頽を結果としてもたらす。ひとは、その欲求が充足され、個人的利益がもたらされるかぎり、自然を利用しつづけ、人間の領域を自然におしひろげようとするだろう。自然は、もはや科学技術的な、実際的な関心の対象にすぎないのだから、ひとはテクノロジーのもたらす自然の感性的性質の変化にたいして、無頓着(無関心)でありつづけるだろう。たとえ虫の音が絶えはてても、化学的に合成された農薬を散布しつづけるだろうし、もはや鳥が歌わないとしても、森の木々を切り倒すことを止めはしないだろう。都市が騒音と排気ガスで満たされたとしても、自家用車を乗りまわすことをやめはしないだろう。感覚(身体の表面)こそがひとと外界の接する面であり、感性が感覚に基礎をもつ認識能力にほかならないとすれば、環境の変化--その汚染と破壊--はまず感性的に認識されるはずのものではないだろうか。だとすれば、感性の衰頽とあのような無頓着(無関心)こそが、環境の汚染と破壊の根本的な原因であるということも、かならずしも不可能ではないだろう。
近代の工業化社会においてみられる感性の「疎外」現象は、じつは自律的な芸術の、いわばネガティヴ・イメージにほかならない。しかも自律した芸術は、たしかにかつての王侯貴族による囲い込みからは解き放たれたものの、やがて「美的(感性的)エリート」とでも呼ぶべき少数のひとびとによって独占されるにいたる。たしかに感性は、芸術の領域において多様化し、洗練はしたものの、個人的欲望の不断の充足という現実的原則の支配からしあわせにも解放された、「美的貴族」とでもいうべき一部特権者による独占は、その代償として、一般的な生活世界における感性の衰頽という現象をたしかにもたらしたのだった。大多数のひとびとは、現実的原則--欲求の満足と利益の追及--によってきびしく支配された世界のなかで生存している--生存してゆかねばならない--ために、環境の感性的な悪化を自覚することがすくなかったと思われる。環境の汚染と破壊に、感性と想像力の衰頽が密接に関係していることはあきらかである。感性の衰頽がその度合を増すほど、環境の汚染と崩壊は深刻の度合を強めてゆくだろう。環境汚染の問題を根本的に解決するためには、近代の理性中心主義と功利主義の枠組を脱して、感性をその本来の場に連れもどすことが不可欠なのではないか。おそらくここにこそ、美的環境としての景観を問うことの、あるいは環境の美学的観点からの検討の根拠があると考える。
6 環境の再生
問題は、感性の特権的な場である芸術を、その自閉的な聖域から取りだし、一部特権者の独占から取りもどすことだろう。ということは、芸術がその近代的なりかたを改めることにほかならない。たとえば美術館は、作品の聖域であることから脱して、ひとびとが感性を涵養するための開かれた場となるべきだろう。近代美学によって芸術の枠外に追いやられていた、テクノロジーの生み出したあたらしいイメージの役割を再評価すべきだろう。そしてテクノロジカルな媒体をとおしておこなわれる芸術の再配分の意義についても、あらためて考えるべきだろう。そして、芸術以外の感性的領域の開拓にも、意を用いなければならないだろう。最終的には、これらのことを通して、理性中心的で、功利的な世界の在り方そのものにたいする反省をうながし、感性をその本来の場にもたらすことを企てなければならないだろう。それは、おそらくは迂遠な道であるにちがいないが、しかし残されたわずかな道のひとつであることはたしかである。
近代の美学が、芸術の自律性を強調するあまり、それと社会との関係を、むしろ否定的にとらえる傾向を示してきたことは否めないのだから、美学は、これまで、間接的にではあったにせよ、かえって感性の衰頽を助長するという、きわめてアイロニカルな役割をはたしたとすらいうべきかもしれない--その点では、美学の社会的役割はたしかに否定的であった--。必要なのは、このことの自覚であり、それにもとづいた美学の自省なのだろう。にもかかわらず、以上述べたことのなかに、美学と社会のかすかな接点をさぐる、いくぶんかの手がかりがあることも、たしかなことのように思われる。美学的観点からなされる環境の記述は、これまでになされてきた社会科学的ないし自然科学的観点からする記述とはあまりにもことなったものであり、緊急の問題の解決にとっては無用のものと難じられるかもしれない。しかしまさにこの迂遠さと無用性こそが、環境のまったくべつのすがたないし側面をあらわしだし、やがては環境問題へのあたらしい視野をひらくことは、いくぶんかは期待できるのではないだろうか。
註
(1) Nicolai Hartmann:Asthetik, Walter de
Gruyter & Co.,Berlin, 1953.8.31
(2) たとえば、宗教的原理による「門前町」、政治的原理による「城下町」、経済的原理による「市場町」、交通的原理による「宿場町」などを考えることができるだろう。
(3) ここで用いた「ふさわしい大きさ」という用語は、いうまでもなくアリストテレスからの借用である。たとえば『詩学』第7章などを参照のこと。
(4) 第二帝政下、ルイ・ナポレオンの命のもとにオスマン(Georges
Eugene Haussemann, 1809-91)が行った改造の結果としてのパリ。
(5) このことについては、マックス・ウェーバー『資本主義精神とプロテスタント的倫理』(Max
Weber: Die protestantische Ethik und der
"Geist" des Kapitalismus, 1920)を参照のこと。
(6) ここでの「功利主義」は、いわば行動基準としのそれであり、倫理、政治、経済などに関する学説を意味しない。
参考文献
Rachel Louise Carson: Silent Spring, 1962.
竹内敏雄:『美学総諭』、1979。
淺沼圭司:『象徴と記号--芸術の近代と現代--』、1982。
Berleant, Arnold: The Aesthetics of Environment,
1992.
Berleant, Arnold: Living in the Landscape,
1997.
Berleant & Carlson(ed.): Special Issue
on Environmental Aesthetics, Journal of Aesthetics
and Art Criticism, 1998.
武藤三千夫(編):「都市環境と芸術:環境美学の可能性」、1996。
学問の理論性と社会性
渡邊二郎
【1】はじめに--本委員会の課題の確認
「学術の社会的役割」特別委員会は、第17期の日本学術会議の活動のなかでも、最も基本的な位置を占める重要な委員会と考えられる。というのは、今期の「活動計画」およびそれに対する「会長所感」のなかで、本委員会の設置目的と密接に関連する事柄が、今期の日本学術会議の最も重要な理念ないし課題として、繰り返し言及され、強調されているからである。
いま今期の「活動計画」のなかに示されている本委員会の設置目的を簡単に再確認してみると、次のようである。
1)学術は、知識体系の「構築」「蓄積」「伝播」「伝承」に貢献するという役割を超えて、「社会」に対して「行動規範の根拠」をも提供するという責務を負う。
2)「日本学術会議」のいままでの活動を「自己点検」し、その「役割」と「今後の在り方」を検討する。
3)こうして、「学術と社会の新しい相互関係」の構築を試みる(「負託自治」の自覚や、それに伴う「倫理」の問題を検討する)。
この構想を、現行の日本学術会議法と比較すると、そこには、ある新しさのあることが明らかである。というのも、従来の規定では、日本学術会議の「目的」は、どちらかと言えば、すでに出来上がっている科学の成果を、「行政に反映させ・産業および国民生活に浸透させる」(第2,5条)という、上からの、やや一方的な、啓蒙・開化・普及・応用・発展などの諸活動に中心があるとされていた。それに対し、ここでは、「学術と社会との新しい相互関係」(「負託自治」「倫理」)を自覚して、積極的に、社会に対し『行動規範の根拠」を提供するという責務が、強調されている。このことは、第17期の「活動計画」全体とそれへの「会長所感」からも、裏付けられる。そこでは、こううたわれている。
1)現代の高度に発達した多様性をもつ社会のなかでは、「人々」は--「個人」「集団」「国家」のすべてを含めて--「行動決定の根拠を学術に求める」ようになっている。日本学術会議は、この「行動規範の根拠を提供する責務」を負う。
2)その際に、「社会に現出する問題」に対して「高い感受性」をもち、「社会における現代的問題に対する自らの領域の責任」を自覚し、「現代的問題と学術の状況との関連について領域を超えた共通の理解」をもち、「共同研究体制」を組み、「現実的な根拠を社会に提供」しなければならない。
3)その場合に、学術の「予見性」ないし「予見能力」--「問題の顕在化に先立って情報を提供する能動的行動」--にもとづいて、「即応性」を発揮することが大事である。
4)しかも、複雑な現代社会の諸問題に対しては、「単一の領域」では解決が不可能で、「複数領域の科学者の協調的作業」が必要である。そのときには、そもそも、科学者に対する「人々の期待を理解し」、「人々から負託を受け」て研究にいそしむことを得ている「自治」を自覚し、「一般の人々」との「新しい型の共同研究」さえも構築し、「大学、国・公立研究所、民間研究所、産業界」の協力を推進し、「文系理系を含む」すべての学問分野の協力が大切である。
5)こうした意味での「開いた学術」を構築して、学術は、社会への「予測的警告者」「提案者」であらねばならない、というわけである。
【2】「行動規範の根拠」の提供ということについて
以上の基本方針には、学問のもつべき高次の実践的性格や社会的使命や倫理的責務に対する自覚が、明確に表明されていて、高い倫理性をそなえた現代学問観が提起されていると言ってよい。
しかし、以上の説明文言のなかには、もしかしたら、多くの人が躓くかもしれないようなひとつの問題点があることに、気付かざるをえない。すなわち、元来「学術的知識」は、「価値から自由」であるべきはずなのに、その学術が、「行動規範の根拠」をも提供しようとすると、もともと「行動規範」は「価値」を根拠としているのであるから、必然的に、学術は、実践的な価値判断に関わることになり、学問のもつべき客観的な理論性を毀損する結果になるのではないのか、という疑問が湧いてくる可能性があるからである。
したがって、ここから、「行動規範の根拠を提供する」とは、いったいどういうことであり、学問の理論性と実践性とは、どのように関係すると考えるべきなのか、という疑問が生じてくる。この問題を推し広げてゆくと、学問のもつ実生活を越えた高次の理論性と、それにもかかわらず学問がもつべき人類社会発展への貢献ないし寄与という実践的社会的使命や役割との間の、関係ないし相剋という、むずかしい根本問題が現れてくる。しかし、いま後者の大きな問題点は後回しとして、さしあたりまず、前者の「行動規範の根拠の提供」という問題点にだけ焦点を絞って、若干考察をめぐらしてみよう。
行動規範の根拠と言った場合、まず行動規範とは、一般に、行動の際に、「則るべき模範」、「実現されるべき理想、理念」、要するに、「当為」ないし「べし(sollen)」の立場を表している。一方、根拠とは、一般に、なんらかの事柄が、そうで「ある」ほかにはない「必然的理由」、その「存在の動かし得ない事実性」、その「存在(Sein)」を表している。したがって、「行動規範」の「根拠」を示すということは、なされるべき「当為」を支持する事実的理由の「存在」を示すということになるであろう。ということは、「当為」を「存在」から、つまり、「べし」を「ある」から導出しようとすることとして、矛盾を孕んだ試みではないのかという疑問が生じかねないわけである。この疑問に答えるためには、ここで、学問と当為・価値との関係、および、存在と当為・価値との関係について、若干考え直しておく必要がある。
まず、一方に、学問は当為に関わらず、事実確認にのみ自己を限定すべきであるという典型的に近代的な考え方がある。一例として、マックス・ウエーバーの『職業としての学問』から一部を引用してみよう。
「教室では、例えば民主主義について語る場合、まずその種々の形態を挙げ、その各々がその働きにおいてどう違うかを分析し、また社会生活にとってその各々がどんな影響を及ぼすかを確定し、次いで他の民主主義をとらない政治的秩序をこれらと比較し、このようにして聴き手が、民主主義について、各自その究極の理想(Ideal)とするところから自分の立場をきめる(Stellung
nehmen)上の拠り所(Punkt)を発見しうるようにするのである」(尾高訳)。
ここで、ウェーバーは、人が行動し態度決定するときの「拠り所」を、学問は提供するものであるというきわめて単純なことを説いているかのように見える。しかし、正確には、ウェーバーの言おうとするところは、やはり、学者は、あくまで「事実をして語らしめる」のみで、いかなる態度や立場を取るべきかを説くのは、予言者・指導者・煽動家の仕事であり、学者の任務ではなく、人は各自、みずからの信ずる規範・理想に従って、態度決定をすべきであり、その際、学者は、さまざまな事実認識を提供することにのみ、禁欲的に自己を限定すべきである、ということなのである。やはりウェーバーは、価値判断と事実認識を峻別しているのである。その根底には、およそ存在から当為を導出することはできず、「ある」と「べし」、存在と価値、事実確認と態度決定とは、決定的に別物だと見なす見解があることは明瞭であろう。
しかし、他面からすれば、別の見方も可能なのであり、そして実際、ウェーバーもそう考えているのである。というのも、事実確認をするときにすでに、その事実を、大事な、有意義な、重要な事柄として取り上げるという「価値意識」が働いているとも考えられるからである。むろん、それは、当の事柄の善悪を「道徳的」に「価値判断」して、「賞賛・非難」したりすることではない。けれども、ある事柄の事実確認は、他のさまざまな事実との連関のなかで、その事実のもつ「価値関係」的な「有意義性」に着目して、その事実を重要だと考えるからこそ、その事実を取り上げるのだと解釈することも可能なのであるから、そこには、「価値理念」が暗黙裡に前提されているとも言えるわけである。実際、さもなければ、無限に多様な現実のなかから、問題となるべき事柄や事実を取り上げるということ自体が、不可能になってしまうからである。なにか(たとえば、民主主義)を問題にするということは、それ自体がすでに、その問題を重要と見る解釈を暗黙裡に前提しているわけである。したがって、なんらかの事実認識は、その事実を、その意味と意義の点から重要と見る「価値理念」(ただし、それは善悪の「価値評価」ではない)を前提していることになる。
実際、これが、マックス・ウェーバーや、その認識論上の先達である哲学者リッケルトの考え方なのであった。無限の多様の現実のなかから、なんらかの事柄の重要性や有意義性に着目するからこそ、私たちは、次に、その事柄の客観的認識に専念できるのである。したがって、「価値からの自由」は、「価値への関係」と矛盾しはしないのである(ただし、むろん、実際の事実認識においては、主観的価値判断によって事実を歪めてはならず、あくまでも客観的に事象に即して実証的に研究を進めねばならない)。
こうした見解の根底には、実現されるべき当為や理想は、その可能的萌芽が、現実の事実のうちに宿っていなければ、それを実現することがそもそも不可能であるとして、存在と当為ないし価値とを、可能性と現実性との関係と捉えて、両者を相互に結びつける考え方があることは明らかであろう。
事実、その後の文化科学・歴史科学の認識論や、現代の科学哲学の認識論的諸思想も、そうした方向に向かっていると言ってよい。つまり、諸事実に着目するとき、すでにそれを包む解釈学的な諸前提を人間はもっており、その事実を重要と見なす暗黙裡の前提の上で初めて、私たちは、個別の学問的研究に取り掛かることができるのである。ただし、私たちはその際、その諸前提を自覚し直して、他の視野との融合を図って、できるだけ広い地平を獲得するように努力することが肝要である。さもなければ私たちは、独断的で偏狭固陋な視界の犠牲になってしまうからである。
いずれにしても、一般化して言えば、経験的事実を取り込む概念的組織なしには、人間の知識は成立しえないとする認識論が、現代の一致した趨勢であると言ってよいのである。換言すれば、現代において、学問や科学の理論や認識は、けっして現実の文化や社会の力動的な歴史的発展過程の坩堝から離れて、宙に浮いて成立するのではなくて、現実の展開のうちに根ざし、そのなかで、より良いものを目指して生きる人間の、可能性から現実性に向けてのさまざまな実践的行動的営為と結びついて展開すると見なされていると考えねばならない。
そこでは、全体を見通す、ある先見的な着想や理念や問題意識にもとづいて、個別の、また共同の研究作業が、具体的に、なんらかの探究課題を自覚的に選び取りつつ、形成され、こうして特殊の専門的な諸研究が、学問の各分野で、実践され、遂行されてゆくのである。しかし、それらの諸研究は、けっして、孤立した、自閉的な専門研究ではもともとなく、必ずや、時代全体の学問的・文化的・社会的・歴史的な広範な問題意識の総体によって、多かれ少なかれ、動機づけられ、影響され、そのなかから、みずからに固有の研究主題を汲み取ってきているはずである。この意味で、いかなる人も、時代の子であることを免れることはできないのである。
したがって、学問や科学の理論性は、その根底において、人間の歴史形成の実践的意識によって、支えられ、養われ、導かれていると言ってよいことになる。学問の理論的認識は、その実践的な理念や価値意識、社会的役割や機能と、けっして矛盾せず、むしろ、後者によって初めて活性化されうる性格を具有していると言うべきことになる。
その点とも結びついて、ぜひとも注意しておかねばならないのは、元来、「知」や「意識」や「自覚」を表す語と、「良心」を表す語とが、西洋においては、同じ語源に発するという事態が存在していたという事実である。そのことの含蓄を平易に噛み砕いて言えば、なんらかの「対象」について「知る」ということは、そのような知識作用を営んでいる「当の自分自身について知る」こと、つまり、そのことについて「自己意識」することを、必ず随伴させている。ということは、その対象についての知を、それについての自己意識にもとづいて、吟味し直すところの「良心的」な反省や、より良い方向に向けてのたえざる乗り越えの運動が、そこには必ず伴うということである。そのことは、知性の十全な活動には、より良いものを目指す意志の働きが、その支えとして、必ず随伴するものであるということを示し、それによって、基本的には、主知主義と主意主義との相互連関の事態が、暗示されているわけである。この意味で、学術や知識の十全な発展のためには、良心や良識にもとづいて、全体のなかに自己を位置づけ直す実践的な使命感や役割意識による自己吟味、それによるたえざる自己超克の精神などが、必然的な運命となるのである。
したがって、時代全体の問題意識のなかで、ある大事な問題点を先見的に主題化し、これについての理論的客観的な調査研究を遂行して、問題解決のさまざまな可能性や選択肢を予見的に提示することによって、「行動規範」の理論的事実的な「根拠」を提示することは、けっして学問の客観的な理論性や中立性を損なうものではないのである。それどころか、現代のように、複雑化してゆく文明社会のなかでは、従来見られなかったような未曾有の新しい事態が種々発生してきて、私たちから、新たな行動規範ないし羅針盤を要請し、知性にあふれた良識ある態度決定の根拠を確立するよう求めてやまないと言うべきである。そうした意味で、現代において、諸学問は、その理論的見識のすべてを引っ提げて、現実対処の最適な諸可能性や選択肢を明示して、さまざまな困難を乗り越えようとする人間的行動に対して指針を提供し、そのための学問的根拠を明示する義務があると言ってよい。
ただし、そうは言っても、学問や科学の理論性・事象性と、実践性・社会性とは、つねに調和するとは限らず、そこには、対立や批判的抗争を結果させるある種の緊張関係が存在し、また現に存在していたことも、事実なのである。過去の歴史的事実は、そのことを教えている。したがって、次に、学問の理論性と社会性とについて、もう少し広い観点から、考え直してみることが必要である。
【3】学問の理論性・事象性と、その社会的有用性・有効性との、連関と対立
(1)問題の発端とその古典的な形態
学問的な思考法の萌芽は、周知のように、古代ギリシアにおいて、直接的な生活の必要から解放された余裕(スコレー)のなかで、冷静にものごとを眺めやる観想(テオリア)の態度から発生した。それによって初めて、たんなる実用的知識を越えた、組織的な理論的知識が誕生するとともに、それ以前の宗教的神話的な見方から脱却した、合理的な思考法が可能になった。合理的、理論的な学問精神の発端は、ここに由来する。そこでは、実際の社会生活への直接的な寄与は当面問題ではなく、人々は「驚き」の精神にもとづいて、森羅万象に知的関心を振り向け、世界と自己のあり方のすべてに対して、知的探究を開始した。そこでは、いわば高い意味での「真理」や「本質」の探究が、目指された。
その結果、そこでは、一方では、虚偽の影の世界しか見ていない一般大衆の誤ったあり方が批判され、光輝く真実の世界に眼を向けねばならない知者の使命が強く説諭された。しかし、他方では、そのようにして少しでも真実に触れた知者が、その重要性を人々に教示し始めるや否や、そうした知者は、逆に、安逸を貪る一般世間からは、尋常ならざる異様な人物として指弾され、迫害される運命に見舞われる恐れのあることが、早くも自覚され始めた(プラトンの洞窟の比喩が、よくこの点を明示している)。したがって、そこでは、知者と世間、学問と社会とは、対立的な関係においてあることが、早くも自覚された。
そこでは、真理を究める学者は、一方で、その高い見識によって、世間の水準を越え、真理を先取りして、世間を啓発し、教育し、指導しなければならない積極的な責務を背負うことになった。しかし、他方で、そうした学者は、しばしば頑迷固陋な世間の偏見と戦わねばならず、場合によっては、世に受け容れられず、あるいは世の仲から迫害されることさえありうるという、否定的批判的な関係のなかに立たざるをえない状況が出現してきた。それゆえ、学問の理論や真理の圏域は、実世間の実利的功利的な修羅場とは、本来、別個であり、また別個の場を保証されなければ、真理の探究は遂行されええないことが、次第に自覚され始めた。
そこからして、逆に、あまりにも時流と密着し、ときにはそのなかで勢力を得るべく、それに合わせて学問的問題群を裁断し、時代に迎合し、時の勢力と社会の一般的趨勢にあまりにも左右されることは、こうした観点から見れば、曲学阿世の徒(ソフィスト)として非難されることにもなった。ただし、このことは、ギリシアの昔にだけあったことではない。また、それは、たんに学問と一般世間との間にだけ存在する問題でもなく、学者や知者相互の間、つまり、学派や専門家集団の内部でも生じうる問題なのであった。
というのも、たとえば、現代の考え方の枠組みを借りて言えば、学問上の真理や知識は、一般に認められまた専門家の間でも一時期支配的になっているところの、問い方や答え方のモデルをなすいわゆる「パラダイム」の形で影響力を振るっている。しかし、それをめぐっては、それでは解決できないさなざまな困難の指摘を介して、たえざる「科学革命」が、つまり、通常科学とそれを破る斬新な着想との間の抗争が、つねに結果してくる構造を本質的に背負っているのが学問や科学というものだからである(クーン)。いずれにしても、学問と社会との関係、あるいは真理およびそれを担う専門家集団と社会との関係、それどころか専門家集団相互の関係は、必ずしも平穏無事ではなく、そこにはさまざまな葛藤や対立のあることが明らかである。ソクラテスの刑死や、ガリレオの宗教裁判といった極端な場合や、あるいは、学問の諸分野におけるさまざまな学派間の論争の場合を想起すれば、この点は明らかであろう。
しかしながら、だからといって、真理探究としての学問研究が、社会との悲劇的な衝突のなかでのみ行われると見るのは、早計である。たしかに、一方で、学問は、その発端において、そしてその研究のさなかにおいて、一般社会の動向から離れた自立的な圏域の保証された場、すなわち、「学問の自由と自律」が打ち立てられたところにおいてのみ、初めて、十全な活動を遂行しうるものである。また実際、そうした理念にもとづいて、近代的な大学での研究教育が、これまで遂行されてきた。そして、そうした研究教育組織の場においては、「研究と教育との一致」という理念にもとづき、最新の研究内容そのものが、そのまま教育内容として、それに関わる知的探究者たちの切磋琢磨において、真剣に伝達され、研鑚の共通対象にされ、討議の課題とされていった。
たしかに、とりわけ「学問の自由と自律」という理念は、きわめて重要である。なぜなら、学問は、直接の功利的な実際的有用性とは別個に、まずもって、諸事象の真実の認識と把握や、真摯な考究と探究の態度においてこそ、初めて成立するからである。実際、たとえば、専門的な学者集団の内部においてさえも、個々人の独自な創意と工夫や、新機軸を開こうとする先駆的な着想や、通説を大胆に切り崩す独創的な発想などが、十分に守られ、評価され、こうして討議に付されうる、自由な、開かれた精神が存立していないところでは、学問や真理が死滅することは必定だからである。なんらかの全体主義的な政治的イデオロギーによって、学問研究の「自由と自律」が圧殺されたところでは、学問や文化の発展が阻害されただけでなく、その支配下にあった民衆のみならず、人類全体の生存の息の根が止められる恐れさえも生じたこと、そして、あまたの戦争、粛清、弾圧などの惨劇が起こったことは、歴史の教えるところである。したがって、実社会とは別個の「学問の自由と自律」の権限は、しっかりと擁護されねばならないのである。
けれども、そのことは、他方において、学問が、人類社会の実生活上の営為とまったく無関係であるということを意味してはいない。なるほど、学問は、多くの場合、実社会の諸問題には無造作には役立たないという面を保有してはいる。このことは、応用科学的な学問においてよりも、基礎科学的な学問においては、いっそう顕著に現れる。けれども、そのことは、応用的であれ、基礎的であれ、総じて学問が、結局のところ、間接的には、人類社会に貢献するものであるという事実を排除しはしない。なぜなら、人間生活の幸福は、ものごとの真実の知識の上にのみ初めて成り立ち、虚偽の知識は、人間の営為を、結局は破滅と不幸に陥れる悪魔の知恵と考えられるからである。したがって、逆説的な言い方をすれば、真実を探究する学問は、ある意味では、必ずしも即座には役立たない迂遠さをもつことによって、かえって、間接的には、また必ずや最終的には、人類の生活に大きく役立つものであるという姿において成立している、と言えるのである。
現実から距離を取ることによって、かえって大きく現実を視野のなかに収め、その真相を把握して、人々の蒙を開き、こうして直接的には必ずしも役立たないことによって、かえって人類社会に大きく貢献するという、この矛盾した、両義的なあり方から、学問と学者のもつ、相反する二面性が結果してくる。つまり、学問は、一方で、功利的な実際生活への無造作な没入を遮断し、場合によっては、文化や社会の閉塞した現状を批判し、ときには反骨の精神をもって、新たな視界を開く積極的な理論的精神の燃焼において、初めて活性化する側面を必ずや含む。しかし、他方で、それは、そうした現状批判的な姿勢をもおのれのうちに含みながらも、やがては真実の知にもとづいて、人類社会全体を指導し、教育し、より良い方向に向けてこれを教導しようとする、現実内在的な、創意に富む実際的諸活動をも必ずや結果させるのである。この二面性のなかを搖れ動きながら、いつの世においても、学者は、それぞれなりに、その営為を展開していると言ってよいのである。
(2)学問と社会との現代的関係の構築を促す諸契機
ところが、現代においては、以上の点に加えて、学問と社会もしくは人間のあり方との、一層密接な、新たな関係を構築し直すべき必然性が、学問自体の内部から生じてきたと言ってよい。そのことは、学問のなかでも、とりわけ近代科学の成立を省みることによって明らかとなる。
ここで肝要なのは、学問一般と、とりわけ近代科学と、後者の工業的技術的応用との、三者を、相互に区別することである。
ここで学問一般と呼ぶものは、諸事象に関する、経験と論証にもとづいた、組織立った認識と洞察の諸体系として、古い時代から現代に至るまで、さまざまな分野で、脈々とその営為を展開し、場合によっては刷新と変化を遂げて、発展し続けている、人類の広範な知的諸活動全体を指している。
しかし、そうした諸学問全体の展開のなかでも、とりわけ西洋の17世紀に成立し、ここ三百年の間に急速に発展し、自立化して大きな社会的影響力を行使しつつあるいわゆる近代科学が、あたかも学問の典型もしくは寵児であるかのようにして、その間に大きく前景に浮かび上がってきたという歴史的事情が、厳然として存在する。
そして、この近代科学が、その本質からして、工業的技術化を生み出し、またその結果、科学と技術の緊密な相互連関を作り出し、こうしてその相乗効果にもとづいて、現代の科学技術の時代が招来されている、と考えることができるのである。
まず、近代科学の成立事情について簡単に振り返ってみよう。
中世において神学の婢に貶められていた学問的精神は、西洋17世紀に至って、とりわけ天文学・物理学における一大「科学革命」となって出現し、これによって人類文化が、それ以前とそれ以後とに二分されるに至ったと、今日では一般に考えられていると言ってよい(バターフィールド)。そのときに生じた「近代科学」の思考法が、それ以後、近代的学問の方法論を典型的に代表するものと一般に目されるようになった。むろん一遍に、中世以来の神学的宗教的な見方が崩れたのではなく、近世初期には、たとえば、「虱」のなかにも神の摂理が働いていると見て(ルターやスワンメルダム)、自然研究が推進されていった。つまり、宇宙の創造主である神の栄光と摂理を証すために、自然の諸事象が見つめられ、研究されていったという面がなかったわけではない。けれども、結局は、やがて、現実を直視する近代科学そのものが、自立的支配権を確立して、自然の見方を規定する決定的な役割を果たした。
その近代科学の思考法は、一方で、経験的事実観察を重んずるとともに、他方で、そのなかに支配する関係を、数学的定式化を用いながら、普遍的法則として捉えることを目指すものであった。したがって、近代科学は、帰納と演繹、実証性と理論性、経験性と合理性論、対応性と整合性との二面を含む現実把握の認識論となって、展開した。
20世紀になって、この近代科学の方法論は、「仮説演繹法」として定式化された。つまり、近代科学は、諸現象を、「もしなになにならば、必ずこうなる」という仮説的な因果法則の形で捉え、そこから演繹される結果を実験的に確かめることによって、その法則の真理性を確証してゆく方法論において成り立つことが、明らかにされた(ライヘンバッハ)。また、この近代科学の思考法は、その因果法則の知による工業的利用の可能性を必ずそのうちに含むので、科学の技術的応用を必然的に結果させ、科学技術による近代的な文明社会を生み出す動因となることも、明らかにされた。
この結果、自然に耳を傾け、「自然に従う」ことによって獲られるこうした「力」としての「知」(べーコン)によって、文明社会を促進しようとする近代人の活力は、19世紀に至って、専門的な職業的「科学者」集団の階層を生み出すとともに、「科学知」によって社会を進歩させうるとする「実証主義」の潮流を広範な形で台頭させた。実証的な科学知こそ、「精密で確実、現実的で有用、建設的で、時代と相関的」だとされた(コント)。その頃からまた、理科系の諸分野のみならず、文科系の諸分野においても、学問を、近代科学の形態に合わせようとして、精神科学や、歴史科学や、文化科学や、さらには、社会科学や、人文科学といった呼称が流布し、近代科学の方法論を学問の典型的代表と見据えながら、それとの共通性や差異性において、みずからの学問の方法論を問い直す、認識論的な学問論や科学論が澎湃として盛り上がった。
現代においては、諸学問の方法・対象・内容は、きわめて複雑多岐にわたっている。そのなかには、必ずしも近代科学の「仮説演繹法」とは直結せず、それでいてきわめて重要な認識や洞察の成果を組織化して、人間的知性の輝かしい証となっている諸学問が、古来から、また刷新を経て、現代においても、数多く存在している。いわゆる科学技術の開発とも繋がる「法則定立的」な近代科学とは別個に、文科系と理科系とを通じて、諸事象の「基本的特質を記述的に組織立って把握する」、きわめて基礎的な諸学問が、あまた存在して、人間の世界認識の基本を形作っていることは、なんぴとも否定できないであろう。
けれども、そうした諸学問の活動のなかでも、前述の「仮説演繹法」を取る「近代科学」の理念が、強い牽引力を振るって、科学技術の現代文明社会を生み出す根本動因となっていることもまた、否定できないのである。ところが、その「近代科学」とその「技術」的応用とに、いくつかの根本的に再反省すべき問題点の含まれいることが、次第に明らかとなってきた。
1)たとえば、まず近代科学は、元来、それ以前の「目的論的自然観」を崩壊させ、現象の「隠れた性質」や「実体的形相」を問わずに、ひたすら現象を冷徹な因果関係においてのみ捉える「機械論的自然観」を取るために、そこでは、出来事の意味・意義・価値・理由などは、かえって抹消され、不明となってゆくという広義のニヒリズムの意識を蔓延させる結果となった。ところが、人間は、そうした客観的な事実確認にとどまることはできずに、世界のなかでいかに生きるべきかの目的や価値や意味を問題にせざるをえない存在者なのである。したがって、実証的な事実確認の科学の知識だけでは満足することができない面が、科学技術の発展に伴って、いよいよ強く人々のうちに自覚されてくるという逆説的な結果が招来された。
2)加えて、科学はつねに個別諸科学として細分化し、その全体が見通せず、専門化と分裂化は、いよいよ甚だしく、総合的全体化は容易ではなく、学際化の動きも再び細分化の流動の渦のなかに巻き込まれてゆき、世界の全体を科学知のうちに集約し尽くすことは、事実的にも、また原理的にも、ありえないことが判明してきた。というのも、近代科学は、「もしなになにならば、必ずこうなる」という、必然的な絶対的法則を打ち立てようとするが、それが経験科学においては、きわめて困難であることが明らかとなってきた。というのは、「もしなになにならば、必ずこうなる」という因果法則の定立は、主として、これまでの観察事実に依拠して提出されたものであるが、その因果的予測は、まだ起きていない未来の現象にも関係している。ところが、有限的な人間は、未来永劫にわたった絶対的な形で、因果法則の妥当性を主張しうる力をもちえない存在者であるから、ほんとうは、「もしなになにならば、ある百分率においてこうなる」というように、科学法則は蓋然的・確率的・統計的な法則として理解されねばならないことが自覚されてきた(ライヘンバッハ)。言い換えれば、科学的法則は、これまでの経験によって「反証」されていないというにすぎず、未来永劫にわたった絶対性を基本的にはもちえず、経験の進行と歩調を合わせて、たえざる吟味と修正を施されてゆかねばならないものであることが、確認されてきた(ポパー)。
3)さらに、科学的知を工業的に応用した技術は、たしかに一方で、人間の労苦を軽減し、快適な生活環境を作り出し、余暇を生み出す利点をもつが、反面で、その技術の肥大化によって、自然資源の枯渇や、さまざまな環境破壊の予測しえない結果が生じ、文明社会の行き詰まりや困難を自覚させる事態が、大きく出現してきた。その上、人間の教育や、愛や、精神的活動や創造の働きは、それなくしては人類社会が発展しえない原動力であるが、これらは、科学技術の知や力によっては、どうすることもできない事柄であることが、銘記されてきた。こうして、科学技術とは別個に、現代の歴史的文明社会のさまざまな難問に答える総合的かつ実践的な知性の必要性が、いよいよ強く、多くの人々によって実感されてきたのが、私たちの生存する現代という時代状況の課している問題点であろう。
さて、こうした状況のなかで、現代人は、いったい、いかなる考え方を取ったらよいのであろうか。
現代という時代の特徴は、従来の学問科学の根底に潜む「客観的」な「真理」観に加えて、さらに、もうひとつ「行為的」な「真理」観をも、私たちがいよいよ真剣に考慮に入れざるをえなくなった時代状況の出現というふうに、これを言い表すことができるように思われる。
その意味を敷衍すれば、次のようになるであろう。すなわち、私たちは、ただたんに、現実から一歩退いて、冷静に、客観的に、諸事象の真実を探究するという認識的行為に、人間的知性の証を求めうるばかりではない。むしろ、私たち人間は、本質的に、見通すことのできない現実のなかに立って、一瞬といえども、いまだない未来に向けて、決断し、行為して生きることを止めることのできない存在者なのでもある。したがって、私たち人間は、その際には、完全ではないかもしれないが真実を教えうる唯一の人間の営みである学問科学の現在の時点での成果と知見の全体をたえず参照しながら、現実の状況が課す困難を解決すべく、より良い未来に向け、より多くの意味と価値と意義にあふれた人間と世界のあり方を目指して、行為し、決断して、生きてゆかねばならないのである。換言すれば、人間は、そうした意味での「善」を目指して、人類の歴史的社会の形成作用のうちに参画することを止めることができない存在者だと言わねばならない。
したがって、現代における学者や知者は、たんにこれまでの経験的事実に立脚した「客観的」な理論構成という事実確認の「真理」観にとどまるだけではなく、それらの知見に根拠を得ながらも、さらに「善」を目指した形での知識全体の再構成と有用化を目指して、すなわち、そうした意味での「善」に根拠を置いた「正当化された信念」の体系である「知の体系」を打ち立てて、現代の諸課題と向き合わねばならないことになる。学問科学が、生存の意味や価値の問いに答ええず、しかも細分化と専門化のなかで、けっして完結することのない試行錯誤の真理探究の途上にとどまり続け、あげくの果てには、その工業的応用としての科学技術が、予測しえなかった多くの困難を招来しつつあるのだとすれば、いまや、私たちは、現在の学術を総覧しつつ、新たに「善」の実現に役立つと信ぜられる「正当化された信念」の体系、すなわち「真」なる「善」、「善」なる「真」の体系を、再確認し、あるいは再構築する義務があると言わねばならない。
「真理」とは、人間の営為と無関係な、「客観的」な存在の事態を指すと考えるだけではなく、存在のうちに「善」を目指して進む運動を洞察し、そうした「善」に支えられ、「善」に向けて活性化されるべき、知性のもつ基本的な良識の性格、すなわち「善」に奉仕するものとしての「真理」の性格を、改めて人は自覚しなければならない時にきているとも言える。そのような「善」が、個人にとどまらず、人類社会全体の「共同善」に繋がり、学問のもつべき新たな「社会的役割」の自覚を結果させることに結びつくものであることは、言うまでもないであろう。
そのときには、学者や知者は、できるだけ多くの人々の間に、そうした「善」なる「真」の内容に関して、「合意」と「同意」を樹立するために、無限の努力をしなければならないことになる。真理は、人間の営為と無関係に、その彼岸に超越的に存在したり、また突然人間の上に天下り的に降ってくるものではなく、むしろ、人間相互の間に「同意」と「合意」を樹立する果てしない人間的努力の上にのみ、ようやく築かれ、達成され、しかも「善」として「社会的に影響力を行使してゆくべきもの」と見なされねばならない。この考え方にもとづいて、学問の各分野で、困難な問題の解決に向け「善処」すべく努力している、さまざまな問題意識や提案が、明確に提示されて、学問に携わる者の実践的な「自己理解」が社会全体に示され、また、社会全体の側からの批判をも仰ぎつつ、「善」なる「真理」の内容に関する「合意」と「同意」が、できるだけ広範な形で達成されてゆくことが必要である。ここに、現代における「学術の社会的役割」の基本的なあり方が成立すると考えられるのである。
(付記。本稿は、1998年4月24目に、「学術の社会的役割」特別委員会において報告され、提出された拙稿に、若干、加筆修正を施して成ったものであることを付言する。1999年12月25日、渡邊二郎記す。)
文科系の純粋基礎研究の重要性
渡邊二郎
日本の社会のなかでは、文科系に属する基礎的諸学問やそこでの基礎研究(これを、理科系の科学技術における基礎研究と区別して、純粋基礎研究もしくは根本研究と呼んでもよい)に対する、無視もしくは蔑視が、大手を振って罷り通っている。この惨状は、眼を覆いたくなるほどの無残さである。日本の社会のなかでは、理科系の科学技術以外は、ほとんど特別の考慮に値しない学問と見られていることは、明らかである。
平成7年に制定された「科学技術基本法」においては、「科学技術」こそが、「我が国及び人類社会の将来の発展のための基盤」であり、その「科学技術に係る知識の集積が人類にとっての知的資産である」と宣言されているが、この「科学技術」からは、「人文科学のみに係るものを除く」ことがそこでは明記されている。この基本法では、我が国の全体をあげて、「科学技術の振興」に関する「施策」を「策定」し、「実施」し、「法制上、財政上又は金融上の措置」を講ずることが明言されているが、そこからは、「人文科学のみに係るものを除く」ことが、明確に宣言されているわけである。
このことは、すでに昭和30年代の初めに、科学技術庁や科学技術会議が設置された時以来の長い歴史をもち、戦後の日本の学術の基本動向を規定してきた考え方である。昭和31年の「科学技術庁設置法」は、その劈頭から、「人文科学のみに係るもの」を「除く」と明記した上で、「科学技術の振興」を図るための「行政」の推進を謳っている。また、昭和34年に制定された「科学技術会議設置法」も、「人文科学のみに係るものを除く」と明記した上で、「科学技術」一般に関する政策の樹立のために会議を開くことを宣言している。
このように人文科学を除いた上で、「科学技術の振興」が目指されるのも、ひとえに「国民経済の発展に寄与するため」にであり(「科学技術庁設置法」)、「科学技術の水準の向上」が、「我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与」し、ひいては、「世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な発展に貢献する」と考えられるからだとされている(「科学技術基本法」)。「科学技術の振興」こそが、「国民経済の発展」や、「我が国の経済社会の発展と国民の福祉」に寄与し、「人類社会の持続的な発展」に貢献すると見なされ、「人文科学のみに係る」固有な文科系の学問は、およそまったく、そうしたことに関わらない、特別に振興の配慮を施す必要のない学問として、ここでは明確に切り捨てられている。
なるほど、平成7年の「科学技術基本法」においては、その間の諸種の苦い経験にもとづいて、「自然科学と人文科学との相互のかかわり合いが科学技術の進歩にとって重要であることにかんがみ、両者の調和のとれた発展について留意されなければならない」と述べられ、「人間の生活、社会及び自然との調和を図」ることの重要性が指摘されている。けれども、その法律において「振興」されるべき対象と目されている「科学技術」のなかには、やはり、「人文科学のみに係るもの」は入っておらず、除外されているのである。したがって、自然科学と人文科学の「両者の調和のとれた発展」ということは、ただの言葉の上での謳い文句にすぎず、もっぱら「人文科学」に関わる振興は、眼中に置かれてはいないのである。しかし、人文科学そのものを振興しないでおいて、どうして、それと自然科学との「相互のかかわり合い」や「調和のとれた発展」などが、十全な形で実現されえようか。
あるいは、人あって、こう言うかもしれない。そこでは人文科学「のみ」に係る研究を除外すると言っているのであって、人文科学が科学技術と学際的、総合的に連携して研究を進める場合をけっして排除してはいず、むしろ「両者の調和」を歓迎しているのである、と。しかしながら、「人文科学」固有の研究には特別の振興を振り向けず、もっぱら「科学技術」の振興に特別の配慮を講ずる旨を断っておいて、それでいて、人文科学に、学際的、総合的研究に加わってみたらどうか、というのは、随分と人文科学を馬鹿にした言い方ではないであろうか。人文科学と自然科学の「両者の調和」を図るなどという文言が、空疎な台詞にすぎないことは、ここからも明瞭である。要するに、人文科学などを振興しても、我が国の「国民経済」や「経済社会」の発展になんらの寄与も期待することはできないから、これを振興の対象から除外するというのが基本の姿勢であり、ただし、少しく、「科学技術」と「人間の生活、社会及び自然との調和」を考慮しないと具合が悪くなったので、人文科学が、学際的、総合的研究に加わってくれるなら、特別の反対はしないという程度のことにすぎない。その場合でも、学際的、総合的研究の主体は、「科学技術」ないし「自然科学」の側にあり、それこそが振興の対象であり、それに付随的に人文科学が付け加わって、対外的な倫理的側面に色合いを付ける役割を演じてくれればいいという程度のことにすぎない。少なくともそれ以上のことは、そこからは読み取ることができないというのが、この条文の偽らざる実態であろう。
人は、しばしば、近時において、学際的、総合的研究の推進とかを話題にする。あるいは別様の言い方をすれば、諸分野全体を誰かが上のほうから鳥瞰し、眺め下ろし、見渡して、これこれの分野は統合してこれこれの問題を考えるべしといった指令を発して、なにやら現実的と思われる研究課題を設定し、人々を煽れば、それによって、学術全体のいっそうの活性化が期待され、達成されるかのごとき風潮が広まっている。
もちろん、現代において、世界全体に関わるような、多くの複雑な問題が出現し、多方面的な解明や、さまざまな専門的知識の糾合が要求される傾向が強まってきたことは、否定することができない。こうした統合化された研究の必要性は、十分理解できることである。けれども、だからといって、学問的研究がすべて、そうした多人数による統合的研究に切り換えられるべきだということにはならない。伝統的な個別の単独な研究も、いぜんとして、それなりの正当性の権利を保有している。学問的研究においては、最終的には、ひとりひとりの研究者の独創的な構想と着想と判断と推察と洞察と探究と立証とに、すべては帰着するからである。
しかしながら、そればかりでなく、およそ、鳥瞰的に複数領域を統合しながら、学際的総合的な連携協力態勢を取って研究を進める場合でも、いったい、誰が、あるいは、どの分野が、あるいは、いかなる理念が、また、どのような方法論が、主軸となって全体を締め括るのかによって、同じ問題を扱うときにも、大きくその様相が変化してくることは明らかである。もしも、その指導的理念が、時流に迎合し、政治的な権力に阿り、経済的効率や実際的利益への奉仕を狙い、その他さまざまな私的な特殊的個別的な利害関心や名誉欲と結び付いているならば、それと直結しない諸研究動向は、直ちにそうした統合的研究から除外されることは明らかであるし、また、そうした研究活動が、政治的党派性を帯びて、学問性を失う危険にさらされやすくなることも自明の理である。したがって、統合的であれば、つねに正当に、公明正大な仕方で、研究組織が構築され、また遂行されていると思うのは滑稽である。およそ、神ならぬ身の人間のうちの誰が、真に全体を鳥瞰しえたなどと自称する権利を持ちうるであろうか。もしも本気でそうしたことを考える人がいたならば、それは尊大の極みであろう。いかなる全体化も、個々人の特殊的な遠近法の視野に伴う制限を免れるものではないからである。
もちろん、自己の特殊性を乗り越えてゆく全体化や普遍化への努力は、つねに尊重されねばならない。しかし、問題は、ひとえに、その全体化の理念と原理、方法態度と学問観、その根底にある人間観が、何であるかに懸かっている。もしも、現在の「科学技術」の根底にある学問観や科学方法論を金科玉条として、これを微動だにさせずにおいて、そこに、取って付けたように、矢庭に、人文科学を追加してみたりしたところで、なんらの真の統合的研究も行われえないであろうことは、火を見るよりも明らかである。
たとえば、すべて人間の活動は脳の働きに帰着すると見なす脳科学研究の原理をあくまでも固持した上で、それの推進に巨額の国費を投入しておきながら、突然今度は、心の教育が大事になったと叫んで、慌てふためいて、心の教育という研究課題を設定してみたとしても、いったい、どうやって、その脳科学推進と、心の教育研究推進とを、統合させ、両立させる研究組織を、矛盾のない原理の上にもとづいて、構築することなどできるであろうか。もしも、脳科学研究を主軸とするなら、脳科学研究者に、脳の機能を操る新薬でも良薬でも発明してもらって、それを飲ませて、青少年の健全化を図るという目論みを設定するのが、最も論理に適っているはずなのだが、さすがに誰もそうしたことを言わないのは、それでは、人間の人格や心の働きをあまりにも侮辱することになり、あらゆるところから反撃されるのを恐れているからである。人間を、脳やその物質的作用の薬理学的効果に還元させるのは、あまりにも極端な、精神蔑視の人間観であることを暴露することになるので、誰も、そうしたことを公言しないのである。けれども、脳科学の専門家の大部分は、やはり、あくまでも、密かに、心を脳に還元できるものと独断的に決め込んでおり、みずからの「科学技術」的研究のそうした基本方針を絶対に変更する気持ちなどを毛頭も持っていないはずである。なぜなら、それを放棄することは、「科学技術」としての脳科学の原理を放棄することに繋がるからである。それなのに、どうして、そこへ、突然、心の研究を重ね合わせることなどできようか。もしも、本気で、心の教育という問題を考え直そうと思うならば、人は、心の働きの主体としての、脳ではない、人間的自己そのものを問題化しなければならない。それは、人文科学の領域に固有に属する問題である。しかし、人文科学は、現代の「科学技術」の振興の対象にはなっていない。しかも、心の働きの主体としての人間的自己という視点は、心を脳に還元しうるとする脳科学の原理とは矛盾する。したがって、この二つの研究分野を真に統合しうるような学際的、総合的な研究組織を構築することは、原理的にきわめて困難な課題となってくる。もしも、それが可能だとすれば、一方を主とし、他方を従とするやり方を取るしかないであろう。そして、もしも世間の人々が、心の教育をほんとうに人事だと思うならば、心の働きの主体としての人間的自己を問題化する人文科学を主とした研究態勢を組み、脳の物質的機能を研究する脳科学の役割を、その物質的機能の疾病に対する医療技術の開発という本来の科学技術の手段知と心得て、統合的研究を遂行するという、現在とは逆転した研究態勢を組織しなければならないことになるであろう。果たして、現代の学術関係者が、この種の問題に対して、こうした逆転した研究態勢を取ることを承認することができるであろうか。多分、それは、ありえぬ事柄であると推断されうる。
いずれにしても、学際的、総合的、統合的、鳥瞰的、効果的、先見的、予測的、予防的な、現実的な研究組織の実践は、かけ声だけでなく、基本の原理にまで遡って、その明確な研究理念と方法論を合意することなしには、正しくは実践されえないのである。このことは、きわめて明らかなことなのだが、誰も真面目にこの問題を考えることをしない。誰もが、ただ付和雷同して、学際的、総合的研究といった合言葉に、うつつを抜かしているだけである。大勢寄り集まった研究遂行の一員になれば、なにか意味のある仕事をしたかのような錯覚と安心感が得られることから、今日、研究者は、単独な学問的研究の真剣さを忌避しようとするばかりか、なによりも、諸学問の根本を省みる原理的基礎的な考究から、眼を背けようとする傾向が強い。もしも、現代の学術に、真に総合的で全体的な視野の樹立が必要であるというのならば、まさに、それら諸学問の基本の理念と方法とを省みて、学問の原理的全体を自覚する、きわめて基礎的な思索が必要であることは明らかである。知や認識の基本原理にまで遡り、人間と世界のあり方を省みる、こうした基礎的研究こそが、いつの世にあってもけっして見失われてはならない学術の根本なのである。それどころか、学術の発展が複雑で多様化してきた現代においては、とりわけ、たんにそれらの特殊的個別的な実証的研究成果の産出に勤しむばかではなく、それらの基本原理に立ち返って、学術や文明や人間社会や文化の全体を反省し直す、純粋に基礎的な学問的探究が必須なのである。あらゆる研究者が、なにほどか、それぞれの領域において、こうした基本的な学問論的反省を遂行しなければならない時代が、現代という時代の運命だと言っても過言ではない。なぜなら、そうした省察なしでは、地球上の人類の生存さえ危ぶまれるほどの文明論的な危機のなかに、現代の人類は置かれているからであり、このことは、ここで改めて縷説する必要もないであろう。
さりながら、そうした基礎的研究ということになると、しばしば人は、「科学技術基本法」において、「基礎研究」が重視されるに至ったと述べて、必ずしも、現代においては、「研究開発」の「実用化」だけが念頭におかれているのではないことを強調する。しかし、「科学技術基本法」で話題になっているのは、あくまでも、「科学技術」に関係する「基礎研究」にすぎない。なるほど、そこでは、「基礎研究」が「新しい現象の発見及び解明並びに独創的な新技術の創出」をもたらし、重要であるにもかかわらず、「その成果の見通しを当初から立てることが難しく」、「その成果が実用化に必ずしも結び付くものではないこと」に留意して、「基礎研究」の困難かつ枢要な役割を認識しつつ、これを「推進」する必要のあることが謳われている。そのために、「研究開発」は、「基礎研究」、「応用研究」、「開発研究」、および「技術の開発」に分けられ、それらにおける「基礎研究」の重要性がたしかに言及されている。しかしながら、看過してはならないのは、それがあくまで、「科学技術」に関わるかぎりでの「基礎研究」にすぎないという点である。つまり、そこでは、「人文科学のみに係る」ような「基礎研究」は、最初から排除されているのである。したがって、文科系の諸学問における「基礎研究」は、現代日本において、特別の考慮を払って振興されるべき学問分野とは見なされていないことが、あまりにも明らかなのである。この法律における「基礎研究」の重視をもって、あたかも文科系の基礎研究をも視野のなかに入れたかのごとき説明をする人は、欺瞞と錯覚によって人を愚弄する虚言者であると言わねばならない。
したがって、我が国においては、積年の間、文科系の純粋な基礎研究もしくは根本研究は、大学等において、途方もない冷遇措置を受けて、非実験講座の名のもと、劣悪な研究環境のうちに置かれ、科学研究費の配分においても、巨額の国費を賄われるビッグ・サイエンスないしメガ・サイエンスと較べて、まことに粗略な扱いを受けるのが実情となっている。これに反して、科学技術関係の研究者たちは、多額の研究費を集めうる研究が、良い研究なのだ、とまで豪語して憚らない体たらくである。お金に眼が眩んだ世間一般の皮相な学術理解の頽廃の極致が、ここに露呈していることは、明白である。学術も国や社会の経済的援助によって成立している負託自治を自覚すべきであると、もしも誰かが本気で主張するのであれば、その人は、これらの巨額の国費によって賄われているビッグ・サイエンスないしメガ・サイエンスが、どれほど適正に国費を使用し、それに見合った研究成果を挙げているのかどうかを審査し、評価する作業を、厳密に励行すべきであろう。
学術は、いつの世においても、その真実の知とそれの応用とによって、最終的には、人間の生活に必ずや貢献するものである。なぜなら、真実に基礎を置かない、あらゆる迷信邪教や、荒唐無稽の所説は、必ず人類を破滅に導くからである。教育の普及を介して広まってゆくべき、こうした学術全般の持つ社会的貢献と役割という事態は、けっしてゆるがせにしてはならない人類社会と文化を主導すべき根本的理念であろう。けれども、そうした学術の社会的寄与を、単純に、その知の応用から生まれる、なんらかの政治的、経済的、工業的、産業的、農業的、医療的な、直接の有用性に限定してはならない。そうした有用性もむろん重要ではある。けれども、実際的効果の産出に先立って、つねに、学術的研究においては、基礎的な調査、事実確認、観察、資料収集、吟味検討、実験、思考、推理、討論、言説的提題その他の、実に労苦にみちた、地道な研究作業が、遂行され、また蓄積されてゆかねばならない。さもなければ、実証性と合理性とを兼ね備えた、着実な学問的探究は、およそ、どこにおいても、成立しないからである。このことは、理科系と文科系とを問わず、あまねく妥当する学問の根本特質を成していると言ってよい。
けれども、理科系の「基礎研究」については、「科学技術基本法」によって、すでに光が当てられている。それに引き替え、文科系の純粋基礎研究もしくは根本研究は、多くの場合、既述のように、非実験講座の扱いを受け、ほとんど世間の公の配慮からは除外され、日の当たらぬ、薄暗い書庫のような狭い場所に置かれて、世間から無視され、冷遇された環境のなかで、わずかに個々の研究者の情熱と使命感に支えられ、その犠牲的奉仕によって、辛うじて維持されているにすぎない。もちろん、文科系の学問も幅が広く、法律学や政治学、経済学や経営学、教育学や心理学や社会学などの、比較的実生活に密着した分野もある。しかし、文科系の最も文科系らしい基礎的学問は、哲学や歴史学や文学などの諸分野のうちにある。これらの諸学問こそは、最も根本的にすべての学術領域に関わるがゆえに、いよいよその基礎的学問としての普遍性を保持している諸探究であると言ってよい。しかしながら、こうしたいわゆる哲・史・文と呼ばれる純粋基礎研究ないし根本研究の分野は、そのきわめて重要な学問性にもかかわらず、多くの学者や研究者や実務家や世間一般の人々からは、不幸にして、その営為の大切さを理解されていない諸学問なのである。
しかしながら、いかなる人間的活動も、言語的表現を離れては十全な形では成立せず、また、言語的表現のうちで蓄積されてきた広範な人間的経験の理解なしには、何事も正しくは遂行されえないのであるから、いかに言語的表現全般に関わる文学が、学術一般を規定する重要性を持つかは、誰の眼にも明らかであろう。現代は、文字の時代でなく映像の時代であるなどという愚説が、テレビなどの普及に伴って、一人歩きしているが、こうした見解が謬説であることは、言語的説明を伴わないたんなる映像の提示が、人間にとっては理解不可能な画像の羅列に終わることを誰もがよく実感すれば、明白であろう。言語は人間にとって本質的だからである。
また、人間が、いかなる活動を展開するときにも、みずからの関わる事柄の歴史的由来とその発展過程、さらにはその事柄の将来におけるあり方の展望などを打ち立てることなしには、人間は、十全には、真に人間的な営為を繰り広げることができないことは明らかである。来し方と行く末を考えるという時間的構造を、人間は免れることができない以上は、どのような場面においても、歴史的理解は必須である。歴史とは、現在と無関係な過去の諸事実を暗記することではない。将来を見通しつつ、これまでの経過を振り返りながら、現在の大切な問題的状況のなかに立ち入っていこうとする人間の本質的なあり方が、歴史そのものなのである。科学技術さえも、その歴史的生成ぬきには、十分に理解されないであろう。歴史的省察が人間にとって本質的であることは、明白であろう。
さらに、人間が、人間らしく、よりよい生き方を目指して、行為して生きていこうとするときに、あらゆる物事の基本を考え直し、この世に生きるときの人生観・世界観的な根拠を自覚して、みずからの存在経験を研ぎ澄ませながら、現実に対処してゆく必要のあることは、言うまでもない。このような最も基本的な考察と反省が、哲学と呼ばれる学問的営為にほかならない。してみれば、人間が生きているところのすべての場面において、哲学的洞察が先導的役割を演じなければならないことも明らかである。とりわけ、社会が複雑化し、文明化が拡大し、科学技術が甚大な影響を及ぼし、あらゆる面でさまざまな考え方が葛藤を起こし、価値観や生活の基本原則が揺らぎ、地球上の人類生活や文化における摩擦が大きくなっている現代においては、人間生活のすべての局面における根本原理の再反省にもとづく哲学的な相互理解と意志疎通が、いよいよもって重要となることは避けがたい。科学や技術、知識や認識、言語や理解、自然や歴史、自己や他者、社会や政治、経済や産業、健康や福祉、美や芸術、道徳や規範、善や悪、宗教や救い、死や幸福、生き甲斐や愛など、ありとあらゆる人間生活の問題場面のいっさいが、いま、その基本的原理をめぐって、哲学的な再反省を要求している。なぜなら、現代は、まさしく、時代の大きな転換期だからであり、また、人間は、たえず思慮しつつ、生きる道を模索せざるをえない形而上学的な動物だからである。この意味で、哲学することは、人間にとって、本質的なのである。
以上のような文科系の純粋基礎研究ないし根本研究が、いま絶対に必要不可欠である。そうした研究と思索にもとづいてのみ、学術の社会的役割という根本問題も、ほんとうに正しく見つめられ、また、実践されてゆくことができると考えられるのである。
現代における哲学の社会的役割
渡邊二郎
1.哲学の社会的役割に関する誤った解釈の事例
哲学の社会的役割といったとき、もしかしたら人は、「これまで哲学者たちは世界をたださまざまに解釈してきたにすぎない、肝要なのは、世界を変革することである」と説いて、哲学を、政治的実践に奉仕させようとした過激な主張を、思い浮かべるかもしれない。けれども、特定の主義主張に固執した、こうしたきわめて党派的な変革の政治的イデオロギーは、やがて、その虚妄を暴露されて、崩壊してゆく運命を免れ難い。実際、20世紀の歴史は、そうしたマルクス主義の瓦解を決定的に刻印づけた。なぜなら、哲学は、やはり、たとえいかに実践的立場を強調するときでも、世界に関する正しい解釈を打ち立てるという、最も基礎的な、理論的洞察の錬磨と自己吟味の作業をけっして怠ってはならないからである。哲学の課題の基本は、あくまでも、存在の真実を、正しく見据えることを目指して、学問的洞察を形成しようとする、細心入念な研鑚と努力に存する。そうした存在経験の精錬を怠った徒に党派的な実践謳歌は、哲学を、短見浅慮の政治的権力闘争の泥沼に陥れるだけであろう。
しかしながら、他方で、そうした理論的な哲学的探究といえども、やはり、さまざまな立場の対立や見解の相違、さらにはそれにもとづく種々の論争や抗争を、払拭できない随伴現象として纏綿させていることも事実である。実際、過去の哲学思想の歴史が、哲学的真実をめぐる激しい闘争の場であったという面は否定できない。そうしたところから、逆に、今度は、哲学的な世界観に伴う甲論乙駁や、諸見解の多元的乱立の状況に耐え難い不満を抱いた一群の過激な人々が、従来のいっさいの哲学思想を、無意味の、にせの命題の集まりと見なし、これを一掃するところに、みずからの哲学の新しい社会的役割を考えるということが出来した。こうした哲学否定の過激な哲学者群の代表が、20世紀の論理実証主義者たちであったと言ってよい。けれども、、過去のすべての思想的営為を、経験的検証を欠いた虚妄の形而上学と断定して、治療的効果を挙げうると錯覚したこの種の偏狭固陋なグループの考え方が、その後、その独断的な暴挙をあばかれて、崩壊したことも事実である。なぜなら、彼らの主張そのものが、経験的検証を欠いた暴論であり、なによりも、そこでは、検証の根拠となる経験の概念に、曖昧さが残ったからである。感覚的経験にすべてを還元しようとする試みが、複雑な人間的経験を正しく汲み取ることのできない偏頗な見解であることは、あまりにも明らかだったからである。
哲学思想の社会的役割を重視する考え方としては、さらに、19世紀後半以来現代に至るまで、広範な形で影響力を行使しているアメリカ発祥のプラグマティズムの思想がある。そこでは、社会的現実のもつ諸問題や諸困難に対する実効性に富む着想や発案の形成が、人間的活動の基本と目されるという、実用主義的な思想が、率直に提起された。そのために、ものごとの理論的な観念内容よりも、その観念のもたらす現実的な結果のほうが重視され、生きることに役立つ有用性が観念の眼目として尊ばれ、困難解決のために有効な道具として働く知性や科学の役割が肝要と見なされた。こうして、そこでは、理論的真理は、ひとえに社会的な善のために奉仕すべきものとして位置づけられ、もっぱら実用的な効果を重視する思想が主軸を占めるに至った。たしかに、ある意味では、こうした考え方が、実効性にあふれた問題解決の努力や、創意工夫や、現実的な施策や処方箋の形成に力を発揮して、哲学思想に社会的役割を保証する大きな可能性を開きうる要素を含むことは、否定できない。けれども、こうした考え方の場合に、いったい社会的効力とは何であるのかが、つねに判然としない点が、最大の問題点として残った。換言すれば、そこで目指されている善が、いったい何であるのかが、やはり、たえず鋭く問い直されねばならなくなったのである。場合によっては、そこでは、与えられた状況に適応して、ひたすら成功裡に自己保存を達成しようとする適者生存の生物学的な本能主義と、それにもとづく自己中心的な党派性やエスノセントリズムが、大きな支配力を発揮する恐れなしとはしないのである。したがって、効率の強調が、ときには、時流に迎合し、その時々の社会の趨勢に押し流され、あげくの果てには、時の為政者のための御用学者集団の形成に役立つだけに終わる場合もあることに注意する必要がある。哲学は、やはり、近視眼的な見方や、短見浅慮を克服して、人間的善に関する正しい考え方の樹立を目指して、たえず自己吟味してゆくべき課題を背負っていると言わねばならない。
2.哲学の基本的性格
哲学は、元来、フィロ・ソフィアとして、愛知を意味し、真理への希求をその根本精神としていた。真理への愛と言ったときの、愛とは、知の欠乏と充実の中間に立って、一方では、安易な独断に対する懐疑や批判、あるいは、みずからの無知を反省する謙虚さや自省となって、否定的な働きを及ぼすとともに、他方では、あくことのない絶対的な確信や信念、もしくは、真理を射当てた充足と自己完成へと向かう、肯定的な位境をも含むものとして成立してくる。哲学的精神は、こうして、その精神に立脚するすべての者に対して、一方で、たえざる探究や批判、吟味や検討を課すとともに、他方で、不動の信念や洞察、もしくは広く深い理解力や思考力を、みずからのうちに熟成させることを要求してくる。
こうした哲学の求める知は、まず、あらゆる事柄に関して、その事柄の本質と基本原理を考え直す思索一般として、どこにおいても、その問題事象に応じて活性化して現れ、当該事象の根本知の姿で出現してくる。哲学の知は、本質的に、きわめて学際的であって、あらゆる場面へと越境して、その問題ごとに、その基本原理を反省的に捉え直す、自己超出的な思索の運動、すなわち自己を全体のなかに位置づけ直す、遡行的な全体化の思索として成立してくる。
したがって、哲学は、まず、実証的諸科学の細分化された領域的な特殊的知を越えて、さまざまな存在者の存在する世界全体を展望しながら、そこでの存在経験の深部へと眼を向けつつ、本質的な全体的原理を獲得しようと試みる。その試図は、広義での世界観の形成の試みと呼んでも差し支えない。しかし、さらに、哲学は、その世界の場のなかでの、自己としての人間の生き方の諸問題をも、さまざまな観点から考究して、より良く生きるための人間的な支えと根拠をも獲得しようと志す。こうした企図は、広義での人生観の形成と言い表すこともできよう。こうして、世界の全体とそこにおける自己の根本的なあり方を原理的に問い直そうとする哲学的探究は、人生観・世界観の根本知に向けられた知的探究として、これを規定することができる。こうした人生観・世界観の大きな体系的知の組織のなかに、さまざまな個別の諸問題に関する原理的な哲学的反省は、ことごとく集約されることができると言える。このようにして、哲学は、そのつどの時代精神の全体を凝縮して映し出す代表的な思想的表現となるのである。ある意味で、それぞれの時代は、それぞれの時代の哲学を要求していると言ってよい。
そうした哲学的探究においては、根本的な問題提起は、世界の全体とそのなかでの自己のあり方に即しながら、人間の存在経験を精錬して、その深部をえぐり出し、その射程を見極め、これを凝縮した形で言語表現にもたすことに向けられる。このようにして、哲学は、来し方行く末を省みながらまさに当代を生きる人間に対して、批判的衝撃とも、指導的理念ともなりうるような、思想的根拠を提起することに全精力を傾注する。哲学が指導性を発揮する場合においても、哲学にあっては、答えよりも、問うことのほうがいっそう重要であるとも言える。鋭い問いかけから始められた哲学的探究が、その輪を広げて、広範な形で、多くの人々の討議と検討を介して、ヒューマンな生き方の自覚や模索へと向けて総結集されるならば、そこにこそ、生きた哲学的精神の浸透と、ほかならぬ哲学の真の社会的役割が、成就してゆくはずできる。哲学の社会的役割は、なにか固定的な教条的テーゼを掲げて、特定党派の実践的活動に奉仕するところにあるのではない。そのようにすれば、たちまち、哲学的精神は、世俗の利害関係と党派的駆け引きの道具に貶められるであろう。人間の歴史形成の根本的起動力となる人生観・世界観的な根拠を示唆しながらも、たえず、哲学は、現実に対して批判的距離を取りつつ、しかも、現実を越えた、未来に向けられた指導性と規範性を保持しながら、問題提起を敢行しようと試みる。こうした、たえざる自己超克の広範な精神の運動のなかでこそ、哲学の真の社会的役割が達成されてゆくと考えられるのである。
3.現代の哲学的課題
現代において、哲学的に存在経験を錬磨し、人生観・世界観的な現実対処の根拠を自覚化しようとするときに、とりわけ留意されるべき大事な現代的問題点の在処として、二つのことを指摘しておかねばならない。一つは、科学技術の意義と限界の問題であり、もう一つは、人間の生き方に関する心の支えという問題である。しかも、この二つの問題は連動している。
まず、現代が、17世紀の科学革命に端を発する近代科学の思考法と、その工業的応用である技術文明とによって根本的に特徴づけられた、いわゆる科学技術時代であることは、多くの識者の指摘するとおりである。その際には、知の組織立った諸体系である学問全般のなかで、とりわけ、この近代科学と呼ばれるものが、特有の方法論と思考法をそなえて成立したその特質と限界とを把握することが肝要である。なぜなら、現代には、あまりにも楽天的な、科学技術による文明の進歩観が蔓延しており、いかに環境問題その他に関する危機意識が広がってはいても、根本的には、科学技術の本質についての洞察が欠如し、人間の生き方の問題が忘れ去られているからである。その虚をついて、突如生じた、たとえば宗教的カルト集団や少年による途方もない凶悪な犯罪等の事件に関連して、慌てふためいて、取って付けたように、心の教育を叫んでみても焼け石に水である。現代には、科学と人間とをともに見据えた、しっかりとした人生観・世界観が欠如しているからである。こうした事態の出現は、世間一般の哲学軽視の当然の結果である。あるいは、それは、科学技術立国と経済大国の樹立にのみ狂奔した、世間一般の無思慮の結果であるとさえ言えなくもない。
現代において、たとえいかに、近代科学とその技術的利用とが、多くの恩恵と快適な文明設備を生み出したとはいえ、科学技術が、万能の魔法の杖ではないことに人々は気づくべきである。およそ近代科学の提出するさまざまな経験的な法則の知は、「こうなれば、ああなる」という形で、諸事象の因果法則を定立しようとし、仮説演繹法にもとづいて、その知の必然性を確立しようとするが、それが絶対的ではなく、たんにこれまでの経験によって反証されていないだけの蓋然的なものであることが、多くの科学哲学者たちによってあばかれた。したがって、科学が、時代の進歩と相関的な、たえざる修正と発展を蒙りうるものであり、世界の諸事象がけっして科学的に解明されおえていないことが、明らかにされた。しかし、そればかりではなく、むしろ、より重要なのは、そうした科学の知が、あくまでも、ものごとの因果的連鎖の仕組みの、いわば機械的かつ自動的な展開過程の、第三者的な観察に終始していて、その結果、人々の間に、この世界の出来事の、いわば決定論的な、なんの意義も価値ももたない、ニヒリスティックな連鎖の意識が浸透していったという事実のある点である。なるほど、この近代科学の知の技術的利用によって、一見、快適な文明的装置が拡大され、豊かな発展や生活が保障され始めたかのような印象を、多くの人はもつかもしれない。けれども、技術文明の拡大は、かえって、人間をその装置のもとに拘束し、また、その展開のための必須な自然資源にも限界があることが見えており、加えて、さまざまな環境問題が惹起され、なによりも、愛情や、精神的感激や、創造的能力など、人間社会維持のために不可欠の精神的高揚は、科学技術の力をもってしてもいかんともしがたい問題であることも明らかである。人間個々人が、やがて死すべき有限の存在者であるという根本事実は、科学や技術によっても変えようのない人間の厳然たる宿命であろう。
しかも、人間の人間たるゆえんは、この現実世界の諸可能性のただなかに立って、より良い未来を切り開こうとして、自由をもって決断し、行為してゆくところに存する。この未来を切り開こうとする人間の英知と創意に導かれてこそ初めて、科学の知も、技術的開発の着想も、ほんとうに活かされ、現実の困難に対処する手段の知の総体として、役立てられうる。人間の英知に指導され、管理されないとき、科学技術の知は、悪魔の知に転化する。しかしながら、いったい、このような人間的自己とは何であり、その自己と他者との共同存在における善と悪とは何であり、また、この人間的自己にとっての生き甲斐と幸福はどこに存するのであろうか。高齢化社会の到来とともに登場した、老いと死をめぐる現代的問題をも念頭に置くとき、このような人間論ないし人生論的探究が、いよいよもって現代において重要性を増す大きな課題群となって出現してくることは明らかである。しかも、こうした問題は、たんに個々人の生き方に関わるだけではない。個々人の人生は、歴史の大きな流れのなかに置かれている。してみれば、いったい、この歴史の由来と行方については、人はいかに考えるべきなのであろうか。しかしながら、人間の生き方に関わるこうした諸問題については、現代においては、ほとんど沈黙が支配している。人生観・世界観としての哲学の英知は、公的には黙殺されている。人々は、ただ情報処理とコンピュータ操作の普及に、現代教育の主要課題を見るありさまである。しかしながら、現代の心ある多くの人々が、こうした現代の趨勢に対して明らかに疑問を感受していることも事実なのである。それらの多くの人々と手を携えて、人生観・世界観的諸問題を考究してゆくところに、現代における哲学の社会的役割が存すると考えられるのである。
経済学における実証理論と規範理論
大山道広
1 はじめに
経済学は経験科学のひとつである。経験科学とは論理学,数学等と違って,経験的に検証可能な命題を導こうとする科学である。物理学,化学,生物学といった自然科学がその代表的なものである。経済学は政治学,社会学等と並んで社会科学に分類される。これはその研究対象が人間の個人的,社会的行動であることによる。経済学は時に社会科学の女王(the
queen of the social sciences)と呼ばれるように,社会科学の中でも最も自然科学に近い科学的構造をもっている。以下,その特徴について説明する。
2 仮説的演繹的体系
一般に経験科学の方法として帰納法(induction)と演繹法(deduction)という2通りの方法が識別されてきた。帰納法は個々の経験的事実の観察から一般的な命題や法則を発見する方法であり,演繹法は一般的な前提から論理の規則にしたがって特殊な命題を導出する方法である。経済学でもこれら2つの方法が併用されてきた。経済学で経験法則(empirical
law)といわれるものの多くは当初帰納法によって見出されたものである。その代表的な例としては、「悪貨は良貨を駆逐する」というグレシャムの法則(Gresham's
Law),「一定面積の土地に投入される労働量が増加するにつれて追加的にえられる収穫は減少する」という土地収穫逓減の法則,「ある財の価格が下がればその財に対する需要が増える」という需要法則(law
of demand),「ある財の価格が下がればその財に対する需要が増える」という需要法則(law
of demand),「家計の支出に占める食費の割合はその所得の増加と共に低下する」というエンゲル法則(Engel's
Law),「経済発展とともに労働人口が農業から工業へ,さらに商業・サービスヘと移動する傾向がある」というベティ・クラークの法則等がある。しかし,こうした経験法則がなぜ妥当するかを説明したり,またどのような場合に妥当しないかを明確にするためには演繹法による再検討が必要になる。現代の経済理論は,経験法則の基礎づけも含めて,ポッパー(Karl
Popper)のいう「仮説的演繹的体系」(hypothetical
deductive system)として構成されている。
仮説的演繹的体系は次のような構造をもっている。ある現象に関する仮説とは,その原因についての一連の仮定(assumption)から成る。これらの仮定のうち普遍妥当性の高いものはしばしば公理(axiom)とも呼ばれる。一連の仮定の関連と意味が分析され,演繹によって関心ある現象についての結論(conclusion)が導かれるとき,仮説的演繹的体系が成立する。その結論のうち,主要なものはしばしば命題(proposition)ないし定理(theorem)としてまとめられる。図1は一般的にm個の仮定からn個の結論が導かれるという形でこのことを示したものである。これから明らかなように,m個の仮定は全体としてn個の結論の十分条件(sufficient
conditions)であり,n個の結論はそれぞれm個の仮定の必要条件(necessary
conditions)となっている。経済学に限らず,あらゆる科学の理論はこのような仮説的演繹的体系であると見ることができる。経済学の場合,それは経済モデル(economic
mdel)と呼ばれ,経済現象の説明・予測,新しい事実の発見,政策・制度の立案・評価などに用いられてきた。
経済現象の説明とは,その因果関係を明らかにすることであり,厳密にはこれこれの原因(仮定)からこれこれの結果(結論)が導かれるという仮説的演繹的体系によって与えられる。たとえば,グレシャムの法則について考えてみよう。ここでの結論は,良貨(金の純分の高い通貨)と悪貨(金の純分の低い通貨)が併存するような場合、早晩良貨は流通過程から姿を消し,悪貨ばかりが出回るようになるというものである。これは,人々が利己的かつ合理的であり,多くの債務が金ではなく名目的な通貨の単位で決められているという仮定から導かれる。利己的な人々は債務を悪貨によって支払い,良貨を手許に温存しようとするであろう。手許におかれた良貨はやがて鋳つぶされ,そこに含まれている金が取り出され,より多くの悪貨と交換される。このとき,良貨は本当にこの世から消えてなくなることになる。
同様に,経済現象の予測もまた仮説的演繹的体系によって行われている。経済成長率や物価上昇率などの予測は,それが個人の権威を根拠として述べられる予言ではなく科学的な予測である限り,条件付きのものである。つまり,これこれの経済構造が持続し,これこれの経済政策がとられるならばという条件の下で述べられるものである。その条件が仮定であり,予測はそれから導かれる結論にほかならない。政府や民間の調査機関が発表する経済予測はたいていの場合「計量経済モデル」(econometric
model)と呼ばれる仮説的演繹的体系に依拠している。そこでは,人々の嗜好や利用可能な資源の種類と数量(ないしその成長率)は所与とされ,技術進歩による生産性の向上は一定のテンポで進み,政府のさまざまな制度,政策も変わらないか,あるいは決まった仕方で変化するものとされる。将来の物価や雇用の予測はこうした前提の上に立ってはじめて可能になるのである。
仮説的演繹的体系は経済法則,あるいはそこまでいかなくとも新しい経済的事実の発見にも役立つ可能性がある。その仮定から導かれる結論の中には従来明確に認識されなかった事柄や当初には予想されなかったような意外な内容のものが含まれているかもしれない。そのような場合,その結論が実際に妥当するかどうか,もし妥当しないとすれば何が原因か(どの仮定に問題があるか)について調べることにより新しい事実を発見することができる。また,ある種の結果が従来必ずしも明確には認識されなかった要因(仮定)に依存していることが示されるかもしれない。そのときには,その結果がどの程度その要因に関連しているかを事実の観察によって調べることが必要になる。たとえば,ある製品に対する需要がいかなる要因にどのように依存しているかという問題は消費行動に関する経済モデルによって解明され,「需要関数」として定式化されてきた。それはさまざまなデータを用いて推計され,多くの新しい事実(ファクト・ファインディング)に貢献している。
政府の経済政策や経済制度もまた何らかの経済モデルに基づいて立案されたり,評価されることが多い。ある結果が望ましいと判断された場合,その実現に役立つ政策や制度を的確に設計し,立案することが要請される。たとえば,物価の安定や雇用の確保のためにはいかなる政策がとられるべきか,公平な所得分配を達成するためにはいかなる財政制度が必要か,さらには乏しい資源を効率的に利用するためにはいかなる経済体制が望ましいか,またこのような問題意識からすると現在の政府の政策や制度はいかに評価されるべきか等々。これらの問題に答えるためには,政策・制度に関するいかなる仮定の下で望ましいと判断される結論が導かれるかを示さなければならない。これは明らかに仮説的演繹的体系としての経済モデルを必要とする仕事である。
3 実証と規範
仮説的演繹的体系としての経済モデルが経済現象の説明・予測や新しい経済法則の発見に役立つ場合,それは実証理論(positive
theory)と呼ばれる。その機能は事実を解明することである。ウェーバーの表現を用いるならば,それは事実判断の体系といえよう。他方,経済モデルは政策の処方や制度の設計の基礎としても用いられてきた。そのような経済モデルは規範理論(normative
theory)と呼ばれる。その機能は所与の目的に適合した政策・制度を提示することである。実証理論はもちろんのこと,規範理論も現実の経済からかけはなれたものであってはならない。したがって,経済モデルの仮定や結論の検証(verification),すなわち関連する経験的事実との斉合性のテストが重要な課題となる。
実証理論は経験的な観察を通じて原理的に反証可能(refutable)な命題,すなわちそれに対応する事実が原理的に観察可能であり,その主張を反証することのできる命題を導き出す。ただし,実証理論の命題に対応する事実は理想的な条件の下では観察可能であっても,実際には観察できないことが多い。ここで「原理的に観察可能」というのは,条件を整えることができる場合には観察可能という意味である。たとえば,「ある製品の価格の低下はその需要の増大をもたらす」という需要法則について考えてみよう。これは,ある製品の価格が低下したとき,「他のさまざまな条件が不変に保たれるならば」(ceteris
paribus),その需要が増大するという主張であることに注意する必要がある。価格の低下とその後の需要の動向が正確に観察され,記録されていたとしても、他の競合品・補完品の価格や人々の嗜好が同時に独立に変化していれば,その後の需要の動向は当然その製品の価格の低下だけでなく,他の諸条件の変化を反映するものとなる。したがって,その製品の需要が減少したことが観察されたとしても,それだけではこの製品について需要法則が有効に反証されたことにはならない。それは他の多くの条件の変化を反映するものであり,適切な事実の観察とは言えないからである。自然科学では,実験室の中で工夫をこらし,「条件を整えた実験」(controlled
experiment)を実行することがかなりの程度まで可能である。しかし,経済学や他の社会科学では,さまざまな理由によってそのような実験を行うことが難しい。そのため実証理論の命題に対応する事実は原理的には観察可能であっても,実際には観察できないことが多い。
需要法則に限らず、経済理論で導かれる多くの命題は条件付きのものである。しかし、条件を整えた実験ができない限り事実上反証可能ではないと断定するのはいささか早計である。需要法則についてみると,ある製品の価格が低下したのに需要が増加しなかったとすれば,少なくとも命題の条件が現実には満たされていなかったということがわかる。そこでその条件のどの部分がみたされていなかったのかが問われ,関連する事実が詳しく調査され,新しい有益な情報がえられるかもしれない。実際、ある製品の需要がその価格だけでなく,代替品や補完品の価格,購買者の所得等に依存するという経済理論の認識に基づいて,その需要量とこれらの諸要因との関係を「需要関数」として定式化し,多重回帰(multiple
regression)の手法によって推計することができる。このように,需要法則そのものが反証不可能であっても,適切に定式化された需要関数は反証可能となりうる。現代の計量経済学では、多くの変数が相互に依存し同時に決定される一般均衡モデルを想定し、利用可能なデータを用いて推計するための技法を開発してきた。それらは、条件を整えた実験を行う代わりに、利用可能なデータに適合するように反証すべき仮説それ自体を「整える」ものといえよう。
多くの変数が同時に変化することを考慮した計量経済学のモデルですら、その検証に必要なデータが本当に利用可能であるとは限らない。観察可能なデータであっても、実際にそれを正確に観察し、記録するためには、労働や設備が必要であり、想到のコストがかかる。そのため、往々にして必要なデータが存在しないか、存在したとしても不正確であることが多い。正確なデータが得られなければ、経済モデルが原理的には反証可能であっても、実際には反証不能となる。このように、実証理論の命題は原理的に反証可能であっても、実際には反証のために必要なデータが存在しない、正確でない、適切でないという理由によって、実際には反証可能でないことが多い。そのような場合でも、それは必ずしも無用の長物と決めつけるべきではない。原理的に反証可能な命題を導くことは現実を理解するためのひとつの出発点になりうるからである。「何らかの現象が一定の条件の下で生じる」というように述べられる命題は,その条件がすぐには作り出せなくても,少なくとも現実にひそむひとつの因果関係をえぐり出しているといえる。ウェーバーはこのような理論体系を理念型(Idealtypus)と呼んだ。理念型は実際に反証できるとは限らないが,それと現実との距離を測ることによって現実を理解するための一助となる。
実証理論は事実判断の体系であると述べたが,ここでいう事実判断とは原理的に反証可能な命題という意味である。それは原理的に反証不可能な命題とは明確に区別されなければならない。原理的に反証不可能な命題とはいかなる事実の観察によっても反証できない命題を指している。数学や論理学の命題は概念や言語の約束に関する命題であって,観察可能な事実に関する命題ではないから事実判断とは言えない。また,ものごとの善悪や美醜の判断を含む命題も事実によって反証することはできない。たとえば,「不平等な所得分配は望ましくない」とか「田園は美しい」といった命題は事実に照らして正しいとも正しくないともいえない。これらは価値判断と呼ばれるものである。
とはいえ,社会の構成員の多くが同様な価値判断を共有することも少なくない。そのような価値判断は社会のあり方を評価したり,政策的な提言をするために欠くことのできないものである。規範理論は,何らかの価値判断に基づいて是認ないし否認される事態がいかなる条件の下で発生するかを明らかにしようとする。価値判断それ自体は原理的にも反証可能でないが,望ましい,あるいは望ましくないとされる事態が成立するための条件は少なくとも原理的に観察可能であり,ある程度まで制御可能でさえあるかもしれない。ある価値判断に立つかぎり,望ましいとされる事態が発生する条件が明らかにされれば,そのような条件を整備すべきであると言える。望ましくないとされる事態が発生する条件がわかれば,それを除去することが推奨される。このように,規範理論は政策・制度の改革を提案するための基礎として重要である。
経済学で従来用いられてきた価値判断のうち最も広く受け入れられているものは「資源配分は効率的になされなければならない」というものである。この価値判断から理想とされる資源配分の状態はパレート(Vilfredo
Pareto)によって明確にされた「他の誰かの効用を低めることなしに何人の効用も高めることができない状態」である。これは技術や嗜好を所与として現存の希少な資源をぎりぎりまで効率的に利用しているためすべての人々の効用を同時にそれ以上高めることが最早不可能になっている状態であり,パレート最適(Pareto
optimum)と呼ばれる。経済学における規範理論は厚生経済学(Welfare
Economics)と呼ばれているが,その基本的な命題の一つは,「理想的な市場機構のもとではパレート最適な状態が実現する」というものである。
実証理論の命題は原理的に反証可能であるという意味で価値判断を含む命題とは峻別されなければならない。しかし、このことは実証理論の命題が価値判断と無関係に導出されることを意味するものではない。たとえば、経済学では個別主体が自らの予算や技術の制約には服するが、他の点では自由に行動することが許されているような「私的所有経済」のモデルが想定されることが多い。上述の規範理論の基本命題はこのモデルを前提として導かれたものである。このモデルそれ自体は、原理的に反証可能であるような多くの実証理論の命題を含んでいるが、私的所有制と個人の経済的自由という現代資本主義社会の基本的な価値観念を反映するものであり、ウェーバーの「価値関係」(Wertbeziehung)に基づくモデルであるといえよう。このモデルで定義される競争的な一般均衡がパレート最適となるという上述の命題は、資源配分の効率性をよしとする価値判断にたって私的所有制と個人の経済的自由がもたらす帰結を評価したものである。
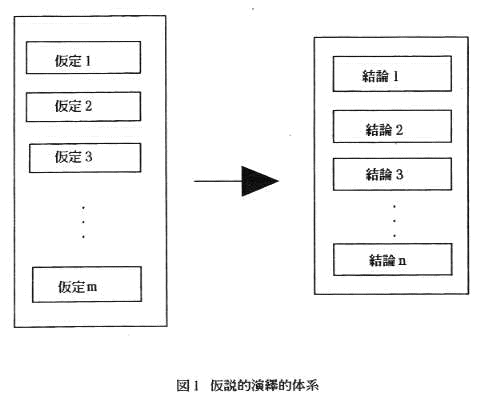
学術と社会
-経済学の視点-
大山道広
1 はじめに
学術と社会の関係は、自然を対象とする自然科学と社会を対象とする社会科学では当然異なったものになると考えられる。社会科学の場合、人間によって構成される社会を対象とする以上、人間をいかにとらえるかという困難な問題に直面せざるをえない。分析的な社会科学では、人間を全体像においてではなく、分析目的に適合した一定の視角から考察することが必要になる。その結果、人間、あるいは社会のひとつの側面に光が当てられる一方、他の側面は切り捨てられる。したがって、限定された範囲においてさえ、人間の個人的、社会的な行動を的確に説明し、予測することが困難になる。本章では、経済学における学術と社会のかかわりはどうなっているか、それを広げ、あるいは深めていくためにどうすればよいかという問題を考察する。
2 経済学における人間
経済学は資源の獲得と活用にかかわる人間行動を研究しようとする学問である。それでは,経済学では人間をどのようにとらえているのであろうか。経済学で主要な研究対象とされる人間は代表的ないし平均的個人(representative
or average individual)である。広い意味では,それは合理的個人(rational
individual)として特徴づけられる。狭い意味では,それは合理的であるだけでなく,文字どおり社会の構成員全体を代表する個人,あるいはその平均的な行動を実現する擬制的な個人としてとらえられる。こうした人間観は日常会話で用いられる人間という言葉のニュアンスや,文学,哲学などで考えられている人間の概念とはかなり異なったものである。そのため,経済学はモノやカネの学問であって,人間の学問ではないといった誤解や非難を受けることがある。この点について多少説明を加えておく必要がある。
現実の社会にはさまざまな個性をもった個人が存在する。自分勝手な個人もいれば,思いやりの深い個人もいる。また,円満で常識的な個人も少なくないが,奇人,変人と言われるような予測不可能な行動に走る個人も無くはない。文学や心理学では,異常な個性の持ち主や奇矯な行動が研究対象とされることがい。経済学では,資源の獲得と活用に当たって大多数の個人がどのように行動するかに関心をもたざるをえない。なぜなら,社会全体としての資源の配分や分配は結局のところ大多数の個人がどのように行動するかで決まるからである。狭い意味での代表的ないし平均的個人という概念は,社会を構成する大多数の個人が資源の獲得と活用に関してほぼ同様に行動するような場合に,最も明確な意味を持つ。この場合には,実際には少数の例外があったとしても,すべての個人があたかも代表的ないし平均的個人としてふるまうと仮定することが第1次接近として許されるのである。
経済学で考えられている代表的ないし平均的個人は、何よりもまず広い意味でのそれであって、合理的に行動する個人,換言すれば明確な目的をもち,その目的に最もよく適合するように行動する個人である。ウェーバー(Max
Weber)が論じたように,合理的な行動は最も明確に理解できる行動である。他の社会科学と同様に経済学で合理的な個人を想定するのは,何よりもそれによって実際の人間の行動がよく理解できるからである。仮に実際の人間の行動が合理的でない場合でも,まず何らかの純粋に合理的な行動として再構成してみることは有用である。そのような方法ではどうしても理解できないときには,最も近い合理的行動からそれがどのようにまたどれだけ乖離しているかをはかることによってそこに働いている非合理的要素を明確に析出することが可能になる。
それでは,狭い意味での代表的ないし平均的個人がもつ目的とはいかなるものであろうか。アダム・スミス以来,それはしばしば「利己的」(selfish)な目的であるとされてきた。このことは,各人は自分の消費(consumption)のみに関心をもち,そこから得られる満足感,あるいは効用(utility)の最大化をはかるというように表されることが多い。勿論,各人はそれぞれの立場でその目的を達成するために暫定的にはもっと手近な目標を追求すると考えられることもある。たとえば,労働者であればできるだけ労働条件のよい働き口を求め,資本家であればできるだけ配当の高い企業に投資し,経営者であれば自分の企業の利益や成長を追求するというように。こうして,各人はそれぞれの立場で自分の所得(income)の最大化をはかるのである。それは各人の効用の最大化のために必要なステップと見ることができる。
スミスの「見えざる手」(invisible hand)の思想は個々の人間が自分の利益を自由に追求することが許されれば,一定の条件の下で社会的調和が達成されるというものである。これは社会を構成する個々人が仮に利己的であったとしても,その行動を制約するのではなくむしろ解放することによって社会的に望ましい状態を実現することができるとする自由放任(laissez
faire)主義を根拠づけるものとなった。現代の経済学では,この主張がいかなる条件の下で,またいかなる意味で妥当するかについて厳密な検討が加えられている。その結果,それがいかなる場合に成り立たないか,また成り立つとしてもいかなる問題が残されているかも明らかにされてきた。このように,経済学はその成立の当初から個人の自由な経済活動と社会的調和との斉合性を問題にし,あるべき経済体制,社会的ルールを模索してきたと言える。
代表的,平均的個人の目的は利己的なものとされることが多いとしても,いつでもそのように考えられているわけではない。実際,多くの人々は自分が何をどれだけ消費するかということだけではなく,自分の近親者,友人はいうに及ばず社会の他の成員が何をどれだけ消費するかということにも関心を抱くものである。それは同情,あわれみといった利他的な関心であるかもしれないし,羨望,嫉妬といった敵対的な関心であるかもしれない。また,そのあり方は時と場所によっても大いに異なるかもしれない。経済学は代表的,平均的個人がこのように利他的ないし敵対的な関心をもち,したがって自分の消費だけでなく他人の消費からえられる満足感ないし効用の最大化を目的とすることを決して否定したり,排除するものではない。しかし,代表的,平均的個人は合理的に行動する。すなわちいったん何らかの目的が定められたら,その目的と斉合的に行動するものとするのである。次節では、従来の「標準的な」経済学の範囲を超えてこのことを明確に定式化してみよう。
3 効用関数の再検討
経済学では、人々の行動規範は効用(utility)という概念で表される。第1次接近として、各人の効用は自己の消費のみに依存すると仮定されることが多いが、すでに述べたように、そのように狭く限定する必要はなく、また限定すべきでもない。仮に各人の効用がさまざまな財の消費量という「経済的な変数」のみに依存すると単純化したとしても、それが当人の消費量だけに依存するとするのは、明らかに過度の単純化である。実際、我々は他者との関係を良好に維持していくために驚くほど多くの支出や労働力の提供を行っている。その最も端的な例はプレゼントである。さまざまなボランティア活動、リーダーシップ活動もその範疇に含められる。しかし、現代の経済学はこのような他者関連的な経済活動に対して十分な注意を払っているとは言えない。
次のようなモデルを考えてみよう。個人の消費は単独消費(consumption
in isolation)と共同消費(consumption in company)に分けられる。前者は、文字通り各消費者が他者と関係なく単独に消費するものである。たとえば、自分用の普段着、一人でとる朝食、独身用のアパートなどである。これに対して、後者は他者との関係を考慮して計画される消費である。社会にn人のひとがいるとすると、1個人が理論上関係しうるグループの数mは
m=1Cn=1+2Cn-1+,...,+1
となる。個人iの効用が自分の単独消費量のベクトルXiだけでなく、共同消費から得られる満足Hiに依存しているものとすると、その効用関数は
Ui=ui(Xi,Hi)
と書けよう。ここで、hiはすべての個人の他者関連的消費のベクトルY=(Y1,Y2,...,Yn)の関数であり、一般に
Hi=hi(Y1,Y2,...,Yn)
と表される。ただし、Yjは個人jが関係するグループごとに定義され、形式的には、
Yj=(Zj1,Zj2,...,Zjm)
となる。ここで、Zjkは個人jがグループkと共同で行う消費のうち自分が関心を持つ消費量のベクトルである。その例としては、本来単独でも享受可能な財を共同消費するケースや排除原則が適用できない公共財(public
goods)を共同享受するケースがある。前者は贈答、会食、団体旅行、クラブや企業の設立・経営に必要な財の共同使用など、後者は消防、国防、堤防、道路・港湾などの享受である。このように、個人の効用関数を拡張することにより、従来経済学ではきわめて不十分にしか取り扱われてこなかった人間的、したがって学際的な問題を経済学的分析の対象として考察することが可能になる。たとえば、次のような問題に新たな光を投じることが可能になる。
1.効率的な人間関係の形成
個人iは、自らの限られた所得(より基本的には自分の保有する資源)を用いて効用関数Uiをできるだけ高めるように行動する。この定式化によれば、個人iの人間関係のための支出は、同一財の限界効用がすべての人間関係グループについて均等化するように決められるはずである。このことから、個人iが強い一体感を持つグループでの共同消費のための支出は弱い一体感しか持たないグループでの共同消費より多くなることが推論される。すべての個人がこのような効用関数を持つものとすると、その一般均衡は各人が互いに他の人々の支出を所与として自己の効用関数を最大にするようにその支出を決めるナッシュ均衡となる。
2.私的所得再分配
各人が他の人々との共同消費だけでなく他の人々の消費にも関心を持つとすれば、私的な贈与が発生する可能性がある。したがって、交換と贈与の一般均衡を考えることができる。このような均衡は一定の条件の下でパレート最適を満たすと考えられる。もしそうであれば、贈与に対して課税することや、累進的な所得税制度を通じて私的な所得再分配を結果を修正することは潜在的な経済厚生の低下につながる可能性がある。
3.ノン・プロフィット活動(慈善事業・公共財の私的供給)
慈善事業とは、「宗教的・道徳的動機に基づいて、孤児・病人・老弱者・貧民の救助などのために行われる社会事業」(広辞苑)である。美術館、庭園、公園、道路のような公共財の私的供給もこれに類する行動である。企業の場合には、長期的な利潤最大化を目指して、短期的な利潤を多少犠牲にしても企業のイメージアップのためにノン・プロフィット事業を行う可能性がある。しかし、個人、あるいは非営利団体のノン・プロフィット活動は、上記のような人間関係を考慮した効用関数の再定式化なしには、十分に理解できない。それが人からよく思われたいという「利己的な」動機に基づく場合ですら、自分が持っている資源を他人との関係の改善のために投げ出すような行動は、他者のあらゆる活動から切り離された「標準的な」効用関数からは導かれない。
4.リーダーシップ
経験的にいって、人間の共同行動、共同生活は何らかのリーダーシップなしには成り立たない。小は家庭、学級から、大は企業、国家、国家連合にいたるまで、全体をうまくまとめていくリーダーが必要とされる。その意味で、リーダーとはリーダーシップという公共サービスを私的に提供する人であるといってよい。この公共サービスはすべての関係者に一括して与えられ、各人の効用を高め、その生産性を高める働きをする。したがって、その活動は前項のノン・プロフィット活動の一種であると解することもできよう。しかし、それは人間の共同行動を円滑に進めるために不可欠なものであるから、別だてにして扱う価値が十分にあると考えられる。
5.企業の形成
企業のような利潤動機に基づいた組織ですら、所与の目的に対して効率的な人間集団として理解することができる。企業は、利潤を生み出すことを主たる目的として、さまざまな資源を持った人々が共同し、各人のインセンティブに適合した行動ルールに則って運営される。ここでもまた、経営サービスという公共財を提供するリーダーとその指示に従って活動する人々の間の分業と相互作用が重要となる。それは複数の個人が共通の目的のために形成した人間関係のグループにほかならない。
4 行動規範と経済学
前節で定義した効用関数は、経済学的な観点から個人の行動規範を表したものとみることができる。通常、それは個人がすでに確実に身につけているものと考えられている。経済学では、個人の効用関数が与えられたものとして、それが個人の経済行動をいかに支配するか、さらにはその帰結として生じる社会状態が各人の効用関数の観点からいかに評価されるかを問題にする。ところで、経済学は個人の行動規範に何らかの根拠を与えうるであろうか。これは、従来の経済学ではあまり取り上げられなかった問題である。これについて,とりあえず次の4つの可能性を考えてみたい。
1.解決すべき問題を指摘することによって人々に自らの行動規範を自覚させる。
人々が当面する問題を認識せず、したがってその解決にかかわる行動規範を十分に自覚していないような場合には、問題を指摘し、関連する情報を提供することが行動規範の自覚を助ける可能性がある。科学は情報提供の一環として何らかの行動規範に関連する情報を示すことはできるが、特定の規範を推奨したり、押しつけることはできない。たとえば、高齢化社会の到来に備えて社会保障制度の維持・拡充を図とすれば、他の政府支出を減らすか政府歳入を増やすことが必要である。経済学者が歳入増加の手段として所得税の引き上げと消費税の引き上げの資源配分上の優劣、所得分配への効果を明確にすれば、政府は自らの価値判断を自覚することによってはじめて対応策を決めることができる。経済学者が資源配分だけでなく所得分配に関心を払い、増税の効果分析に役立つ経済モデルを構築することは、一定の社会的、文化的価値観念に基づく行為である。経済学では、このように一定の価値観念関連づけて理論をたてることは珍しいことではない。むしろ、ウェーバー(Max
Weber)が価値関係的(Wertbeziehung)と呼んだ理念型の構築はきわめて自然に、日常的に行われている。しかし、経済学者がその資格において社会保障制度の維持・拡充の必要性を主張したり、消費税が逆進的であることを理由に消費税の引き上げに反対することは越権行為である。
2.現状に関する最良の情報を提供することによって,人々の意志決定に根拠を与える。
人々が確固たる行動規範を持ちそれを自覚しているとしても、差し追った問題に関する十分な情報を欠いていれば、いかに行動すべきかを決めることはできない。たとえば、経済が不況に陥理、その対策が求められているとしよう。おおざっぱにいっても、公定歩合の引き下げや国債買いオペレーションのような金融緩和政策か、公共事業支出の増大のような財政拡大政策か、あるいはその両方かという選択肢がある。消費や投資の利子弾力性、種々の公共支出の乗数効果など、適切なマクロ経済モデルと必要な情報がなければ、政府はいかなる政策とるべきかについて科学的に判断することはできない。経済学とは関係ないが、癌患者に対して病状を正確に告知すべきかどうかは微妙な問題である。自分の病状について誤った楽観的な情報を与えられていれば、患者は安心して過ごすことができるかもしれないが、本来の行動規範に反した対応をする蓋然性が高くなる。癌に罹病していることを正確に知らされれば、行動規範とより整合的な生き方を追求することが可能になる。いずれの場合にも、主体がすでに明確な行動規範を自覚して持っている場合には、情報の提供は行動規範の根拠を与えることにはならず、単に固有の規範にもとづく判断のために必要な材料を与えるにとどまる。また、主体が明確な行動規範をもっていない場合にも、情報の提供はただちにその行動を根拠づけることにはならない。
3.何らかの行動に関する人々の合意(政府の政策や民間の取り決め)の必要性を示す。
複数の主体がそれぞれ独自の明確な行動規範をもって合理的に行動するとしても、相互に何らかの外部効果(external
effects)を及ぼし合うような場合には、全体として不効率な均衡に陥る可能性がある。(囚人のディレンマ、あるいは複数均衡)。たとえば、自動車の運転は、排気ガスを通じて大気を汚染し、地球温暖化やオゾン層破壊など地球環境問題の原因となる。個々のドライバーがこのことを正確に認識し、環境悪化が望ましくないと言う価値観念を持っていたとしても、彼らは運転をやめようとはしない。個々のドライバーの観点からすれば、自分一人が運転をやめれば、自動車を利用することによる個人的な便益が失われる一方、環境改善にはほとんど役立たないと思えるからである。同様な陥穽は至るところにある。個人間の受験競争、企業間の過当競争、国家間の軍拡競争等)。経済学はそのような均衡が生じる可能性を指摘し、何らかのリーダーシップに基づく人々の協調的行動の必要性を知らしめることができる。
4.人々の行動規範(狭くは効用関数)がいかにして形成されるかを明らかにする。
ある種の行動規範は現状の正当化、あるいは現状の否定という動機から形成される。たとえば、富裕な両親のもとで育った人々は、所得分配の不平等を容認するような価値観念とそれに基づいた行動規範を持つようになるかもしれない。しかし、しばしば観察されるように、逆に所得分配の平等を求めるような価値観念と行動規範を持ちようになる可能性もある。そのどちらに傾くかは、他の条件、たとえば家庭環境や学校教育などによって左右される。初期時点における人々の行動規範のきわめて僅かな差異が時とともにある種の行動の繰り返しと異なる主体との交流によって次第に拡大され、やがて偏執、依存、中毒、狂気にまで発展する可能性がある。(rational
addiction; self-organizing economy).経済学では、このような行動規範の内生的解明の試みはまだ緒についたばかりである。仮に人々のある種の行動規範の形成を何らかの仕方で説明できたとしても、規範それ自体を是認したり否定することにはならない。
このように、経済学が個人の行動規範に何らかの根拠を与えることができるかという問題については、現状ではいささか懐疑的な立場をとらざるをえない。ついでにいえば、複数の個人からなる社会の行動規範についてはいっそう困難な問題が存在する。仮に個人の行動規範が何らの社会的制約もなく無限定に与えられるものとすると、それに基づいて何らかの一貫した独裁的でない社会的行動規範を導くことは一般に不可能である。(Kenneth
Arrowの不可能性定理)。社会的行動規範を個人的行動規範に立脚させるためには、社会の成員である個人の行動規範に何らかの制約を課する必要がある。
地震予知と火山噴火予知・・・・・理学と工学のはざま
第4部 荒牧重雄
○自然災害としての地震と火山噴火
自然災害には,気象災害(風水害全般,例えば,台風,集中豪雨,豪雪,波浪,高潮,洪水などと,異常気象,例えば,干ばつ,冷害など),地盤災害(土地の隆起・沈降,斜面崩壊,地震など),火山災害など多くの種類があるが,また複数の要因の組み合わせとしては,土石流,津波,なども大規模な災害を引き起こす.
自然災害を防いだり,災害の程度をできるだけ減少させるようにする努力が必要であるが,それには,
1)災害となる自然現象の発生を予報できるようにすることと,
2)現象が発生しても大きな被害を被らないような工夫をすること
が必要である.
防災・減災を目的とした予報の例として,気象(天気)予報,地震予報,火山噴火予報の3つを考えてみる現在実用化されているのは気象予報だけであり,後の2つはまだ模索段階にある.
天気予報は1856年,フランス政府によってはじめて事業化されて以来,どの国でも国営事業が主体で,観測からデータの解析まで公的資産が投入されている.予報の確度・精度は時代と共に‘順調’に改善されてきた.一方,日本は地震予知と火山噴火予知に関しては,世界でも先進国であり,明治20年代からその必要性が議論され,組織的な努力が始められていた.それにもかかわらず,最近になっても地震・火山噴火予知の実用化は,どの国でも困難であり,はっきりした見通しも立っていない状況である.その理由について考えてみる:
第1の可能性は,気象災害の規模(相当する金額)は他の2者に比べてはるかに大きいため,予報に対する社会的需要が大きく,それに見合った投資が行われ,それに比例した実績が得られた(予報が実用になった).他の2者はその逆の状態である.
第2は,地震や火山は気象に比べて,現象の自然科学的な解明がより困難であるため,地震と火山噴火の予知の方法論の構築がうまく進まなかった.したがって予報技術の進歩が後れている.
このような議論はこれまであまり行われておらず,定説がないが,両方とも幾分ずつ真実だろうと感じられる.
○自然災害の防災・減災に関する工学と理学の役割
理学の領域にはいるのは,自然現象の物理モデルを確立し,支配する法則を定義することまでである.確立したモデルを使って,どのような特定の事象,あるいはパラメータを予報すべきかということは,社会のニーズによって決まる.したがって,この領域は工学と呼ばれるであろう.
この定義に従えば,工学的研究の課題は,あくまでその時代の社会的要請にあてはまる事項に限られるが,理学的研究を行う動機は,社会的ニーズに束縛されず,研究者自身の探求心の向かうままに行われると言えるだろう.然し,実際には,職業的理学研究者の圧倒的大部分は,政府とか大企業とかの団体によって,給料と研究費の両方が支払われているのだから,巨視的には,彼らの研究内容も,社会の経済的要請や倫理基準によって制約されているとも言えるであろう.
理学と工学の差は,このように連続的なものと考えてよいと思われるが,その差の存在意義は十分にあるであろう.理学研究者は,社会的ニーズという,一種の「雑音」に惑わされることなく,客観的に自然現象を見渡すことができるという長所を持ち,また,研究への出資者は,理学の無責任性をある限度までは許容できると考えているのであろう.
○自然災害の予知・予報
すでに実用化に成功している気象予報では,理学的なモデルの構築はかなり十分な程度に完成していて,流体力学や熱力学などの数式により表現され,それに従って強力なスーパーコンピュータが働き,気象予報というルーチンが業務的に実行されている.一方,地震現象は断層の破断によって発生し,弾性波として固体地球内部を伝搬し,地表面を振動させるものであるという,物理モデルの概念は,ここ30~40年以内にやっと定着したばかりである.地殻内での応力蓄積現象や岩石の破壊現象を相当正確に定義する数式群はまだ得られていないので(もちろん,得られたと主張する研究者はいるが,学界の大勢が認めたという段階ではない),何時,どのような条件で破壊が起きるかを予言することができない.すなわち地震の発生を,実用に耐えうる確度・精度で予測することができないのが現状である.
地震と比べると,火山の噴火は,もっといろいろな物理現象が平行して起きる,複雑な現象である.地震も火山活動に伴って起きるが,それは火山活動全体のごく一部でしかない.それに加えて,マグマの組成分化と混合,マグマの発泡,噴煙柱の動力学,混相流の動力学など,それぞれが地震現象に匹敵するほど理解困難なプロセスを多数平行して扱う必要があり,その多くは,物理モデルがまだ確立していない状態である.従って,気象現象と同じくらいの精度で火山の噴火現象の予報をするということは,現時点では論外である.
このような表現は,それを担当する責任がある理学研究者の立場を代弁しているといえるかもしれない.この種の「言い訳」によれば,気象予報に対してと同じくらいの社会的投資をしても,得られる成果は相対的に少ないという議論になってしまう.この議論はある程度正しいと私は思う.とは言っても,地震予知・火山噴火予知への基礎的研究が否定されることはあり得ず,そのような基礎的研究が,地震・火山現象の解明に大きく役立ってきたことは,識者の間では議論の余地がないであろう.
○防災工学
一方,防災・減災の見地からは,予報が不可能で,ある程度不意に現象が発生しても,適当な予防手段がとってあれば,被害を最小限にくい止められるというのが第2の命題であった.地震災害の場合,すでにこの面が強調されていて,相当程度実行に移されている.地震発生の正確なメカニズムは不明でも,発生した地震波の伝搬状況や地層の応答特性など,観測あるいは近似可能な変数を入れてやれば,任意の地点での地表の振動のシミュレーションはある程度可能である.地盤の振動特性がわかれば,それに堪えられる構造物の設計・製造は可能である.発生する地震の規模の確率が知れれば,耐震都市の設計は可能となる.この分野は「地震工学」としてすでに相当に発達して,実用性か認められている.都市のインフラ構造の耐震化など,多くの分野で工学的な防災・減災対策を進めうる方法論は確立しつつあるというのが私の印象である.したがってこの領域では,投資額にほぼ比例する効果が期待されるから,問題は,社会の防災に対する需要規模がどれだけあり,実際に投資がどれだけなされるかということに帰結する.今後に残された問題の一つは,稀にしか起こらないが,いったん起これば巨大な災害を引き起こすという,関東大震災クラスの地震災害に対して,国家や社会がどの程度の防災投資を決断するかということである.
火山災害の場合,一見,事態はもっと悲観的に見える.溶岩流や火砕流などの持つ運動エネルギーや熱エネルギーは膨大なもので,破壊力はきわめて大きいから,すべての構造物をそれらから積極的に守るという考えは,素人も専門家もともに,非現実的(非経済的)であると見なすだろう.また,その他の,考え得るいろいろな火山災害に対応するために,多大の公的資金を投入することには,これまで多くの官僚や政治家が否定的な態度をとってきたし,将来もそうするだろう.火山災害の場合も,社会の(経済的)ニーズの規模というものが最大の制約条件であることは,現在も将来も変わらないであろう.
火砕流,土石流により多くの家屋が焼失,流失し,44名が死亡した雲仙普賢岳の悲惨な災害ののち,関心を持つ工学者たちが集まって「火山工学」の可能性を検討した.しかし,結論はあまり肯定的ではなく,未だ時期尚早という印象であった.もちろん,火山工学の必要性を否定する人はいないのだが,最大の問題は,専門の工学者を育むに十分な社会的ニーズが無いということにあった.この問題は,工学と理学の関係を鋭く突くものである.そういうわけで,実際には雲仙災害の後も,理学系の研究者が,政府や地方自治体の要請に応じて,火山防災についての助言を引き受けているのが現実である.このことは例えば,火山災害のテレビ報道の際に「専門家」として登場し,解説するのが,理学系の研究者であることに反映されている.他方,十分に実用化された気象情報(天気予報)の場合は,専業化された(研究者ではない)解説者がテレビに現れて,天気現象を分かりやすく解説してくれるのと比べれば,その相違は明らかである.実際には,理学系の研究者は大抵防災・減災の実務には深く関与しておらず,殆ど素人といってよい.地震災害の場合は,気象と火山との中間にあると言えるだろう.
社会的に,あるいは経済的に一定の大きさの市場が存在しなければ,特定の工学の分野は成立しないもののようである.地震災害と火山災害の違いがちょうど理学と工学のはざまに相当しているように見える.
○稀にしか起きない災害にどう対応するのか
気象災害,地震災害,火山噴火災害の順に顕著になる特徴の一つに,発生頻度の低さがある.たいていの気象災害は毎年起きる.たとえば台風は毎年やってくるから,一般市民は台風が来れば強風が吹き,大雨が降り,家屋が破壊される危険性もあれば,鉄砲水で押し流されるかもしれないことはよく知っている.また,大震災の経験はないにしても,たいていの日本人は,震度3の地震を体験しているから,強い地震の際にどのような感じがするかを想像し,それに対応することはそんなに難しいことではない.しかし,火山噴火を身をもって体験した人は稀である(テレビで見るのは別として).‘火山国日本’などといっても,平均の日本人が噴火を体験すると,如何に恐怖し,呆然自失の状態になるかは,最近の数例の噴火を見れば十分にわかる.個人的に体験し,学習したことがないからである.体験の記憶があればパニックは起きにくい.逆に,生まれて初めて味わった衝撃は,人々を容易にパニックに陥れる.
体験の繰り返し周期が長くなれば,学習の能率が低下する.日本における火山災害の繰り返しは,数十年,数百年に1回かそれ以上の間隔であるから,親から子への伝承さえも困難な状態となる.「天災は忘れられた頃やってくる」のではなく,「天災は忘れ去られた後,長い間経ってからやってくる」のである.その結果,わずか数十年しか噴火を休んでいない活火山の周辺の自治体でも,防災担当者でさえもが,具体的な噴火のイメージを持たず,地域防災計画は無いに等しいというケースが,日本では残念ながら少なくないのである.ここで考察した,毎年,数年,数十年,数百年の繰り返し間隔と人間の世代交代の間隔の一致・不一致というものが,防災対策上,決定的な差違を生じうるものであることを明らかに示している.
文明が進み,市民の生活水準が上がれば,それに比例して頻度の低い災害も関心の的になってくる.そのため,数万年に1度しか起こらないような巨大噴火によって引き起こされるような災害も,現在の先進国(日本も含めて)では,近い将来真剣な対象になるだろう.今から約25,000年前に現在の鹿児島湾の北端で起きた巨大噴火では,南九州の大部分が厚い火砕流によって覆い尽くされ,それにともなう火砕サージによって九州の全人口が抹殺されるような規模の被害を与えた.このような突拍子もない災害でも,隕石の衝突によって起こる災害よりは,はるかに現実味がある話である.このような領域について基礎的な知識を集め,何らかの防災上の方法論を整備することは,やはり理学者の責任であろうと思われる.
○ソフト的災害のインパクト
文明が高度になるにつれ,ハード面での災害に比べて,ソフト面の災害の占める割合が増加する.その割合が,気象災害から火山災害へ向かって増大するのは,既に述べた理由による.火砕流の恐ろしさを十分に知らなかったために,あるいは知らされなかったために,雲仙では44名の命が失われた.すべての死者は,入ることを(実質的に)禁止された地域(避難勧告地域)内で発見された.建前では禁止されている区域へ,実際には入ることを黙認するということは,高度にソフト的な事象といえよう.死者の半数以上は,火山噴火を報道しようとして互いに競い合っていたマスコミの当事者あるいは関係者であった.危険をある程度覚悟してでも,禁じられた地域に入ろうとした動機は,高度にソフト的な「報道競争」のためであった.高度にソフト的である報道陣をして死に至らしめたのは,火砕流という自然現象についての無知(情報の欠如)であった.この事故以来,神経過敏になったマスコミは,その8日後に,大噴火が起きるというデマに自ら踊らされて,住民に対する報道義務も放棄して(報道をせずに)島原半島から自分たちだけが撤退するという騒ぎを起こした.その結果,物理的な被害の割には,住民の心に残された傷は大きかった.これらは,社会心理学,マスコミ論等の領域であり,また防災行政のシステムの問題である.理学研究者として,この事件に対する反省は,専門家だけが持っていた,正しく,有用な情報を,非専門家に有効に,時機を失せずに伝達できなかったということである.
○社会学的問題
雲仙普賢岳の噴火災害が最も顕著な例のひとつであるが,災害基本法による「警戒区域」の設定により,住民は強制的に立ち退かされたが,そのときに生じた経済的損害・精神的苦痛の救済が法によって保証されないという状態が発生した.集団避難場を慰問に訪れ,陳情を受けた当時の首相や有力国会議員は,特別立法を考える旨の発言をしたが,実際にはこのような事態を解決する措置は結局とられなかった.住民が受けた経済的損害・精神的苦痛を解決するのは,政治,経済,法律,社会学の専門家の責任であり,理学研究者の役割ではないだろう.しかし,あまりにも身近にこのような社会的困難を見聞したことは,理学研究者にとって強い衝撃となった.
○あいまい予報の有用性と問題点
前節で,火山噴火を予報するには,あまりにも多くの未知の物理モデルを扱わなくてはならないため,実用的なレベルでの予報は現状では不可能であると述べた.しかし,この表現は,たとえば天気予報と比較した場合に正しいのであって,予報の精度や確度が天気予報よりもずっと低くてよいというのなら,話は別になる.たとえば,日本で過去10年間に起きた数回の火山噴火の例を見れば,ある程度の予知が可能であったといえるのである.1986年の伊豆大島の噴火でも,1990年の雲仙普賢岳の噴火でも,その他の多くの場合,噴火に先立つ数ヶ月から数日以内に,何らかの異常が確実にキャッチされていたのである.前兆現象の多くは,火山性微小地震の多発であり,火山体の微少な隆起・沈降であった.その他,地温や噴気活動の上昇,地磁気・地電流の異常,など数多くのパラメータが異常を示す場合が認められた.その結果,理学系の火山研究者の間では,火山活動に異常が発生したとのコンセンサスが生まれ,目立たずにではあるが,観測網の強化とか,噴火に備えての対策をとる時間が確保されたのである.そして結果的には,そのような事前準備が大いに役に立ったのである.しかし,天気予報のように,噴火の日時や場所,そしてどのような様式の噴火が起こるであろうかという予報を,人間の日常生活に直接役立つような精度と確度で公表する自信は,火山研究者にはもちろん無かった.噴火が果たして実際に起きるかどうかという点にも自信がなかった.
しかし,このような「あいまい予報」は,実際には大変有用な面があると思われる.一般市民の日常生活には役立たずとも,自治体や国の政府をはじめとした,社会の「マネージャー」とでもいうべき専門家にとっては,十分役に立つ情報であると思う.予報が可能であるということは,事前に対策がとれるということを意味する.予報は,災害対策の策定・実施に貴重なリードタイムを与え,高価につく事後処理の費用に比べると,きわめて効率のよい対応処置となりうるものである.
ここで問題となるのは,「あいまい予報」を受け取る側の能力と態度である.受ける側が過剰反応をするのも,鈍感すぎるのも有害な結果を残す.理学系研究者の多くがおそれるのは,情報がマスコミに漏れて,根拠のないセンセーショナルな報道をされることである.過去に幾度となく痛い目に遭ってきた火山研究者は,したがって「あいまい情報」を積極的には公表せず,結果的には隠してしまう傾向が身についている.最近の情報開示の潮流に反する事態であるが,現状では,「あいまい情報」を良心的に,有効に非専門家に説明しようと言う理学者の努力は,たいてい報いられない結果となる.誤解を恐れずに言えば,官僚システムにとっては,「あいまい情報」というものは,存在するはずのないものなのかもしれない.
マスコミ問題と同様に,あるいはそれ以上に問題なのが,情報の正当な受け手であるべき防災担当者や自治体首長などの側の準備不足である.なぜか日本国民は,防災担当者をふくめて,火山現象についての知識が十分とはいえず,学習しようという態度が不足しているように見えてしかたがない.もしそうだとすれば,これまで幾度となく,実際に繰り返されてきた過剰反応や無反応の説明がつくのである.少なくとも火山災害についての知識不足を自ら積極的に認識して,国レベルなと,中央へ向かって詳しい情報の提供や即席のブリーフィングの要求をなすべきであると思う.「あいまい予報」は高度の情報であり,内容の正確な理解を必要とする.正しく理解された「あいまい情報」は,防災行政にとって強力な助けとなるはずである.
○理学型学生が目覚めるとき
定説のように,日本では学術の細分化が行き過ぎ,理学の学生は基礎研究をするという意識が強すぎて,応用というものに拒絶反応を示す者が多い.しかし,地震や火山噴火の現場で災害を目撃すると,驚くほど多くの優秀な学生が,彼らの研究課題が社会の幸福に密接に関係していることに突然目覚めるのを目撃してきた.基礎的研究を行うには妥協を許さない態度が必要であるが,基礎研究は上等で,応用研究は下等であるというような,高慢な偏見を許してはならない.日本の現システムは,明らかに理学の社会的責任を軽視しすぎている.やはり,理学研究者自身の認識の改善が必要である.
○理学者の社会的役割
理学者には,いわゆる「学者馬鹿」タイプが少なくなく,人間の社会的活動に関心が低い人が多いが,そのような人が,火山災害の場合のように,社会・行政・経済の知識なしに,問題に深く係わるのは適当ではないだろう.やはり,災害対策に関する知識を持ち,訓練を受けた専門家の存在が必要である.理学者のになう最も重要な役割は,そのような防災専門家や一般市民に対する,「自然科学的知識の伝達」であろう.工学や他の近接領域の専門家との対話の改善が重要であろう.対話を有効にするには,理学研究者側にも,社会的ニーズに関する最低限の知識と理解が必要である.
そして,さらに重要な問題は,直接市民(非専門家)に語りかけて,自然現象への関心と理解を深め,自然と共存してゆく意識の徹底を目標として努力することであろう.平均的な日本人は,日常自然災害に痛めつけられているにもかかわらず,他の先進国の人々に比べて,地学現象に対する関心が異常に低いというのが,心ならずも私の持つ確信である.自分の国には火山を持たない,西欧先進諸国の市民の火山に対する好奇心が,日本人のそれをはるかに越えているという事実を繰り返し見せつけられるのが,私にとってはどうにも理解に苦しむ事柄である.学校教育における,自然現象に対して科学する心の軽視は際立っており,理学の基礎研究者も動員して啓発運動を行うこととともに,教育システムの抜本的見直しが必要だろう.
○誰が災害科学を推進するのか
気象・地震・火山噴火災害を含めて,自然災害の防災・減災への努力は,世界中どこでも,国がそのほとんどを担当している.特に災害の予報・予測に関する業務は,民営の企業化が困難であるらしく,大部分が国の税金でまかなわれている.一部に民間の天気予報会社が存在するが,彼らが利用する一次データの収集事業は,やはり膨大な国家予算によって支えられている.環境問題一般に共通する問題として,国レベルでの主導が,現時点では重要視されるべきであろう.
気象学や地震学では,すでに理学と工学の分担が明らかになっていて,それなりに効果が上がっているが,火山災害に関しては,隣接科学での十分な連携がまだ実現していないのが現状である,当分は実質的に,理学出身者が災害の実務者と協力してやっていかねばならないだろうが,将来へ向けてより効率的なシステムが構築されて行くことを望むものである.
「科学者の社会的責任」をめぐって
長 岡 洋 介
本稿では、科学のもつ負の役割に対して、科学者自身がこれまでどのように対決しようとしてきたか、その歴史を物理学の場合を中心にふり返り、問題点を探りたいと思う。これが、将来に向けて学術の果たすべき積極的な役割を示そうとするとき、まずなすべき作業の一つだと考えるからである。
1.核兵器と物理学者
「科学者の社会的責任」の問題が最初に提起されたのは、核兵器の出現によるものであった。核兵器の出現とその後の科学者の運動の経緯は、年表にまとめると次のようになる。
1938年 ドイツの化学者ハーン等によるウランの核分裂の発見
1939年 アインシュタイン、ルーズベルト大統領に書簡を送り、原子爆弾の開発を提案
1942年 マンハッタン計画始まる。ロスアラモス研究所長に理論物理学者オッペンハイマーが就任
1945年 原爆の研究に携わったシラード等一部の物理学者が核兵器の国際管理を提案(フランク報告)。これら物理学者は後に原子科学者同盟を結成
7月 原子爆弾が完成し、ネバダ砂漠で実験
8月 広島、長崎に原子爆弾投下。日本降伏
1949年 ソ連核実験に成功
米国原子力委員会一般諮問委員会(委員長オッペンハイマー)が水爆開発に反対意見
1950年 米国水爆開発を始める
1954年
3月 米国ビキニ環礁で最初の水爆実験。日本漁船第五福竜丸が被曝(9月 久保山愛吉氏が死去)
6月 原子力委員会、オッペンハイマーの公職追放を決定
1955年 ラッセル・アインシュタイン宣言。湯川秀樹等18名が署名
1956年 第一回パグウォッシュ会議。日本からは湯川秀樹、朝永振一郎等が出席
1962年 第一回科学者京都会議
アインシュタインの手紙は、シラード等ハンガリーからの亡命科学者が作成し、アインシュタインに署名を求めたものである。手紙の趣旨は、核分裂の発見によって原子爆弾の可能性が明らかになり、ナチス体制下のドイツが原子爆弾を持つ危険が生じた、その前に米国がそれを持つようにしなければならない、とするものであった。
原子爆弾が完成したとき、ドイツはすでに降伏していた。完成した原子爆弾を日本に対して使用することに原爆開発に関わった科学者の一部は反対したが、トルーマン大統領は使用に踏み切った。
シラード等一部の物理学者は、原子爆弾が人類の滅亡への道を開いたことに危機感をいだき、1945年原子爆弾の完成を前にしてシカゴで会議を開き、原子爆弾の国際管理の必要性を説く報告書(フランク報告)を作成して政府に提出した。しかし、その後の冷戦激化の中でこの提言は入れられなかった。オッペンハイマー等の水爆開発反対の主張も入れられず、オッペンハイマーはスパイの容疑を受けたことがきっかけとなって、公職から追放されるに至るのである。
1954年の水爆の完成とビキニ環礁における実験、それによる日本漁船の被曝は世界に大きな衝撃を与え、原水爆反対の世論が高まった。哲学者ラッセルは、次に世界戦争が起こるなら、それは確実に人類の滅亡につながるとして、アインシュタインとともに戦争の廃絶を訴える宣言を発表した。これに応えて翌年開かれたのがパグウォッシュ会議である。さらに、1962年には湯川、朝永等の呼びかけによって、第一回科学者京都会議が開かれている。
これらの運動において、科学者が特に核兵器、平和の問題に責任があると考えられたのは、第一には科学者が核兵器の出現に直接、間接に関わったことに基づいている。湯川の核力の理論(中間子論)が直接核兵器を生んだのではない。しかし、原子核物理学の発展の中で核分裂の発見があったことは紛れもない事実である。もしもハーン等の核分裂の発見が核兵器の出現に対して責任があるとするならば、その責任は原子核の研究者全体、ひいては物理学者、科学者が連帯して負わねばならないものであろう。
とくにアインシュタインの場合、彼が署名したルーズベルト大統領あての手紙が核兵器開発のきっかけとなったことに深い罪の意識を感じていたと考えられる。直接核兵器開発に携わったオッペンハイマー等の場合はさらに複雑なものがあっただろう。
もう一つの視点は、核兵器の危険を最もよく理解しているのは物理学者、科学者であるから、彼らにはそのことを正しく市民に伝える責任がある、とするものである。第三回パグウォッシュ会議の声明は次のように述べている。「科学者は彼らの専門的知識のゆえに、科学上の諸発見から生ずる危険と望みに早く気がつくよう十分な用意ができている。このため彼らは、私たちの時代のもっとも切実な諸問題について、特別な資質と特別な責任をもっている。」
原子爆弾が完成する前後、核兵器がいかなるものであるかを知っていたのはその開発に関わった科学者たちのみであった。フランク報告によって核兵器の国際管理を提言した科学者たちはその責任を自覚していた。広島と長崎、そしてビキニ環礁における水爆実験を経たとき、核兵器の脅威は事実によって明らかであり、もはや科学者の警告は不要となったかに見える。しかし、米国のスミソニアン博物館における原爆展の中止、インドとパキスタンによる核実験等を見るとき、核兵器をめぐる状況はそのような楽観を許さないのが現実である。
第三の視点は、科学には本来国境がなく、科学者には国際的な協力の習慣が身についている、国際的な対立の中では科学者こそ対立緩和の先頭に立たなければならない、とするものである。ラッセル・アインシュタイン宣言が世界の科学者に、あらゆる体制を超え人類の一員として戦争の廃絶のために集まろうと呼びかけたとき、希望を託したのは科学者のもつ国際性であった。しかし、その呼びかけに応えて始められたパグウォッシュ会議は回を重ね、規模を拡大するに従って次第に変質していった。出席者がそれぞれの国益を代表するようになったのである。出席した湯川の報告にもそのような状況へのいらだちの色が見えている。体制化した科学には厳然として国境があった。それが現実だったのである。
核兵器の出現とともに始まった科学者の運動の最大の意義は、科学者の役割は真理の探究であり、その成果がどのように利用されようとそれは政治の問題であって、科学者が責任をもつべきことではない、とする考えを否定し、「科学者の社会的責任」の問題を提起したことであった。科学者の運動については、その限界も含め歴史的評価がなされなければならない。
2.科学者と軍事研究
第二次大戦中、とくに米国において核兵器やレーダーを初めとする軍事技術の発達に果たした科学者の役割はきわめて大きいものであった。戦争終結後も冷戦体制の下、科学者の動員体制も継続されることになる。米国においては、直接的な軍事研究だけでなく基礎研究に対しても、研究費の大きな部分が軍事費から支出されて、研究が軍の統制下に置かれるという異常な体制が長く続くのである。
戦時下の科学者の戦争協力はわが国においてもこれと異なるものではなかった。学術会議の前身である学術研究会議に1945年に置かれていた特別委員会は、熱帯医学、地下資源開発、航空燃料、国民総武装兵器、磁気兵器、電波兵器、現代支那等であり、戦争協力一色であった。1941年から45年にかけて全国の各大学には多くの研究所が設置されたが、その多くは超短波研究所(1943年、北大)等の軍事研究に直結する工学系の研究所、もしくは航空医学研究所(1943年、名大)、東亜経済研究所(1942年、東京商大)、南方科学研究所(1945年、東大)等の軍事研究あるいは占領政策に関わるものであった。ここにも大学が組織として戦争協力に突き進んだ状況を見ることができる。
学術会議は、1949年1月に開催された第1回総会において声明を発表し、「これまでわが国の科学者がとりきたった態度について深く反省し」、わが国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献することを誓った。また、1980年第19回総会で採択した「科学者憲章」では、第1項目で「自己の研究の意義と目的を自覚し、人類の福祉と世界の平和に貢献する」と述べている。学術会議は戦時下における科学者の態度を反省し、今後戦争への協力をしてはならない、と誓ったのである。
軍事研究拒否は日本物理学会において一つの具体的な運動となった。1966年9月、わが国で開催された半導体国際会議に米軍から資金が提供されていたことが、後に新聞報道によって明らかにされた。これに対して、その責任を追求する声が会員からあがり、1967年に開催された臨時総会において次の決議が採択された。
「日本物理学会は今後内外を問わず、一切の軍隊からの援助、その他の一切の協力関係を持たない。」
その後、物理学会はこの決議に基づいて、物理学会が主催する会議(国際会議を含む)、物理学会の刊行する学術雑誌への軍資金による研究の発表を拒否することとなった。このことは、とくに国際会議の場合、大きな問題を生じさせることになった。基礎科学の分野においても軍の資金を受けることが常態化していた米国の物理学者の研究発表が阻害されることになったのである。実際には、それらの研究論文が軍への謝辞の削除を条件に受理されることがしばしば行われている。
この決議にはその後さまざまな批判が寄せられた。それは、たとえ資金が軍から出ていようと、研究の内容が軍事研究でなければよい、あるいは米国等において軍の資金が広く基礎研究に出されている現状では、この決議は国際的な学術交流を妨げるものだ、などの点であった。確かに、わが国で開催される国際会議を組織する立場にあった物理学者たちにとって、この決議が重荷であったことは事実である。また異なる立場からの批判として、核兵器の例でも見られるように、科学には常に軍事的に利用される可能性があるのであり、基礎研究と軍事研究とを区別するのは原理的に不可能である、軍資金の問題も論文から謝辞を削除するなどの姑息な便法で現実をおおいかくすのはむしろ有害である、とするものであった。
これらの批判はそれぞれに本質的な問題を指摘していたといえる。しかし、日本の物理学者がこの決議によってなしくずし的に軍事研究に取り込まれることを拒否したこと、またそれによって米国における、基礎研究が資金的に軍の統制下に置かれている状況が決して正常なものではないと主張したことの意義を忘れてはならない。
この決議は長く、物理学会が主催する講演会のプログラムの第1ページに掲載されていたが、1997年からは削除されている。削除に当たって物理学会の中で再度決議の意義について議論されたが、統一した評価がなされたわけではない。この決議に関しては今後も議論し続けなければならない問題が残されている。
3.唐木順三の批判と朝永振一郎の自省
以上述べてきた科学者の運動の中で、科学者の社会的責任として主張されてきたことは次の二点である。
1.科学は人類の福祉に役立てられるべきである。科学者は軍事研究に参加してはならない。
2.科学は基礎研究であっても常に悪用の危険にさらされている。科学者は科学の悪用に反対しなければならない。
これらの主張の根底には、科学それ自身には善悪の差はないとする考え方がある。この点に疑問を投げたのは、哲学者唐木順三であった。
唐木は、遺著「「科学者の社会的責任」についての覚え書」(1980年)において、ラッセル・アインシュタイン宣言からパグウォッシュ会議、科学者京都会議に至る科学者の運動について深く思索し、「宣言」の精神がその後の運動において変質していると指摘した。唐木は「宣言」が「私たちは、人類として、人類にむかってうったえる-あなたがたの人間性に心をとどめ、そして他のことはわすれよ、と」と述べていることに注目し、この「宣言」に署名した科学者たちは科学者としての立場を離れて、人類の一員として発言している、とした。これに対して、第1回パグウォッシュ会議の声明は、科学の自由な発展を是認しつつその成果の悪用には反対するという二元論に立っているとして、その態度の矛盾を指摘している。そして、「今度生まれ変ったら、科学者にならないで、行商人か鉛管工になりたい」というアインシュタインの晩年の言葉を引き、アインシュタインには核兵器を生んだ物理学の研究を行ってきたことへの深い罪の意識があったと述べている。
唐木はこの未完の「覚え書」の最後に、まさに覚え書的にこの問題に対する湯川と朝永の態度を比べ、朝永には科学それ自身への深い自省があったとしている。唐木が取り上げているのは、朝永振一郎のこれも遺著となった「物理学とは何だろうか(下)」(1979年)に収録された講演「科学と文明」(1976年)の記録である。朝永はこの講演で「科学ははたして人間のためになるものであろうか」という疑問に正面から向き合っている。
朝永はゲーテの「ファウスト」の例を引きながら、近代科学を生んだヨーロッパ文明の伝統の中でも、科学のもつ原罪に目が向けられていたとし、さらに次のように述べている。知識が罪であるというのは、実は知識の悪用がなされるからであって、知識そのものが罪ということではない-と言う考え方もあろう。しかし、現在の世界は科学が自然の解釈、認識だけの段階に止まっていられない状況にある。その中では、悪用の危険のある科学自体のあり方に目を向けなければならない。20世紀における現代物理学の特徴は普遍性の追究であった。それは物理的世界だけでなく、化学や生物学の一部までもおおうきわめて広いものとなった。その普遍性の追究は、実験によって自然を変え、実験室の中に自然にはない異常な現象を実現することによってなされてきた。このような現代物理学の性格自体が悪用の危険を孕んでいた。科学はこれとは異なる、日常的な自然そのものを対象とする道に戻るべきではないか。これが朝永の述べたことである。
4.現代の問題
朝永の提起した問題は、現代物理学と核兵器に限るものではない。同じ問題として、化学が作り出したさまざまな合成化学物質による環境汚染がある。核兵器を作り出したのは国家の論理であったが、環境汚染の背後にあるものは企業の論理である。いま核拡散は最小限に止まっているが、化学物質は広く地球上に拡散してしまい、その除去は不可能に近い。この状況も科学が自然を作り変えようとして、その「成果」として生じたものである。
核兵器と合成化学物質は、いずれも人類の将来にとってきわめて重大な脅威となっているが、それらは私たちにいわば外側から迫るものである。これに対して、近年の遺伝子工学の進歩は人間の存在を内側から危うくしている。ここでも、遺伝子操作技術という、まさに自然を作り変える研究がその根元にある。
朝永の念頭にあったのは物理学の将来であった。普遍性の追究を続ける物理学は次第に大型の実験装置を必要とし、それはいつか大きさと費用の点で限界に達するだろう。そのとき、物理学は日常的な自然を対象とする道に戻らざるを得ないことになる。朝永はそのように考えていたと思われる。
化学や分子生物学は高エネルギー物理学と違って、ビッグサイエンスではない。自然の作り変えは狭い実験室の小さな装置の中で行われる。作り変えは生活の便宜や病気の治療などの人類の福祉を目指しているのであって、初めから人類の脅威となることを意図しているのではない。しかも、その背後にあるものは、ある意味では国家よりも強力な企業の論理である。科学が体制化されたこの時代に、科学はほんとうに日常的な自然を対象とする謙虚な道に戻りうるのだろうか。私は唐木の根元的な科学批判と朝永の深い自省の意義を認めつつも、科学はすでに後戻りの効かない地点まで来てしまっていることも認めざるを得ない。
核兵器から遺伝子工学まで、それが人類にもたらす脅威はすでに科学者が責任を負いうる範囲をはるかに超えている。もはや科学自身の自己変革にまつ余裕はない。まず、科学は市民社会に対して開かれなければならない。そして、科学者と市民の協力により、両者の合意に基づくなんらかの外的な規制が定められる必要がある。古くは学術会議が論議した原子力研究3原則がそれであり、物理学会における軍事研究拒否の運動はその一つの試みであった。現在、遺伝子工学やクローン技術について論じられているものもそれである。そして、その中においても、科学者の社会的責任の問題はつねに、くり返し問われ続けられなければならないと思う。
学術の社会的役割と教育
長 岡 洋 介
教育の問題は、16期では後継者養成の問題として、今期は環境問題と関連する視点から特別委員会の課題に取り上げられ、検討された。問題は種々の側面をもち、この小論においてそれを全面的に論じることはできない。ここでは、本委員会の課題である「学術の社会的役割」の中における教育の問題の位置づけ、という観点から若干の問題点について述べたいと思う。
学術の社会的役割には次の三つの側面がある。
(1)「技術」の基礎として
(2)「社会に対して行動規範の根拠を提供する」
(3)「文化としての学術」
(1)の「技術」には自然科学を基礎とした狭い意味での技術に限らず、社会科学が政策決定に寄与する場合等も含める。(2)はもちろん、本委員会の出発点となった今期活動方針の一つである。(3)は16期の特別委員会で取り上げられた課題であるが、その委員会は報告をまとめるに至っていない。「文化」とは何か、の理解に隔たりがあったことが報告のとりまとめを不可能にした、と審議経過報告は述べている。確かに、技術を含む人間活動の全体を文化と見なすならば、「文化としての学術」という課題は学術のすべてを意味しており、課題としての意味を失うだろう。しかし、ここでは漠然と(1)、(2)の面を除く学術の役割と理解しておきたい。
もちろん、これらの側面は相互に深く関連しており、明確に分離することは不可能であろう。例えば、ITER(国際熱核融合実験炉)計画について。実際にITER計画を進め、熱核融合を将来エネルギー源として役立てようとする研究は、まさに(1)に属する役割である。しかし、このビッグ・プロジェクトを国として取り上げるかどうかの政策決定には市民の判断が必要であり、その判断を求めるには、市民に対して計画の内容が負の側面をも含めて明らかにされていなければならない。研究者には研究の推進とともに、まさに「社会に対して行動規範の根拠を提供する」責務が負わされている。しかし、いわゆる「エネルギー問題」は、将来予想されるエネルギーの不足を核融合のような新しいエネルギー源の開発により補うことによって解決しうるものであるのかどうか。本質的な解決は、人間の止まることを知らぬエネルギー消費の増大をそのままにしてはあり得ないのではないのか。このような観点に立つなら、ITER計画に対する判断は文明のあり方じたいに関わるものにならざるを得ない。そのとき、「行動規範の根拠」を提供しうるものは、人文科学も含むいわば「文化としての学術」全体であろう。
学術がこのような社会的役割を果たそうとするとき、直接その責任を負うものは学術の研究に携わる研究者である。ここに「学術の社会的役割」の中における教育の問題がある。(1)では単に「技術」の基礎となる学術の研究を進めるだけでなく、その技術を担う技術者の養成もなされなければならない。これが今日、大学教育の大きな部分をしめるものになっている。
しかし、(2)、(3)も含む学術の役割を考えるとき、教育のなすべきことはそれに止まらないだろう。上で述べたITER計画の場合、市民の判断を得るにはまず核融合について正しく理解する市民の存在が前提となろう。この点について、日本の市民社会はいま危機的な状況にあることが指摘されている(風間章子「国際比較から見た日本の「知的営み」の危機」、大学の物理教育1998-2号)。それによると、市民の科学技術に対する関心の度合いが日本は先進14カ国中最下位にあるという(OECDの調査報告1997)。この報告は、これまで日本においては高い教育水準が科学技術の先進性を支えてきたとされていたが、このことがすでに過去の神話と化したことを示している。
何がこのような状況を作り出したのであろうか。一つには学校教育の問題が関わっているに違いない。高校教育の目的が大学受験になり、大学教育が就職が目的の専門家教育となっていること。学校教育が判断力、批判力をもつ市民を育てていないことに責任の一端があることは否定できない。しかし、同時に学術じたいにもまた責任があるのだと思う。根本的には、極度に専門化、細分化した学術が学界の内部に閉ざされていることである。だが、このような学術の現状は世界的なものであるし、学術の発展の中である程度避けえないものでもあろう。その中でとくに日本の市民社会が危機的な状況にあるとすれば、日本の研究者の責任と言わねばならない。なすべきことは、閉じた学界の中から市民社会に向けて発信し続けること、そのことによって市民に判断力、批判力を養う場を提供することである。ここに広い意味での「教育」の問題がある。
市民社会へ向けての発信には、具体的に言えば啓蒙的な書物や論文の執筆や市民むけの講座や講演が含まれよう。研究者のこのような活動は研究者の重要な役割の一つとして評価されなければならない。しかし、それは一方的な情報の提供に止まるべきものではない。かつて昭和30年代に原子核研究所が田無に設置されようとしたとき、住民の反対運動が起きたことがある。このとき、朝永振一郎ら核研設立を進めた当時の学術会議物理学研連のリーダーたちは住民と真剣に話し合いを続け、住民の理解を得て核研設立にこぎ着けることができた。その後、原子力発電所をめぐり、あるいは遺伝子組替え研究施設をめぐって、しばしば研究者、技術者と市民との直接の対話の場が持たれている。そのような場こそ重要な「双方向教育」の場であり、研究者、技術者に真剣な対応が求められると思う。
より根本的には、学術のあり方そのものの問題がある。学術が専門化した現在、学術論文はすべて専門家を対象として書かれている。経済学者内田義彦は著書「作品としての社会科学」の中で、果たしてそれでよいのだろうか、と疑問を提起している。専門家を対象とした学術論文は経済学の比喩でいえば生産財に当たるであろう。しかし、学問が最終的には社会のためにあるのだとすれば、芸術家がその作品を専門家ではない人びとに向けて制作しているように、学術論文もまた作品として直接市民に向けて書かれるべきではないのか、というのがその主張である。ここでは問題は「教育」を超えて学術のあり方そのものに関わっている。
確かに、例えば新しい定理を証明する数学の論文がそのまま市民に向けた「作品」となりえないのは明らかであろう。しかし、厳密な論証をすすめる数学の方法じたいは市民社会にとっても重要である。内田の主張は個々の学術論文すべてに適用できないものであったとしても、学問のあり方に根元的な反省を求めるものとして受け止められなければならないと思う。
本委員会において、医学、農学、工学、地球科学等の個々の分野における学術の社会的役割を検討したとき、つねに市民社会との関わり方、いわば広い意味での「教育」の問題が取り上げられてきた。学術の社会的役割は教育の問題を抜きにしてはありえない。個々の分野における問題はそれぞれの報告で述べられる。
学術の社会的役割-物理学の場合
長 岡 洋 介
本稿の目的は、「学術の社会的役割」という課題を物理学の場合について検討することである。物理学は近代科学の成立、さらには20世紀におけるいわゆる「科学革命」を先導する役割を担った。それだけに、社会との関わりの面においても最も早く深刻な、原理的な問題に直面してきたと言える。したがって、物理学における問題を検討することは、学術一般の問題を論ずる上で、重要な意義をもつものと思う。この委員会の課題は「学術はいかなる社会的役割を果たすべきか」の検討にあるが、私はここでむしろ「物理学はいかなる社会的役割を果たしてきたか」について述べたい。その検討が「果たすべきか」について考えるための前提になると考えるからである。
以下では、まず物理学の技術的応用の基礎としての役割について述べ、つぎにそのことから生じる物理学と政治との関わりについて検討する。物理学は近代科学を先導するものとして科学の方法としてのモデルを提示してきた。これは「社会的」役割と言うべきではないが、近代科学を方向づけることを通して、社会的にもある役割を果たしている。そのような立場から、この問題にも触れたい。最後に、最も基本的な役割として、「文化としての物理学」について考えたいと思う。
1.技術の基礎として
現在、電気は動力源、熱・光源、通信、情報処理等ときわめて広範に利用されている。現代の文明が電気の利用なしではあり得ないことは明白であろう。
電気のこのように広範な利用を可能にしたのは、19世紀における電磁気学の成立であった。蒸気機関を動力源とする機械は、力学・熱力学の基礎なしでも経験によって実現することができた。しかし、電気の利用は電磁気学の基礎なしではあり得ず、とくに電磁波の利用はマクスウェルの理論ぬきでは考えられない。
情報技術をハードの面で支える半導体技術は、量子力学に基づく固体物理学を基礎としている。超伝導体その他の新素材の開発も同様である。
このような、現代文明を支える技術の基礎としての物理学を考えるとき、もう一つ忘れてならないのは、核兵器を生み出した物理学の役割である。核兵器の存在が戦後の国際政治に果たした役割は計り知れないものがある。電気の利用はあまりに広範であるために、その基礎にある物理学の存在が意識されることは少ないが、核兵器の場合はその出現の鮮烈さのために、物理学の役割がマンハッタン計画における物理学者たちの役割と重なって、人びとに強く印象づけられたのである。
ここで強調しなければならないことは、電磁気学、量子力学、原子核物理学等の物理学の発展が、技術への応用を意識することなくなされたことである。マクスウェルが目指したものは、電磁場(エーテル)という新しい対象の従うべき自然法則の確立以外になかった。量子力学確立への端緒を開いたプランクの熱放射の研究は、高温の測定という技術的な課題に触発されたものであったが、それを超えてミクロな世界における自然法則の探究へと進んだのであった。核兵器を可能にした原子核分裂の発見も、原子から原子核へという研究の流れが自然にたどり着いたものである。
しかし、基礎科学の研究が、電磁気学や量子力学のようにつねに技術的応用へ結びつくと期待できる訳ではない。例えば、一般相対性理論や素粒子の構造の理論が技術と結びつくことはあり得ないと思われる。それは、技術が地球上に生活する、有限な大きさと時間をもつわれわれ人間に関わるものだからである。そこに宇宙規模の大きさで重要になる一般相対性理論や超高エネルギーの世界での自然法則が関わることはない。人間を中心にある広がりで、技術と関わりうる物理的世界があって、その外の世界との間には境界があると考えられる。
しかし、これは境界の外の基礎物理学の諸領域が技術的応用にとって無意味だということではない。物理学は科学として一つのまとまった体系であって、その諸分野は相互に深く関連しあっているからである。物理学が技術の基礎としての役割をもつというとき、例えば固体物理学が半導体技術の基礎となるように、直接には個々の分野がその役割を担っている。しかし、固体物理学が物理学の他の諸分野から孤立してはありえない以上、基礎にあるのは物理学全体であると考えなければならない。
このことは同時に、物理学の負の役割に関しても指摘されなければならないだろう。核兵器を生み出したのは、直接には原子核物理学であった。しかし、科学の側がその責任を負わねばならないとすれば、それは原子核物理学のみでなく、物理学全体が連帯して負わねばならないものである。
2.政治と物理学
原子核物理学の研究が核兵器を生み出したことは、技術の基礎としての物理学の役割を大きくクローズアップしただけでなく、その政治的役割をも明らかにした。技術的応用の目的が兵器である場合、それは国家、政治と結びつくことになる。物理学、とくに原子核物理学から発展した高エネルギー物理学は、核兵器を超えるものさえ生み出しうる潜在的能力をもつものと見なされ、冷戦下とくに米ソ両国において特権的地位を占めるに至ったと考えられる。大型加速器の建設が巨額の費用を必要とする、いわゆるビッグサイエンスであったこともあって、それは国力を誇示する役割をも担うこととなった。
もう一つのビッグサイエンスである宇宙開発も同様の役割を担ってきた。そこで用いられるロケット技術は、直接長距離ミサイルと結びつくものだからである。かつてソ連が米国に先だって人工衛星の打ち上げに成功したとき、それは米国が単に科学上の競争に破れただけでなく、軍事的にも劣勢に立ったことを意味していた。米国に与えたショックの大きさがそのことを示している。
高エネルギー物理学の軍事力の基礎となることへの期待はその後後退したが、ビッグサイエンスを推進しうる大国としての威信を誇示するという、歪んだ形の基礎科学の推進が冷戦下で続けられることになったのである。
このことを明瞭に示したのが、冷戦終結後に起きた米国におけるSSC計画の挫折である。それを推進した科学者の意図はともあれ、SSCの予算が認められたのはソ連に対抗する米国の威信がそこにかけられていたからであった。計画が科学者の主張した国際協力の形をとらなかったのもそれ故であった。冷戦の終結はこのような役割をもたされたSSC計画を政治的に不要のものとしたのである。
基礎科学が不幸にももつに至った政治的役割への反省と、ビッグサイエンスの推進が現実の問題として一国では負担しきれないものになったことから、国際協力による道が求められている。しかし、国際協力によって推進されるにせよ、それが巨額な予算を必要とする限り、そこに政治的判断が入り込むことは当然であり、基礎科学といえども政治的に自由ではありえない。それは「ビッグ」になってしまった科学の宿命というべきであろう。
3.科学の方法として
近代科学は17世紀におけるニュートン力学とともに誕生したといわれる。力学の方法の特徴は、自然法則を数学の手段を用いて表現し、それによって現象の定量的予測を可能にしたところにある。ニュートン力学の成功はその方法の威力を強く印象づけるものであった。
19世紀末になると、電子の発見等によって物質の微視的構造が明らかになり、1920年代に至って微視的世界の自然法則として量子力学が確立した。そして、量子力学に基づく物質構造の解明が進み、固体物理学、分子科学の諸分野が大きく発展した。さらに、DNAが生物における遺伝情報伝達の担い手であることが明らかになり、生物もその基本においては物理法則に支配されていることが示されたのである。一方、原子から原子核、素粒子へとより微視的な構造の解明が進み、物理学は今や自然の最も基本的な構成要素とその力学法則(統一理論)の発見に向けて探究を続けている。
このような物理学の方法は、対象をそれを構成する基本的な要素に分解・還元し、それら要素の運動を記述する物理法則を明らかにすることによって、すべての自然現象を解明しうるとする「物理帝国主義」を生みさえした。物理学の成功は、社会科学の分野においても物理学を模範としてその方法を取り入れることによって、理論の確立を目指す流れを生み出した。
しかし、現実の対象にこのような方法を適用するには、その対象の中で本質的な部分に着目し、それ以外のものは切り捨てることによって理想化されたモデルを設定する必要がある。近年、そこで切り捨てられた「複雑さ」それ自体に現実の対象の本質がある場合、この方法は無力であるとして、物理学の「要素還元主義」の限界と、それを超える新しい科学の方法の必要性が説かれている。「複雑性の科学」の主張である。
私は、このような主張の重要性を認めつつも、物理学の中にもすでに単なる「要素還元主義」を超えるもう一つの方法があることに注目したい。熱力学と統計力学の方法がそれである。
熱力学は、熱の関わる現象の分析からその基礎にある法則を発見し、エントロピーの概念の導入によって、きわめて一般性のある現象論を作り上げた。統計力学は、熱力学の対象とする巨視的な物質が莫大な数の粒子(原子、分子等)の集合であることに立脚して、熱力学を基礎づけるとともに、個々の物質の特性を明らかにする方法を示した。莫大な数の粒子を直接扱うのでは何も知ることができない。そこでは、全体の巨視的な性質にとって本質的な、多数の粒子の運動をまとめた少数の自由度を発見することが問題解決の鍵である。
この方法も、多数の要素の中から本質的な少数の要素を取り出すという点で、一つの「要素還元主義」といえるかも知れない。しかし、例えばエントロピーの概念は一粒子の力学的(量子力学的)運動においては存在しえないものであり、巨視的物質においてはじめて現れる新しい「要素」である。単純な「要素還元」的な方法によっては到達しうる概念ではない。「複雑さ」を対象とするとしても、それをとらえる新しい要素(概念)を発見することなしでは、複雑性の「科学」とはなり得ないのではないだろうか。
以上に述べたことは、物理学の社会的役割というよりはむしろ、学術の中における物理学の役割である。近代科学の先頭を走った物理学は、方法の面においても諸科学に対して一つのモデルを提示し続けてきたのである。社会的役割を担う学術を方法の面において先導した物理学の役割を、その限界を含めて確認しておきたい。
4.文化・思想としての物理学
中世においては、地上の現象と天体の運行とは異なる法則に基づくと考えられ、天の世界と地の世界は峻別されていた。これをうち破ったのがニュートン力学である。ニュートン力学は天体と地上のリンゴは同じ力学法則に従って運動するものであることを明らかにし、地球は宇宙の中心にあるのではなくて、太陽系の一惑星に過ぎないことを示したのである。人間の存在の相対化がなされたと言ってよい。それは人間中心の中世的世界観への革命であった。
20世紀におけるもう一つの「科学革命」は量子力学と相対性理論によってもたらされた。量子力学は微視的な世界における因果律が確率的なものであることを明らかにし、力学的決定論を否定した。相対性理論は、ニュートン力学においては絶対的なものと見なされる時間と空間が、観測者に依存する相対的なものであることを示した。これらの理論の出現は、それまで絶対的な真理であると考えられていた力学法則にも限界があることを明らかにした点においても重要である。さらに、近年における宇宙論と素粒子論は、物理法則自体が宇宙の膨張とともに変化するものであることを示している。
このような物理学の発展は、絶対的な真理を求めながらすべてのものを相対化し、絶対的なものを否定する方向に進んでいるように思われる。それは、欧米中心の進歩主義的な価値観を否定し、多様な価値を認める考え方の流れにも添うものであると言えよう。しかし一方において、「相対主義」は科学そのものをも否定するという危険な傾向も生み出している。いわゆるニューサイエンスの流行がそれであり、理系の大学で学んだ人びとがオカルト宗教に取り込まれたオーム真理教の事件がそれであった。もちろん、このような「相対主義」は物理学の成果の誤解に基づいている。ニュートン力学は量子力学や相対性理論によって否定されたのではない。われわれの身の回りの日常的な大きさの世界では、ニュートン力学は今でも正しい。
誤った「相対主義」が物理学の専門家の中にさえ存在することを示したのが常温核融合のスキャンダルであった。これまでの原子核物理学の成果の上に立って見るならば、固体の中であっても核融合が常温で起きえないことは疑う余地がない。曖昧な「実験事実」を信じて多額の研究費が投じられ、高名な物理学者までがその可能性を論じたことは笑い事で済むことではない。誤った「相対主義」の危険は、科学への不信がオカルトヘ走らせるように、それがしばしば危険な「絶対主義」に結びつく可能性を持つことである。
このように、物理学は人びとの世界観に大きな影響を与え、時代を変えることさえしてきた。同時にそれは時代の思想から無縁ではありえなかった。そのような意味で物理学は常に文化の一部だったのである。科学の啓蒙主義の時代は終わったと言われる。しかし、文化としての学術の役割が不要になることはあり得ないだろう。いま新しい「啓蒙」の必要な時代が来ているのではないだろうか。
小島 圭二
社会における科学・技術の共有
--地球・資源・エネルギーの工学の立場から--
○「不確定性の大きい科学技術の世界」での情報の共有
学術は難しいもの、しゃばの世界とは無縁なもの、象牙の塔……これらが、社会が認識する従来の学術のキーワードであろうか。「学術」を「科学技術」に限定して話をすすめる。近頃は科学技術の安全だけでなく、社会がこれなら安心という認識をしないと地域社会の合意がいる公共・公益事業は動かなくなった。このように、社会が科学技術を共有し、自ら安全を考え、安心することが益々重要になっているにもかかわらず、(1)行政も、技術者も判断の前提を語らずに「絶対安全」、「万が一でもありえない」を連発しすぎた。ここに直ぐには修復しがたい不信の蓄積が生じた。(2)情報を公開しないか、するにしても情報量が少なすぎた。(3)公開されても、情報が難解で理解できないものが多かった。この結果、社会は、人任せで自分で技術の安全を考えなくなったし、災害や事故が起こると不信だけが先行するようになった。(1)(2)は改善されつつあるが、とくに(3)に社会における科学技術の共有のボトルネックがあるように思う。最近の科学技術の進歩と専門情報の氾濫は、専門家も束になってかからないと追いつけない事態にいたっている。それだけに最近の科学技術がどれだけ社会に理解されているだろうか。少なくとも、社会に理解する基礎知識が不足しているなど、科学技術が理解される背景が整っていない。この相乗作用が理解を妨げているように思う。専門化と一般化それぞれに科学技術の共有の課題がある。
地球・資源・エネルギーの工学は、地球科学をベースにする科学技術である。ここは人間の生活圏の時間・空間と異なる長い時間と大きな空間を扱う学問分野である。ものを作る工学でも、たとえばエレクトロニクス、遺伝子工学などミクロの時間・空間と両極端に位置する学問分野である。このような科学技術の例として典型的な分野は、一次資源の開発・生産、建設/調査・設計・施工そして維持・管理、自然の環境保全と防災などがある。このような分野の科学技術について、社会への科学技術の伝達、社会における科学技術の共有について考える。
技術者が求める安全と社会が感じる安心とにギャップがある。社会は科学技術で何でもわかっている、あるいはわかると思い込んでいた。そうではなかった時、必ずしも事前にそうではないことを知らされていなかったことを憤る。また専門家の中にもわかっていると思い込んでいて、不用意に安心しなさいという人もいる。専門家にも、不確実性の大きい分野では、判断がモデル化/簡略化された論理の上にたっていることを忘れている人も多い。とくにコンピュータを扱っている人に、そういう錯覚に陥っている人が多発する。最近、社会の「安全の考方」が変わってきた。とくに阪神淡路大震災(1995)は急激な変化をもたらしたことはいうまでもない。北海道の豊浜トンネル(1997)の岩盤崩落も人任せの防災に対する社会の認識をかえた。高速増殖炉もんじゅの事故(1995)、新幹線の巻き立てコンクリートの崩落(1999)は材料等の技術への不信を、そしてJCOの臨界事故(1999)が「安全な日本の管理システム」の神話を覆した。国や地方自治体に安全を任せっぱなしの時代から、地域社会が身をもって防ぎ方、逃げ方を考え、地域から安全を提案する時代へと、時代は急速に変わりつつある。そして社会が、技術の絶対安全の追求では納得しなくなった。事故想定とリスク評価を求めるようになってきた。安全の理解ではなく、安心するためにとでもいえようか。
このためには、設計で想定している安全の限界を、技術者だけでなく、社会が理解していることが重要である。例えば自然災害に関しては、防災施設の設計には限界があり、堤防では100年に一度の大洪水には耐えられる/防げるが、それを越えたら逃げたほうがよい。高潮・つなみに対する防波堤もおなじである。いきつくところ、身の安全は個人の判断次第である。ここまでは防げる、いつ逃げたらよいか、地域社会の個々人が、この設計の事情をよく知っていることと、限界を超えたとき具体的にどんな災害が生じるかを認識していることが基本であり、決め手である。設計は安全の技術であり、万が一の災害の認識は、安心への情報である。
一方、専門家にも不確実性の実感と経験を積む場を設ける必要がある。こんな当たり前のことが、現実を直視しないでも、科学技術がイマジネーションの世界で独り歩きできる今のコンピュータの時代には、専門家にもこの努力がいる。特に日本では、大学の研究者に実務の経験がない人が多すぎる。欧米諸国の多くがそうであるように、実社会でのコンサルタント業務等の仕事との兼業がもっと真剣に検討されてよい。また科学技術の大前提は、「人が運用を誤れば、安全の努力も水の泡」、日本の家芸であった、システム管理にも崩壊の兆しが見えてきたのだろうか。コストと機能が優先する社会の変化、個人の技能(職人技)や会社帰属意識の崩壊、前述の東海村の臨界事故にも繋がる風潮なのだろうか。事故対応も含めてますます社会が科学技術を共有することが重要になりつつある。
○科学技術情報の公開と情報の加工
科学技術の情報の理解度……どうすれば理解されるか。人は「はじめに得た情報」が先入観となって、ものごとを判断しがちである。不信が先に来ると、次の説明も言い訳に聞こえ、事実の理解に時間がかかることもしばしばである。先入観を提供するパンフレットと詳細な根拠を示す報告書との間には、技術のギャップがあるのが通例である。この間を分かりやすく、かみくだいて説明する情報の加工が重要になる。アメリカでも、最近Data
Cookingという用語が使われだした。例えば放射性廃棄物の地層処分では、パンフレットには「深い地下が安全」、もう少し詳しい説明書では「深い地下とは数100mから1000mの地下」、何故1000mか、もっと詳しく知ろうとすると、とっつきにくい、難しそうな、詳細な報告書に飛んでしまう。そして通常はそれを参考にするよう指示してある。専門家はこの説明で、理解してもらったと思い込んでいる。この間の橋渡し、情報加工技術をみがくことが、社会が科学技術を共有するキーポイントの一つである。ちなみに日本の官公庁や企業の広報室には、このような情報加工・伝達のプロがほとんどいない。海外の先進国の多くは、専門の博士が専任している例も見受けられる。
○科学技術の理解に関する教育技術の低迷
一方では、社会に科学情報を理解する下地がなさすぎる場面にも、しばしば遭遇する。基礎的な知見が乏しいことと、論理の展開の仕方(知見の活用の仕方)が身についていないことである。世の中の事象は、とくに不確実性の大きい、データにばらつきがある事象は、その発生確率と平均値が判断の基本である。この考え方もあまり理解されていない。世界と比較した、日本の理科教育の不振が叫ばれているが、とくに地球の科学技術については、知見も考え方も身についていない人が圧倒的に多いのが実感である。日本のあちこちにある、火山から噴出した岩「安山岩」、小中学校で習ったはずのこの岩の名前すら知らない大学生が大部分である。また知識があっても、その活用はもっと苦手である。安山岩は溶岩が固まったものである。溶岩は地表で急に冷え固まるとき多数の割れ目ができる。従って水透しがよく、トンネルを掘ると水が出やすい……。というように、知識を生活/仕事に結びつける発想には、なかなかいたらないのが現状である。
○科学と技術の違いの認識
科学は、法則性とメカニズムの追求が目標であり、仮説をたてて、これを実証することに多くの時間が費やされる。とくに不確定性の強い地球科学の分野では、観測・計測データが不足しがちであり、種々の仮説が示され、学会等においても議論がなされ、時間をかけて有力な仮説が生き残り、法則性が固まっていくものである。なかには、ウェーゲナーの大陸漂動説という仮説のように、現在の地球科学の大前提の理論の一つで、地殻の動きを論ずる「プレートテクトニクス」として、決着を見るのに数百年かかるものさえある。
技術が科学の知見を使うとき、科学では、学会での個人の研究発表は、仮説の段階の知見も多いことに配慮する必要がある。また社会は、学会に発表された研究・報告は、すべて学会がオーソライズした「真実」であると思い込みがちである。一方、技術は科学の知見を応用、実用化することが目標である。知見の不確定の部分は、安全率/保守的な判断をすることで安全を担保することが特徴である。また知見の蓄積を待ち、必要に応じて修正を加え、安全率を下げる努力もなされる。技術的な判断のリスクをなくすため、技術指針等が策定され、学会でもコストを考慮した安全の範囲が議論され、技術判断の合意が形成されていく。
社会に科学と技術の違いの認識がないことが、やたらに仮説を真実と思い込んだり、科学の未完成に不安をつのらせ、技術に不信をいだくもとをつくっていると思われる。
○社会の合意と地域社会からの発信
「まだまだ自然は分からないことだらけ」これを改めて認識することが、地球の科学技術の安全と安心の基本であろうか。謙虚に技術を進展させることはいうまでもないが、昨今は、絶対安全が強調された公共・公益事業の御上主導の説得の時代から、地域社会が、技術の安全を理解し、絶対とはいえないリスクを認識した上で、利便との天秤にかけた検討をおこない、合意とより地域に即したものを選択、提案する時代へと、時代が急速に変わりつつある。社会がどこまで安全の技術の考え方、意志決定の仕方を理解し、合意に至るかには、情報のやりとりの仕方に工夫がいるし、地域社会が、自ら安全・環境を考えることが習慣になるのも重要な要因と考える。現時点は、習慣ができる過渡過程であり、合意の形成に、地域からの提案の発信に、プロの個人もしくは組織の相談役が必要であろう。
○不信派・反対派とのボタンの掛け違い/その原因と科学技術情報伝達のあり方
地震が恐い、断層が気になる、だから原発立地に反対、というよりは、原発そのものが「いや」「嫌い」が先という先入観、またゴミ処理のように、社会的には必要に迫られており、総論は賛成せざるを得ないが、自分の近くにつくることには反対という、いわゆる地域エゴ(NIMBY:not
in my back yard)、本音と立前の問題もある。だから原発にしてもゴミにしても、技術の安全の考え方を理解するよりは、感覚/先入観の世界でもある。社会的にはこういう場合、不信・反対の風潮が強い地域の判断は、相当安全な保守的な設計値であっても、設計基準を厳密に満たしているかだけが論議の中心になりがちである。基準値がどのようにして決まったか、どう使うのかは考えないし、理解させてくれる人もいない。また他の理由、例えば環境破壊、希少生物保護や洪水、崖崩れなどの災害をよりどころに反対する場面も多い。第三者の立場で疑問に気軽に答えてくれる開業医、例えば地面の問題は「Geo-doctor」というような技術診断を引き受けてくれる人がいない。この不安が不信・反対につながっている事例も多い。一方情報を伝える側も、不都合なことは積極的にいわなくなる。ここにもボタンの掛け違いの原因がある。例えば、地滑りや活断層、問われてから念のため調査してみたら古傷が見つかったという事例は、よくあることである。はじめから「想定されたが規模が小さく、安全を設計で担保できるから問題ない、だから詳細な調査はしなかった」という工学的判断をきちんと説明していれば、掛け違いもなかったかもしれないという事例は多い。また技術者自身も、「技術者の慣れ」安全と思いこんでいて、社会が不安に思っている問題を、説明しないか、説明することを気が付かない事例も少なくない。
○資源開発に関する社会の認識の変遷と科学技術の共有
資源開発には、かつて山師というアイドルがあった。目前のコストと開発過程の機能が重視される昨今では、社会の概念から山師が消えた。例えば油田の発見率は、近年では1%にも満たない。その割に探鉱の費用は増大の一途をたどっており、国の盛衰を左右するエネルギーの重要な一翼を担う石油資源の確保には、いぜんとして海外の油田の自主開発は重要であり、各国ともその覇権を競っている。一度当たれば長年の出費を取り戻せる可能性も大きい。長い目で見たコストに関する社会の合意、また世界の大石油開発会社(メジャー)が探しまくった鉱区の中や周縁に小規模でも、コスト削減も含めた技術を結集すれば生産にのる油田もある。「大きい油田が無いと分かっているところに無駄な投資」と非難するジャーナリストもいるが、当たれば元をとる、ないに新天地をかける山師の世界/リスクとベネフィットの賭け、これに技術開発を付加した現代の山師、このような世界も社会の科学技術の共有に理解を求める努力が必要になった。
○産学官共同、実態と実現の道
産学官の共同組織があちこちでやっと動き出した。しかしこれが根付いて成果をあげるには、まだまだ課題が多いというのが実感である。産官は従来から実績はあるが、産学には依然として問題が多い。箱(建物と施設)と金(研究費)だけでは解決しない分野が多いにもかかわらず、とくに「学」「官」の発想が変わっていない。従来通り箱を作ることから計画がはじまっているものが多い。金はあっても、金を使える組織、参画する研究者、研究を支援する技術者を融合させた、人が動ける組織が「学」に育っていない。こういう組織の多くは産に頼っているのが現状である。独立した、対等な立場で(自分がもっているアイデアと実働できる組織を含めたツールを出し合って)研究開発に参画することがプロジェクトの基本であり、成果をあげるみちであるが、この要件がなかなか満たされない。このような問題の解決策はいろいろと検討されているものの、まだまだ発想が箱と金から抜けきれていない。とくに地球・資源・エネルギーの工学は、Field
Engineeringと深くかかわった分野である。ここでは箱よりは人、金を使える組織が重要である。研究者個々の対応には限界があり、データ取得と雑務に追われ、創造的発想をするゆとりが知らぬ間に失われがちである。箱をつくる、その中に高価な計測・分析機器を納めるなど、国の研究費の付け方は、どうしても「もの」に偏りがちである。人(人件費込みの研究費)につける思い切った施策もいる。例えば、海外の大学との共同研究を、日本側が積極的に計画しても、相手は人件費込みの予算をもってくる。従って2桁ぐらい違う予算を要求する。日本はこういう研究費をつける制度に乏しく対応に苦慮するのが常である。共同研究の実績があがらない。人権費は箱に付随するポストに付いているのがまだ一般である。産学共同、国際プロジェクトがうまく動かない難題の一つである。また研究のサービス部門の充実が欠かせない。例えばコンピュータソフトのプログラマー、技術の下請けの技術室、経理や特許、人材交流などの専門事務組織など、どれをとっても、これらの基盤が整っていないのが現状であろう。さらに諸研究分野への研究費配分を考えるとき、社会的にニーズが大きい分野に、人も、研究費も集中するのは世の常である。しかし一方では、日が当たらないが、風通しがよい縁の下があってはじめて、日本古来の家は維持できる。技術においても、縁の下/下請けを切ると、とたんに技術が落ちる事実は、アメリカが経験し、修復にやっきになった事例が目に新しい。それでも欧米には、裾野が広い膨大なボランテアファンドがある。科学技術を支える土台となる、しかし日の当たらないじみちな研究にも、どこからか研究費の手がさしのべられている。このようなボランテア基金が脆弱な日本では、欧米と同じ発想で、重点的に科学技術を先導すると、すぐ底がしれることになりかねない。いまの産学官の共同構想に、バブルの時代に林立したリゾート開発のイメージが重なって見える。もう一つ、Field
Engineeringの分野では、「大学教官がコンサルタント業を併任」が欧米の趨勢である。そこに実務経験から社会のニーズをつかみ、研究開発を発想する基盤がある。日本の大学には、この経験が極端に欠けている。社会に入り込んで、その中から社会のニーズを直に知り、社会とプロジェクトを組む。こういうトレーニングの場をつくることが急務である。社会と学術が共有できてない遠因がここにもある。産学官の共同により、社会の中でプロジェクトを先導する、例えば大学が中心となったコンソーシアムなど、こういう場での研究開発も社会が積極的に科学技術に目を向ける原動力であるかも知れない。動き出した産学官共同の研究を機運に、とくに学にある、以上述べてきたような懸念の改善・充実を期待したい。
○まとめ
社会における科学技術の共有ができていない。情報加工技術/社会への情報の伝達のプロが要る。社会の疑問・不安に答える地域の開業医、例えばGeo-doctorが要る。そして社会の科学技術の共有に「理科・社会」基盤の失地回復が要る、知見もさることながら考え方、使い方のトレーニングも含め教育技術を見直す時期である。この社会環境の中で、科学技術の共有の中で、地域社会からの提案/発信と合意が生まれよう。提案の発信や行政側から提示されたオプションの選択、これらを企画・検討するプロ集団/地域に密着した相談役の組織も育つであろう。また産学官の共同による、社会の中にあって、そのニーズを先導するプロジェクトも、社会が積極的に科学技術に目を向ける原動力となるかも知れない。このような社会における科学・技術の共有の風潮から、社会に総論賛成の基盤が形成され、各論の合意形成に向けて、後は行政の腕のふるいどころとなることが期待される。
Copyright 2002 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN