についての提言(報告)
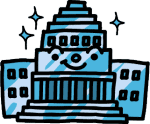
| 委員会名 | 第1部、第2部、第3部 |
| 報告年月日 | 平成9年6月20日 |
| 議決された会議 | 第883回運営審議会 |
| 番号 | 各部16−61 |
| 国立アジア共同研究機構の設立推進 についての提言(報告) |
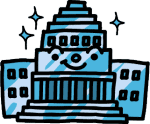 |
|||||||
|
![]()
| 第16期日本学術会議は、アジア学術会議(Science Council of Asia ; SCA)の設立にむけて多大の努力を重ねてきている。また「アジア太平洋地域における平和と共生特別委員会」を設置し、「国際的な平和の問題が新たな様相を呈している冷戦後の世界情勢を検討する中で、特にアジア太平洋地域における平和と安全に関連する諸要因を分析し、貧困の克服と福祉の増進、経済発展と科学技術、文化の相互関係と多様な価値の共存の問題など、平和と共生に寄与するための学術的視点について、アジア・太平洋地.域に重点をおいて検討する。」ことを課題としてきた。 |
![]()
| ヨーロッパ連合(EU)、北米自由貿易地域(NAFTA)を始めとして、今や地域協力が世界的に進展している。アジアにおいても東アジアの経済社会の発展を契機として地域協力の必要性と可能性が急速に増大してきている。それにもかかわらず、我が国におけるアジアの地域研究は、未だ十分組織的になされているとは言えず、21世紀を展望する現代的要請に応えるものにはなっていない。 そこで、アジア研究の日本での研究ネットワークの中核として機能する総合的な研究機構の創設を計画することは、緊急の課題となっている。 |
![]()
緊急の国家的課題として、国立アジア共同研究機構の設立へ向けて、速やかに検討を開始すべきことを提言する。
ネットワーク中核体の機能として、以下の機能を付与することを提言する。
| (1) | 本機構は、情報科学の発展を踏まえた学術研究体制の整備を、広く人文・社会科学諸分野において一挙に促進する機能を発揮するように構築されるべきである。また、本機構は日本を含むアジア地域の研究に関する情報発信の重要な拠点を作り出し、多角的な双方向の情報交流・研究協力により、多言語情報の国際的共有を保証するネットワークの中核として策定されるべきである。 |
| (2) | このような機能をもつ六機構は、アジア学術会議(SCA)において目標となるアシア諸国の学術交流 のネットワーク化とアジア諸国との共生の発展に、人文・社会科学の立場から寄与しようとするもの である。 |
| (3) | 我が国におけるアジア研究の連携中枢を作り出すことは、何よりも人文・社会科学 における学際的総合を推進する上で画期的であるのみならず、自然科学・技術諸分野(生態・環境、資源、医薬災害等の研究)との協力をも著しく促進するものである。 |
![]() 青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
| 近代以降のアジア研究、 第二次世界大戦後のアジア研究、 アジア歴史情報資源センターの目的、 アジア法政研究センターの必要性、 アジア比較経済・経営研究センターの課題 関連研究機関・学協会 アジア経済研究所(通産省)、京都大学東南アジア研究センター、名古屋大学国際協力研究科、神戸大学国際協力政策研究科、横浜国立大学国際開発研究科ほか |
Copyright 2003 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN