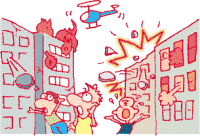
| 委員会名 | 安全工学研究連絡委員会 |
| 報告年月日 | 平成9年6月20日 |
| 議決された会議 | 第883回運営審議会 |
| 番号 | 連絡16−59 |
| 社会の安全・安定化への道の確立について −安全工学の立場から− | 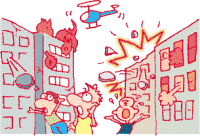 |
|||||||
|
![]()
| 安全工学研究連絡委員会は、第16期日本学術会議・活動計画に則り、我が国の社会の安全・安定化を図り、国際情勢に基づくものとして確立する方策について、以下のように提言するものである。 これは第14期以来、引き続き検討を続けてきた本課題に、偶々1995年1月、阪神淡路大震災及び3月のオウム真理教問題で社会の不安が増大したのを機に、改めて討議を行った結果をまとめたものである。 この討議に当たっては、毎年開催されて来ている安全工学シンポジウム、及びほぼ1年半間隔で開催されてる公開の安全工学ワークショップの場で,関連技術者・科学者が中心となり、一般市民もまじえ講演発表・パネルなどの形で討論を含めて検討して来た成果を参考とした。 この際、さらに広い立場からの批判・検討を求めるべく、委員会対外報告として取りまとめた。 |
![]()
以下は提言の骨子である。
| 提言1 | 社会の安全を確保し,その安定化を行うことは,、工学の一つの責務であり、の方法論につき他分野と協力しつつ検討し、確立しなければならない。 |
| 提言2 | 社会の安全を確保するためには、個々人の安全はもちろん重要である、それをシステム化し、群としての安全を確保するための論理的研究が必要である。 |
| 提言3 | 個々人の安全から、群としての安全を得るためには、幼稚園・小学校レベルから研究者・社会人レベルに至るまでの組織的な個人教育・集団教育が必要である。 |
| 提言4 | 社会の安全を確保し、リスクを低減するためには,国際的な研究の発展からそのシステム化・国際規格化が必要であり、そのための国際研究連絡機関の確立を我が国が中心となって図るべきである。 |
![]() 青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
| 安全制御と国際的標準化、 コンピュータと安全制御、 安全ライフサイクル、 安全インテグリティ、 安全教育と小/中/高校教育、 安全教育と大学教育 関連研究機関・学協会 安全工学協会 |
Copyright 2003 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN