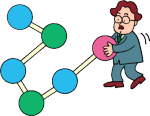
| 委員会名 | 生体機能応用技術研究連絡委員会 |
| 報告年月日 | 平成9年6月20日 |
| 議決された会議 | 第883回運営審議会 |
| 番号 | 連絡16−52 |
| バイオテクノロジーの現状と課題 | 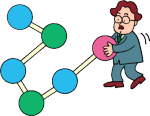 |
|||||||
|
![]()
| バイオテクノロジーの発展に伴って、ここ数年バイオテクノロジーが社会に大きなインパクトを与えつつあり、実際、遺伝子組換え農作物が食品として食卓に上るようになり、また、遺伝子治療も臨床応用されるようになってきた。 このような状況の中で、日本学術会議・生体機能応用技術研究連絡委員会は第16期の重要な活動として、バイオテクノロジーに関する現状分析や将来展望などの評価を行い、今後の活動の参考とするためにアンケート調査を実施した。 今回のアンケートについてはその方式等に関して問題も含まれているが、今後、バイオテクノロジーの成果が社会に適切に利用され、容認されてゆくためには、パブリック・アクセプタンスや生命倫理に関する問題等の調査をさらに続けてゆく必要があり、今回のアンケートはそのための第1段階として位置づけられる。 本報告はそのアンケート結果をまとめたものである。 |
アンケート結果
本アンケート調査を通じて、概ね次のことが明らかになった。
| (1) | バイオテクノロジーは、21世紀の基盤技術となるだろう。とくに、農林水産業や医療・医薬品の分野への応用に高い期待が寄せられている。バイオテクノロジーの更なる発展のためには、十分な研究費と研究者の育成が必要である。 |
| (2) | 我が国のバイオテクノロジー研究は、欧米と比較すると、基礎研究の立ち後れとオリジナリティーの低さが顕著である。従って、今後は基礎研究の充実に力を入れるべきである。一方、応用研究に関しては、バイオテクノロジーに従事する多くの研究者は、我が国がすでに欧米をしのいでいると考えている。 |
| (3) | バイオテクノロジーのパブリック・アクセプタンスや生命倫理の問題については、科学者が市民に対して正確な情報を提供し、社会的合意を得ることが必要である。現在は、高校や大学でのバイオテクノロジー教育が不十分であるが、それを充実させることも必要である。 |
| (4) | 今後のバイオテクノロジーのさらなる発展のためには、日本学術会議が、国際協力の推進、高校・大学レベルでの教育の推進、生命倫理の問題解決、といったことに関して積極的な役割を果たすことが求められている |
![]() 青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
青色のキーワードをクリックすると解説文がご覧になれます。
関連研究機関・学協会 |
Copyright 2003 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN