「学術の社会的役割特別委員会報告」
学術の社会的役割
平成12年6月26日
日本学術会議
学術の社会的役割特別委員会
この報告は、第17期日本学術会議学術の社会的役割特別委員会の審議結果を取りまとめ公表するものである。
[学術の社会的役割特別委員会]
委員長 関口 尚志(第3部会員、フェリス女学院大学国際交流学部教授)
幹 事 渡邊 二郎(第1部会員、放送大学教養学部教授)
柳澤 信夫(第7部会員、国立診療所中部病院院長)
委 員 淺沼 圭司(第1部会員、成城大学文芸学部教授)
大谷 實(第2部会員、同志社大学大学院総合政策科学研究科長)
竹下 守夫(第2部会員、駿河台大学長)
大山 道廣(第3部会員、慶應義塾大学経済学部教授)
荒牧 重雄(第4部会員、日本大学文理学部教授)
長岡 洋介(第4部会員、関西大学工学部教授)
小島 圭二(第5部会員、地圏空間研究所代表)
三井 恒夫(第5部会員、東京電力株式会社顧問)
高倉 直(第6部会員、長崎大学環境科学部長)
武田 元吉(第6部会員、玉川大学農学部客員教授)
角田 文男(第7部会員、労働福祉事業団岩手産業保健推進センター所長)
要 旨
(1)作成の背景
1-1 今日、学術は知的体系の創造・伝承という固有の使命を超えて、人々に「行動規範の根拠」を提供するなど、社会に「開いた学術」であることを求められている。1-2 この要請に応えて、日本学術会議では、今期の「活動計画(申合せ)」を受けて、「俯瞰的な科学的知見」の提供することを主軸に「自己改革」の実施を決定した。1-3 この動向を背景に、現代における「学術の社会的役割」を多面的に省察し、多様な社会的取組の経験を総覧して、学術と社会の新しい相互関係の在り方を提示する。
(2)現状及び問題点
2-1 学術とくに科学技術の圧倒的な成果が社会の隅々まで浸透し、同時に核兵器、地球環境問題、クローン人間誕生の不安など難問を引き起こすことになって、学術に対する人々の期待と不安が高まり、古典的な「象牙の塔」での「学問の自由」と「固有自治」の理念はそのままでは存立し難くなっている。
2-2 学術の専門化・細分化が著しく、複雑な現代社会の問題に十分対応できていない。
2-3 科学者が社会の負託を受け、社会のニーズを先見的に感知して、現代の諸問題を総合的・俯瞰的に考察し、その結果を適確にまた達意に発信して市民や政府に「行動規範の根拠」を提示し、社会に対する説明責任を果すという、「負託自治」の理念と倫理を確立し実践するうえで、取り組むべき多くの課題が存在する。
(3)改善策、提言等の内容
3-1 俯瞰型研究プロジェクトの本格的な推進 現代社会の諸問題は複雑な諸要因の絡み合いであり、個別領域での「合理的」な「解決」はしばしば領域外に重大な「負の効果」を引き起こす。俯瞰型研究様式の推進は、領域を超えた「広域の俯瞰」「本質の俯瞰」「負の効果への挑戦」を可能とし、「負託自治」実践上不可欠な課題である。
3-2 基礎研究の振興 基礎研究の過度な対外依存は、果たすべき国際貢献の回避として経済摩擦・文化摩擦の火種となる。「基礎研究タダ乗り」論は過去のことではない。大型プロジェクト研究の推進が「純粋基礎」的な基礎科学の等閑視になりかねないという「負の効果」を予防する意味でも、文科系を含む基礎研究の振興が課題である。
3-3 教育の再構築 日本が科学に基礎をおく優れた教育体制と教育水準の高い多数の人口を擁しているという常識は、過去の「神話」である。若者や市民の、世界でも異常な徹底した「理数科離れ」「知の営み離れ」があり、大学では「教養の凋落」が著しい。いま「総合的な学習」や「新しい教養」の構築が課題とされ始めたように、「俯瞰」は研究だけでなく「俯瞰型教育」の視点なのでもある。学術の社会的役割の大きな柱は教育である。その危機は「科学者の代表機関」として座視し難い事態である。
目次
前文-いま、なぜ「学術の社会的役割」なのか
第1章 学術の本来的使命
1-1 「学問の本義」-知の創造・伝承-
1-2 学術と社会-「学問の本義」と「知者の使命」-
1-3 古典的な「学問の自由」-「固有自治」の理念-
1-4 受容と変容-日本の場合-
第2章 現代社会における学術の役割
2-1 学術と社会の新しい関係-社会の期待と学術の状況-
2-1-1 学術の現代的使命
2-1-2 背景:現代社会の期待と要請
2-1-3 内在的契機:学術の状況と自己革新の胎動
2-2 現代社会における「学問の自由」-「負託自治」の理念
2-2-1 「俯瞰型」研究様式と「負託自治」構築の課題
2-2-2 「負託自治」の理念
2-2-3 「負託自治」と「固有自治」
2-2-4 変革の課題
2-3 科学者の社会的・倫理的責任-「負託自治」の倫理
2-3-1 科学者像の変革
2-3-2 「学問の自由」と「法による規制」
2-4 行動規範の学術的根拠-科学と実践との連関について
2-4-1 事実認識と価値判断
2-4-2 政策論的思惟の学術的「客観性」
第3章 学術と社会
3-1 新しい科学論の挑戦-「モード2の科学」と「政策過程研究」
3-1-1 「負託自治」と「俯瞰型」研究様式構築の課題
3-1-2 モード2の科学
3-1-3 政策過程研究
3-2 学術の在り方、社会の在り方-現場からの教訓
3-2-1 現場での経験、経験からの教訓
3-2-2 学術の在り方
3-2-3 社会の在り方
第4章 重点的な推進課題
4-1 「俯瞰型研究プロジェクト」の振興-課題的専門化=領域的総合化-
4-1-1 俯瞰型研究プロジェクトの理念と様式
4-1-2 俯瞰型研究プロジェクトの特徴
4-2 「基礎研究」の重視-「基礎研究タダ乗り論」の教訓から
4-2-1 現代産業社会における基礎研究の役割
4-2-2 科学技術の「日本問題」
4-2-3 科学技術基本法と基礎研究重視の課題
4-2-4 文科系基礎研究の現代的意義
4-3 「教育」の再構築-「知の衰退」と「科学技術創造立国」への困難な道-
4-3-1 科学教育立国「神話」の崩壊
4-3-2 「理数離れ」と「教養の凋落」
4-3-3 「俯瞰型教育」と「考える教育」実践の課題
4-3-4 「新しい教養」教育の構築
第5章 日本学術会議の社会的役割
5-1 創立50周年の自己点検・評価-変化の胎動
5-2 今後の在り方-変革の理念と重点
[参照文献]
[附属文書]
前文-いま、なぜ「学術の社会的役割」なのか-
この報告は日本学術会議が第17期に設置した「学術の社会的役割特別委員会」の報告書である。日本学術会議は「第17期の活動計画(申合せ)」において、「学術全体を俯瞰的に見る視点」を重視することと、社会に対して「行動規範の根拠を提供する」「開いた学術」を構築することを「活動の基本的方向」ないし「重点課題」として強調した。今日、学術は知的体系の創造・伝承という役割を超えて、社会的行動規範の学術的根拠を人々に示すことを期待されている。本特別委員会は、このような「活動計画」の理念や課題に即して、現代における学術とその担い手の社会に対する役割と責任を多面的に検討し、「学術と社会の新しい相互関係」の構築・深化について審議を重ねてきた。
この間、日本学術会議では運営審議会が設置した起草委員会を中心に「自己改革」の草案を取纏め、昨年秋(1999年10月)の総会で「日本学術会議の自己改革について(声明)」を採択した。この声明は、日本学術会議の創立50周年を機会に「現状の問題点」を点検し「改革の方向と具体策」を示したものであるが、「省庁再編(行政改革)」など困難な状況のなかで、「現行の日本学術会議法の下で実行可能な改革」に限るなど、比較的短期に合意形成が可能な、制約条件のもとでの最適策の提示が目標とされたため、残された課題も少なくない。しかし、それにもかかわらず、「自己改革(声明)」は「行動規範を求める社会のニーズに先見性をもってこたえ」、「それに資する俯瞰的な科学的知見を」「行政、産業及び国民生活に還元する」ことに「特に力点を置く」と述べているように、明確に今期「活動計画(申合せ)」の基調を「改革の方向」に据えて、当面実施すべき「具体策」を迅速に策定することができたという点で、画期的な成果ということができる。
本特別委員会は、「学術の社会的役割」をテーマとするにもかかわらず、この改革案の策定・審議のプロセスに委員会として積極的に関与することを避け、いま報告書を公表する途を選択した。それは、委員会が、発足当初から、やや長期的に腰を据えて新しい「学術の社会的役割」の意義・内容をできるだけ根本から歴史的・原理的に省察し、また多様な社会的取組の経験を総覧して、学術の在り方、社会の在り方、日本学術会議の在り方をアカデミックに整叙するという、いわば「後衛」の役割に徹する方針をとってきたからにほかならない。法的枠組等の制約条件も、時には一応外してみて、といってもよい。一例をあげて、そのことの意味を考えてみよう。
日本学術会議法の第2条、「日本学術会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的とする」という規定のうち、前段における代表性の解釈に関しては、改革論議なかで詳細な検討が加えられてきた。しかし、後段、とくに社会に科学を「反映浸透させる」という表現については、今日まで特段の吟味もなされてはいない。しかし、「反映浸透させる」という、上からの、やや一方的な表現は、「象牙の塔」の高みから「栄華の巷」を下に見て政府や国民の蒙を啓くという、基本的には「固有自治」の響きを有している。すくなくとも、そこには、国民の負託に応え、社会のニーズを感知して、現代社会の諸問題を学術の課題として構成し、研究の成果を社会に還元するという、「負託自治」の理念は的確に表現されていない。「学術と社会との新しい関係」構築の課題は、実は日本学術会議法の規定を超える「革新性」をもち、この法を「読み抜き読み破る」意識変革の作業が創立50周年の課題として、いま、会員一人一人に提起されている。この程度の感覚と掘り下げた問題認識が改革には必要なのではあるまいか。
それにしても、学術はそもそも「社会の役に立つ」ものでなければならないのか。純粋な「知者の楽しみ」から生れた学術の成果が、やがて社会を変える科学技術や人々の生き方を支える文化科学として「実用の知」に結実した事例はいくらもある。いずれにせよ、現代社会となれば、科学技術を初めとして、政治・経済、医療・福祉、教育・娯楽など、社会生活のどの場面をとっても、学術研究の成果が取り込まれていないところはない。人々は、行動規範の根拠もまた多かれ少なかれ学術に期待するようになっている。
もちろん、「実用の知」はしばしば「悪魔の知」としても現われる。地球環境破壊など現代社会の様々な病理はほとんどが科学技術に支えられた経済効率優先の開発の結果であり、その解決もまた科学技術の成果に依存せねばならないジレンマが存在する。複雑な現代社会の諸問題は多元的・複合的な諸要因の複雑な絡み合いであり、個別領域での「合理的」「解決」はしばしば領域外との関連で重大な「負の効果」を引き起こす。「複数領域の科学者の協調」が「複合汚染」の予測的警告を可能にし、経済開発の「副作用」に対して有効な処方箋を書くために必要とされている。行動規範の根拠を提供するためには、人文・社会科学の知見も含めて、技術を超えた広い視野からの考察が求められている。
本報告では、現代における学術の多様な社会的役割のなかから、とくに重要な推進課題として、「俯瞰型研究プロジェクト」の本格的な振興をあらためて強調した。実践的・課題的専門化(理論的・領域的総合化)、すなわち学際化・超領域化・「統合科学」化を目指す新たな研究様式の創出である。
報告ではまた、かつて科学技術に関する「日本問題」として展開された「基礎研究タダ乗り論」が過去のものでないとの見地から、基礎研究の重視を重要な推進課題と位置づけた。基礎研究の成果は人類の公共財であり、基礎研究を過度に外国に依存し続けることは単純な国際間の技術分業の問題でなく、果たすべき国際貢献の回避として経済摩擦・文化摩擦の火種となる。また、概して実用的な効果を期待しうる大規模なプロジェクト型研究の重点的な推進は、往々、その「負の効果」として、「純粋基礎」的な個別研究を含む重要な基礎科学を等閑視することになりかねない。俯瞰型研究プロジェクトを推進する日本学術会議は、「俯瞰型」の長所である「負の効果」への予測的警告者の観点からも、基礎研究の重視を重要な推進課題とすべきである。
第3の重点課題として、本報告は「教育」の再構築が急務なことを強調する。「科学技術創造立国」論に関連して、日本は「科学に基礎をおく高度な教育体制を確立し」「その中で育った優れた国民」「教育水準の高い人口」を「多数擁する」という「実績」が常識のように語られるのが普通である。しかし、この認識は最近では過去の「神話」になりつつある(あるいは、なってしまった)ことを示す調査が増えている。若者や市民の世界でも異常な徹底した「理数科離れ」、「知の営み離れ」をどうするのか。学術の社会的役割の大きな柱は教育である。大学では「教養の凋落」も著しい。初等・中等教育でも高等教育でも、いま、「総合的な学習」、「新しい教養」の構築が課題とされている。「俯瞰」する視点は、研究だけでなく、「俯瞰型教育」の問題としても重視されつつある。「科学立国」「教育立国」の危機は、「科学者の代表機関」である日本学術会議として座視し難い事態である。危機意識とそれを反映した教育改革のプログラムが必要とされている。
第1章 学術の本来的使命
1-1 「学問の本義」-知の創造・伝承-
学術の使命は、本来、真理探究であり、「真実の知」の創造である。「知の創造」は知的財産の継受を基盤とする営みだから、「知の創造と伝承」が「学問の本義」といってもよい。いずれにせよ、それは単なる「実用の知」(実生活の直接の必要)や原生的な「悪魔の知」(呪術の園)から解放された「真理」や「本質」を求める純真な行為である。「純粋な知的好奇心」を動機とし「象牙の塔」にふさわしい「学門のための学問」の世界である。「余裕」(スコレー)とか「観想」(テオリア)といった古代ギリシャの言葉が、そうした学問の原点を伝えている。
1-2 学術と社会-「学問の本義」と「知者の使命」-
学問は人類の知的財産の創造という、それ自体に内在する文化価値を有している。したがって、「無用の用」というべきか、学問はその存在そのものによって最も本質的な「社会的」役割を果している。学術と社会の古典的・原基的な関係は、ひとまずこのように単純化して理解できる。この「学問の本義」は現代社会でも忘れられるべきではない。
ところで、学術は現実には実践的・功利的関心に導かれて存立・発展する一面をもっている。「実生活の必要」が「生活の知恵」として学問的な思惟を促した事例は古くから存在した。また学者は因習と偏見に囚われた大衆の蒙を啓く「知者の使命」をもち、ソクラテスやガリレオなど、権力や時流を批判して「真実の知」に殉じたケースも少なくない。学術と社会はその古典的な関係の場合にも、すでに、「学問の本義・本質を守る」ことと「社会に影響を与え奉仕する」こととの緊張を含んでいる。封建的な専制政治の桎梏のなかで「精神の王国」を理想としたフィヒテの時代には、真理探究という「理念の内面的純粋さ」と、「歩み出て世を掴み」人々の「信任」と「大事の委託」に応えるという「外面的活動との相克」が、知識人の論題になっていた。しかし、市民的秩序と産業社会の登場に至るまでは、「実際の社会生活への直接的な寄与」は一般には重要な課題でなく、むしろ「学問の理論や真理の圏域は、実世間の実利的功利的な修羅場とは本来別個である」という自覚の確立が、学問に生きる人々の基本テーマとなっていた。
1-3 古典的な「学問の自由」-「固有自治」の理念-
「学問・大学と社会・国家」の問題は「学問の自由(自律)」「大学の自治」の問題であり、後者の在り方は時代や社会によって変化してきた。
中世ヨーロッパでは、ボローニャ大学など、学生の集団や教師の同業組合(ウニヴェルシタス、コレジウム)の「自治」が形成されたが基本的には教会から与えられた特権で、後見的自治にとどまった。「学問の自由」はなく、学術(哲学)は「神学の婢」の地位にあった。しかし、宗教改革で「良心の自由」「思想の自由」、17世紀「科学革命」で「哲学する自由」「思索する自由」が次第に普及した。
「学問の自由(自律)」と「大学の自治(固有自治)」は「純粋な学問」論の立場から主張された。国家権力などの関与は「純粋な真理探究」になじまない。学問とその諸分野は固有の内容・方法をもち、その正否は専門家しか判断できない。そうした学問の本質に由来する「学問の自由」と、学問により必然的に生じる「専門家の自治」が確立した。いわゆる「固有自治」としての「大学の自治」、「研究・教育の自治」である。
背景に、18世紀末~19世紀初頭、ベルリン大学などを拠点に展開したドイツ理想主義哲学と、とくにその大学理念(フンボルト理念)が存在した。その特徴は、
①純粋な「真理のための学問」の主張に基礎付けられた「固有自治」(上述)の立場。当面、啓蒙的専制君主国家プロイセンが支配する後進ドイツの時代的制約もあって、その「学問の自由」「大学の自治」論は社会に開かれた「負託自治」(後述)の契機を展開できず、「市民的な自由」と異質な「治外法権」(自由であることの特権)、そうした高い城壁をめぐらした閉鎖的な「学者共和国」(「象牙の塔」)の形成を導くこととなった。
②学問は個々の領域に分立する様々な知識ではなく、本来、哲学を結集軸とした諸学の全的な統一体として存立した。哲学が諸学の中枢として他の学問分野に理念的な基礎(学問的・倫理的な意味づけ)を提供し、諸学が学問外の要求に屈して学問の道を踏み外すことのないよう律していた。大学は基礎的な哲学部と職業分野に対応した上級諸学部(法学・医学・神学)の統一体であり、「大学の自治」も本来は -学問の専門分化とともに一般化する「学部(教授会)」(同業組合)の自治でなく- 総合「大学」の自治だった。
③「研究と教育の一致」。この理念も、哲学部(およびこれを中核とした諸学の統一的な体系としての大学)において成立する(成立すべき)研究・教育の理想であり、日本で誤解されてきたように、個々の専門学部すべてに直接に適用されたものではない。
1-4 受容と変容-日本の場合-
明治以降、戦前日本の大学は、基本的には19世紀中葉の欧米の大学をモデルにしていたが、「国家ノ須要ニ応スル学術技芸」(帝国大学令、第1条)を教授攷究する帝国大学を中心に、工学、農学など、国策型「実学」に重点を置いて発展した。帝国大学形成期に工学部、農学部をもつ総合大学は世界で例がなかったから、日本の大きな特異性である。和魂洋才、明治政府の独特な工業化・西欧化政策が背景に存在した。イギリス産業革命期の技術革新が科学の成果でなく職人の現場の経験の所産だったのと対比して、19世紀後半の技術は科学を基盤としていたから、最初から工学を学問として受け入れる(科学を技術のための科学として導入する)素地が整っていたという事情もある。
日本が西洋の大学をモデルとして受容し変容した過程で、大学自治の伝統的理念もまた移植され、独自な「自由」と「自治」の慣習へと育てられた。市民的自由が欠如する環境のなかで、行財政の規制を受け「国家ノ須要ニ応スル」という「官制自治」「下達自治」の枠内で、「学問の自由」が特権として享受されるという構図である。研究・教育は国家の要請に安易に応じる傾向をもち、社会に対する建設的な批判や提言など大学の「社会的奉仕」には消極的で、逃避的・防衛的な体質が作り出されていた。学問の「総合性」についての関心が薄く、「学部(教授会)の自治」や「講座制」の垣根が重視された。「研究と教育の一致」も専門領域ごとに強調され、リベラル・アーツとユースフル・アーツを協調的・統合的に捉えようとする意識は弱かった。
敗戦で市民的自由が成立し「学問の自由」も保障された。大学制度の改革も実施されている。しかし「大学の自治」の伝統的・日本的な理念や慣行は「ほとんど戦前のまま」残された。大学紛争後、東京大学の『改革準備報告書』は「一般社会から隔絶した『象牙の塔』として存在することは不可能になったにもかかわらず、大学は、『大学の自治』の伝統的理念が旧来のままの形で実質的意義をもち続けているかのような錯覚に陥っていた」と反省した。21世紀の国立大学像を論じた吉川弘之国立大学協会会長(当時)は、「負託自治」の概念を提起して、「国家によって与えられた自治を持つ国立大学を、改めて民主主義国家にふさわしい、自発的であるがしかも国民に認められた自治を持つ大学へと変身させていくという仕事が、まだ達成されていない課題として残されている」と強調する。「学術の社会的役割」の再検討は社会の発展と学術の展開に対応するグローバルな現代的課題であるが、日本の場合、それは学術と社会の関係(「大学の自治」の在り方)の近代化を促す意味を併せもっている。近代化・現代化の同時的な達成の課題である。
第2章 現代社会における学術の役割
2-1 学術と社会の新しい関係-社会の期待と学術の状況-
2-1-1 学術の現代的使命
今日、学術は純粋な真理探究、「学問のための学問」という本来の古典的な使命を超えて、新たな社会的役割を負託されている。日本学術会議は「第17期の活動計画(申合せ)」(1997年10月)において、社会に対して「行動規範の根拠を提供する開いた学術」を目指すことと、そのために「学術全体を俯瞰的に見る視点」を重視することとを両軸として、「学術と社会の新しい相互関係」を構築することを重点課題として決定した。
「現代の大学」(あるいは「未来の大学」)では旧来の「研究」(知識の獲得)や「教育」(知識の伝達)とならぶ第3の機能として、知識の社会的な「応用」(K.ヤスパース)ないし「社会奉仕」(A.パーキンス)が重要な役割を期待されている。第3の機能といっても、「社会奉仕」の主な内容は「学問のための学問」に対する「社会のための学問」であり、「後継者の養成」に対する「社会が必要とする人材の養成」なのだから、むしろ「研究・教育の新しい在り方」といってよい。研究成果の社会への還元が求められているのである。この場合、日本学術会議の問題提起、すなわち人々に「行動規範の根拠」を提供する「開いた学術」の立場は、社会的要請に単に「受け身」で対応する消極的なものではない。研究者が社会から負託された「負託自治」の責務を自覚して、社会的現実への「高い感受性」を不断に研磨し、こうして積極的に社会の現実的な諸問題を予見し探知し解明して、人々に「行動規範の学術的根拠」となるべき情報を提供する、そうした能動的な新しい学術的態度が意味されているのである。国民の負託に応え、人々の期待、社会のニーズを感受し学びとって、現代社会の諸問題を学術の課題として構成し、研究の成果を社会に還元するという、双方向的な「学術と社会との新しい関係」をデザインしようとする「負託自治」の理念である。
2-1-2 背景:現代社会の期待と要請
学術と社会の「新しい関係」が必要とされ必然とされている背景には、学術に対する現代社会の期待と要請が存在する。技術革新と経済社会の発展が、それを可能とした学術、とりわけ科学技術の「実際的有用性」を社会の側に強く意識させた。科学は、今日、ニュートンやガリレオの時代と違って、社会や生活の隅々まで入りこんでいる。政治・経済、運輸・通信、医療・福祉、教育・娯楽など、また一国の軍事・防衛から市民生活の物質的・精神的な豊かさ・貧しさまで、学術や科学技術の発展とその在り方に左右されない分野はない。現代社会は「文化国家の基礎」としての科学に大きな期待を寄せている。
反面、人々の危惧も高じている。国立教育研究所の調査では、小学5年生に科学技術の印象を聞いたところ、「科学のために世界がだんだん破壊されている」、「世の中の困ったことの多くは科学技術が原因になっている」といった悲観的な見方の方が多数だったという。たしかに、原爆の開発からクローン人間の恐怖まで、「真実の知」「実用の知」が「悪魔の知」に堕落する不安が存在する。科学技術の発展に支えられた産業社会・情報社会の展開は、一方で経済格差、情報格差、「心の貧しさ」を生み、資源・エネルギー・食糧問題や地球環境問題、有害化学物質、新手の感染症など、社会や人々の生活に複雑で困難な課題を突き付けた。しかも人々は、こうした現代社会の病理の解決についてもまた、多くを自然科学と先端技術に依存し、人文・社会科学を含む学術の叡智に期待せねばならないというジレンマに立っている。
こうして現代の社会は、どの切り口をみても、様々な形で科学を抱え込んでいる。科学は優れた産業技術の母胎としてだけではなく、-「無知もまた罪」、たとえば環境科学や生命科学の学術情報を知ることが、日常生活や政策選択にさいして市民や政府の「拠り所」となり「義務」ともなるというように- 人々の「行動規範の根拠」とされるという意味でも、重要な社会的役割を期待されている。いうまでもなく、民主化された市民社会では、君主や国家が「行動規範」や「期待される人間像」を上から開示してその鋳型に人々を押し込むことは難しい。とりわけ冷戦構造が崩壊し価値観も多様化した現在、人々は「市民的公共」の意識を身につけた自立した個人として、一人びとりの日々の生活の経験を通して、それぞれの「行動規範」を彫琢すべき立場にある。学術的な知見はそのさい一つの重要な「行動規範の根拠」となる。
この点も含めて、科学は現代社会の様々な次元に浸透し嵌込まれ制度化されている。グローバル化が進展して、従来は国内問題と見做されてきた問題の多くも国際的・地球的な広がりの中で考察されるようになった。逆にその解決は地域社会での人々の地に足のついた取組の積み上げに依存することも、「グローバルに考え、ローカルに行動せよ」という格言に託してしばしば強調されている。こうして様々な次元や広がりで科学を抱え込んだ現代社会は、もはや、学術研究を「象牙の塔」という特殊な空間に囲い込み、そのなかで学者が自己の知的好奇心を充足する、自己完結的・閉鎖的な営みと位置づけることは、できるべくもない。「固有自治」から「負託自治」への転換(重点移動)の背景には、社会の側での学術に対する期待・要請のこのような変化が存在する。
2-1-3 内在的契機:学術の状況と自己革新の胎動
学術の側でも、近代科学の思考方法や研究様式に問題があって、そのために社会から提起された諸課題に十分に対応できていないのではないかという反省が提起され、これを内在的契機にして「学術と社会の新しい関係」を模索する自己革新の胎動が生じてきた。
(1)近代科学の成功と領域区分の制度化
17世紀ヨーロッパで自然科学を中心に成立した近代科学は、物理学とくにニュートン力学に代表されるように、経験的な「観察と実験」の方法と厳密な「数学的定式化」の方法を武器に、対象としての外的世界を普遍的・形式的な客観的因果律(法則性・規則性)において認識する知識体系である。科学(自然科学)の圧倒的な成功と近代の社会と学術におけるその地位の確立につれて、人間の社会や文化に関する諸々の学問も社会科学・人文科学の概念でくくられる傾向が広まったが、そこには学術一般に占める科学(自然科学)の「範型」的地位が表現されている。
ともあれ、近代の知は、行為の動機である主観の働きに対して人間の意志や感覚から自立した客観の世界を対置し、自然と社会と文化の関連を切断する抽象化の操作によって、普遍的な因果性の論理が貫徹する科学を誕生させることができた。自然・社会・人文諸科学への領域区分が当然の前提とされ、さらにその内部で専門化・細分化が進展する。とりわけ19世紀以降、科学の様々な体系が組織化され、専門化・細分化が進展して、科学は認識の体系として制度化された。また社会的な需要を反映して、学部・学科のなかに講座ができ、科学研究の組織も制度化されている。同時に科学者も職業倫理をもつ専門の職業人として確立し制度化されていく。
(2)要素還元主義と巨大科学の限界
近代科学の特徴的な思考方法に要素化(要素への還元)と数量化(量への還元)が存在する。要素還元主義の考えでは、複雑な現象を背後で規定している本質的なものはその現象の最も簡単な構成要素に遡ることによって把握される。また、本質的なものは質的には同一で、すべては量の差に還元されるという数量化の立場から、現象を支配する法則性は量と量との数式的な関係として説明されることになる。裏からいえば、近代科学は、ニュートン物理学から近年の素粒子論や分子生物学にいたるまで、対象を要素化・数量化しやすい領域や問題に限定することによって大きな成果を上げることができた。経済学など社会科学の分野でも、要素化・数量化による普遍的・形式的法則性・規則性の究明という、近代科学の思考様式は多くの場合基本的に共有されている。
19世紀末以降の「物理学の革命」で要素還元論が一段と徹底され、現象(物質)の「最も簡単な」構成要素が、分子、原子、さらには、原子核と電子になり、原子核も陽子と中性子の複合体であることが解明されて、この3種が素粒子とされたこともある。しかし、その後実験装置が大規模になり、次々に素粒子が見つかって、いま「最終」単位とされるクォークを確認するためには、超巨大装置と巨額な資金が必要とされている。各種の巨大実験装置の建設は大国にとっても負担であり、アメリカの議会は超伝導超大型加速器(SSC)の建設を承認しなかった。アメリカ政府はまた、国際熱核融合実験炉(ITER)計画からの撤退を決定した。巨大科学の際限のないマンモス化には国民のコンセンサスという歯止めがある。基礎研究は原則として公的な資金で賄われているから、研究者や大学は国民に対する説明責任(アカウンタビリティー)負っている。政府と納税者がどれだけの費用を認めるのか、他の科学技術や福祉・医療・教育を含む公的負担との兼ね合いで、どのようなプライオリティーを付けるのか-「学術と社会の新しい関係」のなかで、何をどのように研究するかは研究者自身が決定するという「固有自治」の原則は、このような制約との緊張関係におかれることになる。
(3)専門化・細分化の進展と学際化・超領域化の胎動
20世紀には、相対論と量子力学を契機に、確率論的な「法則」理解への旋回と要素化・数量化の深化や情報概念の組み入れを伴いつつ、近代科学の思考法が仮説演繹法として定式化された。仮説的演繹的方法の体系化・精緻化にともない、科学の操作可能性が増大し(条件Aを与えれば結果Bが生じるという関係が明らかになれば、Bを手に入れる可能性が生まれてくる)、研究そのものが本質的に応用可能な属性をもつことになった。このことは、一方では現代文明の形成・発達の基盤となり、同時にまた、学問の動機・目標が「真実の知」(「真理」の探究)から「実用の知」(「精密さ」の追求)へと重心を移動する傾向を助長した。科学技術の反社会的・軍事的「悪用」の危険も増大した。
現代科学の仮説演繹的な性格は、妥当範囲を限定するほど精度を高めるから、学問領域の専門化・細分化を加速した。専門化・細分化は学術研究の高度化・情報化・加速化によっても促進されている。高度な知的情報の加速的な氾濫と急速な陳腐化は、専門領域の限定によって速報的な業績をあげる傾向を助長したのである。専門化・細分化にともない、複雑な現代社会とその複合的な病理を総合的に理解し予防し制御することは困難になっている。個々の領域での個別的な「確率的法則」ともいうべき因果の蓋然性を把握することは比較的容易である。しかし現代世界を多元的・複合的な連関構造へと構成する「諸法則の束」、そうした複数の法則性・規則性の連鎖を「束ねる論理」を捉えること、そして、そのうえで、個別分野で練り上げられた経済政策や開発された科学技術が他の諸分野にどのような「副作用」を与えるかを予測して、未然にそれを予防したり緩和したりすることは容易でない。まして、普遍的な論理の整合性を求めて自然・社会・文化の関連を切断した「知の領域区分」が支配する近代科学の問題的な状況のなかで、諸々の事象の客観的な因果関係の分析だけでは満足せず、出来事の意味や価値をも併せて考究し人々に伝えることは、「意味喪失の時代」に生きる人々が求める重要な関心事ではあっても、普通の経済学者や科学技術者には -学際的な協力の態勢なしには- 困難な仕事である。
そもそも現代社会の深刻な問題の多くは「専門主義の野蛮性」(オルテガ)の所産であり、複合的な病理をもっている。学際的(interdisciplinary)・超領域的(transdisciplinary)な挑戦など「学術の俯瞰的構造」への胎動は、過度な専門化・細分化と専門知識の独断に陥りがちな学術の在り方への問いかけであり、また、研究者が「精神のない専門人」(ヴェーバー)への頽廃を克服して主体性を取り戻し、研究者集団が《university》(統一性・共同性)を回復して真の「学術の自律と責任」を保持しようとする、学術主体の在り方への真剣な問いかけを意味している。
経済の発展と生活の便利さを支えてきた科学技術が、地球温暖化、人口問題、生命倫理など、「自ら生み出した」困難な課題に直面し、「問題を生起させた責任」を問われている。成長率を上げれば豊かな生活が約束されるという未来図は、開発計画の多くが自然破壊をもたらし、生活の利便性がしばしば重大な生態系の破壊によって購われたという現実を前に、無条件では信じられない虚構になっている。「自然との共生」「未来世代との共生」をキーワードとする「持続可能な発展」の模索が、地球規模でのプロジェクト型共同研究の課題となっている。人口爆発や食糧問題の誘因に優れた医療技術や薬品の開発があり、分子生物学と遺伝子操作の目覚ましい発達は生命倫理の試練を投げ掛けることになった。これらはいずれも、多様な構造連関をもっ社会システムに対して、科学技術システムの特定分野に係る観点・論理・技術が他の諸分野との調和を欠いて作用した結果、社会の様々な分野に「予期せざる」副作用の連鎖が起き、社会システムの秩序が破壊された事例である。多様な要因が複雑に絡み合った結果だから、縫れをほどくには多様な視角をもつ学問諸分野の総合的な取り組みが必要とされている。
ところで、現代科学の「負の効果」を「副作用」とも表現してきたが、たとえば公害問題は、科学技術や工業の発展過程で生じた産業社会の副産物といっては済ませない重みをもっている。すなわち、第一に、学問の専門化・細分化が進み研究者の分業が行き過ぎているために、資源・環境問題等、自然・人間、社会の問題を総合的に考える有効な手立てがない。第二に、近代科学の論理は「数の論理」であり「無限の拡大を前提とした論理」である。従来の経済学には、地球環境や地球資源の有限性を前提とした成長のモデルはない。「無限性を前提とした量の論理を基礎にした発想からは、それを解決するための科学的方法がうまく出てこない」(竹内啓)。近代科学の本質に係わる根本問題なのである。
20世紀には、物理学にも(相対性原理、量子力学)、生物学にも(分子生物学、脳神経生理学)革命的な変化があり、コンピューターや情報を含めて科学技術も加速度的に発展した。同時に地球規模での困難な諸課題が噴出して「知の組み替え」が求められている。改革は本来「科学者の内発的な作業」であるが、「学術と社会との共同作業」も必要とされている。いずれにしろ、必要な前提は科学者の意識改革である。学術と社会の接点では多様な問題について様々な角度から「科学者の社会的・倫理的責任」が問われている。
(4)グローバル化と「新しい一般理論」への途
現代社会の複雑なテーマは多くがグローバルであり、発題も解答も国際的・地球規模的な視点を求めている。「学術と社会の新しい関係」は、学術の国際化、社会のグローバル化をふまえて論じられなければならない。近代科学の認識の枠組は、グローバリゼーションの進展によっても再吟味を求められている。その場合、国民国家を前提とした社会科学や文化科学、とくに経済学の枠組が再考を促されていることはいうまでもない。が、同時に、グローバル・スタンダードの重要な意義が認識され強調されるにつれて、逆説的であるが、経済社会の歴史性・国民性があらためて浮き彫りにされ、経済システムや経済発展の「文化的多様性」が強調されるようになったことに注目すべきなのである。
近代の経済学はイギリスなど西洋先進国の、それも最盛期の諸事実に対象を限り、「合理的に行動する経済人」という抽象的な前提を出発点にして産業社会の複雑な運動や構造を純粋なモデルに構成した。しかし、自然も文化も異なる後進諸国や低開発諸地域の経済社会の現実は、この抽象化された普遍性の論理では分からない。「経済大国」となった日本でさえ、「政治寄生的」「談合的文化」や「派閥」「人脈」、「過当競争」と「独占」癖、「身内」と「余所者」といった意識や関係が未だに根強く経済社会のなかに埋め込まれて共生し、大きな力を振るっている。経済学の「文化的限界」を自覚して、経済と文化(経済発展と文化摩擦)を統合し、欧米起源の方法的枠組を相対化する「一般理論」(大塚久雄)を創造すべきこと、「先進国にしか意味を持たない」学問を「地球上の全人類に、できれば等しく有用な、真に汎用的な学問」(吉川弘之)へと改変すべきことが、様々な角度から提唱されている。要素要素に還元して個別領域の枠内でそれぞれの論理や法則を整合的に理解する -そうすれば複雑な全体も説明できる- といった従来の学問の「蟻の眼」の手法ではグローバル化の時代像を捉え得ないという、幅広い不信感が「鳥の眼」の俯瞰を求めている。観点をずらしていえば、専門知の「ひたすらな精緻化」と「独断」を排して、「日常生活に根ざした問題群がもつ具体性との豊かな交流」を基盤に、「自然が発する声なきメッセージヘの畏敬」と「異文化的な背景をもつ他者への配慮」(山之内靖)を支えとすることが、新たな学術の出発点に必要とされているのである。
2-2 現代社会における「学問の自由」-「負託自治」の理念-
2-2-1 「俯瞰型」研究様式と「負託自治」構築の課題
学術と社会の「新しい相互関係」においては、学術の側は、第一に、閉鎖的な「象牙の塔」の硬直した「固有自治」に閉じこもるのではなく、社会の負託に応える「負託自治」の立場にたって現実の困難な諸問題と積極的に取り組み、人々に「行動規範の根拠」となるべき情報を提供するなど、研究の成果を社会に還元する「開いた学術」を構築することを求められている。そのためには、第二に、専門化・細分化した学問領域の枠組をいたずらに墨守するのでなく、複雑な現代社会の問題群に対応して関係諸領域間の共同研究体制を組織するなど、「学術全体を俯瞰的に見る視点」の重視が必要である。
科学者が社会の期待を主体的に感知し内面化して、人々が「行動規範の根拠」とするに値する研究成果を社会に提示し還元すること、そのための「新しい作業」として専門知の枠を超えた総合知・実践知の形成を軸に「知の組み替え」に努めることは、伝統的な「学問の自由」「大学の自治」の考え方の枠組を超える、その意味で「学術と社会の新しい関係」を象徴する事態である。俯瞰型研究様式構築の課題の背景(ないし根底)には、純粋な「学問のための学問」論を究極の拠り所とする古典的な「固有自治」の理念・体制から社会の負託に応える開かれた「負託自治」の立場への旋回の課題が存在する。
2-2-2 「負託自治」の理念
「学問の自由」と「大学の自治」は、戦後日本社会が最高の価値序列に位置づけてきた基本的な理念である。日本国憲法(23條)には「学問の自由は、これを保障する」と書かれている。たしかに、現在、高度産業社会、情報化社会になって、学術や科学技術の社会的影響力が強まり、研究・教育に対する社会の期待・要請や財政支援も拡大した。大学は社会の重要な一部として埋め込まれ「制度化」して、その社会的責任が増大した。学術と社会のこの「新しい関係」のもとでは、「象牙の塔」での「知の探究」という「学問の本義・本質」に由来する古典的な「固有自治」はそのままの形では存立し難くなっている。市民的な社会的合意のシステムのなかで、研究者が国民の負託を受け、社会の期待に応える責任を負って成立する「負託自治」が、現代における「研究の自由・自律」を特徴づけている。それは世の中の要請にへつらい流行に流される他律的・消極的な「受け身」の態度を意味するものではない。むしろ、研究者が社会の現実の諸問題を主体的に予見しテーマ化し解明し意味づけて、人々に「行動規範の学術的根拠」を提供することによって、負託された自治への説明責任を果すという、双務的な関係が「負託自治」であり、研究者の思考や判断の自主性・自律性が根底に置かれているという意味で、「自由」と「自治」の本質は損なわれていない。
2-2-3 「負託自治」と「固有自治」
現代の社会でも、大学は社会の知的活動の拠点であり、人類の根源的な知識欲の凝集点であって、「真実の知」の創造が本義とされている。学術は、産業や国民生活の有用な基盤として圧倒的な重みを加えてはいても、学術それ自体「文化」としての価値を有している。むしろ、科学技術が発展し「実用の知」(ユースフルアーツ)が重用されればされるほど、「真実の知」(リベラルアーツ)への関心が回帰して、「無用の用」が注目されてくる。大学は世俗社会の修羅場にあってその流行や利害に囚われず、この世のあるべき真実を探求する「超然的な場」として存在意義がある。常識外の奇抜な着想、既存の通説や社会・社会意識の批判など、自由で闊達な雰囲気が保障されていなければ、社会や学術の進歩はない。もちろん、社会一般に市民的自由が確立されている場合には、この「固有自治」の保障といっても「象牙の塔」を構える必要はなく、大学は市民社会に立地する「小高い丘」として存立する。
こうして、現代的な「学問の自由」は、近代化された「固有自治」と、積極的に社会に開かれた「負託自治」という、二つの側面(契機)をもっている。両者の緊張関係(調和と相剋、補完と対立)が現代社会における「学問の自由」「大学の自治」を成立させている。あるいは、「負託自治」のなかに「固有自治」の契機が揚棄(止揚) -高められて保存- されている、といってもよい。このことを、日本学術会議の総会における「共通の理解」を取纏めた会長発言要旨(1998年4月)は、以下のように述べている。「学術の影響というものを考えるとき、科学技術政策への関与というのは、ある一つのことにすぎないのであり、研究者・科学者というのは本質的に自分が関心を持つ研究をする人々であるという基本的姿勢が、日本学術会議の本来の成立根拠であることを常に忘れてはいけないのであって、学術というものの本質を守ることと、社会に影響を与えることをどういうふうに調和させるかが、現代の学術に与えられた本質的な課題である…。」
2-2-4 変革の課題
学術と大学の社会的役割が増大し、社会との関係が緊密になるほど、「開いた」大学と「市民」社会にとって、真の「学問の自由」「大学の自治」の存在が重要になってくる。それぞれの大学は、その理念に従って、「大学の社会的奉仕機能」をどの程度、またどのように重視していくのか、専門化した学問諸分野の深化・充実と学際的・総合的な研究・教育の創造・育成とをどのように組み合わせ、また、リベラルアーツとユースフルアーツの関係をどうするのかなど、学術の基本的な在り方を構想することが急務である。そうした学術再編成の要請に対応して、上述した「固有自治」と「負託自治」の相互関係や緊張関係に留意しつつ、自らの「学問の自由」「大学の自治」を主体的に確立して、適切な研究・教育・管理の組織や運営の変革に取り組むことが求められている。
日本の場合、戦前の「国家の大学」への反省もあって、社会に対する積極的な提言など大学の「社会的機能」には概して消極的で、地球的症候群に対処すべき学術の「総合性」についての関心も近年まで稀薄だった。大学を「民主主義国家にふさわしい、自発的であるがしかも国民に認められた自治を持つ大学へと変身させていくという仕事が、まだ達成されていない課題として残されている」のだから、変革の大筋は、社会に開かれた「負託自治」のシステムの構築であり、俯瞰型研究プロジェクト構想に代表される学術のテーマ凝集的な「実践的専門化」(学際的・超領域的な「理論的総合化」)を妨げることのない柔軟な研究・教育組織の創出である。こうした大局的な方向を展望して、しかし、変革はそれぞれの大学や分野に応じて多様であることが望ましい。世界には現在、社会的な奉仕と大学の自治の観点でみると、比較的に「古い大学」も「新しい大学」も併存する。ケンブリッジ大学もカリフォルニヤ大学も、それぞれが個性をもって独自な社会的役割を果している。自主性の尊重と画一性の排除が改革のモットーとされるべきであろう。
社会に開かれた「知性の府」の確立に向けて「新しい自治」を形成するために、必要とされる具体的な改革のプログラムは多彩である。現代日本の代表的国立大学の理学部物理学科が内外の学者の協力を得て実施した外部評価では、大多数の教授・助教授が世界的な研究業績をあげていることが評価された反面、研究者の関心や視野が狭隘なことが指摘されている。その原因としては、学会全体における「業績主義」(したがって業績評価の在り方)が大きいと考えられるが、日本の大学一般についていえば、「講座制」の残影が業績の細分化をもたらしていることも否定できないであろう。(一般に物理学の分野では講座制の弊害が早くから自覚され、その改善に熱心に取り組まれていることが定評となっている。)「業績主義」や「講座制」のほか、「学部(教授会)自治」の在り方の再検討、大学における領域変更の規制緩和(講座・学科・学部・研究科等の統廃合・再構成、教員組織の流動化、サバティカル制度等の活用)、領域間交流と産学協同の促進、プロジェクト型研究・教育体制の推進、専門教育とリベラルアーツ教育の統合を含むカリキュラム改革の検討、自己点検・評価や外部評価の在り方、等々。また、一学部、一大学の枠を超えた複数学部・複数大学の協調的・連帯的自治、大学連合体の集団的自治についても、大学の相互評価を含めて、「新しい自治」の在り方の一環として積極的に検討の課題となる。
2-3 科学者の社会的・倫理的責任-「負託自治」の倫理-
2-3-1 科学者像の変革
科学技術の社会的影響力が決定的となり、学術と社会との新しい関係が、社会に開かれた「負託自治」と俯瞰型への「知の組み替え」を双軸として構築されるためには、新しい時代に対応した科学者像の変革、「負託自治」の倫理の確立が必要とされている。実際、研究と社会との接点では、多様な問題について様々な角度から「科学者の社会的・倫理的責任」が問われ、自覚されている。諸々の領域での科学的知識の発達・応用が、人々の夢を現実化する挑戦であったとともに、地球上に貯蔵された膨大な核兵器、開発と格差、環境汚染、資源・エネルギー・食料問題、クローン人間の恐怖、等々、現代社会の悪夢のような問題群の発生の一因にもなっているという《結果に対する責任》の意識。この複雑な問題群の把握と解決にとって専門化・細分化した個々の学術では十分な知識を提供できないという《認識の一面性》についての自覚。《無知もまた罪》、「知の組み替え」等、叡智を結集して諸課題の解決に貢献し研究成果の《社会的還元》を果たそうとする、社会に対する学術の《説明責任》の義務意識。これらの事柄について人々の理解を得、共に歩もうとする真摯な努力が、困難な現場の経験のなかから形成されつつある。
「精神のない専門人」として科学の至上主義に安住するのでなく、社会の自律し責任ある学問主体として、個々人の研究がもつ社会性を自己確認することが、「負託自治」の倫理の基本をなしている。全米科学アカデミーが科学者を志す若者に配布している行動規範の文書(On Being a Scientist)は、最終章で「どれほど応用から遠い領域で、純粋研究に従事しているときでも、それが及ぼすかもしれない社会的影響の可能性について、常に最大級の注意を払わなければならない」という趣旨を強調している。日本学術会議でも、たとえば「高度研究体制の確立について(要望)」(1995年10月)に付された会長報告で「科学の進歩が引き起こす可能性のある社会的な影響について考察し、好ましくない影響を未然に防ぐために配慮すること」を重要な「研究者の倫理」と述べ、「研究者は科学的成果を挙げることに専念すればよく、その成果をどう利用するかの責任は政治やその他の社会の権威にある」という「科学の中立主義」を批判して、科学の濫用・悪用を防ぐため「歴史から教訓を学び、科学のもたらす結果についての倫理的な考察を確立する」ことを求めている。
知識の生産を無条件で善とし正義とし、真理の探究が邪であるはずはないと単純に思い込む純粋でナイーブな時代に終止符を打ち込んだのは、「核兵器を生み出した物理学の役割」や「戦時下の科学者の戦争協力」への反省である。工学の分野でも、マンハッタン計画の反省を原点に、「工学者はその時点での短期的展望のみならず将来を見る目を養い、社会的責任を自覚してプロジェクトに参加して、人類興亡の責任を負うべき時代になりつつある」ことが確認された。また、近年の意識調査では「工学者は製品の直接的な安全性にのみ目を向け、環境、資源などに対する配慮を著しく欠いていた」として、意識転換、パラダイム転換を必要とする意見が浮き彫りにされ、「これからの工学者は、単に技術の開発だけでなく、その社会的、歴史的効果までも考察できる幅広い思考能力を必要とされるし、結果に対してより重い責任も生じる」ことが指摘されている(日本学術会議第3常置委員会『学術の動向とパラダイム転換』1997年6月)。
日本学術会議の総会が採択した「科学者憲章」(1980年)は、冒頭、「自己の研究の意義と目的を自覚し、人類の福祉と世界の平和に貢献する」ことを科学者の責務として宣言した。今日では、どの学問分野でも、問題を生起させた、また生起させうる責任と、自己の認識の一面性についての自覚に立ち、それ故にまた、人々の要請や課題の存在を早期に探知する「高い感受性」と、社会や学術を広角的に展望し歴史の未来を遠望して見通す「広く深い視野」とを研磨して、学術が社会に与えうる「負の効果」をも予防し制御しつつ、人々の夢と福祉と平和の実現に役立とうとする、意思と能力にみちた人材が「期待される科学者像」として求められている。学術審議会は「21世紀に向けての研究者の養成・確保について」の建議(1996年7月)のなかで「新しい時代に対応した望ましい研究者像」の一項を設け、「細分化が進む学問領域に閉じこもることなく、社会や学問全体を視野に入れながら、社会に果たす自分の役割や使命を自覚するとともに、科学と人間、社会あるいは地球環境との調和が求められている状況において、科学の社会的役割ないし責任を正しく理解出来る豊かな人間性を持つことが強く求められている」と強調した。大学審議会も「平成12年度以降の高等教育の将来構想」を策定するにさいして、「学術研究の成果と人間や社会との関わりに関する高度の識見を身に付け」「学術研究面での貢献を通じ、地球環境問題、食料問題、エネルギー・資源問題などの地球的規模の課題を解決」していく人材が重要になっていると論じている。
多くの学協会でも倫理綱領や行動規範を定めている。現代の科学は二重に「社会化」されている。一つには、科学は様々な「制度」を通じて社会に堅固に組み込まれ、それゆえその社会的影響と責任は大きくかつ日常化されている。同時に、研究者は専門的職業人として「科学者共同体」を形成し、学協会等の組織を場として活動することが多くなっている。科学の影響力の増大に対処して、学協会や病院・大学等が倫理規定を定めたり倫理審査委員会を設置するケースが増えているのである。最近では日本機械学会が倫理規定を制定した。会員は「自らの良心と良識に従う自律ある行動」が「科学技術の発展とその成果の社会への還元」に不可欠であることを自覚して、「人類の持続可能性と社会秩序の確保にとって有益」であると判断したうえで研究や業務に参加し、人類や環境への影響を予測評価し、研究等の内容や結果は積極的に公開して説明することを求められている。日本化学会でも行動規範を策定し、人類の発展への奉仕、社会の利益や福祉への貢献、環境汚染の防止、知識の限界の認識と真実を謙虚に受けとめる責務などを求めている。
工学系では技術者資格制度が検討され、日本工学会と日本工学教育協会が中心となって日本技術者教育認定機構も発足して、技術者の社会的・倫理的責任や工学教育における倫理教育の重視が強調されることになった。技術者の資格としては、高い専門知識と応用能力のほか、その技術の社会的意義、倫理性、他技術との関連、相乗効果、資源・エネルギー・環境・人口など人類の重要課題との関連を洞察する能力が問われることになる。
しかし、楽観は許されない。いま研究者や技術者の社会的・倫理的責任が一斉に強調されていることは、むしろこうした側面が従来ないがしろにされていた証拠である。実際、産官学の構造的な癒着や安全性への配慮義務の希薄さ、患者や被験者の人権の軽視など、かつては聖職(profession)といわれた専門「職人」の職業倫理やプライドは、その死角に一部ではあっても深刻な綻びを見せている。それにまた、日本では、歴史的に「企業や組織に対する(しばしば連帯的な)責任」の意識は強くても、企業や組織から自律した個人について、その「社会に対する責任」の意識は育ちにくい。「負託自治」の倫理は「自立した個」としての研究主体が社会の負託に応える説明責任の意識であり、生半可な努力では日本の文化的風土に定着するものではない。
日本学術会議は、このような困難な状況までも見通したリアルな人間理解のうえに立って、しかし、現場の経験のなかから生まれようとしている「負託自治」の倫理を根づかせ育てるために、その環境を整備し、学術の成果が人々の利益と正義に合致して正しく用いられるよう、基準や規範の作成に寄与するなど、必要な措置を講ずる役割をもっている。「科学者像について、その変革の方向を探る仕事が日本学術会議に課されている」(吉川弘之会長)のである。
2-3-2 「学問の自由」と「法による規制」
「学術と社会の新しい関係」の確立にとって、研究者個々人の倫理は大切だが、問題は更に深刻で根源的である。その象徴が、クローン人間づくりを違法とする、法による研究規制の問題である。そこには、すべてを「研究者の倫理」と古典的な「学問の自由」「大学の自治」にまつことは出来ないという切迫した状況が投影されている。科学技術の発展とその社会的インパクトはそれほど強烈で加速度的である。学術と社会の関係は、今日、部分的とはいえ、基礎研究に国家が立ち入ることを制度化するほど、根底的に構築し直すことを求められているのである。
核兵器を製造したのは直接には国家の論理であり、環境汚染の原因には企業の論理が存在する。しかし、その背後には、国家・企業による悪用・濫用の危険を可能とした科学技術の在り方が存在した。自然を観察し自然と共生する力にとどまらず、自然を作り直し破壊する力を秘めた科学技術の論理である。この点で、科学技術はもはや後戻りの効かない地点まで来たかの如くである。今世紀中葉、DNAの発見など生物学革命を展開し、世紀後半には情報革命と結合し躍進して、21世紀を代表する科学として期待されている生命科学は、遺伝子操作の科学技術を基礎に据えて、革新的な医療や新薬の開発に貢献すると同時に、原理的には人クローン個体(特定の人と同一の遺伝子構造を有する人)の人為的作製さえ可能にして、人類にとっての「可能的な脅威」に成長した。
科学には正負両用の効果が存在する。「科学技術の在り方」といったが、現実には「両刃の剣」、悪用できない科学や技術はほとんどなく、科学技術の進歩にはほとんど常に光と闇が付き纏うといってもよい。光の部分を生かし、闇の部分を制御することが、第一義的には研究者の、しかし、困難な場合には国家(また国際機関)の責務となる。
本来、生命諸科学は人間(ヒト)を含む生命現象の全体像や多様性を総合的に捉えることを使命とする。そして、人間の生存を直接に介助する医学をはじめとして、生命諸科学は、ヒトの存在に意味や価値を認めてこそ成立する「人間の尊厳」を基盤とした科学である。その生命諸科学は、臓器移植、人工臓器、生殖医学、遺伝子診断、遺伝子組換えや、さらにはゲノム(とくにヒトゲノム)解析とクローン技術を加えて、新しい医療技術や創薬原理の開発に大きく貢献し、農業、畜産、食料、環境保全等、地球的規模での諸課題に挑戦して、人類の発展に寄与している。DNA鑑定の犯罪捜査への応用など、その威力は広範に浸透した。こうして、生命科学は人間や産業のあり方に大きな影響を与えるものに成長したばかりでなく、それゆえにまた、人間の尊厳、人権、安全について、ときに深刻な問題を提起することになった。生命科学の発展は、生命倫理、すなわち生命科学の時代に人々(とりわけ研究者)が拠るべき新しい行動規範(研究規範)を求めている。生命科学の研究が生命倫理の裏付けをもって健全な歩みを続けるには、倫理的、法的、経済的など、広く人文・社会科学を含む俯瞰的「人間学」的な観点との交流も必要とされている。そうした総合的な視点から、今日、社会によって負託された「負託自治」の理念に立ち、「研究の自由」に対する自主的な、また時には法的な規制や制約が、どのような場合にどのような形態で、またどのような根拠に基づいて必要とされ許容されるのか、包括的な議論をふまえた社会的合意の形成が課題である。
人の遺伝情報全体であるヒトゲノムの本体は塩基約30億個で構成されるDNAであり、この膨大な塩基配列を読み取り、解読した遺伝子の機能を解析することによって、様々な病気の遺伝子や新薬開発に役立つ遺伝子を特定することが期待されている。遺伝子多型の測定によって個人毎の木目細かい治療や処方も可能になる。我が国でも産官学共同の「ミレニアム・プロジェクト」の一つとして、高齢化社会に対応し、2004年を目標に「痴呆、がん、糖尿病、高血圧等の高齢者の主要な疾患の遺伝子の解明」を基礎に「オーダーメイド医療を実現」し「画期的な新薬の開発に着手」することが決定されている。
DNAが「遺伝情報」を担う実態であることの発見は、宇宙の原理的構成要素が「物質・エネルギー」と「情報」であることを認識させ、「情報」概念は人間の主観的な意識や知識から解放されて、遺伝子に媒介された独立の客観的なシステムとして捉えられることになった。ヒトゲノムDNA配列の解読には膨大な作業量が必要で、その急速な進捗はコンピューター技術の高度化なしには不可能であった。ゲノム研究は、生物現象から遺伝子へという、近代科学の要素還元的・解析的な方法を最も忠実にふまえて最も成功した分野であるが、今後は、逆に、遺伝子から遺伝機能、生物機能へという、演繹的、統合的な方向へと転回して、生命科学のパラダイム転換を促す役割を期待されている。このような生命科学の展開とともに、情報革命の成果への依存はますます大きくなる。科学研究や技術開発の情報化は、研究を効率化し予想を遥かに超えた成果をもたらすと同時に、科学技術を自己目的化し、研究をオートメ化する傾向をもつであろう。自己展開する研究がたどる複雑で長い連鎖の彼方に何があり、その意味は何なのか。研究者でも見通せない予期せぬ危険が伏在する。生命倫理とともに情報倫理、メディア倫理が必要とされている。
遺伝子研究の社会的・倫理的問題については、欧米では早くから論議があり、1997年11月にはユネスコ(国連教育科学文化機関)の「ヒトゲノムと人権に関する世界宣言」、翌月にはWHO(世界保健機関)の「遺伝医学の倫理的諸問題および遺伝サービスの提供に関するガイドライン」が採択されている。これにより、人間の遺伝子情報は人類の遺産であり、ヒトゲノムを経済的利益の対象としてはならないこと、遺伝子研究やその診断・治療・予防への応用にさいしてはインフォームド・コンセントの徹底が基本であり、仮にも「望ましい遺伝的な資質を国家が選ぶ、という優生学」と妥協してはならないことが確認された。個人のプライバシーや家族情報を保護し、遺伝情報が結婚・雇用・保険加入などの差別に利用されることのないように配慮することが求められ、クローン人間づくりは禁止すべきことが宣言されている。研究の自由と人間の尊厳の両立のために、加盟国は国内で必要な措置を講ずることが要請されている。
日本では、若干の関係学会が、たとえば受精卵(胚)の着床前診断を重篤な遺伝子疾患に係る場合に限るなど、遺伝学的検査に関するガイドラインを定めている。しかし、学会の自主規制には強制力がないのが一般的で、また民間の「遺伝子ドック」等を有効に規制できないことや、学会のルールと大学の倫理委員会の見解とが食い違うなどのケースもあり、より実行ある措置を求める声も少なくない。
本年(2000年)厚生省が、国としては初めて遺伝子解析研究について協力者の同意の取り方や個人情報の保護を求める指針案を策定した。病院や研究機関に外部委員が半数以上を占める「倫理審査委員会」を設置し、「情報管理担当者」を配置すること等が定められているが、厚生省の補助金を受けない一般の研究は適用の対象外とされている。科学技術会議や学術審議会も、ゲノム研究推進のための基本的な原則案を策定中である。
1996年にイギリスでクローン羊「ドリー」が誕生し、その後、牛や豚についてもクローン動物の作成が成功した。これらは、均質な医学実験用動物や肉質・乳量に優れた畜産動物の大量育種に道を開き、また遺伝子組換え技術と結合してヒトの特殊な遺伝子を組み込んだ動物からクローンを作成することによって、拒絶反応のない移植用臓器・組織や優良な医薬品の提供動物を効率よく量産することを可能にする半面、クローン技術のヒトヘの応用にどう歯止めをかけるのか、新しい「生命倫理」と「法による規制」の問題を一挙にクローズアップすることになった。
クローン人間の作製(成体体細胞由来核の除核未受精卵への移植による人のクローン個体の産生)は、特定の遺伝的形質をもつ人を、受精(その「神秘的偶然」)によることなく、人工的(意図的・選択的)に多数産み出すことを可能にする。この点、それは体外受精等の既存の先端的な生殖医療技術とは決定的に本質を異にしている。一個の精子と一個の卵子が偶然に等しい確率で組み合わさり、染色体(遺伝情報)が組換えられて唯一無二の「かけがえのない個人」が誕生するといった、「人間の尊厳」の基礎がそこにはない。特定の目的のために特定の性質をもった人を人工的に作製するという、人間の手段化・道具化、「人間の尊厳」の侵害がそこにある。クローン技術は人間に好都合な「優良品種」の家畜を効率よく量産する「動物工場」を目指して開発されたが、「人間の尊厳」は多様な個性の存在と交流を前提としているから、クローン人間の作製にはなじまない。少なくとも、それは、現在の人類諸社会を律している基本的な倫理性、その背後にある社会的合意に反した科学技術である。そのほか、クローン技術は、産まれてくるヒトの安全性の点で不安があり、環境の変化に弱い社会集団を作り出す恐れもある。社会的な偏見から人権の侵害が生じる可能性も少なくない。
1997年5月にWHOはクローン技術の人間への応用を容認しない旨の決議を採択し、同年11月にはユネスコもクローン人間づくりを「人間の尊厳に反する行為」と宣言した。主要な西欧諸国では従来から生殖医療関連の国内法で人の胚の取扱が規制されており、クローン人間作製が禁止対象に含まれることが確認されていた。欧州評議会や米国政府も禁止の立場を表明した。日本では、まず1997年3月に人のクローンに関する研究については当面政府資金の配分を差し控える措置がとられ、引き続き、科学技術会議を中心に審議が進められた。同会議は、クローン人間の産生については、「人為的な手段により特定の遺伝的性質を持つヒト個体を選択的に産み出し、人間としての人格を作り出そうとする点で人間の尊厳にかかわる種々の倫理的問題を内包している」ことを指摘して、「これを実施しないこととすべきである」と結論し、さらに、常設の生命倫理委員会を設置して人文・社会的な観点も含めて幅広く検討した結果、昨年末(1999年12月)にこれを法律で禁じる方向で見解をとりまとめた。
これを受けて政府が作成した「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案」によると、人クローン胚、つまり、特定の人と同一の遺伝子構造をもつ胚(胎児の始まりの状態)を人の胎内(子宮)に移植することは、その他の特定胚を動物または人の母胎に移植することとともに、法律で禁止(罰則つき)される。人胚性幹細胞(ES細胞)からの個体産生等も、法律に基づく指針により禁止される予定である。また人クローン胚を取り扱う研究で胚を胎内に移植しないものについては「医療の向上に貢献する可能性がある」ので容認されるが、事前の届出など、指針によって厳格に規制されることになる。
「これは、科学の基礎研究に、部分的ではあれ、倫理の観点から国が立ち入ることを制度化するものだ。『研究の自由』と『研究者の自治』を重んじてきた科学の伝統が変わる節目と見ることもできよう。」大新聞の社説はこのように論じて、この「法による研究規制」が「科学と社会との関係を築き直す大事な一歩である」と結んでいる。たしかに、学術は研究者の「知りたい」という純粋な動機を原動力として、自然や社会の未知の事実や原理・法則を明らかにしてきた。知識の正誤は同僚の研究者によってのみ判定され、権力や一般社会に左右されるべきものではない、という「固有自治」の伝統が、色は褪せながらも、近年まで、専門集団のなかに閉ざされた研究活動を支えてきた。しかし、学術、とりわけ科学技術の社会的影響力が未曾有に拡大し、核兵器から遺伝子工学まで、人類に対するその脅威も「すでに科学者が責任を負いうる範囲をはるかに超えて」いる。こうした事態への有効な対処を「もはや科学自身の自己変革にまつ余裕はない」という切迫した状況のなかで、「固有自治」への素朴な思い入れは曲がり角に立っている。(もっとも、現在のアメリカでは、クローン人間は本当に作れるのか、作ってみたい、という「純粋な」動機で「研究の自由」を主張する声が少なくないといわれている。「企業化」動機のカモフラージュでないとすれば、純粋「固有自治」論も簡単に消え失せたとはいいがたい。)社会から負託され社会に説明責任を負う「負託自治」の理念に立ち、市民社会に開かれた学術の観点から科学技術の独走をコントロールするために、-研究者自身が倫理的・社会的責任を自覚して厳しい自主規制を課しつつ研究することは勿論であるが-研究者は積極的に市民と協力して適切な外的規制を定めたり、時により場合によっては一定の「法による規制」を求めたり受け入れたりすることも必要になっている。人間の尊厳や安全性の問題など、社会に対する「負の効果」が予測される場合には、適切な社会的規制は「学問の自由」に対する「不当な制限」とはいいえない。
今回の法案では、体細胞クローンよりも実現性が高いといわれる受精卵クローン技術の取り扱い等は先送りされている。また、対外受精や着床前診断など既存の生殖技術全般について、人間の手が、どのような根拠で、どこまで介入できるのか、多くの人々が納得する包括的・整合的なルールを作ることも、残された課題である。生命科学技術をはじめとして、21世紀に確実に訪れる科学技術のいっそう急速な発展に備えて、適正なルール作りを念頭に議論すべき倫理的・社会的問題も少なくない。社会の変化と学術や科学技術の発達に対応して、公的・自主的な諸規制とその運用の不断の見直しを行なうことも必要である。日本学術会議は、こうした課題について社会的合意の形成に積極的な役割を果すために、適切な組織の在り方を検討し、常時、情報の収集・分析と審議・研究を積み重ねていくべきであろう。このような体制を整備して、一方で、人間の尊厳を犠牲にして科学の成果が邪悪な野望の達成や貧欲な営利追求の手段とされる場合には、適切な規制のあり方を提言してこれを防ぎ、同時に、硬直した過剰な法的規制が周辺領域の基礎研究を畏縮させ科学の健全な進歩を妨げることのないよう柔軟で細心な配慮をすることが、日本学術会議の取り組むべき一つの課題である。
2-4 行動規範の学術的根拠-科学と実践との連関について-
2-4-1 事実認識と価値判断
学際的な「俯瞰型」研究組織を編成し、「負の効果」を予防しつつ、政策批判・政策提言を含む課題解決型の研究成果を社会に還元し、人々に「行動規範の根拠」を提供する。-このことが学術の現代的な使命の核心に位置づけられている点は、日本学術会議の第17期活動計画のなかでも特別に注目すべきことの一つである。そこには、科学と実践、学問と政治、学術と倫理、事実認識と価値判断など、多くの重要な問題が絡んでいる。
「行動規範」とは実現されるべき価値理念であり、人々の行動の「当為」すなわち「為すべきこと」であるから、「行動規範」そのものを学問なり科学者が一方的に決定し指示・命令することは妥当でない。そうではなく、「行動規範の根拠」を提供するのである。ある人々は宗教とか政治的な信条を根拠にして行動規範を選択する。だから、学術は行動規範の「一つの根拠」となりうるというのである。この点、「活動計画」には「行動規範そのものを提供するのでなく、人々が自らの責任において行動するために必要な学術的根拠を提供する」と、明瞭に説明されている。(総会で採択された声明「日本学術会議の自己改革について」では「社会に対して行動規範を提供する」となっている。)-具体的には、現代社会で生起する複雑かつ多面的な問題を予見し探知し解明して、「人々が行動規範を構成するときに有効な情報を提供する」のであり、そのさい、できるだけ「可能なシナリオのオプションを提示」する、つまり「選択しうる複数の道を示し、しかもその各々について予想されるメリットとリスクを提示する」ことが望ましい、というのである。
事実、後段で引用するが、近年、国際シンポジューム等では、その成果を環境対策の策定に役立てることも重要だが、むしろ研究が人々の「価値観に働きかけ」、人々がライフスタイルを再考する一つの根拠になることの方が、「もっと重要な」意義がある、と、啓蒙の役割を強調するケースが増えている。
ところで、すでにもう一世紀も前に、社会学者マックス・ヴェーバーは、このこと、つまり「各自その究極の理想とするところから自分の立場をきめる上の拠り所(Punkt)を発見しうるようにする」ことこそ、学問がなしうる実践への積極的な寄与であると考えてその意義を強調し、科学と実践との区別と連関を多面的に深く省察した。ヴェーバーのいう《Wertfreiheit》(「価値自由」)を「没価値」と誤認し(Pseudo-wertfreiheit!)、そこに「学問の完全な技術化」、「象牙の塔」(講壇)への遁走をみようとする俗説は、いまでは余り聞かれなくなったが、ヴェーバーの学問論、とりわけ科学認識論や政策論的思惟の革新性が、いま、あらためて見直されてよいであろう。「固有自治」を「負託自治」へと突き抜ける現代性や、個別学問領域での認識の成果とそれを俯瞰的構図へと立ち上げる手法なども、ヴェーバーの所論から読み取ることができるように思われる。
2-4-2 政策論的思惟の学術的「客観性」
ヴェーバーは、科学的認識が価値理念や価値判断をもった学問主体の営為であり、事実認識の背後にはすでにその事実を選択した価値意識が働いていることを指摘して、「没価値」、つまり価値判断「排除」(Ausscheidung)の立場を否定する。そして、それだからこそ、科学的認識と実践的価値判断との混同を戒め、両者を「区別」(Scheidung)したうえで、その関係を自覚しつつ統御する「価値自由」な方法的態度を要請した。
実践的規範の妥当性と科学的認識の妥当性とは「問題の次元を絶対的に異にする」ものであって、政治と学術を不用意に、また意図的に混同するのは許されない。しかし、学者も政治家も、知的誠実さで両者の統合に努めること、問題意識(実践的関心)をもち、責任倫理の立場で科学的合理性を尊重すべきことに関しては、立場や職業の違いがあり関心や重点の置き所は異なっても、相互に大きい相違はない。学者が「精神のない専門人」として、目的の意味を問わずにひたすら技術的コメントに終始したり、決断すべき政治家が科学的洞察をもたず、ただ政治的心情で行為することは、知的誠実に欠けている。
ところで、現実は無限に多様である。また、すでに述べたように、科学的認識は、一定の価値前提に立って「知るに値する」、その意味で「本質的」なものを対象として整叙する、「価値関係的」な選択的再構成の行為である。それは「有限な人間精神による無限な現実の思惟的認識」であって、「特殊な『一面的』観点から離れては、文化生活・『社会現象』の『客観的』科学的認識はありえない。」
こうした、個々の「認識の一面性・相対性」の承認を出発点として、多様な現実を多元的・立体的な現実像として構成する複眼的な思考法(その可能性)が開けてくる。
政策的実践においては、行為の意味と結果ができるだけ正確に把握され決断されなければならないであろう。現実の社会は多数の諸原因や多様な諸条件が複合的に作用する「協働」(Zusammenwirken)の場なのだから、意図と結果が乖離し、同一の行為が異なる結果をもたらすことも稀ではない。「悪魔は歳をとっている。」「無知もまた罪」-行為者は可能な限り明確な見透しをつけ、決断し、行為の結果に責任を負う義務をもっている。
科学は実践的行為の意味と結果を解明し、学術の立場から、行動規範の「拠り所」となる情報や評価を提供する義務を負っている。この場合、ヴェーバーによれば、科学が科学として為しうること、為すべきことは、以下のとおりである。
①《「技術的批判」》:与えられた目的に対する手段の適合性(目的合理性・内的整合性)の吟味。そのためには、可能的因果連関の分析が必要である。近代科学は本質的に技術論的性格をもち、「目的の自明性」の仮象を前提として成立しているが、しかし、技術的批判には限界があり、科学、さしあたり社会科学的・社会政策的認識にとって、為しうること、為すべきことはこれに限られている訳ではない。
②《「価値解釈」》
a.《価値理念の開示》:特定の目的の根底にある価値理念を開示し、「価値関係」の内容を解明して(価値合理性の検証、意味連関の分析)、人が前提している価値基準を意識させ、意欲し選択する行為の意味を理解させる。
b.《可能的価値関係の分析》:「与えられた現象に対して可能かつ有意味な諸々の立場」-選択しうる客観的可能性-について価値解釈を展開し、人が広く他の視野と比較・融合する地平に立ち、その価値前提を自省するための情報を提供する。
この場合、価値解釈は価値判断ではなく、価値自由な対象の評価であり、自己の価値判断を抑えて「立場を交代する」能力を前提する。この想像上の観点移動という価値解釈の方法的態度が、複雑な現実を俯瞰的に把握する際には必要である。
c.《価値理念の学術的評価》:価値自由の要請を忘却しない限り、積極的な、価値判断や理想の科学的批判・批判的評価も有用で避け難い義務である。
ヴェーバーは、およそ以上のように科学と実践、学術的認識と価値判断の区別と関連を考察した。そうした脈絡で、学術は各人が自己の「立場をきめる上での拠り所」(「行動規範の根拠」)となりうることを論証した。それは「一つの真理認識」で、価値判断ではない。しかし、それを越えて「拘束的な規範や理想を発見し、それから実践に対する処方箋を導き出すということは、断じて経験科学の課題ではありえない。」善い悪いの判断は科学的論理からは出てこない。「知性のなしうる最後の仕事」は人々を「世界観の前にまで導いていくこと」なのである。
-ヴェーバーが論陣を張った19世紀末から20世紀初頭のドイツでは、大学を取り巻く権力構造が変化し、従来支配したプロイセンの国家官僚に加えて、議会・諸政党・諸団体が台頭して、「大学の自治」(「固有自治」)は様々な諸利害、価値観が対立する「神々の闘争」のなかで翻弄されていた。激流のなかでヴェーバーは、自己の価値理念を放棄して「近代科学の技術的性格」を隠れ家とする「没価値」の立場に遁走するのでなく、自己の価値理念をもつ「自立した個」としての学問主体として、「価値自由」の立場で、政治と科学を混同し学術と倫理の峻別を拒否する権力や諸党派と闘いつつ、社会科学と社会政策の認識の客観性の論理と首尾一貫する形で「行動規範の根拠」を人々に提供する、開かれた「負託自治」の科学論的な裏付けを探究していたように思われる。そうした学術と社会の関係の近代化・現代化の時代的状況と重ねるとき、彼の所説の「革新性」(現代的意味)が理解されるのではあるまいか。
第3章 学術と社会
3-1 新しい科学論の挑戦-「モード2の科学」と「政策過程研究」-
3-1-1 「負託自治」と「俯瞰型」研究様式構築の課題
現在、学術は「象牙の塔」のなかで伝統的な「固有自治」に閉じこもるのではなく、社会の負託に応える「負託自治」の立場で現実の諸課題の解明に取り組み、研究成果を社会に還元して人々に「行動規範の根拠」を提供するなど、「開いた学術」であることを求められている。そのためには、研究者は専門化・細分化した学問領域の枠組を超えて、複雑な現代社会の問題群に対応して関係諸領域間の共同研究体制を組織するなど、「学術全体を俯瞰的に見る視点」を重視することが必要になっている。
学術は、本来、領域化を求め、領域内での組織だった理論的体系の構築を求める本質をもっている。個々の実用的な問題の解決にとって、領域化された、それゆえに整合的な科学的知見が有効な場合も少なくない。しかし、現実は多くの場合、多元的・複合的な構造をもっている。しかも、個別的な領域からみて「合理的」な「解決」は、しばしば領域外との関連で重大な「副作用」を引き起こす。たとえば、経済成長・経済効率一本槍の「正確な」処方箋は「正確に」環境破壊や資源・エネルギー問題を引き起こし「持続的発展」の基盤を掘り崩す。だから、「単一の領域は、現実的に有効性を持つ殆どの行動規範の成立にとって、十分な知識を提供するものではない。」(吉川弘之)「この世界は、意味を失うことなくしては部分に還元できないようなシステムで満ちあふれている。」(C.ハムデン-ターナー=A.トロンペナールス)
情報革命や環境、生命問題など地球規模での課題の噴出に対応して、研究・教育機関は「知の組み替え」に迫られ、創造的な「課題探究能力」を備えた「専門性に立つ新しい教養人」の育成を求められている。はたして「知の組み替え」はできるのか。専門化が進みタコツボ化した学問をどう総合化していくのか。「複雑性の科学」をはじめ、「比較制度論」「プログラム科学」「綜合科学」など、新しい科学論の挑戦は、それぞれに「組み替え」の方法や枠組を示唆している。しかし、不均等に発展する学術諸領域間の交流・統合を促し、学術全体を俯瞰して問題の本質を洞察しようとする体系的な方法は未開発といってよい。学際的な交流・協力に対しては抵抗する社会的・心理的な障壁も少なくない。「ディシプリンの文化」は認識論的というより社会的・組織的に作られ維持されているという指摘も存在する(トニー・ベッカー『学問的部族とその領土』)。そうした障壁を調査・研究し、学際化・超領域化を刺激する適切な戦略を構築することも課題である。自然科学と人文・社会科学の両方の核心をつかむプログラムを策定しえたときにのみ、真の学際化・総合化への前進は可能となる。
また、研究の成果を社会に還元し人々の行動規範や政府の政策形成に有効な影響を与えるには、異なった価値観や利害関係が絡み合う状況のなかで意識やライフスタイルを変革し利害を調整して政策への社会的合意を形成する仕組み(「合意形成」の社会装置)や、科学技術アドヴァイザーの制度や技術マネージメントの手法を動員して研究開発の成果を埋もれずに社会で生かせる仕組み(「技術移転」の社会装置)など、社会エンジニアリング的な装置研究も必要になってくる。科学、技術、社会の境界面を構造的に解明する新しい科学技術社会学(SRS[Science,
Technology & Society])の動向も期待される。理論を行動へと架橋する動因と構造はどうなのか。「理論と行動との関係の科学的解明は、各学問領域における固有の対象の解明に匹敵する重さを」もつ課題である(「会長就任あいさつ」)。人類の破滅があるとすれば、それは技術開発能力の限界でなく合意形成能力の限界によることは間違いない。
いずれにせよ、新しい諸研究はいずれも発展途上であり、期待されるべき今後の課題である。俯瞰型プロジェクト研究といっても、当面、新しい科学方法論や装置論的研究を下敷きにした「理論的」(method-oriented)な挑戦というよりは、課題解決型の「実践的」(program-oriented)な経験の積み重ねとして展開されるほかはない。そのことを前提としたうえで-またそうした試行錯誤的な「経験の積み重ね」にさいしてホイリスティシュな有効性をもつという意味で-以下、簡単に「モード2の科学」と「政策過程研究」に言及する。前者は、現代社会が直面する諸矛盾・諸問題の解決にむけて、複数の諸要因・諸条件が同時に存在し影響しあう現実を総合的に解明する新しい研究様式の試みであり、後者は、政策形成への社会的合意の諸過程を体系的に提示しようとする研究である。
3-1-2 モード2の科学
「モード2」の科学とは、旧来の科学が一般に専門領域(ディシプリン)のなかに閉ざされた知的生産の様式(「モード1」)であるのに対して、現在の多元的・複合的な難問と取り組むために必要な、課題解決的で超領域的(トランスディシプリナリ)な新しい、開かれた知的生産の様式を表現するために、マイケル・ギボンズその他(『現代社会と知の創造』)が提唱したコンセプトである。従来の学術では、個別領域内の論理や関心で研究テーマが決定され、研究成果も同僚の専門研究者によって評価され共有されて、一般社会に届くことは少なかった。これに対して、モード2の場合には、複数の領域の研究者が緊密に連携し、必要に応じて産業界や政府の専門家、「注意深い」市民等の参加を得て、環境問題、都市問題等、公共性の高い課題を対象に短期凝集的な共同研究を実施する。研究者は社会に対して説明責任を負い、情報を公開し成果や危険を説明して評価を受ける義務をもつ。科学技術の社会に対する影響が大きくなり、研究の倫理性や安全性の評価も重要になって、同僚評価(ピアレビュー)が評価を独占することはできなくなっている。
「モード2」は必ずしも「新しいトランスディシプリナリなディシプリン」の確立を目指すものではない。むしろ共同研究は「本質的に一時的な結集」であり、研究者は比較的短期間、「本籍」(モード1)を離れて-といっても多くの場合インターネット等を活用する分散型の研究スタイルが採用できるから、研究者の空間的な結集が構想されている訳ではない-テーマ凝集的に共同研究に専念し、終了後一般には本来の個別領域に復帰するものと想定されている。二つの研究様式は併存するものと考えられているのである。しかし、研究者が「副業」でなく一時的にせよ当面のテーマに専念する点は、通常の「学際的研究」と異なっている。
「モード2」に近い研究の様式は、昨今、かなり見受けられるようになっている。『科学技術白書』(1998年度版)も、地球的・人類的課題の解決に向けて科学技術の研究が、次の4点を柱にその在り方を見直すように呼び掛けている。総合的視点で「見つめる」、適切な目標を設定し変革につながる成果を「生み出す」、研究成果を社会に「生かす」、研究を厳正に「評価する」、の諸点である。
3-1-3 政策過程研究
「政策過程研究」は政治学を中心に近年活発に研究されている分野である。社会人大学院の政策科学カリキュラムの中核に位置づけられているケースもある(付属資料、武藤博己論文、参照)。政策とは市民社会が問題を解決するための手法(作業仮説)であり、政策過程研究は政策が形成され実施されるプロセス(作業仮説の設計の手順)を、問題の発見(市民社会にとっての問題の緊急性・重大性、社会のニーズとは何か)、公共的問題の選択(市場に委ねるべきか行政の問題か)、問題解決手法の考察(その問題をどこまで、どのように解決しようとするのか、科学的・客観的な検討に基づいて、できるだけ複数の選択肢を提示する)、組織内調整(法的根拠、財源、人員等)、決定=合意形成の社会過程(議会の代表性と行政の透明性、審議会や市民参加、住民投票など)、執行(政府直営か特殊法人、民間企業、第三セクター、町内会、市民クループ等に委ねるか)、評価(多様な評価基準、「時のアセス」)、フィードバック(計画の再検討)など、いくつかの段階を追って検討する。
もちろん、政策過程の在り方は、工業化、都市化、市民化、分権化、透明化、効率化、規制緩和、環境問題、グローバル化、少子化・高齢化、男女共同参画社会、NGO・NPOなど、政策環境の歴史的変化によって変化するし、「日本型」合意形成が問題になるように、国や地域によっても異なっている。そうした歴史的・地域的背景をふまえて政策過程研究を具体化することによって、有効な政策管理が可能となる。かつて(1977年)国際協力開発機構(OECD)では、日本を対象に「政策決定過程において、社会科学の成果とその思考方法がどのように利用されているか」を調査したことがある。調査結果(『日本の社会科学政策』)には、「日本の大学は伝統的に学部、学科、講座という組織形態を有している。この制度は、固定的で柔軟性に欠けがちである。各種専門分野の研究協力を妨げがちであり、『目的指向型』の研究計画の要請には、なかなか対処しにくい。」「学際的な研究やプロジェクト型の研究はあまり実施されていない。」「研究成果に対する評価の方式が確立していない。」「社会科学の開発と利用を振興しようとする政府の努力は自然科学の場合ほど成功していない。」「政策決定過程において審議会の占める実際上の影響力、あるいは審議会がどの程度実際に社会科学を利用しているかについては、かなり意見が分かれている。」「行政官の決定を承認するだけのもの」だったり「官僚機構内部の実態を公衆から隠蔽し」「外部からの批判に対する防壁を作るための手段として使われ得るとの見方もある。」等の指摘がなされている。これらの問題点は、今日、果たして、どこまで、またどのように克服されたのか。
学術の立場から的確に社会に訴え有効に政策批判や政策提言を行うには、どのような配慮とプロセスが必要か、そもそも政策形成過程に学術はどこまで関わるのか-そうした論点に政策過程研究は多くの光りを与えている。また、社会人大学院における政策科学の教育は、学術研究の成果を実務(行政実務を含む)に生かす変換技術を身につけた社会人の養成を主眼する。研究成果に関心のある実務家と研究成果を社会に還元しようとする研究者との協働こそ、「俯瞰型研究プロジェクト」を「行動規範の根拠」の提供や「政策形成プロセス」へとスムースに架橋する重要な条件であるが、政策科学の教育はそのために必要な人的基盤を形成するものと期待される。
3-2 学術の在り方、社会の在り方-現場からの教訓-
3-2-1 現場での経験、経験からの教訓
新しい科学論や政策過程分析は、問題発見的な有効性を有している。しかし、それらは概して未確立である。俯瞰型研究プロジェクトは、学術と社会の境界面で様々な課題と取り組む現場での経験を積み重ね、現場からの教訓に学びながら、構築されるほかはない。
学術の社会的貢献に関して、本特別委員会では各委員が分担して学問領域別の事例報告(領域固有の問題に関する報告のほか、複数の領域の協力を必要とする問題についての主管的領域からの報告を含む)を執筆し、付属資料として本報告書に添付した。執筆に際しては、共通の了解として、学術と社会との新しい関係の構築について、できるだけ具体的なケース・スタディを折り込み、研究の現場や社会との接点での経験を通じて、「学術」の側での反省と自己理解を深めるとともに、「社会」の側の問題点も指摘して理解を求めること、その際とくに「俯瞰型研究」の必要と「行動規範の根拠」をめぐる問題にも現場の経験をふまえた教訓として言及することを目標とした。詳細は付属資料にゆずり、ここでは、その一端を紹介し、委員宛に実施したアンケートや委員会での議論のほか、著書、論文、調査やシンポジュームの報告書、新聞の記事やコラムなどからの補充を加えて、学術の在り方、社会の在り方について「現場の経験」「経験からの教訓」を例示しておきたい。(付属資料やアンケート、新聞等からの引用については、出典を省略する。)
3-2-2 学術の在り方
○研究の目的(その哲学的・思想的基礎)を自覚し反芻する必要がある。(地球的課題の予測と解決策の模索に有効として多用されるコンピューターによるシミュレーション分析なども、反面、没人間的な数字的遊戯となり、「正確に間違う」危険をもつ。)
○「科学・技術とは一体何であり、人間が生きるとは一体何であるのか。」「現代の学術や科学技術が十分に答えず、しかし現代人の多くがたえず気にかけ問わずにはおれないような根本問題を、率直に提起すべきである。現代の学術の学際性や総合性を強調する議論を繰り返してもあまり意味がない。現代の根本問題群を明示することが『学術の社会的役割』を提示することになる。」
○「純正研究とは問題の本質、すなわち自然界や社会の諸現象、人間社会の諸問題の本質を見極めようとする、研究者の押えようのない欲求から出て来るものだ。…本質とは何か?…自然科学は、そしておそらく学術全体も、一つの地下水脈でつながっており、それが究極の本質だという感じしか私には書けない。…私の専門の生物物理学での経験でいえば、生物の本質を極めようとして自然科学全体を眺めると物理の本質が見えて来る(ような気がする)し、その逆もまた真だからだ。…俯瞰的視点は、一見多様な地表によって覆い隠されている普遍原理つまり本質を、高いところから見透す視点である。…科学技術全体を俯瞰する哲学的洞察なしに行うと学問が退廃する」(和田昭允)
○「美学は…社会との接点のもっとも少ない学問といえるかもしれないが、根源的な感性論としての観点から、環境の問題にたいして、ある新しい視点を提供する可能性はもつと考える。なぜなら、その原点における環境とは、感性的に把握された個にとっての外界にほかならず、現代における環境の悪化の原因として…感性の衰退、とくに想像力の貧困化があると思われるからである。」
O「分析的な社会科学では、人間を全体像においてではなく、分析目的に適合した一定の視角から考察する…結果、…人間の個人的、社会的な行動を的確に説明し、予測することが困難になる。…経済学では、人々の行動規範は効用(utility)という概念で表される。第一次接近として、各人の効用は自己の消費のみに依存すると仮定されることが多いが、…過度の単純化である。…現代の経済学は[プレゼント、ボランティア活動、リーダーシップ活動のような]他者関連的な経済活動に対して十分な注意を払っているとは言えない。個人の効用関数を拡張することにより、従来経済学ではきわめて不十分にしか取り扱われてこなかった人間的、したがって学際的な問題を経済学的分析の対象として考察することが可能になる。」
○環境問題、環境意識、環境行動、環境文化の社会学的研究を課題とする「環境社会学」の分野では、たとえば、むつ小川原開発計画と核燃料サイクル施設建設をめぐる社会的諸問題を地域格差、地域開発、原子力政策、政策決定と民主主義、巨額不良債権、女性の環境行動等の問題群について「検討」し「教訓を整理」した調査研究(船橋晴俊ほか編『巨大地域開発の構想と帰結』)など、プロジェクト研究の経験が重ねられている。
○西洋先進国の最盛期の経験をモデルにした従来の経済学や学問領域構造では、自然も文化も異なるアジアや途上国の社会経済現象は分からない。従来の社会科学を超える「一般理論」(大塚久雄)の形成、「真に汎用的な学問」(吉川弘之)への改変が課題である。とくに、アジアに位置して欧米の学術、科学技術を需要・変容した「日本人の眼」が、新しい方法的枠組を構築するうえで大きな役割を果せるはずである。「経済大国と談合的文化」の複合連関や、談合・派閥・人脈、過当競争と独占癖、身内と余所者、それらをすべて背後で繋り合う事象としてシステマティックにつかみうる方法的枠組を開発しない限りは、経済現象と文化現象、経済摩擦と文化摩擦を理論的に接合し、複雑な世界の現実に学術の立場から実践的に対処することはでき難い。かつてミュルダールは共同プロジェクト「黒人問題の総合的研究」を主宰し、また『アジアのドラマ』全3巻を上梓して、現場での経験、現場からの教訓を俯瞰型の学術的に結晶させている。
○問題を予見する意志と能力、人々の-隠れた-期待を受信する装置の欠如。社会のニーズをどう掘り起こすか。利害関係者の声は大きいが、声なき市民の声は届かない。
○「認識の一面性」の自覚と「専門の壁を破る」ことの難かしさ。柔軟で開いた研究体制を構築する難しさ。「ジャンルを超える」ことは何事についても難しいが、とくに「効率性」「収益性」といった一応共通した明確な目標をもつ私企業の新製品開発プロジェクトと異なり、公共性の高い応用課題・政策課題の場合には、観点や専門を異にする研究者や異なった立場の人々が共同研究を組織することは、意外に困難な作業である。
○「本籍」(講座の専門)を離れて研究課題を変更する自由や、短期凝集的に「本業」以外のテーマに専念できるサバティカル的な制度が十分に保証されていない。
○戦前・戦中の前市民社会型「国家の大学」のヒストリシス(履歴記憶)から、大学の社会的「奉仕」機能や「負託自治」の受容には消極的な意見も少なくない。
○未開拓な課題への研究費の確保など、プロジェクトの支援制度が確立していない。とくに、萌芽的な研究課題について、研究計画の学問的意義や社会的意義を立案段階で判断する公正で透明な事前評価の制度と人材が、常に保障されているとは限らない。
○研究成果の事後評価についても同じである。社会への説明責任を果たすには、「自分で自分の脈拍を診る」自己点検・評価を表面的・形式的な時流・奔流に終らせることなく日本の学術文化に定着させること、研究成果と波及効果について、ピアレビューにせよ第三者評価にせよ、学際的・超領域的課題について内容的に評価できる制度を整備し適材を養成することが、なお今後の課題である。
○研究成果を社会に伝達する有効で迅速な装置を整備し活用することが必要である。公開シンポジュームや広報活動を充実して、研究の結果を積極的に社会に発信し、啓蒙し、批判を仰ぐ努力がいる。
○「報道陣をして死に至らしめたのは、火砕流という自然現象についての無知(情報の欠如)であった。」「物理的な被害の割には、住民の心に残された傷は大きかった。これらは社会心理学の領域であり、また防災行政のシステムの問題である。理学研究者として、この事件に対する反省は、専門家だけが持っていた正しく有用な情報を、非専門家に有効に、時機を失せずに伝達できなかったということである。」
○「理学系研究者の多くがおそれるのは、情報がマスコミに漏れて、根拠のないセンセーショナルな報道をされることである。過去に幾度となく痛い目に遭ってきた火山研究者は、したがって『あいまい情報』[天気予報ほど精度や確度が高くないが、災害対策の策定などには十分役に立つ情報]を積極的には公表せず、結果的には隠してしまう傾向が身についている。」
○「学術に不信なのではなくて、学術の伝達に問題があったのではないか。判断の前提を語らずに『絶対安全』『ありえない』を連発しすぎ不信が蓄積した。公開する情報量が少なすぎた。公開した情報が理解されていなかった。…分かりやすく、かみくだく情報加工が重要。…情報加工技術/社会への情報の伝達のプロが要る。社会の疑問・不安に答える地域の『開業医』(Geodoctor)が要る。」
○「現状の科学技術では[有害化学物質の]リスクアセスメントには大きな不確実性が含まれ、得られたリスクの値にある種の不信があるのも事実である。…発がんを引き起こす危険率がどの程度ならば、国民が許容できるかは、自然科学の問題ではなく、政策的判断、ひいては国民の判断の問題である。環境保健学は国民へのリスク情報の提供にあたり、従来みられた一方通行的な『リスクメッセージ』ではなく、情報発信者(行政、企業、専門家など)と受診者(市民など)との相互理解を深め、相互の情報交換『リスクコミュニケーション』による協調関係の構築に大きく寄与せねばならない。」
○「原子力発電は、多くの専門分野の『工学』を集合した総合的な『システム技術』で構成されている…ばかりでなく、人文科学、社会科学からの研究・評価が不可欠な人工物でもある。…工学的安全性は保たれているが、社会的に一般の人々が安心感を得ているかというと、必ずしもそうではない。…世論調査によれば、必要性(80%)は認めるものの、安全性については30%の回答しか得られていない。…原因の一つとして、原子力発電に関する情報が当事者と国民の間に正しく伝わっておらず、特に事故発生時には当事者の対応や情報伝達が遅く、一方において隠し事があったり、事実と異なった誇張や誤報もあり、国民側の不信感につながっていることもあげられている。原子力発電は現在電力供給の40%近くを占め、社会的に大きな存在となっているので、原子力発電の安全性が社会へもたらす影響は極めて大きい。したがって、国・事業者は原子力発電に対する社会心理の動向を十分理解して対応し、社会的に安心感が得られるようにする事が重要である。同時に、このための社会科学的な研究・学術が必要である。」
○「核兵器の出現とともに始まった科学者の運動の最大の意義は、科学者の役割は真理の探究であり、その成果がどのように利用されようとそれは政治の問題であって、科学者が責任をもつべきことではない、とする考えを否定し、『科学者の社会的責任』の問題を提起したことであった。…近年の遺伝子工学の進歩は人間の存在を内側から危うくしている。ここでも、遺伝子操作技術という、まさに自然を作り変える研究がその根元にある。…核兵器から遺伝子工学まで、それが人類にもたらす脅威はすでに科学者が責任を負いうる範囲をはるかに超えている。もはや科学自身の自己変革にまつ余裕はない。まず、科学は市民社会に対して開かれなければならない。そして、科学者と市民の協力により、両者の合意に基づくなんらかの外的な規制が定められる必要がある。」
3-2-3 社会の在り方
○「知性の時代」「科学の時代」という反面、「[市民的]価値への不信」「科学離れ」も進んでいる。「社会に科学情報を理解する下地がなさすぎる場面にも、しばしば遭遇する。」「科学する心の軽視は際立っており、理学の基礎研究者も動員して啓発運動を行なうことともに、教育システムの抜本的見直しが必要だろう。」
○「先端研究と一般の人の認識の間にあるギャップが気になりますね。うちの母親あたりは、遺伝子組換え食品を食べたら、自分の遺伝子が組換っちゃうと思っている。」
○「組換え作物食品の『安全性』が全面的に『社会に許容される』までには時間が必要であろう。」「『予防原則』という考え方が欧州を中心に提唱され、遺伝子組換え食品の規制などで実際に適用され始めている。これは『規制はもっと科学的データが集まってから』といっていると、取り返しがつかない重大な害が起こるかもしれないので、とりあえず予防的に規制しようという考え方だ。」
○「『花粉症の原因は花粉である』と単純に思っている人が多い。…80年代から、花粉症の一因はディーゼル排ガスの微粒子であることが、ほぼわかっていた。その時点で、ディーゼル排ガスの厳しい規制を始めることはできたはずだ。このように科学的には早くから原因が明らかになっていたのに、国の対応の遅れや報道の不十分さなどから、患者数が増えてしまった例は、水俣病や薬害エイズをはじめ数多い。専門家や国、マスコミの責任は重大である。」
○生活の快適さは求めても、価値観やライフスタイルの転換を求める学術の警鐘は社会に届かない。「分かっちゃいるけど止められない」という社会的風潮の中で研究が社会の行動規範に働きかけるにはそれなりの工夫が要る。科学の知識は、必ずしも行為への十分な実践的起動力とはなり難い。学術のアドバイスがなぜ社会に無視されるのか。その人間行動の分析と実践への多面的な装置研究が期待される。
○「稀少動植物を保護するのか、有効活用するのか。[ワシントン条約締結国]会議は具体的な方向を打ち出せなかった。…政治的な駆引を条約会議の場からどう排除するか。科学的で冷静な議論と話合いによる合意を重視する事務局が今回、頭を悩ませた点だ。国際捕鯨委員会(IWC)が政治的駆引の場になり、科学的な議論ができなくなっている、とクジラ問題をこの会議に持ち込んだのは日本だった。…異なる利害をいかに調整していくのか、という大きな課題が残った。」
○低開発社会やヴェンチャー企業への技術移転の障害は、技術(その研究開発)そのものよりも、受け入れる社会の側での技術マネージメントの欠陥に依ることが多い。教育・研修の制度や内容を改革し、起業家精神をもった人材やアイディアの開発・交流を促すなど、社会的インフラの充実が急務である。
○社会とは何か。国際社会・国民国家・地域社会、政界・官界・財界、労働組合・住民団体・市民運動・NGO・NPO、世代、ジェンダー、等々。様々な「社会」との困難な意見対立と共同作業、軋轢と協調、利書調整や合意形成の努力のなかで、現場の研究者は、戸惑い、ためらい、時には身の危険も感じながら、しかも、しばしば「都合の良い所だけを」利用され、「隠れ簑」にされ、「責任を転嫁」されている。
○課題解決型の研究では、研究者の主体性を基礎としつつ、産業や行政、また市民や市民団体の協力を必要とする場面も少なくない。「産学協同」「産官学協同」「産官学市協同」の適切な在り方を検討して、社会に負託され支持される学問形成に資するとともに、他面、仮にも企業や業界の「金力」に屈し「権力」や「省益」と癒看して「産官学の利権構造」を疑われることのないよう、注意しなければならない。
○市民社会が成熟し市民一人一人の意識が向上しないと、学問の社会的役割は発揮され難い。たとえば、「個人の意思を主張し、それを尊重する習慣のなさが脳死臓器移植の議論にも存在することは日本の特徴として外国からも指摘されている。」
○法学の分野で今日〈社会の「法化」〉が議論されているのも、行政主導の「規制社会」でやってきたこれまでの日本の法的な枠組を変革し、グローバル化の21世紀に向けて、民主主義と市民社会に相応しい、規制緩和と自己責任の公正な「法化社会」を実現しようとする試みにほかならない。
-こうした現場の経験、現場の教訓に学びつつ、次章では、「学術と社会の新しい関係」を構築するための重点的な推進課題を取り上げることになる。
第4章 重点的な推進課題
4-1 「俯瞰型研究プロジェクト」の振興-課題的専門化=領域的総合化-
4-1-1 俯瞰型研究プロジェクトの理念と様式
「多数の領域を擁する学術全体を俯瞰的に見る視点の重要性」は、日本学術会議の「第17期の活動計画(申合わせ)」(1997年10月)で「活動の基本的方向」の第1にあげられている。注目したいのは、俯瞰的視点の重視が、本来、プロジェクト研究に限った問題提起ではなく、より広く、また根底的に、各学問領域の進展が「相互に独立」「不調和」であるという「学問体系の不均質性」を指摘し、俯瞰的視点に立ってこそ現在の社会に現出する「問題の本質を見究め」得るという認識に立脚して、「均衡のとれた学術の進展」に努めることを学術会議の課題とするためのものだった点である。「活動計画作成に際しての会長所感」でも、日本学術会議の長所として、科学者が「審議と研究連絡を通じて関連領域の状況を理解しつつ社会における現代的問題に対する自らの領域の責任を察知」して「領域を超えた共通の理解を」もてることと、会員の領域が「文系理系を含むすべてに亙る」ためにその共通の理解が「本質的なもの」となりうることが強調されている。そのさい、また「会員は、各専門を代表するものであるが、それは利益の代表でなく、学術全体の調和のとれた進化を担う、俯瞰的な眼と全体最適を価値とする存在でなければならぬ」と説かれている。このように、学術全体を見通す俯瞰的視点は-たとえばプロジェクト型といった-特定の研究様式に必要な眼である前に、日本学術会議の眼、会員科学者の眼なのであり、さらには専門を問わず現代のすべての研究者に求められる視点だといってもよい。そして、俯瞰的視点は、「一見多様な地表によって覆い隠されている普遍原理つまり本質を、高いところから見透す視点」(和田昭允)として重要な意味をもっている。基礎研究であれ応用研究であれ、また個別研究であれプロジェクト研究であれ、学術「全体を俯瞰する哲学的洞察」なしには、その学問は「退廃」することが力説されている。
この点を確認したうえで、「行動計画」(および「会長所感」)は、課題の解明・解決にとって個別的学問領域の役割も大きいが、問題の多くが複合的で複雑なため、単一の領域は現実的に有効な行動規範の成立にとって、ほとんどの場合、十分な知識を提供するものではないと述べ、「複数領域の科学者の協調的作業」による「共同研究協力体制」の必要を強調した。その後「俯瞰型研究プロジェクト」論として展開されるものである。
ところで、取り組むべき課題が複合的・多面的という場合、その問題を生起させ構成している要因が複雑で複合的なばかりでなく、その影響もまた多面的で複雑なことを意味している。学術研究、とりわけ領域化された科学技術は、「正の効果」をもたらして社会に「貢献」すると同時に、予期せぬ「負の効果」を生んで社会の「脅威」となることが少なくない。複数領域の研究者が協同して実施する俯瞰的な研究様式の創出は、この「負の効果」の「脅威」を未然に、また早期に感知し、危険を予防したり緩和したりするうえでも有効である。日本学術会議創立50周年記念の会長特別談話「俯瞰型研究プロジェクトの推進と総合的な科学技術政策の樹立に向けて」とその「説明(私案)」(1999年1月)では「負の効果が発現してから改めてそれを抑止したり除去しようとすると、大きな負担を生じる」ことを指摘し、「負の効果を抑止するか除去する」「一つの方法」として「俯瞰型研究プロジェクト」が構想されたと説明されている。そして、この「新たな研究の様式」は、「研究目的の設定、計画の立案、期待される効果の推定、研究の実施、中間評価、計画の修正、成果の公表、成果の効用評価などの研究の全段階を通じて」研究の効果や影響を「多面的かつ同時並行的に評価する俯瞰的な視点によって判断できるよう、その研究分野の科学者を主体としつつも、同時にその研究成果が関係する他の領域の科学者」、とくに「その研究成果によって影響を受けると予想される分野に携わる科学者をも加えて推進するプロジェクト」と定義されている。
同年「日本学術会議の自己改革について(声明)」(1999年10月)が総会で採択され、俯瞰型研究プロジェクトの推進は改革の重要な柱とされることになった。声明は「日本学術会議は、近年における個別の科学技術進歩がもたらしたプラスの面に比べて、マイナスの面への対応が必ずしも十分ではなかった」ことを反省し、「俯瞰的視点から取りまとめる科学的知見を行政や社会に提供すること」を「今後特に力点を置く」目標として掲げている。科学は人々に大きな夢を与えるが、反面、人類の福祉にマイナスの副作用をもたらす危険もある。研究者自身がこうした「負の効果」を事前に、また早い段階に察知して対処することができれば、真に持続的な「夢への挑戦」の第一歩となるであろう。本特別委員会は、日本学術会議が以上の経緯を継承して、俯瞰型研究プロジェクトの振興に今後いっそう本格的に取り組むことを期待したい。
4-1-2 俯瞰型研究プロジェクトの特徴
俯瞰型研究プロジェクトでは、参加者は問題を予見し探知して課題として構成し、これを学際的・総合的に究明して、診断の結果についての情報や選択可能な解決の処方箋を、起こりうる様々な影響、とくに「負の効果」についての評価とともに社会に迅速に提供する。先見性、構想力、総合性、即応性、そしてとくに、人々の期待、社会の要請を感受する意志と能力、「行動規範の根拠」に関わる学術の役割の自覚、そうした「負託自治」の倫理が求められている。プロジェクトは、その課題に直結する主管的領域の研究者や、多様な経路で因果的に関連する領域の研究者、「負の効果」など様々な副作用を受ける領域の研究者のほか、研究の社会的・倫理的・哲学的意義を評価できる研究者・有識者が参加して構成され、また産業や行政、あるいは市民の協力が望まれる場合もある。また、人々の期待や心配を的確に受信するために、非専門家である市民や市民団体の直接・間接の参加が必要な場面も少なくない。今日では「学際的」な共同研究は珍しいことではない。日本学術会議でも、学際的・超領域的な連関構造を包括的な視点から捉えることを重視して、地球環境、エネルギー、資源、食料、社会システム変革、生命科学・生命倫理などの諸問題を取り上げてきた。俯瞰型研究プロジェクトはその延長線上に位置している。しかし、それは単なる「学際的」研究ではなく、「新しい作業」「新しい型の共同研究」(吉川弘之)であり、「従来のアカデミズムにない全く新しい学問のスタイル」(吉田民人)であることが強調されている。その特徴(備えるべき条件)を考えてみよう。
(1)広域の俯瞰
俯瞰型研究プロジェクトは、いうまでもなく、細分化しタコツボ化した既成の学問の領域的な枠組では捉えきれない複雑な問題の全容を、複眼的・広角的な広がりで学際的・超領域的に解明することを課題とする。この点は従来の「学際的」研究様式と同じである。理論的(領域的)総合化=実践的(テーマ凝集的)専門化といってもよい。「平和研究」は戦争に直接関係するテーマを総合的に考察するほか、現在では、平和を実現するには貧困、人権、開発等の問題群の解決が必要であるとする考えから、より一層多角的な、複合領域の代表格に成長した。「地球文明の条件」に関する研究は経済問題(成長と格差)、資源・エネルギー問題、環境問題というトリレンマの同時解決を学際的な課題とする。
(2)本質の俯瞰
複雑な問題の「本質」や「意義」は、領域知では覆われて見えない深層に伏在する。俯瞰型研究プロジェクトは、個々の領域を超えた透徹した俯瞰的「哲学的」洞察によって根底的なレベルで問題の「本質」や「意義」を見透し理解することを重要な使命とする。人文・社会科学系の純粋基礎領域(哲学・歴史・人間学)を含む様々な領域の参加者が、専門領域に拠りながらも領域知を相対化する俯瞰的な観点に立つことによってプロジェクトは全体の共同作業として「本質の俯瞰」と取り組む望楼(楼外楼)を築くことができる。
地球や地域環境を破壊する力をもった人間が、危機の時代を乗り越えるため、知恵と技術を結集して地球再生、地域復興の包括的な処方箋を書こうとするとき、在来の学術、社会、人間の在り方の単純な延長線上に「学際的」プロジェクトを組織すればそれで足りるものではない。何よりも必要とされるのは、人間生活の足下を蝕む地球規模での環境破壊を克服するための哲学的な基盤を確立して、それを俯瞰型研究プロジェクトの核心に内蔵させることである。環境科学の研究に環境倫理の認識が不可欠なように、生命科学系、情報科学系の研究プロジェクトには生命倫理、情報倫理の共有が前提となる。情報技術革命の進展は、人々に幅広い情報源や選択肢を提供して豊かな情報社会を育てる可能性をもつとともに、情報格差や労働のロボット化、生活のバーチャル化を促進して、人間への新たな問いを生じさせている。巨大なメディア複合体が増殖したり政治権力の情報操作が始まって、公正取引の原則や報道の自由が侵され、超管理社会に道を開く恐れもある。人間中心の情報通信社会はどうすれば可能なのか-プロジェクトはこの問題を不断に問い続ける組織であることを求められる。それにまた、科学研究や技術開発そのものの情報化、オートメ化も進展して、そのため一方では研究者の「意味からの逃避」が助長されると同時に、それ故に逆に「知の主体性」の復権が真剣な課題となる。「人間がコンピューターの主人に」なり「コンピューターの理解できない『目的』や『感情』を持つ」(竹内啓)ことが、学術、とくに俯瞰型研究プロジェクトの最も重要な課題となる。俯瞰型研究プロジェクトの場合、「自然科学と人文・社会科学の両方の核心をつかむ」「真の学際化」が必要不可欠であり、「学際性の名のもとに、実際のところは、生産性の高い学問領域に対する弱小科学の一方的依存関係が形成される」といった事態は無縁な筈である。
(3)「負の効果」への挑戦
諸原因が複合して構成される現実の複雑な諸事象は、それぞれ、その影響も多面的で、様々な波及効果を秘めている。学術研究も、一般に予期せぬ効果を生むことが多い。とくに複雑な対象をその一部分を切り取って考察し、その限りで「正確な」処方箋を書くという個別領域別の研究の場合には、その処方箋が他の領域の観点からみると「正確に」不都合をもたらす-しかも処方した領域ではそのことに気づかない-ことが少なくない。これに対して研究が関連諸領域を糾合した俯瞰型研究プロジェクトの様式で行なわれる場合には、マイナスの影響を受けると予想される領域の研究者が参加することによって「負の効果」の発生を事前に探知し予防したり、研究の初期に発見して悪影響を緩和することが期待される。好ましくない副作用が拡がってからでは、負の効果を除去するのは容易でなく、時間もコストも大きくなる。早期発見・早期防除、俯瞰型研究プロジェクトは「負の効果への挑戦」を可能にする研究様式として構想されている。
俯瞰型研究プロジェクトは、意図しない副作用にも迅速に対応して、誤算を好機に転化できる体制である、ということもできる。たとえば、経済成長や有効需要の創出による失業対策など現実社会に有効な処方箋を提供してきた経済学は、環境問題、とりわけアジアにおける開発と環境といった問題や持続型社会形成のための学際的な研究に参加することによって、経済学の「文化的限界」を意識することができる。経済開発が自然環境に与える影響については、共同研究に参加している自然科学諸分野が迅速に正確な情報を提供する。経済学の側でも、その情報を共有して、経済分析がもつ現実からの距離を自覚し、それをバネとして経済学を「社会学や歴史学などを含んだ総合学問」(森嶋通夫)に再構成し、従来の社会科学を超える「一般理論」「汎用理論」につなげていこうとする動向も盛んになる。俯瞰型研究プロジェクトは、それを構成する個別学問領域にその見直しを促すという、好ましい波及効果を有している。
今日では、大規模地域開発プロジェクトには、経済効果の確認とともに、事前の環境評価が欠かせない。臓器移植、クローン研究、バーチャル・リアリティの研究には、個人の死、人間の尊厳、自然との関係に係る社会的影響への配慮が不可欠の前提になっている。産学官共同のミレニアムプロジェクトとして政府は情報通信、環境、高齢化の三分野で新産業を育てる技術革新の推進を計画し、その一環として「経済社会に明るい夢と希望を」もたらし「便利で快適な生活をもたらす技術開発等の研究」の提案公募を実施している。「実用への応用を視野に入れない基礎研究」は「対象外」である。しかし、たしかに技術革新はこれまで人類に「明るい夢」と「快適な生活」を与えたが、半面、戦争と核兵器の脅威、地球温暖化、環境ホルモン等々、人類の生存に危機をもたらす「負の効果」も大きかった。科学技術は、新しい千年紀にかかり、自らが生み出した困難な問題と対峙して試練の秋を迎えている。それらの困難な問題は技術革新だけで克服できるのか。できるとすれば、その場合、真の開発研究は、したがって象徴的に「ミレニアムプロジェクト」もまた、「希望」と「便利」さを追うばかりではなく、科学技術の「歴史」と「本質」を反芻し、「負の効果への挑戦」の視点を研究プロジェクトの内部に組み込んだものでなければならない筈である。自然科学の「ツール」を有効・適切に活用するには人文・社会科学という「ソフト」の充実が必要なことも忘れるべきではない。
(4)「負託自治」の実践
科学者が社会の期待を主体的に感知して、人々が「行動規範の根拠」として期待する研究成果を社会に提示し還元すること、そのための「新しい作業」として専門知の枠を超えた総合知・実践知の形成を軸に「知の組み替え」に努めることは、伝統的な「固有自治」の枠組を超えて、社会の負託に応える開かれた「負託自治」の立場に立つことを意味している。研究者は社会の問題、時代の要請を、未顕示のニーズを含めて掘り起こすために、非専門家である一般市民の未彫塑な期待や不安を聴き取り、調査し、またマスコミ等を介して情報を収集しするのであり、その意味で、プロジェクトは一般市民を一種の「参加者」とする「新しい型の共同研究」を揺り篭として誕生する。またその研究成果の社会還元のプロセスでは、住民が理解しやすい言説(言葉)が工夫され、社会的合意形成の理性的な筋道も提示されて、未来へのシナリオの実行可能性が試されることになる。
1997年、温暖化防止国際会議のホスト都市となった京都市は、会議に先立って地球温暖化対策地域推進計画を宣言し「京(みやこ)のアジェンダ」を策定した。環境地球工学の専門家を委員長とする検討委員会は、アジェンダを完全な公開と市民参加で作成し、現行の経済成長率を前提する限り二酸化酸素の「すべき削減」と「できる削減」のギャップは到底埋められないという認識を示したうえで、省エネ、リサイクルなど身近な市民行動と産業・エネルギー構造や交通体系の変革などの重点施策を提言した。「価値観の転換」をともなう持続型「循環共生社会」に至る「具体的シナリオ」を示して「市民の行動選択」を促すという、俯瞰型研究プロジェクトの理念と方法が地方自治体の政策形成に援用されている。日本学術会議がホスト機関となったインターアカデミーパネル(IAP)2000年会議は、「50年後の地球-科学の役割」をテーマに自然科学、経済学、哲学など「各方面の学術的な観点から」、人口や環境に関する「問題解決のために科学は何をなすべきか、また、なし得るかを探究し、それに基づいて21世紀に人類が進むべき道を科学者からの宣言として」グローバルにアピールする国際会議だった。
人文・社会科学が主役の学際的共同研究でも、平和や男女共同参画社会、世代間の持続的共栄の問題を含めて、人々に発信し続けるべき課題は少なくない。1980年代から90年代のアメリカでは、当時の日本経済の強さについて技術開発、企業経営、産業政策、金融問題から教育に至るまで、徹底した社会科学的な実証研究が有力大学を中心に重ねられ、自国の産業競争力の国際比較を踏まえて、有効な政策提言が行なわれた。これに1対して日本ではバブル崩壊後「経済学は現実の問題に答えられるのか」が繰り返して疑問視され、『経済学の終わり』(飯田経夫)が宣告されてもいる。経済情報と経済対策の作成・決定は官庁と一部の専門家に独占されている。社会科学の分野で広範な学術的・実践的研究が総合的に組織され、政策の決定に先行して様々な研究者が様々な選択肢を提示して国民的に論議が深められるという、成熟した民主主義のプロセスはみられない。競争力の日米比較に関する総合研究など、千年紀プロジェクトでは忘れられた、人文・社会科学的なアプローチを中心とする俯瞰型研究プロジェクトも重視すべきである。
学術を単に知識のための知識の生産とするのでなく、学術が社会の様々な場面に正・負両様、時には予期せざる大きな影響を及ぼすものであることを自覚して、社会の学術に対する負託に応え、社会に対する学術の説明責任を果すことが、俯瞰型研究プロジェクト振興の主眼である。俯瞰型研究プロジェクトは「負託自治」実践の道場にほかならない。
4-2 「基礎研究」の重視-「基礎研究タダ乗り論」の教訓から-
学術研究は本来、人類の知的財産を創造するという、それ自体として「文化価値」をもつ行為である。同時に、学術の成果は人材養成の糧となり、人間活動の知的・精神的な拠り所とされ、また科学技術の基盤として産業の発展や人々の生活向上に資するなど、社会への「実際的有用性」を有している。とくに、社会や技術のシステムが高度化し複雑化して、人々の価値観や関心も多様化した現在、環境問題、平和問題、生命倫理や精神的貧困の問題等々、多元的・複合的な関係構造をもった地球的規模での困難な課題が簇生して、専門化・細分化した学問領域の壁を超え学際的・超領域的に「学術全体の俯瞰的視点」から問題を把握し制御することが求められている。これまで、この報告では「俯瞰型研究プロジェクト」の組織的推進を現代における「学術の社会的役割」として強調した。
そのことは、しかし、「真実の知」の探究という学術本来の使命や、個別領域での学術研究、とりわけ「基礎研究」がもつ重要な意義を軽視するものではない。学際的・超領域的なプロジェクト研究そのものも、個別科学(ディシプリン)の幅広い創造的な研究に支えられて可能になる。科学の発展には、求心的に巨大な計画を推進する側面と、分散的に小さな種を育てる配慮とが必要である。時には、大型実験炉の建設を要する国際的開発研究プロジェクトに参加するよりも、小さな基礎実験を着実に積み上げるほうが成果が大きい場合もある。長い目で見れば、「科学技術の振興」のためには、基礎研究、応用研究、開発研究の、また自然科学と人文・社会科学との、調和のとれた発展が重要である。とくに文科系の純粋基礎研究の視点は、とかく忘却されがちだが、科学技術や俯瞰型研究プロジェクトの意義や本質を問うためにも、「科学技術の暴走」をコントロールし、科学者の倫理、市民の生活、環境との調和を重視した経済社会の持続的発展を図るためにも、不可欠であり、今日ますます現代的意義を加えている。
基礎研究のなかには、その成果が応用されやがて産業技術の開発につながる「応用研究の基礎」と、そうした「実際的有用性」をもつことなく「無用の用」にとどまる「純粋な基礎研究」が存在する。現実には、ナイロンの発明の例のように、実用化を前提としない「純粋に科学的な研究」が大きな実用的価値をもつ発明に結びついた例も少なくない。以下では、、「応用の基礎」たると「純粋基礎」たるとを問わず、また「プロジェクト型」たると「純粋個人研究」たるとを問わず、「基礎研究の重視」を日本学術会議が重点的に推進すべき第2の課題として取り上げたい。(従来から用いられている「基礎研究、応用研究、開発研究」に対して昨年、第3常置委員会の報告では「創造モデル研究、展開モデル研究、統合モデル研究」という分類が提示されている。見識ある提言ではあるが、統計の一貫性も重要なので、本報告では、一般の分類に従った。)
なお、特定課題、重点課題として大型のプロジェクト研究が推進される場合には、概して、その研究は比較的効率的に、短期間に目に見える実際的な成果を上げることが可能である。その結果、往々、「負の効果」として、「純粋基礎」的な個別研究を含む基礎科学が等閑に付されることにもなりかねない。俯瞰型研究プロジェクトを推進する日本学術会議は、まさに「俯瞰型」の長所である「負の効果」への予測的警告者の立場にある。この観点からも、基礎研究の重視を重要な推進課題とすることが望ましい。
4-2-1 現代産業社会における基礎研究の役割
産業技術と自然科学とは源泉を異にしている。イギリス産業革命期の機械技術は作業現場で叩き上げた職人の知識や経験の所産であり、科学の理論や知識は必要としなかった。しかし、19世紀中葉のベッセマー製鋼法前後から、科学と実験に基づいて新技術を発明し新産業を起こす事例が増加し、「自然現象を弛みなく科学的に研究することこそ産業進歩の父である」(L.モンド)といわれる時代が到来した。
産業技術の観点からみると、研究開発は通常「基礎研究」(特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形成するため若しくは現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論又は実験的研究)から「応用研究」(基礎研究によって発見された知識を利用して、特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究及び既に実用化されている方法に関して、新たな応用方法を探索する研究)、「開発研究」(基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識の利用であり、新しい材料、装置、製品、システム、工程等の導入又は既存のこれらのものの改良をねらいとする研究)へと進んで、製品が登場する。もちろん、超音速航空機の出現が超音速気体力学の研究を促したように、工業化技術の成果が基礎研究を刺激するという関係も見受けられる。基礎研究と産業技術の間には、双方向的な相関が存在するのである。しかし、一般的にいえば、産業社会における基礎研究は工業化技術形成の不可欠な基盤であり、幅広い基礎研究の裾野の存在は、長期的にみて、その産業社会の技術力・経済力の厚みと強さを示している。
4-2-2 科学技術の「日本問題」
産業技術の発展は、一方で領域の細分化・専門化で効率を高めるかたちで行なわれた。自然科学分野における学問領域の細分化・専門化の背景には、産業技術や産業分野の要請が存在する。他方、一つの発明を企業化するためには関連諸技術の活用が必要で、とくに大規模現代企業にける統合化されシステム化された技術の場合には、複数技術領域にまたがる総合性が不可欠になっている。複合的な技術の企業化にさいしては、構成要素技術間に技術開発の水平的な分業が形成される傾向が見受けられる。一方、基礎研究と工業化技術の開発(応用研究・開発研究)とが、国際間の垂直的な分業をなして展開する場合も少なくない。しかし、基礎研究の成果は人類の公共財であり、基礎研究を過度に外国に依存し続けることは、単純な国際技術分業の問題でなく、果たすべき国際貢献の回避として、しばしば経済摩擦・文化摩擦の一因となっている。「科学と技術に関する『日本問題』」はその代表的な事例である。
日本では近年まで、基礎科学や基礎技術の研究は欧米に任せて、その応用・改良・実用化に努めるのが効率的な技術開発の方法だと説かれてきた。アメリカで発明され補聴器ぐらいにしか用途がないと考えられていたトランジスタをみて、《pocketable
radio》の開発を着想するのも一種の「創造」だが、他国の発明をモノにしてチームワークで新製品を世界に送り返すことが重なると、国際的な反撥も激しくなる。
1980年代前半から90年代初めにかけて、欧米とくにアメリカで《科学技術に関する「日本問題」》(the
"Japan Problem" in science and
technology)が盛んに議論された。日本叩きである。論点は日本が他国の基礎研究の成果に「こそこそとタダ乗りしている」(sneaking
a free ride)ということで、関連して日本人の模倣癖、情報と人材の片貿易、閉鎖的な談合文化などが爼上にあがっている。要するに、日本は基礎研究を「タダ乗り」して、集団的な一致協力で技術と経済を急速に発展させ、基礎研究の提供国を含む海外諸国に安価な製品を輸出し、閉鎖的な市場障壁を構えてこの体制を保護している、というのである。論旨には反駁すべき点も少なくない。超伝導巨大加速器(SSC)の建設費を日本も分担すべきであるという米国政府の圧力が議論を過熱させたことも事実である。
しかし、日本が基礎研究の多くを外国に依存してきたことも確かな事実である。1988年に出された我が国初の『産業技術白書』は、応用・開発面での産業技術水準はハイテク分野を中心に急速に世界のトップレベルに近づいているが、基礎技術分野の研究水準は相対的に立ち遅れが目立つこと、研究開発投資は全体として世界レベルに接近しているが、政府の研究開発費の水準は低く、そのためもあって基礎研究への投資が十分でないことなどを指摘して、日本は基礎的・独創的研究の強化と国際貢献の促進に強力に取り組むべき転換期にあると強調した。その後、科学技術基本法が成立し改善は見られるが、問題の本質は不変である。日本の研究開発投資はGDP比3.1%(97年)で世界最高になったが、その8割は基礎研究の少ない民間の負担であり(米国7割、独・仏6割、英国5割)、基礎研究の主流をなす政府資金の割合は2割程度にとどまっている。研究開発費に占める基礎研究の割合は、全体で15%程度(大学では50%強、企業では7%弱)である。学術研究の論文数は世界2位になったが(『教育白書』)、科学論文数の3分の1はアメリカが占める「一強多弱」であり、引用回数は4位(論文に対する論文引用回数の比は世界で18位)である。大学別特許登録件数(1998年)では年間5千件を超えるアメリカの大学に比べて日本は百件に満たないのが現状で(『特許行政年次報告書』)、「大学の基礎研究力の差が際だって」いる。1993年を転機に日本は技術輸入国から技術輸出国に変わったが、技術貿易収支比率(95年)では米国の4.3に対して1.3である(総務庁『科学技術研究調査報告』)。「米国の強みは、基礎研究に対する国の支援と、得られた成果を産業に結びつける仕組の両方がそろっていること」で、「欧州には、そのひとつだけ、国の支援がある。その両方が欠けているのが日本だ」と、米国ヒトゲノム科学社の会長は語っている。
明治以来近年まで、日本は先進国に追いつくことを至上の国家目標に掲げ、科学技術を手段として「追いつき型」工業化の馬車道を驀進してきた。その「成功」は、日本社会の奥深く、学術や科学は国家・社会に役立つためにのみ存在するという、国策型「実学」重視の観念を刻み込んだ。政府が音頭を取り、和魂洋才、「国家ノ須要ニ応スル学術技芸」をつまみ食いして移入し振興し、富国強兵・殖産興業に邁進した。地道な基礎研究を息長く育てるのではなく、個性や独創は「出る杭は打たれる」風土のなかで窒息する。こうして「科学の樹を育てる人ではなく科学の果実を切り売りする人」(『ベルツの日記』)を求める文化が形成され体質となって、今でも人々を捉えている。
欧米では、科学研究や基礎技術の研究開発に多年、多くの人材と公共的な資金を投入してきた。基礎研究は人類共通の「文化」であり、その成果は人類の「公共財」である。公共財の形成に参加することなく、ひたすら他国の基礎研究の成果に依存して技術開発と営利活動に没頭することは、形式的には科学技術の国際分業として合理的な選択ではあっても、往々-お祭の寄付を出さない氏子のように、また、教養教育を拒んで専門研究や学外講演に没頭する教師のように-身勝手なルール違反と受け取られる。科学技術創造立国を標榜する以上、いつまでも許されることではない。それにまた、基礎研究の放棄は研究開発の足腰を弱め、自前の産業技術の培養を困難にする行為である。技術貿易の国際摩擦が激しくなるなかで、外国の基礎研究の成果を支障なく手にし続けられる保障もない。技術交換契約や高額の特許料を求められる恐れもある。基礎研究の重視は、とくに日本の場合、学術の重要な課題である。
4-2-3 科学技術基本法と基礎研究重視の課題
科学技術基本法(1995年)が成立し科学技術基本計画(1996年)が策定されたのは、まさに「基礎研究タダ乗り論」が燃え盛った直後だった。基本法は科学技術に係る知識の集積が、一つには「人類にとっての知的資産」であり、同時にまた「我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与」し「世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的発展に貢献する」という二つの見地にたって、日本の科学技術の振興を図ることを立法目的に掲げている(第1条)。そして「基礎研究、応用研究及び開発研究の調和のとれた発展」を重視することと(第2条)、とくに-「基礎研究が新しい現象の発見及び解明並びに独創的な新技術の創生等をもたらすものであること、その成果の見通しを当初から立てることが難しく、また、その成果が実用化に必ずしも結びつくものではないこと」等に鑑みて-「基礎研究の推進において国及び地方公共団体が果たす役割の重要性に配慮」すべきことをうたっている(第5条)。これを受けて策定された基本計画も、「日本は基礎研究において欧米に遅れをとり」、生命科学、材料科学、海洋学、地球学、コンピュータ科学など「少なからぬ領域で遅れは拡がっている」という認識にたって、「政府は、民間ではなし難い基礎的・独自的研究を推進すべきである」と強調した。
「基礎的・独自的研究」、すなわち個性的で創造的な基礎研究の推進が国民的な課題と宣言されたことは、上述した明治以降の日本の歴史的・構造的な問題的状況を考えると、画期的な意義をもっている。もっとも、体質化した風土や文化が一朝一夕に変化するわけではない。基礎研究は、定義上、個々の研究者の学問的な好奇心に導かれた内発的な営みであるが、現代産業社会における学術研究は、基礎研究であっても外的・社会的な環境から遮断された「象牙の塔」で営まれているわけではない。産業社会での基礎研究は社会の価値意識や期待のあり方と研究者の内発的インセンティヴとの緊張関係によって盛衰し変容する。科学技術基本法は科学技術の社会的役割を強調するが、社会の在り方が学術や科学技術の在り方に大きく影響するのも事実である。基礎研究と創造性を重視する社会意識の形成と、それを背景として、個性や創造性を評価する研究評価、研究費配分審査のシステムを構築することが、真に価値のある基礎研究を奨励する前提条件なのである。日本の学術や社会の文化的現実を直視し洞察したうえで評価の理念と組織を再構成することを抜きにして、ただ科学技術関連の研究資金を潤沢にするだけでは、独創的な基礎研究の推進は画餅となり、科学技術に関する「日本問題」の再燃も避けられない。
日本の基礎研究と助成方式の問題点について、ある大学広報誌の匿名短評欄(1998年)には、次のような辛辣な一文が載っている。「先の見通しの立った課題の選択、短期集中型投資、短期的評価などの現行の助成方式は、目先がきき腕力のある人材、短距離競争向きの選手が登場しやすい環境を設けている。若い学徒は、より苦労の少ない資金豊富な応用科学に集中する。この状況を、どこに研究資金があるかを上目使いにさぐりながら進むという意味で“平目の科学”というむきがある。独創性をもとめてやまない学徒は、やむをえず心に期した目的を隠して、研究費の潤沢なところに慈悲を乞うてみせかけの仕事をし、苦しい報告書を書いている。これについては“言い訳の科学”と呼ぶむきがある。当代は“平目の科学”と“言い訳の科学”があふれている時代と言えないか?」
研究資金の配分は、総花的ではなく、公正で厳格な研究評価によるべきだが、重要なのは評価基準である。個人の自由な発想による個性的で創造的な基礎的・基盤的研究を育てるには、息の長い視点で、研究の萌芽期から、個性や創造性を含めて、テーマよりもヒト(研究の担い手)を評価できるシステムが望ましい。もちろん、競争型の研究費配分であるから「順位づけの」(summative)評価となることはやむを得ないが、多様な「基礎的・独自的研究」を奨励する「形成的な」(formative)評価の要素を最大限もりこむ工夫がいる。基礎研究では「道具としての効率性」よりも「文化的公共財としての価値」が問われる筈である。「テーマの流行性」(重点課題・推進課題)にこだわったり、「業績主義」を強調して短期的に効率よく成果をあげようとする自閉症的なテーマ矮小化の風潮を助長するのでは、創造的な「基礎的・独自的研究」は育ちようもない。「俯瞰型研究プロジェクト」や「戦略研究」の傘に依存しないでも個別研究が個別研究として認知され、「応用の基礎」となる研究だけでなく「純粋基礎」の研究もそれなりの居場所をもてるような、そうした評価システムの開発に、日本学術会議も取り組むべきではないかと考える。
基礎研究の振興に関しては、その他、多数の群小国立研究所の基礎研究部門を統合し省庁の壁を超える新しい基礎研究機構群を設立したり、世界やアジアの公共財として環境問題に関する国際共同利用の基礎研究施設を設立するなど、検討したい構想は少なくない。
科学技術基本法を転機に日本の基礎研究の状況が改善され始めたことは確かである。日本は国際的な「基礎研究推進の主役」として期待されているともいう。「好機」である。しかしここで手を抜けば「後戻り」であろう。そして、おそらく、幾度も繰り返されてきた基礎研究振興の願いにとって、今が残された「最後のチャンス」なのである。
4-2-4 文科系基礎研究の現代的意義
科学技術基本法は、「自然科学と人文科学[人文・社会科学]との相互のかかわり合いが科学技術の進歩にとって重要であり、また科学技術は「人間の生活、社会及び自然との調和」を大切にすべきであるとの見地から、自然科学と人文・社会科学との「調和のとれた発展」が必要なことを強調している(第2条)。しかし、同法は、対象とする「科学技術」の範囲を限定して、「人文科学[人文・社会科学]のみに係るものを除く」と定めている。この点に関しては、かつて1966年に科学技術会議が公表した科学技術基本法の要鋼では人文・社会科学も適用範囲とされていたものが、与党の反対で政府原案では適用範囲外に変更され、結局、国会では1968年に野党の反対で否決された前史がある。(日本学術会議は、1967年10月、人文・社会科学を適用外とする政府原案に対して反対の決議をした。)したがって、科学技術基本法のもとでの科学技術の振興には、諸科学の「調和的発展」という建前に反して、文科系(とくに文科系基礎科学)を「除け物」「添え物」扱いにする、大きな限界が存在する。
ちなみに、同法は「基礎研究、応用研究及び開発研究の調和のとれた発展」を強調し、とくに基礎研究については「その成果が実用化に必ずしも結びつくものではない」ので、国等の公的支援が大きな役割を担うべきことを認めている。「応用の基礎」だけでなく、直接には役に立ち難い「純粋基礎研究」も振興することが約束されたといってよい。しかし、現実には、ミレニアムプロジェクトの一環として政府が推進する「革新的な技術開発の提案公募」をみても、「実用への応用を視野に入れない基礎研究」は「対象外」と明記されている。このことに象徴されているように、理科系でも「純粋基礎」は日陰者にされがちなようである。当面、新設される総合科学技術会議の体制のもとで、より総合的な学術政策、科学技術政策が樹立されることを期待したい。
ともあれ、今日、基礎研究の重要性は、自然科学だけではなく人文・社会科学についても強調されなければならない。とりわけ、文科系「純粋基礎」研究の現代的意義を忘却すべきでない。人文科学・社会科学でも、法学・政治学、経済学・経営学、社会学・心理学・教育学など、政府や企業の行動とか人々の実生活と密着して、実学的な役割を果している分野がある。他方でまた、哲学、歴史学、文学のように、具体的な応用を待つまでもなく、存在の真実を洞察し、過去と対話し、人間的経験を理解するなど、それ自体が人間にとって本質的で、人々の精神生活を豊かにする、純粋な基礎研究も存在する。科学技術が発展し「実用の知」が重用されればされるほど、むしろ「精神の知」がもつ「無用の用」が求められ、そうした学術の文化的価値が認識されてくる。「意味喪失の時代」に生きる人々は、諸々の事象の客観的な因果関係の分析だけでは満足せず、出来事の意味や価値を語りかける学術を探している。
生命科学の発展は生命倫理の覚醒を促し、あらためて「人間の尊厳」の省察を必要にした。地球環境科学は自然との共生、未来世代との共生の課題を人々に提起し、とめどもない「物質への欲望」を制御して持続可能な循環型社会を指向するライフスタイルの転換を迫っている。情報革命の展開は、いまの情報化が本当に人々の幸せにつながるのか、人々の心にどのような影響を及ぼすのか、などの問題を投げかけ、また氾濫する情報のなかで「知の主体性」の大切さを考えさせることになった。情報や技術や経済のグローバル化は画一化を懸念させ、言語や文化の多様性の重要さを浮き彫りにしてもいる。生命科学、環境科学、情報科学の展開は、我々がどこから来てどこへ行くのかという根源的な問題に人々の関心を向けることにもなっている。世界と時代と人間を最も根底的に洞察し問題の本質を究明するのが哲学-そして歴史と文学(人間学)-だとすれば、現代はまさにこうした文科系「純粋基礎」研究(「根本研究」)の出番である。
「社会が複雑化し、文明化が拡大し、科学技術が甚大な影響を及ぼし、あらゆる面でさまざまな考え方が葛藤を起こし、価値観や生活の基本原則が揺らぎ、地球上の人類生活や文化における根本原理の再反省にもとづく哲学的な相互理解と意思疎通が、いよいよもって重要となることは避け難い」(渡邊二郎)。人文・社会系の基礎研究は、自然科学や科学技術が掘り起こした現代の諸問題を受け止めて、その社会的・歴史的・人間的意味を考察し、課題解決に努めるとともに、「科学技術全体を俯瞰する哲学的洞察」(和田昭允)をもって科学技術の意義と限界を指摘し、その在り方をチェックすることができる。そのためには、文系「純粋基礎研究」の側でも、現代におけるその在り方について反省が必要なことは、いうまでもない。
21世紀を展望して「人文社会科学系と自然科学系が融合して新しい学問分野を切り開いていかなければ、人類の未来はない」(井村裕夫)。「二つの文化」(P.スノー)のギャップを埋めることが急務であり、そのためにも文科系を含めた総合的学術政策の樹立が望まれる。
4-3 「教育」の再構築-「知の衰退」と「科学技術創造立国」への困難な道-
4-3-1 科学教育立国「神話」の崩壊
「科学技術創造立国」論に関連して、しばしば、「我が国は、科学に基礎をおく高度な教育体制を確立し」「その中で育った優れた国民」、「教育水準の高い人口」を「多数擁する」という「実績」が強調されきた。多くの「国民が科学者に期待」しており、「意欲ある優れた若者の多くが科学者になってほしい」というのが「国民の悲願」であるといった説明も間違ったことではない。事実、シンガポール科学アカデミーのレオ・W.H.タン会長も、日本学術会議50周年記念講演で、「日本は、仕事の場における科学技術振興という点で、アジアの模範」であり、「若い人たちを科学技術のキャリアに引きつけることに成功している」と話された。しかし、事柄の半面を語られた、とわれわれは自覚すべきである。というのは、こうである。1995年に実施された第3回国際数学理科教育調査から中学2年生の調査結果をみると、日本は「理科が好き」な生徒の割合でも、「将来、科学を使う仕事をしたい」生徒の割合でも「世界最低」で(図A)、「理科はやさしい」お
よび「理科は日常生活において大切」という両項目でも最低、さらに「理科は楽しい」と
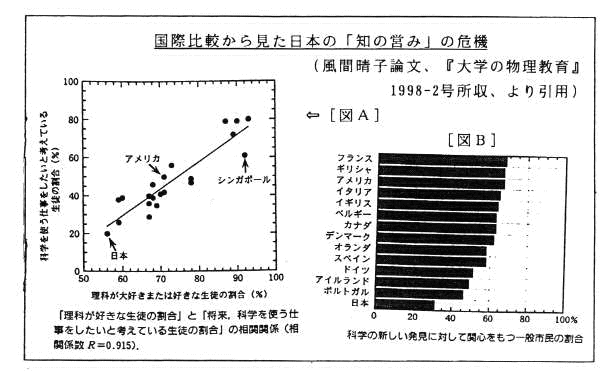
第5章 日本学術会議の社会的役割
5-1 創立50周年の自己点検・評価-変化の胎動-
日本学術会議は、戦後、「科学が文化国家の基礎であるという確信」に立って、学術の進歩に寄与し、「わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献」する使命をもって設立された。その目的は、科学者の「代表機関」として「科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させる」ことと規定されている(日本学術会議法第2条)。学術の社会的役割が、政治や経済や国民の生活に科学を「反映浸透させる」という、上からの、やや一方的な関係として捉えられている点、「象牙の塔」の高みから「栄華の巷」を啓蒙するという、どちらかといえば「固有自治」の立場であり、国民の負託に応え社会のニーズを感受して研究し、成果を社会に還元するという「負託自治」の理念は的確には表現されていない。
それはともあれ、日本学術会議は、創立以来、学術体制や研究計画、各種専門分野の研究課題や境界領域科学の問題等、学術や科学技術政策に関する重要事項を審議して、答申や勧告・要望を政府に提出し、また対外報告や声明、アピール、談話等のかたちで見解を公にしてきた。学問・研究の自由と平和な人類社会のために科学者の良識を訴え、また、学協会との研究連絡、共同研究・プロジェクト研究の推進、シンポジューム・講演会の開催、国際学術交流の促進など、各種の事業も展開した。
しかし、全体としてみると、「象牙の塔」(「固有自治」)を守り「科学のための政策」(科学技術政策)の拡充を求める問題意識の強さに比べて、社会のために科学的知見を積極的に提供し奉仕する意識は弱かった。伊藤正男前会長は、16期に脳科学と計算機科学の推進について政府に勧告を行ったが、「何れも科学の振興のための行政措置を要請する」もので、その一方「最近の生命倫理の問題など、政策の形成、実施に大きく関る問題について日本学術会議の審議が迅速を欠きがち」なのは「政策のために科学の知識を積極的に役立てようとする動機付けが会議内部に希薄ではないかとの疑念を呼び起こす」と述べ、「行政だけでなく、産業、国民生活に科学を反映する道についてももっと積極的に考え、工夫する必要がある」と書かれている。とくに、国民の負託に応えて社会の現実の諸課題と取り組み学際的・総合的な共同研究を組織的に推進するという面では、「場当たり主義的傾き」(川田侃・元副会長)が強く「負託自治」の意識は低かった。「象牙の塔の内側からの視点に偏したのではないか。」政策批判はあっても「代案の提案が無いため建設的役割を果せなかった」というのが、今日、大方に共通した「内側からの反省」(金岡祐一・第7部部長)となっている。
このような傾向に対しては、内外の批判や提言も早くから存在した。たとえば、のちに日本学術会議の副会長となる川田侃教授(国際学)は、すでに30年前、設立20周年にさいして、日本学術会議の「役割に大きな期待」をもつ一研究者の立場から、次のような「切なる注文」を述べている。すなわち、激動する世界にあって「既存の理論的専門領域の枠組では扱いきれない」「複雑で多面的な」「新しい具体的でかつ実際的な諸問題」が「つぎつぎと発生」し、そのため、「新しい研究分野の開拓と発展」を求める「切実な社会的要講」が生まれている。日本学術会議はこの新しい「社会的要請」とその「背後に存在」する「一般民衆の鋭い自覚」と「期待」に応えるため、依然として「学問的なナワ張り争いに固執する」「旧来からの学界の弊風」を打破して、「隣接諸科学がそれぞれ理論的専門化の枠を乗り越えて、課題の解決のために協力しあうインターディシプリナリーな総合研究の方法」を開拓し、「諸専門領域間での開かれた学術交流にもとづく」「総合的な共同研究」を組織するなど、「新しい研究体制の確立のために」「もっと真剣に取り組むべきであろう」、というのである。
こうした先覚的な提言があり、また時代や学術の状況も変化して、日本学術会議でも、1990年の前後から、「負託自治」と「俯瞰的視点」が-そういう言葉はなかったが-しだいに重視されてきた。日本学術会議が主催・共催した国際学術交流シンポジウムをみても、研究成果を公表して市民や行政に「行動規範の根拠」を提供しようとする、科学者の新しい役割の自覚が看取される。
たとえば、1993年9月、AASSREC[アジア社会科学研究協議会連盟]総会シンポジューム「環境と持続可能な開発-社会科学の視点から-」で「開会の辞」を述べた川田侃[連盟会長・学術会議副会長]は、「環境問題については、社会科学者も重要な貢献を求められている」と述べ、「社会科学が理論的に発展するのみでなく、実践的にも有効であるように」、シンポジュームでは「政策関連にとくに強調点」が置かれることを説明した。そして「政府サイドからの参加と社会科学および自然科学双方の科学者サイドからの学術的な参加」により「多様な視点、異なったアプローチ、そして幾つかの理論的見解」など「多様性が反映されることが期待され」ると強調した。同年11月、第一回「アジア学術会議・科学フォーラム」(ACSC)でも、主催した日本学術会議を代表して、同副会長は、「環境問題は、単に技術的発展が生んだ結果であるのではなく、経済的、社会・政治的、行政的な人間行動が生んだ産物」なのだから、「学際的研究や学問の総合化」「人文・社会科学と自然科学という両学系列の融合こそが大切」なことを力説した。そのさい、「地球環境問題について、ここ数年『持続可能な発展』というキャッチフレーズはたしかに普及」したが、しかし、地球環境変化、地球気候変化に対処すべき国際的な合意の形成に関しては「世界の人々の意見や意識には、まだかなりの隔たりがある」ことを指摘して、次のような訴えがなされている。「このような状況を顧みるとき、こんにちの世界において、私どもが必要としているのは、明らかに力ではなく、知識であります。学習の繰り返しと知識の積み重ねとその普及を通じて、人々の意識の変化をよび起こすこと、そしてそれを背景として、地球的規模の症候群の克服に向けて、適正な国際政策の立案、実行を的確に推し進めていくための知的リーダーシップを発揮することが、いま私ども科学者らに強く要請されています。」-人々の「行動規範の根拠」となり「政策形成の基盤」ともなる「俯瞰型研究プロジェクト」推進の必要が説かれているのである。
その数年後、1998年2月、日本学術会議・国立環境研究所共催のIGBP[地球圏-生物圏国際協同研究計画]シンポジューム「21世紀に向けての地球環境研究のあり方」では、「現代では科学的な知識が人々の価値観を大きく左右するようになっている。オゾン層に関する知識や温室効果の知識が国際政治に大きな影響を与え、条約の締結まで可能にした」と、力強い言葉が述べられた。「地球や生態系に関する研究が進めば…有限な地球という見方もより深く定着する。研究成果を利用して環境対策を考えることも大切だが、もっとも重要なことは研究が社会の価値観に働きかけることである。」
とはいえ、学術研究の新しい様式、学術と社会の新しい関係への胎動は、多くの場合、顕在化した問題と切実化した社会的要請に対する「受け身」の対応であり、対応の「時間の遅れ」も免れない。日本学術会議の「第17期の活動計画(申合せ)」(1997年10月)は「多数の領域を擁する学術全体を俯瞰的に見る視点の重視」と「行動規範の根拠を提供する開いた学術の構築」を活動の基本的方向に掲げている。計画作成にさいして、「会長談話」は、学術会議がすでにシンポジューム等を通じて「複数領域の科学者の協調的作業」の成果を人々に提供してきたが、その多くは「社会において問題が発生したことを契機とする受け身の行動」で、「学術の持つ予見性」が生かされていないと指摘している。
学際的「総合研究」を個別領域的な接近の単純な集合に終らせないことも容易でない。多様な諸領域の諸事実・諸関係の超領域的な連関構造を俯瞰的に捉え、問題が発生しまたその問題の解決から発生する因果の連鎖、とくにマイナスの副作用を的確に把握し、問題の意味を多面的に深く掘り下げて、得られた情報を迅速に社会に還元するという、「広域の俯瞰」、「本質の俯瞰」、「負の効果」への挑戦、「負託自治」の実践、そうした内容を包括した本格的「俯瞰型研究」の組織的推進は今後の課題である。研究の成果を「政策形成」(問題解決の可能的選択肢の提示)につなげる「政策過程」研究、「合意形成」プロセスの検討も、あわせて必要とされている。
5-2 今後の在り方-変革の理念と重点-
日本学術会議は、1999年10月の総会で、「日本学術会議の自己改革について(声明)」を採択し、上記「活動計画(申合せ)」を受けて、「現代社会で生起する複雑かつ多面的な問題を予見し、探知して、社会に対して行動規範[の根拠]を提供するという新たな学術的課題に向けて、積極的な役割を果す」ことを決定した。本特別委員会は、この「自己改革」の路線にしたがい、「俯瞰型研究プロジェクト」の一層活発な推進を基軸に据えて変革の理念と重点を構想することが、現在、日本学術会議がその社会的役割を果たすうえで重要な課題であると考える。あわせて、「俯瞰型研究プロジェクト」の推進にともなって有り得べき-また有ってはならない-「負の効果」(とくに「純粋基礎」的な個別研究への皺寄せ)を防止し、基礎研究を重視すべきこと、また「俯瞰型」は研究にとってだけではなく、今日、喫緊な「教育」再構築の課題にとっても不可欠な視点であり、「俯瞰型教育」の重視が必要とされていることも強調されるべきである。そうした観点から、学術の社会的役割に関して、日本学術会議が当面取り組むべき変革の理念と重点について略記したい。
(1)負託自治の理念と俯瞰型研究
日本学術会議は、社会から負託された「負託自治」の自覚に立ち、現代社会の諸問題を予見し探知して、積極的に学術の課題として構成し、「多数の領域を擁する学術全体を俯瞰的に見る視点」を重視し、とくに学際的・総合的な「俯瞰型研究プロジェクト」を編成して、研究の成果を社会に還元する。そのさい、「学術の先見性」を生かして、問題の顕在化・深刻化に先行して情報を開示する予測的提案者・警告者の役割を重視し、とくに、ある個別領域での「正確な」処方箋が場合によっては他の領域に「正確に」不都合な副作用をもたらすことがあることを銘記して、そうした「負の効果」を警戒し予防するように努力する。また、選択可能な問題解決の選択肢を提言して、人々が「社会的行動規範の学術的根拠」をもちうるように配慮する。
もちろん、日本学術会議は、学術研究それ自体がもつ固有の文化価値や個別領域での学術研究が果たす社会への貢献を尊重し、とくに基礎研究・個人研究の重要性を軽視するものではない。そのうえで、しかし、現代社会に生起する複雑で多面的な問題が、多くの場合、既存の専門領域の枠組や個人単位の研究では把握し解決し切れない現実に鑑み、また日本学術会議が「わが国の科学者の内外に対する代表機関」であり、会員は個別の専門領域を基盤として選出されるが、日本の学術全体の発展に寄与する役割を期待されていることに鑑みて、局所的な領域的課題から大局的な統合的課題へと重点を移動することが社会の負託に応える所以である。学術の新しい在り方、学術と社会の新しい関係を構築して、学術に対する社会的要請、その根底にある一般市民の学術への期待に応えること、「固有自治」と「負託自治」の緊張にみちた調和として「学術研究の自由(主体性・自律性)」と「学術の社会的役割」の両立を図ることが、現代の課題である。
(2)日本学術会議と俯瞰型研究プロジェクト
日本学術会議は、自然科学、人文・社会科学を含む学術全体を代表する組織であり、本来「学術全体を俯瞰的に見る視点」に立つべき使命と適性を有している。日本学術会議はまた、「科学の向上発達」を図るとともに、「行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させる」ことを目的としているから、学術の社会的役割を重視し「負託自治」の実践を課題とする俯瞰型研究プロジェクトの振興は、その意味でも本領といってよい。
もっとも、日本学術会議は基本的には審議機関であり、自身で本格的にプロジェクト研究を行なうのは任でない。学術会議が俯瞰型研究プロジェクトに関して果たすべき主要な任務は、プロジェクトの在り方やその振興策を審議して、その結果を「行政、産業及び国民生活に反映浸透させる」ことであり、また審議に必要な調査研究を行なうことである。具体的には、プロジェクトが取り組むべき「課題の提起」、プロジェクトを立ち上げるための「予備的研究」があり、また研究成果の「社会への発信」も重要な役目である。
「課題の提起」に関しては、学術の動向、社会の状況を総覧し、人々が学術に抱く-しばしば未顕示・不定型な-期待や不安を探知して、プロジェクトが取り組むべき課題を選定する。また、プロジェクトを構成すべき学術分野(主管分野、関係分野、協力分野や「負の効果」が予想される分野、等)や人材など、研究態勢の概要を審議する。
「予備的研究」では、提起された課題につき学術全体を俯瞰して、問題の意義・本質、研究の現状、方法、効果・副作用等を調査研究する。また、関連する内外の大学・研究機関、学協会、行政、産業、市民団体等と研究連絡や連携を行ない、本格的な研究プロジェクトの形成を支援する。
「社会への発信」に関しては、学術会議は「わが国の科学者の内外に対する代表機関」として、プロジェクト研究(予備的研究を含む)の成果を迅速に公開する。とくに、人々の行動規範の根拠となる学術情報や、政策形成・政策批判の基礎となる「未来へのシナリオ」を重視し、対外報告、公開講演、シンポジューム、懇談会、『学術の動向』、ホームページや、勧告等(勧告、要望、申し入れ、声明、会長談話等)を活用して、効果的に社会に説明する。情報発信には、表現の質の向上、即応性、柔軟性が求められ、とくに非専門家への情報伝達では、達意にかみくだく情報加工技術の研磨が必要である。
なお、学術会議が実施する俯瞰型プロジェクト(予備的研究)を含めて、プロジェクト研究は「研究目的の設定、計画の立案、期待される効果の測定、研究の実施、中間評価、計画の修正、成果の公表、成果の効用評価など」研究の全段階を通じて研究の効果や影響を多面的に評価することが必要である。日本学術会議がその評価を支援することも検討されてよい。この点も含めて、日本学術会議は、俯瞰型研究プロジェクトの振興のために、「俯瞰型の審議」や「俯瞰型の調査研究」の体制を整備・充実して、社会の負託に応える信頼できる組織として成長することが期待されている。
また、俯瞰型研究プロジェクトに関する審議や審議に必要な調査研究を実施するためには、日本学術会議は常時、内外の学術の動向や社会の状況全般について充実した調査研究を行なうことが必要である。
(3)「基礎研究」の重視と「教育」の再構築
基礎研究は本来、人類の「知的公共財」を形成する、したがって公共的費用が投入されて然るべき営みであり、他国の基礎研究に多くを依存して技術開発と営利活動に没頭することは「公共財」の分担を拒否する身勝手なルール違反とみなされる。そもそも、産業社会では基礎研究は産業技術形成の裾野であり、生命科学、環境問題、情報革命の進展は人・世界・時代の本質を根底的に洞察する文科系「基礎科学」の重みを増してもいる。俯瞰型研究プロジェクトの多くは哲学的・倫理的また感性的な「本質の俯瞰」を求めているが、反面、「学際性」が「生産性の高い学問領域に対する弱小科学の一方的依存関係」の別名になりかねないのも事実である。日本学術会議は、「負の効果」の予防をうたう俯瞰型研究プロジェクトを重点的に振興する以上、その振興が基礎研究にマイナスの副作用をもたないのか、この点を含めて十分に審議研究し、科学技術基本政策、学術政策の在り方に対して、基礎研究を重視する学術の立場から発言すべき立場にある。
同時に、教育の在り方に関しても日本学術会議が社会的役割を果すべき分野は少なくない。とりわけ、中学生でも一般市民でも「世界で最も徹底した」理数離れが伝えられ、大学でも「知の衰退」が著しいなど、「教育日本」の「神話」が崩壊して「科学技術創造立国」への道は教育の足下から揺らいでいる。「科学者の代表機関」である日本学術会議として座視できぬ事態である。総合的な「俯瞰型」学習、「考える教育」、「知の創造に参加する能力の養成」、最先端の科学や哲学を文系にも理系にも分からせる「面白くて為になる」「知の技法」の開発、「新しい教養」の構築など、「知の衰退」の実態や原因の組織的な調査を基礎に、検討すべき教育問題は山積する。とくに、「俯瞰型」の視点は「研究」だけでなく、総合的な「俯瞰型の学習」を求める「教育」の視点でもあるという観点から、教育再興の課題に挑戦することは、学術会議のもう一つの社会的役割なのである。
(4)科学者の倫理と社会的責任
そのほか、「科学者の倫理と社会的責任」のテーマも今後ますます重要になることは必至である。クローン人間の産生の禁止に類した、「学問の自由」に対する「法的規制」の問題も、ゆるがせにできない課題である。日本学術会議としても、準備・検討を怠るべきでない。
(5)制度・運営の改革
こうした重要な諸課題と取り組むには、制度・運営の改革について検討されるべき事項も存在する。もとより日本学術会議の改革に関する包括的な検討は本特別委員会の任務でない。また、この問題に関しては「日本学術会議の自己改革について(声明)」(1999年10月)が総会で決定されたばかりであり、そこには、「俯瞰的視点から取りまとめる科学的知見を行政や社会に提供すること」を柱に、「現行の日本学術会議法の下で実行可能な改革の具体策」が、「組織・運営にかかわる改革」を含めて周到に提示されている。本報告は、この「自己改革」の枠組を基本的な前提として、主として運営面で若干の補足を試み、また将来的な一、二の検討事項に簡単に言及するにとどめたい。
本報告が重点的な推進課題とした三者のうち、「俯瞰型研究プロジェクトの振興」を除き、「基礎研究の重視」と「教育の再構築」に関しては、運営審議会附置「企画委員会」の議を経て、できれば各々「臨時(特別)委員会」を設置し、その「機動的活用」によって、推進の具体策を緊急に審議・立案することが望ましい。また、「科学者の倫理と社会的責任」の問題は、今後頻繁に対応を迫られることが予想され、常時審議可能な態勢をとることが必要である。「俯瞰型研究」に関しては、すでに実施の段階にあり、今後、一層活発に、企画委員会による「課題の提起」を受けて、選定されたテーマごとにプロジェクト(予備的研究)の実施に当たる委員会が組織されることが期待される。なお、臨時(特別)委員会については「外部委員の参加」も積極的に考慮されてよい。「自己改革」(声明)には、「部横断組織としての常置委員会と臨時(特別)委員会」の委員構成に関しては、「適任者の配置を優先する視点に立って、任務の達成上必要がある場合には、会員でない委員を積極的に加える」と書かれている。また情報の組織的な収集と機動的な発信のために、「広報室」の活躍も必要とされている。
一般に、従来の専門領域別の組織体制を、学際的・部横断的な研究活動に適合するように工夫し改めることが、日本学術会議の社会的機能を強化する観点からも、これからの検討課題である。研究連絡委員会を改編して、領域別研連や課題別研連のほか、部横断的な広域的・学際的活動に対応する「広域型課題別研連」を設置したり、人文科学部門3部、自然科学部門4部からなる現行の7部制(「専門部」制)に加えて、部横断的な「複合部門」を新設して若干の「複合部」を併置するのも一案であろう。なお、1997年5月、将来計画委員会は「第125回総会への提案」のなかで、「現行の7部制が一種の縦割り構造として働くことのないよう配慮し、日本学術会議としての一体感を醸成することが重要である。このため、部は会員のいわば本籍とし、各部横断的な活動を促進するように工夫を凝らすことが特に必要である」と指摘している。
これと関連して、日本学術会議法の改正を前提すれば、全ての会員が学協会という専門領域を根拠とする縦割り組織で推薦された者のなかから選ばれるという現行の「会員選出方法」を変更して、定員の一部を、領域を超えて活躍する科学者-そしてまた女性科学者等-のなかから選ぶ制度を工夫することも、選択肢の一つになる。
日本学術会議の「財政と人的支援体制」の充実など、社会的役割を高めるために不可欠で困難な問題も存在するが、この報告では触れられない。
終に、日本学術会議が全国の科学者の代表機関として果たさなければならない、なお一つの重要な社会的責務、すなわち「全国的な規模で新しい研究・教育体制を実現するための支援体制」の構築について一言する。「新しい学術の在り方」と「学術と社会の新しい在り方」の構築は、日本の学術全体の課題である。日本学術会議は自ら率先して「学問の自由」の在り方を問い、社会に開かれた「負託自治」の理念に立って、自己の審議研究体制を改革し、現代の複雑で困難な課題の解決に立ち向かうため、専門化し細分化した学問領域の垣根を超えて、総合的・俯瞰的な視点を重視する新しい研究様式を提唱した。それはまた「知の衰退」と対峙する「総合的な学習」、そうした俯瞰型への教育様式の転換にも通じている。しかし、そうした「自己改革」だけでは、日本学術会議はその役割を十全に果たしたとはいい難い。わが国の科学者の「代表機関」として、全国の大学等の研究・教育機関が現代における「学術の社会的役割」に覚醒し、それぞれに適した研究・教育体制を彫琢する、その努力を支援することも、日本学術会議の重要な責務である。
日本の場合、戦前の「国家の大学」へのヒストリシスもあって大学の社会的役割には消極的で、学術の総合性への関心も稀薄だった。負託自治の理念と学術の「実践的専門化」(「理論的総合化」)を妨げない柔軟な研究・教育組織の構築は、今なお困難な課題である。閉鎖的な「講座制」や硬直した「学部自治」の残影が大学における領域変更の規制緩和を遅らせ、「学術全体を俯瞰的に見る」視点を妨げてきたのである。
研究・教育の現場からは、個別大学では「利害や予算が絡み」「総合的視点」に弱いため、たとえば総合社会科学大学院を構想しても「ほとんど注目されるに至らなかった」といった「経験」が聞こえてくる。しかも、そうした苦境のなかから逆に、「理念を明確にし、それを達成する研究組織を具体的に工夫する提案を学術会議が行なうことで、やがて個別の大学や研究機関での変革が可能になる」という、日本学術会議への励ましの一節が添えられているのである。-日本学術会議は専門領域に基礎を置きながらも領域に囚われず、一歩離れた立場から学術全体を俯瞰する立場にある。それだからこそ、日本学術会議は、その自己改革が「やがて」個別大学の変革を可能にするという真摯なエールに満足することなく、科学者の「代表機関」として、「俯瞰型」研究・教育体制や「負託自治」の確立に向けての諸大学・諸領域での多様な改革の試みに関して、改革に対する制度的障害を除去し、改革の自律的な意欲を支援するように、国の学術政策・教育政策に適切な提言を惜しむべきでない。また、現場との交流を深めつつ、直接・間接、必要な助言を試みることも、日本学術会議の任務である。この責任を果すために、学術会議は有効で適切な支援体制を組織することが望まれる。
【参照文献】
「附属資料」所収の個別論文は略。また新聞記事・社説・論壇類も略。署名入りの論壇時評等の場合、原則として本文の引用箇所にカッコで執筆者を記してある。
○活動計画・自己改革関係
日本学術会議「第17期の活動計画(申合せ)」(1997/10/22)『学術の動向』1997/12
吉川弘之「日本学術会議第17期活動計画作成に際しての会長所感」同上
同「俯瞰型研究プロジェクトの推進と総合的な科学技術政策の樹立に向けて」99/1/20
同「『俯瞰型研究プロジェクト』についての説明(私案)」同日
日本学術会議「日本学術会議の自己改革について(声明)」(99/10/27)、同「日本学術会議の位置付けに関する見解(声明)」(同日) 『学術の動向』99/12
○政府文書・審議会答申等
学術審議会「21世紀を展望した学術研究の総合的推進方策について(答申)」92/7
科学技術会議「科学技術基本計画について(答申)」96/6
学術審議会「21世紀に向けての研究者の養成・確保について(建議)」96/7/29
大学審議会「平成12年度以降の高等教育の将来構想について(答申)」96/11
文部省「教育改革プログラム」97/1(97/8改訂)
科学技術会議「国の研究開発全般に共通する評価の…在り方について…意見」97/7
学術審議会「学術研究における評価の在り方について(建議)」97/12
大学審議会「21世紀の大学像と今後の改革方策について(答申)」98/10/26
技術同友会「日本産業システムの変化から見た民間研究開発のあり方(提言)」98/12
○日本学術会議・委員会等報告
第3常置委員会報告「学術の動向とパラダイムの転換」97/6
日本学術会議・環境庁国立環境研究所主催「IGBPシンポジウム:21世紀へ向けての地球環境研究のあり方(報告書)」98/2/16
第3常置委員会報告「新たなる研究理念を求めて」99/4/12
第2常置委員会報告「大学問題-危機とその打開への道-」00/1/17
○第1章・第2章関係
J.G.フィヒテ(宮崎洋三訳)『学者の使命・学者の本質』[1794-1811]岩波文庫1942
藤井かよ『大学“象牙の塔”の虚像と実像』丸善1997
高柳信一「学問の自由と大学の自治」、山崎真秀「戦前日本における『学問の自由』」東京大学社会科学研究所編『基本的人権の研究 4』1968
H.パッシン(国弘正雄訳)『日本近代化と教育』サイマル出版会1969
島田雄次郎『大学とヒューマニズム』勁草書房1970
『大学の使命』(『教育法』1997年7月臨時増刊号)
OECD調査団報告(文部省訳)『日本の社会科学政策』日本学術振興会1978
大学基準協会大学院問題研究委員会報告『大学院の諸問題と改革の方向』1993
関口尚志「大学評価の歴史的・文化的基礎」 大学基準協会『会報』94/4
『財界の21世紀戦略と大学』 高等教育政策研究所東京センター94/7
国際シンポシウム『Crisis & Reorientation〈21世紀の大学の役割〉』筑波大学1995
関正夫『日本の大学教育の現状と課題』広島大学 大学教育センター1995
同「現代社会における大学の理念と役割を考える」『全大教時報』95/8
吉川弘之「21世紀における国立大学」国立大学協会『文化学術立国を目指して-国立大学は訴える-』95/1
青木宗也・示村悦二郎編『大学改革を探る』大学基準協会1996
鳥居泰彦編『学術研究の動向と大学』大学基準協会1999
村上陽一郎「科学・技術と社会」「学術の動向』99/11
吉川弘之「科学者の倫理」同誌97/9
同「科学者像の変革の方向を探る」同誌99/10
マックス・ウェーバー(富永・立野訳)『社会科学方法論』[1904]岩波文庫1952
同(中村貞二訳)「社会学ならびに経済学における“価値自由”の意味」『山口経済学雑誌』17/5・6,18/1,18/2,18/3
同(尾高邦雄訳)『職業としての学問』[1919]岩波文庫1936
潮木守一「上山安敏著『ウェーバーとその社会』(そのドイツ大学史研究への貢献)」『社会科学の方法』78/9
大林信治『マックス・ウェーバーと同時代人たち』岩波書店1993年
ヴォルフガング・シュルフター(住谷・樋口訳)『価値自由と責任倫理』未来社1984
○第3章関係
ユルゲン・ハーバーマス(長谷川宏訳)『イデオロギーとしての技術と科学』[1968]紀伊国屋書店1970
山内恭彦編『現代科学の方法-自然・人間・社会の認識-』日本放送出版協会1971
竹内啓・広重徹『転機にたつ科学-近代科学の成り立ちとゆくえ-』中公新書1971
マイケル・ギボンズ編著(小林信一訳)『現代社会と知の創造』丸善ライブラリー1997
松本三和夫『科学技術社会学の理論』木鐸社1998
寄本勝美「政策の形成と研究者の立場」『書斎の窓』97/12
『社会科学の現場』(岩波講座『社会科学の方法』4)1993
船橋晴俊ほか編『巨大地域開発の構想と帰結』東京大学出版会1998
船橋晴俊・飯島伸子編『環境』(『講座社会学』12)同1998
「特集 企業が変わる法化社会」『法律文化』98/1
「特集 ライフスタイルの転換と新しい倫理」『学術の動向』98/10
○第4章関係
関口尚志「経済大国と談合的文化」『学術の動向』98/1
和田昭允「“しかし、応用研究のみを行うと退廃する”」同誌98/4
吉川弘之「俯瞰型研究プロジェクト」同誌99/1
M.Matsumoto, The 'Japan Problem' in Science
and Technology and Basic Research as a Culture,
in : AI & Society, 1999/4,pp.4-21
黒川清「あまり知りたくない辛口『日本の研究とその評価』」『学術の動向』2000/5
トク・ベルツ編(菅沼龍太郎訳)『ベルツの日記』岩波書店1979
風間晴子「国際比較から見た日本の『知の営み』の危機」『大学の物理教育』98/2
立花隆「20世紀-知の爆発-」「文藝春秋』99/2
薩摩順吉「大学における数学教育の現場から」『UP』99/6
山本真一「科学・技術と社会-教育論の立場から」『学術の動向』99/11
大山道廣「科学技術離れの経済分析」同上
加藤洋治「文系・理系・教養・教育」同上
山崎正和「現代の教養をめぐって」『学士会会報』99/3
飯島宗一「日本の高等教育を考える」同誌『講演特集号』99/11
村上淳一「『司法制度改革・法学教育改革』管見」『UP』99/11
江里口良治「『宇宙地球科学』の講義と文科系学生」同上
小玉重夫「総合学科と総合学習-その歴史的・社会的文脈に着目して」『教育』608号
レオ W.H. タン「明日の科学者を育てる」『学術の動向』2000/3
○第5章関係
『日本学術会議50年史』日本学術会議99/3
伊藤正男「日本学術会議とは何か」『学術の動向』97/8
金岡祐一「日本学術会議の第三世代」同98/7
川田侃『国際政治経済研究』東京書籍1998 (「『日本学術会議』20年-専門領域の交流図り、新しい研究体制の確立を-」1968/4;「開会の-AASSREC10回川崎大会に当たって」93/9;「アジアにおける学術の発展のために-第1回アジア学術会議の開催に当たって[基調報告]-」93/11などを収録)
田中敏弘「『俯瞰型研究プロジェクト』と学術会議改革について」『学術の動向』99/8
【附属文書】
報告に関連した参考資料として、ここには、本特別委員会の委員や、委員外の会員、会員外の有識者に依頼して、21編の論文を収録した。とくに、日本学術会議50年史編集室長であられた加藤幸三郎会員には『日本学術会議50年史』からみた「日本学術会議の社会的役割」について、20世紀の学術と新しい科学の形態・方法特別委員会委員長の竹内啓会員には「新しい科学論の挑戦」について、また法政大学の武藤博己教授には「政策過程研究の課題と方法」について、それぞれ特別寄稿をお願いした。本委員会委員の論文には、「学問の理論性と社会性」、「科学者の社会的責任」、「学術の社会的役割と教育」など、個別学問領域を超えた普遍的な主題について、報告を敷衍したり、やや異なった角度から論じたものと、報告では詳細に立ち入ることの出来なかった個別領域を中心に学術の社会的貢献を論じたものが存在する。後者の場合、共通の問題意識として、学術と社会の新しい関係の構築にむけて、参考となる具体的なケース・スタディをできるだけ折り込むこと、その際、領域(各部)固有の問題のほか、可能ならば関連領域にまたがる問題も視野に置いて、学術の在り方、社会の在り方、また、とくに、「俯瞰型研究」の必要と「行動規範の根拠」の提供をめぐる問題について言及するように配慮することが申し合わされた。これらの参考資料は執筆者の責任で書かれているが、原則として執筆以前に委員会に付議されて質疑・応答があり、完成原稿は全委員に配布された。
(学術の社会的役割特別委員会委員長 関口尚志)
Copyright 2002 SCIENCE COUNCIL OF JAPAN