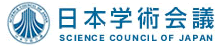公開講演会・シンポジウム報告
宇宙と生命、そして人間を考える-人類の未来のために
■プログラム(PDF)
■イントロダクション(笹月 健彦)
■講演要旨
生命を生んだ宇宙の拡がり(海部 宣男)
原始生命から人類までの進化戦略(長谷川 眞理子)
脳と心を科学する(宮下 保司)
免疫システムによる自と他の認識-脳への問いかけ(笹月 健彦)
自己認識する動物-哲学から見た人間-(野家 啓一)
日本学術会議主催公開講演会 「宇宙と生命、そして人間を考える-人類の未来のために」
■イントロダクション
本日は「宇宙と生命、そして人間を考える --人類の未来のために」を企画致しまし たところ、沢山の方々にご参加頂きまして誠に有り難うございます。
企画の責任者と致しまして、本講演会の主旨をご説明申し上げます。
現代の人類が抱えている数々の問題、たとえば地球環境の破壊、人口/食料問題、エネ ルギー問題、紛争、経済、医療、教育問題、あるいは人間社会の未来へ向かっての理想の喪失、倫理感の鈍磨など、枚挙にいとまがありません。
これらの問題一つ一つについて深く検討することは勿論重要でありますが、私はこれらの問題には共通の解決すべき課題があり、それの検証と克服を目指すことなしには、抜本的な解決は難しいと考えております。
何が問題なのかと申しますと、
1. 人間が大脳を進化させ、それを用いた全ての人間活動の結果が今日の多くの課題の根 源にあると思います。
2. しかもその人間活動のエネルギーのvector は、遠い将来の人類の未来を見通すのでは なく、個の保存、個のcomforts(安楽安寧)を追求する方向で働いている。それは種 の保存、種のcomforts とは必ずしも相容れるものではない。
3. この場合の人間活動の中心は科学技術であります。科学技術の持つ光と影、とよく言 われますが、私たちは科学・技術の進展を止めることは出来ない。それは科学技術の光の部分を必要としているからだけではなく、本来ヒトはneophilia(好奇心に富んだ、 新し物好き)であることから、止めることが出来ないのです。
もしそうだとすると、科学の成果・技術の成果の応用に際して、(1)原始生命から独特 の戦略で進化した人類という生物の理解、(2)同じ生物の中でも特に大脳を進化させた人 間の総合的理解、という二つの理解に基づいた新しい知の構築が必要であると思います。
特に最近の科学と科学技術の進歩を眺める時、その進歩を時間軸で比べてみますと、19世紀は100年単位で歯車が一つ動いたのに比して、20世紀では10年単位、21世紀は1年単位となったと思います。このような現代において、今こそ人文学(ヒューマニティー)と科学(サイエンス)を真に融合させるための意識的な努力が必要であると思います。
元々、science はphilosophy から分化してきたものであり、これをもう一度元の鞘に戻 すといっても、もう戻れないと思います。私は、新しいhumanities & sciences とでもいうべき知の領域の創出が必要であると痛感致しております。
今回この公開講演会を企画するに当たって心したことは、
1.まず第一に、皆様方に答を提供するのではなく、現在の科学の現状をお伝えし、問題を共に考える
2.この講演会を、新しい知の領域を模索するきっかけにしたい
3.そしてそのためには、継続可能な-sustainableな-方策を検討するきっかけとする
4.みずみずしい好奇心と未来へ向かった高い理想を掲げている若い人達の参画を促すということでありました。特に最後の点に関しましては、いくつかの努力を致しました。多くの方々のご協力を得て、ここから拝見しますと、若い方々の姿が何人も見うけられま すので、大変嬉しく存じます。
本日は、日頃の時計を外して、果てしない宇宙の拡がり、36億年という進化の時間、2の10兆乗といわれる脳の多様な機能状態、そして人間そのものについて、それぞれ第一線でご活躍中の方々のお話に存分に身をゆだね、春の土曜の午後のひとときをお楽しみくださるようお願い致しまして、イントロダクションに代えさせて頂きます。
笹月 健彦(国立国際医療センター総長)
生命を生んだ宇宙の拡がり 海部 宣男(自然科学機構・国立天文台 名誉教授)
1.無数に存在する太陽系外惑星
太陽以外の恒星をまわる惑星系(太陽系外惑星系)が、すでに200個以上見つかっている。 太陽型の恒星の5%以上が惑星を持つので、銀河系の中の惑星系は1億を越える計算になる。膨張宇宙全体では、それこそ無数であろう。
恒星は遠く、それをまわる惑星は小さく暗いため、まだ直接は観測できない。主な観測手 段は、ドップラー法である。中心の恒星(太陽)は、周りをまわる惑星の重力でほんの少し振られることを利用し、中心星の光を高精度で分光して、わずかな円運動のためドップ ラー効果で生じる光の波長の周期的なずれを検出する。
観測精度の制限上、太陽系外惑星は質量が大きくて中心星に近いものから見つかる。また、 比較的近くの恒星でしか観測が進んでいない。それでも、宇宙の惑星系についての理解は、めざましく進んだ。これまで人類にとって唯一の惑星系だったわが太陽系の、宇宙での位 置づけがわかりはじめたのである。
2.宇宙における太陽系と地球の位置
地球は比較的小さな岩石主体の惑星で、このサイズの惑星の検出はまだできていない。し かし惑星が恒星の前面を通過する現象(トランジット)をとらえる宇宙空間からの観測で、ここ数年以内に地球サイズの惑星はたくさん見つかると思われる。これまでの観測から、 質量が小さいほど惑星の数が急激に増加する傾向にあるからである。地球のような小さな岩石惑星は非常に多いだろうことは、十分予測される。
太陽系外惑星では、つぶれた楕円軌道をまわる惑星が非常に多いという驚きの発見もあっ た。諸惑星が折り目正しく円軌道をまわるわが太陽系は、特別なのかという疑問も沸く。だがこの発見から、質量の大きな惑星が複数存在する場合には、惑星系の形成後大きな力 学的不安定が起きることが、わかってきた。これに対し大惑星が少ない太陽系の場合のシミュレーション計算では力学的不安定は起こらず、惑星は円軌道をほぼ維持して百億年以 上まわり続ける。観測による確認はこれからだが、太陽系のような小さな惑星の系は、安定に存在するらしい。
生物の発生に必要とされる、水はどうか。恒星・惑星を生み出す母体である宇宙の暗黒星雲は、砂粒や水の氷などの固体微粒子を多量に含み、多彩な有機分子を内部で生成している。暗黒星雲が自己重力で収縮し分別凝縮して生まれる惑星には、砂成分(大地)、水成分 (海)、有機分子(生命材料)が普遍的に備わることになる。地球はむしろ、生成過程で水をかなり失った惑星と位置づけられる。
3.生物の存在も普遍的であろうという予測
こうした観測から、地球的な小型岩石惑星がどの程度普遍的かを、大雑把に推定できる。 生物を育み得る地球的惑星を持つ太陽型恒星の数は、少なめに見ても天の川銀河系で100万個程度と推定される。「第二の地球」は、たくさんあるらしい。
中心星(太陽)からの惑星の距離は、放射による気温と海の維持など、生物にとって重要 なファクターとなる。惑星系中で生物存在が可能とされる領域を表面に液体の水が存在できる領域で代表させ、「ハビタブル・ゾーン」と呼ぶ。太陽系では地球はもちろんOK だが、火星、金星もボーダーにある。生命の発生・維持には、このほか惑星の大きさ、表面温度維持のバランスなどがかかわる。
星間分子雲や太陽系外惑星形成、彗星の観測などから、宇宙には炭素の多彩な反応性を基 礎とした有機物環境が広く存在することも、はっきりしてきた。生物を育む惑星は相当たくさんあるだろうという予測は、いま天文研究者の共通認識になりつつある。実際に生物 を育む惑星を確認するための計画も、さかんに検討されている。
4.宇宙生物・文明探査と地球生物・人類文明
21世紀は、宇宙生物探査の時代となるだろう。可視光・赤外線・電波の観測技術に基づけば、遅くも21世紀前半には、生命がほぼ確実に存在する惑星が見えてくる可能性が高い。さらに宇宙の「地球的な文明」の電波探査(通信ではない)も進み、少なくとも宇宙の文明の存在数について、科学的な意味を持つ上限値が得られる可能性がある。それは人類自身の文明についても、ある種のインパクトを与えるかもしれない。
私たちが宇宙の中でどのような存在なのかを知ることは、地球生物の長い進化の過程で発生した人類と文明とを問い直すことでもある。私たち人類はいま、物質の根源、宇宙・地球の歴史、生物の進化としくみ、人間の脳と行動までを深く問い、多様な視点から「私たちとは何か」を考えようとしている。
時を同じくして、かつ重大なことに、私たちは文明の特性である倍々ゲームの生産・消費の増大が、生態系や文明自体を危機に陥れつつあるのではないかという認識を、共有しはじめるに至った。これは、単なる歴史上の偶然ではない。科学を含む人類文明の活動が、そのような総合的認識を抱くことができる到達点(曲がり角と言うべきか)にさしかかっていることを、示しているであろう。人は死ぬことを知っている動物だが、現代はその社会=文明の寿命を意識するようになった時代ということもできよう。
いまここにいる私たち人類とは、どういう存在か。それを理解することは同時に、文明の危機という曲がり角の先にどんな展望が開けるかを、知ることでもあるだろう。それを見通してゆくのも、人類を人類たらしめた英知と科学の役割であると、考えたい。

海部 宣男(かいふ のりお)1943年生。天文学者。放送大学教授・国立天文台名誉教授、理学博士。日本学術会議会員(第三部部長)。1966年東京大学基礎科学科卒業、同大学院天文学専門課程を経て同大助手,同大助教授,国立天文台教授を経て,2000年から2006年まで国立天文台台長、1997年から2003年まで国際天文学連合副会長を務めた。専門は電波天文学、赤外線天文学。長野県野辺山の口径45m電波望遠鏡,およびハワイの口径8.2mすばる望遠鏡の建設などをリード。星間物質,星と惑星の形成を研究し,ミリ波天文学の開拓で1987年度仁科記念賞,星間物質の研究で1998年度日本学士院賞を受賞。宇宙と人間の関わりをさまざまな角度から追い,科学の普及にも力を注ぐ。『宇宙マンガシリーズ』『宇宙の謎はどこまで解けたか』(ともに新日本出版)、『宇宙をうたう』(中公新書)、『すばる望遠鏡の宇宙』(岩波新書カラー版)、『天文歳時記』(角川選書)など一般向け著書多数
原始生命から人類までの進化戦略 長谷川 眞理子(総合研究大学院大学・葉山高等研究センター 教授)
この地球上に生命が誕生したのは、およそ38 億年前と考えられている。最初の生命がどのようにして生じたのか、どんな生物だったのか、詳しいことはわからない。いずれにせよ、最初の生物は単細胞だった。それがずっと続いてから、20億年ほど前に多細胞生物が生まれた。そして、およそ6億年前のカンブリア紀の大爆発以降、多くの大型生物が繁栄している。
現在、地球上に存在する生物で、名前がつけられているものの総数は、およそ175万種である。しかし、もちろん全種が調べられているわけではなく、今でも大量に新種が発見されている。全部が記載されたときにいったい何種になるのか、それは誰もわからない。一方で、現在の地球環境の破壊により、18分に1種の割合で絶滅が起こっているという試算もある。
「生物」とはなんだろうか? 膜につつまれた細胞という構造を持っており、代謝を行い、成長し、自分と同じようなものを複製する存在。熱力学の第二法則に(表面上)反して、時間を経てもつねに秩序ある構造を保ち続けている存在。過去に絶滅したものも含めれば、何億種とも言われるほど多様な生命の形態全部に対し、「進化戦略」を抽出しようとするのはたいへんに難しい。
しかし、38億年の生命の進化史から、生物の戦略として、メタ的に大きな共通パターンを抽出することができるだろうか? その一つは、複雑化に向かう方向である。
もちろん、進化は場当たり的に起こり、目的や計画性など何もないのだが、生命の歴史 を見ると、時間とともに複雑さを増す方向に向かう傾向が見てとれる。一旦進化で作られた複雑な構造が、のちに喪失されたり、単純化したりすることもあり、それは退化と呼ばれる。そのようなことも起こってきたが、一般的傾向は複雑化である。
もう一つは、その複雑化が実現してしく仕組みとしての、「共生」である。原核生物の遺伝子は、核というものに包まれていない。真核生物には核があり、遺伝子は、染色体上に並んでいる。異なる遺伝子が一緒になって、染色体と核という新しい「共生」の集合体を作って、あらたな道が開けた。真核生物はさらに、ミトコンドリア、葉緑体などと細胞内共生を行うことによって発展していった。多細胞生物ができたとき、また新たな「共生」の集合体が生まれた。
そして、互いに情報を交換しながら個体が集まって作る、社会が生まれ、生物には、また新たな「共生」の姿が加わった。植物にも社会はあるが、神経系の発達した動物の社会 はきわめておもしろい。その中で、ことさらに高度な分業と共同作業を発達させて大繁栄 しているのが、アリ、シロアリなどの社会性昆虫と、人間である。
社会性昆虫と呼ばれる昆虫たちは、大きな巣を構築したり、餌を探して蓄えたり、敵を撃退したり、子どもを育てたりするなど、さまざまな仕事を分業している。分業の種類ごとにからだの形さえ変化してしまうこともある。こうして何十匹、何百匹、ときには何百万匹もが共同作業することにより、1匹ではできないことを達成している。アリ類は世界中に分布し、自分たちのからだの何万倍という大きさの構築物を作り、生息地の環境を変 化させ、生物量では人間全体の生物量にも匹敵する。
人間も、世界中に分布し、世界の環境を改変し(破壊し)、今や人口が65億にもなるほどに繁栄している。その成功のカギは、やはり分業と共同作業にある。人間も、みんなで 協力し、一人ではできないことを次々に成し遂げてきた。しかし、社会性昆虫で分業と共同作業を成り立たせている原理と、人間でのそれとは非常に異なる。社会性昆虫の分業と 共同作業は、きわめて単純なメカニズムで動く個体どうしの自己組織化によって、驚くほど複雑な社会が生み出されているようである。
一方、人間の分業と共同作業は、高度な脳機能を備えた個体どうしが、他者の心を理解 し、言語その他の方法でコミュニケーションを行い、さまざまな概念も伝え、共感と信頼を介した相互扶助関係を築くことで行われている。そして、「文化」という形で蓄積された 知識や物体が世代を超えて伝わっていくことにより、他の生物に類を見ない強力な繁栄を達成している。
人類の進化史を振り返ると、人類の生業形態、社会の構造も、単純なものから徐々に複雑化し、分業の度合いが深まってきた。機能ごとにコンパートメント化し、専門化し、分業のネットワークを複雑化する方向に向くのは、生命体も文化も同じであるのだろう。 この観点から、人類の未来について、少しばかり考えてみたい。
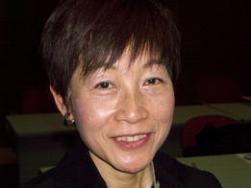
長谷川 眞理子(はせがわ まりこ)総合研究大学院大学先導科学研究科教授専攻分野「行動生態学、進化生物学」、昭和51年3月 東京大学理学部生物学科卒、昭和58年3月 東京大学大学院理学系研究科人類学専攻博士課程修了、昭和55年から2年間タンザニア野生動物局に勤務。昭和58年4月 東京大学理学部人類学教室助手、専修大学助教授、教授、Yale大学人類学部客員準教授、早稲田大学政治経済学部教授を経て、平成18年より総合研究大学院大学教授。平成19年より先導科学研究科生命共生体進化学専攻長平成20年より日本進化学会会長。野生のチンパンジー、イギリスのダマジカ、野生ヒツジ、スリランカのクジャクなどの研究を行ってきた。最近は人間の進化と適応の研究を行なっている。著書:「クジャクの雄はなぜ美しい?増補改訂版」(紀伊国屋書店)、「進化とは何だろうか」(岩波ジュニア新書)、「ダーウィンの足跡を訪ねて」(集英社)など。訳書:「人間の進化と性淘汰I, II(チャールズ・ダーウィン著)」(文一総合出版)、「ダーウィンの種の起源」(ジャネット・ブラウン著)(ポプラ社)など
脳と心を科学する 宮下 保司(東京大学医学系研究科教授)
今日、「脳の科学」も「こころの科学」も急速な進歩を遂げつつあります。イメージング を基礎とした「脳もこころも扱う」と豪語する科学もあらわれました。現在の科学者達は、一昔前の科学者達とは異なって、「脳とこころ」を二元論的に考える必要性(悪夢?)にあまり悩まされなくなったようにみえます。その背景には、「脳の中の神経細胞群(ニューロン群)の活動を実験的に操作することによって、主観的認知を『因果的に』操作しうる」ことを示す実験的研究の成果が広く知られるようになったことが挙げられるかもしれません。一昔前の脳科学は、「こころ」側を独立変数として、「脳」の側に起こる変化を精密に計測することには自信をもっていました。今やその逆方向、「脳」側を独立変数として、「こころ」の側に起こる変化を計測することも可能である、ということになりました。こうした双方向的な実験操作で行き来が可能な世界は、たとえ記述言語のレベルが異なっているとしても、全く別の世界であるとは感じられなくなった、ということでしょうか。よく知られたアナロジーを借りれば、ちょうど物理学の世界で、同じ気体や液体の性質が、一方では、熱力学的に圧力や体積やエントロピーといった言語で記述されるのに対し、他方では統計力学的に粒子数や速度分布や分配関数といった言語で記述されることに何の違和感も感じないのと同様に、ということでしょうか。
確かに、「こころ」という言葉は沢山の微妙なニュアンスを含んでいます。ことに日本語で「こころ」という場合は非常に多義的で、いろいろな文脈・意味あいで使われます。米国の友人と話してみても、英語表現には、heartやsoul、spiritやらmindやら、いろいろあります。それを全部十把一からげにして「こころ」と呼んで良いものか?宗教的背景が影を落としているのは明白なのでますます難しい。しかし、ここでも多くの科学者の方法論は単純で、取り敢えず扱えそうな具体例――ある種のモデルと呼ぶべきもの――の解析からはじめます。そうした具体例がどこまで一般化できる射程を持っているかは、何十年かの歴史の審判に任せておけばよい、という楽天主義です。最近、神経倫理学(neuroethics)という言葉が、従来のEthics of neuroscienceだけではなくNeuroscience of ethicsをも意味する状況が増えてきたのは、倫理的判断ethical decisionをする際の脳活動についての研究が可能であることが認知されてきたせいでしょう。科学的方法論で扱える「こころ」の範囲がさらに広がってきた実例です。
今回の講演会では、議論の主な対象を絞り、「こころ」のある側面――mindに近いでしょうか――を採り上げて、脳科学の現在の到達点についてお話しようと思います。問題の切り口は次のようになります。実際に眼の前にあるものを見るときと、眼の前にないものを想像する、イメージする――これを英語では「Seeing with mind’s eye」つまり「心の眼で見る」というのですが――この二つの場合で脳の働き方がどう似通っていて、どのように違うのか。つまり実際に「見る」ときと、「心の眼で見る」ときとでは、脳の働きのどんなところが同じで、どこがどう異なっているのか。現在の結論から先に申し上げますと、イメージを創る力の根本は脳の高次視覚領野から低次の領野へと情報を送り返す「逆向性」 の情報の流れ(backward signal)――トップダウンtop-down 信号とも呼ばれます――にあります。他方、実在するものを見る通常の視覚では、眼の網膜から脳の高次視覚野へ向かう「順向性」の情報の流れ(forward signal)――ボトムアップbottom - up信号とも呼ばれます――が主役となっています。まずこの順向性の情報処理を少し詳しく見てみましょう。ヒトの網膜もテレビカメラも、その最初の過程は似ています:二次元面に敷き詰められた多数の光受容素子が、飛んでくる光量子を電気信号に変換し、外の世界の明るさについて の二次元マップをつくります。しかし、ヒトの脳はこの情報を自在に使います。コーヒーカップは、どんな角度から見ても、どんなに遠くにあっても、大きくても小さくても、コーヒーカップだと判かります。単純な金属のカップも、装飾過多の陶磁器のカップも、やはりコーヒーカップに見えます。こうした情報処理を脳は易々とこなしますが、コンピューターにやらせてみれば如何に難しいか直ぐに判明します。秘密は、この情報処理過程を 媒介する手段として脳が色々な「世界の脳内表現( または内部表現internal representation)」を形成することにあります。脳の高次視覚中枢には種々の対象物の脳内表現が作られているわけです。講演中でご紹介しますように、「脳内表現」は脳の多数の神 経細胞と神経回路(遺伝情報と生後の学習の産物!)で造られるわけですから、外の世界 の対象とはズレた知覚が生ずることも不思議ではありません――錯視と呼ばれる一群の知覚はその例です。では、「逆向性」の情報処理はどのように行われるのでしょうか。トップダウン信号も「世界の脳内表現」を利用しているのでしょうか。トップダウン信号の内容を具体的に解析することができるのでしょうか。講演の中でスライドを使いながらお話したいと思います。

宮下 保司(みやした やすし)東京大学医学系研究科教授(生理学)、東京大学理学系研究科教授(生物物理学)。1972東京大学理学部卒業、1978東京大学医学系大学院博士課程修了、1989東京大学医学部教授、1996東京大学理学系研究科教授併任。2003慶応医学賞、2004朝日賞、2007日本学士院賞"Image,Language,Brain", MIT Press (2000)、 "Cognition,Computation,Consciousness", Oxford University Press (1997).、「脳から心へ」岩波書店(1995)
免疫システムによる自と他の認識-脳への問いかけ 笹月 健彦(国立国際医療センター 総長)
I. はじめに
自己を認識すること、認識している自己を観察すること、そして死の必然を認識するこ とは、人類を他の生物と著しく際だたせている特徴である。自己とは何か、そしてそれを自己と認識しているものは何か。他とは何か、そしてそれを他と認識しているものは何か。
高度に脳を進化させた人類は、それを知りたいと願う。知に対する渇望である。近年著しく進展した分子生物学など自然科学の知識と技術は、この疑問に対する限りない挑戦にとって、有効な戦略たり得るであろうか。
人類は、ウイルスや細菌など病原体を他と認識し、これらを排除して死から免れる。このような免疫システムは、他人から移植された心臓、肺、腎臓などを他と認識し、免疫反応によって拒絶する。ところが、自分の臓器を治療のため一度体外へ取り出した後、元に戻しても拒絶反応を受けることはない。このことから、免疫システムは自と他を明確に識別していることがわかる。
生体の中でも特に高次で複雑なシステムの一つとして、1016 に及ぶ多様性を持つ免疫システムは、どのようにして自と他を識別しているのであろうか。この問いに対しては、分子細胞生物学、遺伝子工学、発生工学など、科学の知識と技術を駆使した戦略が功を奏し、その大綱についてはほぼ解答を手にしたように見える。
このことは、ひるがえって人間における自と他、そしてその認識機構について考察する上で、どのような意味を持ち得るであろうか。
II.自と他の認識に関する免疫システムから脳への問いかけ
免疫システムは膨大な数の病原体に対応して、高度の多様性(1016)を創り出した。それは、遺伝子の再編成でまかなっている。
他方、自と他を認識し、識別している我々の脳の多様性は2の1兆乗(10の3,000億乗)とも言われる。この膨大な多様性創出のメカニズムは、109個のニューロンと、各ニューロンの103個のシナプスとが創り出すネットワークのon-off状況で決まると考えられる。このように、多様性創出のメカニズムは、免疫システムと脳とではまったく異なっている。このことは、高度の多様性に富むこれら二つの複雑なシステムが用いる“自”と“他”の認識機構も異なっていることを示唆する。
これら二つの認識システムは、多様性の創出機構だけでなく、構成している細胞群、分子群も勿論異なることから、認識機構の相違は当然であるが、それでもなお認識に関する概念的な共通点を探ることは意味を持つだろうか。すなわち、免疫システムによる自他認識に関する知見は、脳における自他認識のメカニズムを解明する概念としての糸口となり得るのであろうか。
以下が、免疫システムから脳への問いかけである。
免疫システムが認識する“自”はタンパク分子の複合体(自己のHLA分子と自己のペプチドが結合した複合体)であり、それを認識するのもタンパク分子(T細胞レセプター)である。
脳が認識する“自”は分子ではなくネットワークであろうが、それはいかにして形成されるのか。そして、それを自と認識する機構は何であろうか。
免疫システムで自を認識するT細胞は胸腺(Thymus)での選択を受けて出現する。自己認識できないT細胞は、胸腺で死滅する。すなわち、免疫システムはすべからく自を認識するT細胞で成り立っている。そして、これが他をも認識するのである。
脳が自や他を認識する機構はすべからく自を認識するもので成立しており、それが他をも認識するのであろうか。
免疫システムでは自が先天的に欠損していると、自己認識するT細胞は出現しない。し たがって、他を認識することも出来ず、ウイルス、細菌などの感染源を認識・排除出来ず、感染症に斃れる。
脳が認識する自が存在しなければ、自を認識する機構が成立せず、したがって他を認識することも出来ないのであろうか、そしてそれはなんらかの疾病をもたらすであろうか。
免疫システムは1016の多様性を持つが、自、他の認識は共にHLA分子による制約(拘束)を受けている。
脳における自、他の認識においても、何らかの制約(拘束)を受けているのであろうか。
免疫システムにおいては、自をあまりに強く認識するT細胞は、胸腺で死滅し排除される。この排除がうまくいかないと、リウマチ、バセドウ病、I型糖尿病、SLEなど様々な自己免疫疾患を発症する。
脳がなんらかの障害で“自”を強く認識しすぎると、自虐的な、自己過剰認識症候群とでもいうべき現象(疾病)が生じるのであろうか。
免疫システムにおいて、胸腺におけるT 細胞の教育(正と負の選択)を、HLA ではなく、 まったく別の分子に行わせると、正常では、無視されたT細胞として死滅していたはずのT細胞が、新しいその分子を認識して選択され、登場するかもしれない。すなわち、暗闇に 葬り去られていたT細胞レパートリーが陽の目を見て、まったく別の認識システムが構築される可能性がある。
脳における認識システムの構築にも、このような作業仮説が成り立つのであろうか。すなわち脳における認識において、“自”と認識されるシステムがあるとして、それに変異が起こると、“自”および“他”の認識がまったく別世界のものとなるのであろうか。“自他”の認識システムを何で教育するかで、まったく別の認識システムを構築することになるのであろうか。この仮説をさらに一歩進めると、統合失調症における“自”と“他”の認識の異変を考える時、統合失調症における主遺伝子を明らかにすることが出来たとしたら、これは“自”と認 識されるものの構築を支配しているかもしれず、“自”の理解の鍵を与えてくれるであろうか。
自らを“自”と認識し、かつ他人を“他”と認識する人間の脳は、この免疫遺伝学からの問いかけに、どのような考察を示してくれるのであろうか。
III. 免疫遺伝学からのメッセージ
免疫システムは1016に達する多様性を持っていることから、外来侵入物に対しては何に でも応答できる。しかし、応答するためにはその抗原に暴露されることが必須である。ただし一方では、HLAによる拘束があり、しかもHLA には高度の多型性があることから、同 じ抗原に暴露されても応答する人としない人が存在する。
脳における天文学的多様性に鑑み、外来刺激(教育)に対する応答性はどこまでも保証されているのであろうか。何かが拘束因子となるようなことがあるのだろうか。
免疫システムはウイルスに対してこれを排除すべく免疫応答をするが、そのことが逆に臓器を傷害し、応答したために死に到る場合もある。これは遺伝子レベルで決められている。
人間活動の何が、どこまで遺伝子に拘束されているのであろうか。 逆に、人間はどこまで遺伝子から自由であり得るのだろうか。
我は何か、何処から来て何処へ行こうとしているのであろうか。
 笹月 健彦(ささづき たけひこ)国立国際医療センター総長、1940年4月福岡生まれ。1968年3月九州大学医学部卒業後、1970年3月東京医科歯科大学大学院医学研究科内科専攻修了し医学博士号取得。1973年8月から3年間、米国スタンフォード大学へ留学。帰国後、免疫学や難治疾患研究、人類遺伝学を専門とし、東京医科歯科大学教授、のちに九州へ拠点を移し九州大学教授、さらに1990年4月には同大・生体防御医学研究所長就任、2001年4月に国立国際医療センター研究所長を併任し2004年4月に国立国際医療センター総長、現在に至る。1996年パリ市功労賞(フランス)、1999年日本医師会医学賞、2001年武田医学賞、2002年紫綬褒章、2003年Rose Payne賞(アメリカ)授賞。2005年10月日本学術会議第20期会員。
笹月 健彦(ささづき たけひこ)国立国際医療センター総長、1940年4月福岡生まれ。1968年3月九州大学医学部卒業後、1970年3月東京医科歯科大学大学院医学研究科内科専攻修了し医学博士号取得。1973年8月から3年間、米国スタンフォード大学へ留学。帰国後、免疫学や難治疾患研究、人類遺伝学を専門とし、東京医科歯科大学教授、のちに九州へ拠点を移し九州大学教授、さらに1990年4月には同大・生体防御医学研究所長就任、2001年4月に国立国際医療センター研究所長を併任し2004年4月に国立国際医療センター総長、現在に至る。1996年パリ市功労賞(フランス)、1999年日本医師会医学賞、2001年武田医学賞、2002年紫綬褒章、2003年Rose Payne賞(アメリカ)授賞。2005年10月日本学術会議第20期会員。
自己認識する動物―哲学から見た人間― 野家 啓一(東北大学副学長/大学院文学研究科教授)
1.人間性の危機
人間は自己認識を目指す動物、すなわち「人間とは何か?」あるいは「自分は何ものである のか?」と問わずにはいられない動物である。それゆえ人間は、古来、人間自身をさまざまに定義することを試みてきた。すなわち「理性的動物」をはじめ「羽のない二足動物(プラトン)」「ポリス的動物(アリストテレス)」「道具を作る動物(フランクリン)」「シンボルを操る動物(カッシーラー)」などである。
これらはすべて動物との「類と種差」によって人間を定義している。しかし、20 世紀後半に おける生命科学の進展は、ゲノム解析によって人間とチンパンジーのDNAが98%一致している ことを明らかにし、人間と動物との差異よりは連続性が浮き彫りにされている。他方で情報科 学や認知科学の発達は、人間の心をコンピュータと類比することによって、人間を「複雑な情報処理機械」と見なすにいたっている。つまり、人間と動物ないしは機械との差異は、いまや 「種類の差 (difference in kind)」であるよりは、「程度の差(difference in degree)」に すぎないと見なされている。その意味で、人間の自己認識は現在、動物と機械のあいだで揺れ 動き、一種の「アイデンティティ・クライシス」に陥っているのである。
2.鏡像段階:「自我」の成立
だが、人間が「自己」を認識する能力をもっていることは、人間を他の動物から区別する極 めて大きな特徴である。もちろん、「自己」は脳の特定の部位に局在しているわけでもなけれ ば、解剖によって取り出せるような実体でもない。それでは、人間はいかにして「自己」を認 識するのか。心理学や精神医学では、生後半年から一年半の乳幼児に「鏡像段階」(J.ラカン)と呼ばれる自我の成立に関わる独特の時期があることが知られている。具体的には、鏡を見て、 鏡の中の像が「自分」であることがわかる、そういう発達段階のことである。鏡に映った像を 見て積極的な反応をするのは人間の乳幼児だけであり、犬やチンパンジーには見られないことが報告されている。
鏡の中の像が自分の身体像であることを知るのはそれほど簡単なことではない。それは「鏡 の中の像は他人の目から見られた自分である」ことに気づくことだからである。つまり、自分の身体が統一性をもった物体であり、「自分は見るものであると同時に見られるものである」ことを自覚することが「自己の確立」の第一段階にほかならない。言い換えれば、自己の認識には自己を見る他者の眼差しが不可欠なのである。そのことは、自己認識がはじめから他者との社会関係の中に組み込まれており、他者認識と表裏一体のものであることを意味している。 多少もってまわった言い方をすれば、自己とは「他者の他者」なのである。
3.一人称「私」の文法
鏡像段階を経た幼児は、やがて3~4歳になると「僕」や「私」といった一人称を苦もなく 使うようになる。だが、この「私」という一人称は不思議な働きをもった言葉である。つまり、この言葉は「机」や「椅子」のような複数の対象を指す一般名詞でもなければ、「夏目漱石」や「アインシュタイン」のような唯一の対象を指す固有名詞でもない。「私」は自分自身しか指さないにもかかわらず、状況に応じて誰をも指すことができるのである。私が「私」と言うときとあなたが「私」というときとでは、異なる人物を指すにも関わらず、「私」という言葉の意味は同じでなければならない。その意味では、「私」という言葉の使用法を習得することはかなり複雑なことなのである。
「私」という一人称代名詞は「自己中心的」な言葉であるが、私は他人が「私」と言ったときにもその意味を理解することができる。つまり「私」は自己中心的であると同時に「脱中心的」な言葉なのであり、この自己中心化と脱中心化の二つの働きをともに理解しないと「私」という言葉は使うことができない。言い換えれば、「私」という一人称は、私の独自性や固有性を否定することによってはじめて、一般的に流通する言葉となるのである。そのことをJ.デリダは「私の死が、<私>という語を発するのに構造的に必要不可欠である」(『声と現象』)と述べている。いささか逆説的だが、人間は唯一の固有な私が消滅することによって、「私」という一人称で表現される「社会的な私」になるのである。
4.死へ臨む存在
人間は自己を認識するとともに、自己が「死すべき者」であることをも認識する。そして、 死を前にしたとき、それが他人に代替してもらうことのできない、私固有の出来事であることを自覚する。すなわち、死に直面した私は「社会的な私」から「かけがえのない私」あるいは 「代替不可能な固有の私」へと立ち戻るのである。ハイデガーは『存在と時間』のなかで、「死へ臨む存在」あるいは「終末へ臨む存在」を自覚することによって、人間はその「本来的全体 性」を取り戻すことができる、と述べたことがある。
そのことを「個」としての人間から「種」としての人間、すなわち「人類」へと拡張することも可能であろう。現在、人類は地球環境の変化という未曾有の危機に直面しており、「人類の滅亡」もまたありうべき事態として取りざたされている。しかし、京都議定書をはじめとす る地球温暖化対策は「国民国家」ないしは「国民経済」という壁に阻まれて、いっこうに進捗しない状況にある。だとすれば、先のハイデガーの言葉を、「滅亡に臨む存在」であることを自覚することによって、人類はその「本来的全体性」を取り戻すことができる、と言い直すこ とも可能であろう。すなわち、「人類の滅亡」を諸国家の現実的課題として引き受けることによって初めて、われわれは「人類」という抽象観念に「国家」を超えたリアリティを吹き込むことができるのである。その意味で、逆説的ではあるが、「人類の滅亡」をたじろがずに見据える眼差しを獲得することこそ、21世紀を生きるわれわれの唯一の「希望」であると言わねばならない。 当日配布資料(PDF)
 野家 啓一(のえ けいいち)東北大学副学長・大学院文学研究科教授、専攻分野:現代哲学、科学哲学、昭和24年仙台市生まれ、昭和46年東北大学理学部物理学科卒、昭和51年東京大学大学院理学系研究科科学史・科学基礎論専攻博士課程中退、昭和51年南山大学文学部助手、同講師、プリンストン大学客員研究員を経て、昭和56年東北大学助教授、平成3年同教授。同大学院文学研究科長を経て平成17年より副学長・附属図書館長。第20期日本学術会議第一部会員、哲学委員会委員長。平成15年7月から19年6月まで日本哲学会会長。著書に「科学の解釈学」「言語行為の現象学」「無根拠からの出発」「物語の哲学」「クーン」「科学の哲学」「歴史を哲学する」など。
野家 啓一(のえ けいいち)東北大学副学長・大学院文学研究科教授、専攻分野:現代哲学、科学哲学、昭和24年仙台市生まれ、昭和46年東北大学理学部物理学科卒、昭和51年東京大学大学院理学系研究科科学史・科学基礎論専攻博士課程中退、昭和51年南山大学文学部助手、同講師、プリンストン大学客員研究員を経て、昭和56年東北大学助教授、平成3年同教授。同大学院文学研究科長を経て平成17年より副学長・附属図書館長。第20期日本学術会議第一部会員、哲学委員会委員長。平成15年7月から19年6月まで日本哲学会会長。著書に「科学の解釈学」「言語行為の現象学」「無根拠からの出発」「物語の哲学」「クーン」「科学の哲学」「歴史を哲学する」など。
※PDFファイルを表示させるには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はこちらから無償でダウンロードできます。![]()